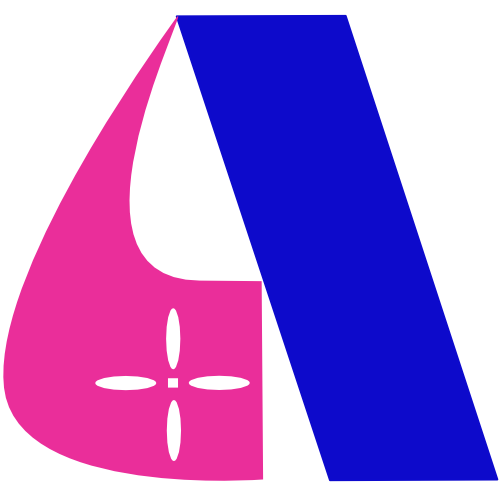皮膚科のトリビア
〜素晴らしきムダ知識〜
皮膚科医になって40年がたちました。皮膚科の事ならだいたいはわかっているつもりですが、まだまだ知らないこともたくさんあります。
ここでは、学会や講演会で聞いた「へぇ~」をご紹介していきたいと思います。私自身の覚え書きにもなりますので。なお、講演内容からの耳学問で、ご講演の先生のご承諾はいただいておりませんので、あしからず。
-
チタン試薬のパッチテスト結果の報告。某歯科大学金属アレルギー外来を受診したチタンアレルギーが疑われた344名(男性74名・女性270名)のうち、何らかの金属に陽性だったのは256名(74.4%)で、そのうちチタン試薬では24名(7.0%)が陽性だった。チタンに陽性だったのは歯科用インプラント治療後の患者に多かった。チタンも必ずしも安全な金属ではない。
パッチテストに用いた試薬がなんだったかはわからなかった。歯科の文献では2%硫酸チタン溶 液(林純薬工業)、1%塩化チタン溶液(和光純薬工業)の 記載がある。現在皮膚科ではSmartpractice CANADAのtitanium(iv)oxide、0.1%, petとtitanium,、1%, petが入手可能であるとのこと。
-
30歳代の女性。4年前に妊娠11週の時に熱発を伴う頭頸部の紅斑が生じ、Sweet病と診断されステロイド内服による治療を受けた。その後は再燃なく経過していたが、3年後の第2子妊娠の際にも、妊娠11週で顔面に紅斑が生じた。プレドニン20mg/日の内服を開始し、直後から紅斑は消退。その後妊娠中、出産後も再燃はない。妊娠に伴うSweet病は初期から中期にかけて発症し、顔面など頭頸部に限局していることが多い。
経験はないが、どういった機序なのだろう。妊娠は病気ではないが正常な状態でもないということか。
-
30歳代男性、左下腿の疼痛と腫大が持続するため受診。CPKは正常だったが、アルドラーゼが6.7U/Lと軽度上昇。造影MRIではヒラメ筋と三頭筋に高信号あり。ただし三頭筋の筋電図では神経原性の変化であった。腰椎椎間板ヘルニアがあり、S1神経根症に起因する限局性筋炎と診断した。皮膚筋炎/多発性筋炎の鑑別疾患として知っておくべき疾患である。
筋電図で神経原性の変化があることが鑑別として重要。治療はステロイド内服が必要な場合もあるが、椎間板ヘルニアなどの神経根症の治療を優先することになる。始めて知った疾患だった。
-
ロチゴチンパッチ(ニュープロR)をむずむず脚症候群に対して使用中の50歳代女性。使用開始1年後に貼付部位に痒みと発赤を生じるようになり、ステロイド軟膏の外用で治療していた。さらに1年後、貼付部位である両肩に脱色素斑が複数生じているのに気づいた。病理組織では表皮基底層の空疱変性と真皮の細胞浸潤があり、MelanA陽性細胞は消失しており、ロチゴチンパッチによる脱色素斑と診断した。ロチゴチンパッチはドパミンアゴニストの経皮吸収剤であることから、チロシンキナーゼ阻害やメラノサイトに対する直接的な細胞障害が関与している可能性がある。
接触皮膚炎も生じていることから、炎症後の色素脱失なのかもしれないが、薬理作用で生じているかもしれない。むずむず脚症候群のほかにパーキンソン病にも使用されているらしい。そういう薬剤があるとは知らなかった。興味深い症例だった。
-
20歳代の男性、口腔内びらん、眼症状を伴う体幹・四肢の滲出性紅斑を繰り返している。病理組織では表皮の個細胞壊死が目立つ。単純ヘルペスウイルス(HSV)によるStevens-Johnson症候群(SJS)を考え、アシクロビルとステロイドの全身投与が行われたがステロイド減量によって再燃。胸部の水疱と口腔内びらんから、水痘・帯状疱疹ウイルスDNAが検出され、VZVによるSJSと診断した。治療にはシクロスポリン内服を要した。
HSVによる多形滲出性紅斑は経験があるが、VZVが原因だった例はこれまで経験がない。今後は軽症の紅斑症でもVZVの抗体価変動を確認することにしよう。
-
70歳代の女性、20年前から糖尿病があり、2か月前からSGLT2阻害薬のトホグリフロジンを開始。その1か月後から両手の後爪廓に鱗屑を伴う紅斑と腫脹が出現。爪甲のdystrophyを伴った。KOH検鏡でカンジダなし。足趾には病変なし。病理組織では軽度の錯角化と表皮の肥厚があり乾癬型の反応。被疑薬の中止後、徐々に皮膚症状は改善した。
尿糖の排泄増加作用という薬理学的機序とは関連なさそうで、乾癬型薬疹としてよいのではないかと思った。ちなみにSGLT2阻害薬の薬疹はまれではなく、発売1か月後の2014年に日本糖尿病学会から注意喚起があったとのこと。知らなかった。
-
甲殻類によるアレルギーの主要なコンポーネントの一つであるトロポミオシンについての検索。30人のエビアレルギー患者のうち4人でトロポミオシンの特異的IgEが陽性であった。陽性例は全例ダニ、アニサキスの特異的が陽性で、3人にアトピー性皮膚炎があった。一つのサブグループと考えてよさそうである。
甲殻類とダニの交差反応はなんとなく想像できるがアニサキスも関連するとは思わなかった。問診や検査項目の選択に役に立ちそうだ。
-
DIHSの治療経験からの報告。DIHSの病態は薬剤アレルギーとそれに引き続くHHV-6、CMVの活性化である。DIHS早期にはHHV-6のレセプターであるCD134+のT細胞が増加する。早期のステロイド投与はこのT細胞の増殖を抑える。また、sIL-2が高いとHHV-6の増殖が抑制されるのでウイルス血症になりにくい。DIHSの予後はそのあとのCMVによって決まることが多く、後半はステロイド内服が負に働く可能性が高い。これらの理由から、DIHS発症後7日以内にプレドニソロンを1㎎/㎏/日で10日間使って速やかに中止するのがよい。
多くの経験から得た指針で、病態からしても納得できる。sIL-2、TARCも指標になるようだ。覚えておこう。
-
ファミシクロビルで治療を行った患者の神経痛残存率調査(FAMILIAR study)の結果のおさらい。2010年から2012年までの調査で、登録は約700人。疼痛消失率が50%になるのが全年齢平均で21日で、50歳以下だと16日、50歳以上だと23日。皮膚病変が軽微だと15日、軽度だと18日、中等度で26日、重症だと66日。疼痛残存率は30日で31.6%、60日で19.0%、90日で12.4%、180日で7.1%、360日で4.0%。3カ月で8人にひとりという結果。
なるほど。日頃の患者指導に使えるデータ。現在アメナメビルで同様の疼痛残存率調査が行われているが、違いが出るだろうか。最近は軽症患者が以前より多いような気がするので、比較の際には注意が必要だろう。
-
カンジダ血症では、適正な抗菌薬投与が行われていなかった時期にはカンジダ性眼内炎が1/4の患者に認められた。カンジダ血症のもっとも重要な合併症であるため、全例眼科受診が必要である。カンジダ血症は中心静脈留置針が感染源になることが多いが、カンジダ性眼内炎の患者の多くは、留置針が原因である。まず網脈絡膜炎が生じ、さらには硝子体内に浸潤する。失明のリスクが高いので早期診断・早期治療が必要である。
重要なことは、まず中心静脈留置針を抜去すること。他の深在性真菌症と同様に、免疫抑制状態、特に白血球減少がリスクになるとのこと。覚えておこう。
-
50歳代の男性。10数年来の足白癬で抗真菌薬外用を行っている。足背の体部白癬および足爪白癬のためテルビナフィン125㎎/日の内服を行ったが、3カ月目に症状が増悪した。真菌培養の結果はTrichophyton rubrumで、テルビナフィンに対して低感受性(MIC>128μg/mL)を示した。ルリコナゾールの外用で症状は改善した。
白癬菌でも薬剤耐性が問題になっていくのだろうか。他施設の報告によれば、テルビナフィン感受性低下は、エルゴステロールの合成に関与するスクアレンエポキシダーゼの遺伝子変異により、スクアレンエポキシダーゼ阻害薬の感受性喪失が原因とのこと。ちなみに、三環系抗うつ薬は内服のテルビナフィンと併用すると血中濃度が3~4倍に上昇し、めまい、倦怠感などの副作用が現れることが知られている。またこの相互作用は長期間持続するという特徴があるそうだ。
-
血清中クレアチニンは、GFRが120から80に低下しても大きく変動しない。GFRが60、クレアチニンが2をこえると急速に上昇(腎機能が悪化する)。過去のデータから、クレアチニンが2以上の患者で適切な治療を行わないと、4年後には3/4の患者が、12年後にはすべての患者が透析治療に移行した。
最近では投薬の際にもeGFRを念頭に置くことが多い。感染症やアレルギーなどで採血する機会があるときも、クレアチニンだけは見ておいた方がよさそうだ。
-
70歳代の男性、四肢、体幹に多発する紫紅色結節が10数年来あって、緩徐進行性。病理組織でHHV-8陽性、HIV陰性で古典型カポジ肉腫と診断。治療としてエトポシド単独を用いて改善した。AIDS関連のカポジ肉腫ではドキソルビシンリボゾーマル(ドキシル注)が唯一の保険適応薬で、これが第一選択薬となる。パクリタキセルも用いられるが、両者とも古典型カポジ肉腫への適応はない。
保険診療内で稀少がんの治療を行うことの難しさを感じた。制度を改めるしかなさそうだ。
-
OVOL1は上皮細胞の分化に重要な働きを有している転写因子であるが、グリテールは芳香族炭化水素受容体(AHR)の活性化を介してOVOL1、さらにフィラグリン(FLG)の発現を増強する。また表皮細胞にIL-4を加えると核内へのOVOL1移行が減少し、それとともにFLGの発現が減少した。この現象に対して、グリテールによる刺激を行うと、核内のOVOL1の発現が増加し、それとともにFLGの発現も増加した。アトピー性皮膚炎の治療のターゲットになりうる分子機構である。
以前にも聞いたことがあるが、油症の研究から発展した成果で非常に興味深い。グリテールは大豆由来だが、そのほかにもドクダミ、ウチワサボテン、アンチチョークも同様の働きがあるらしく、そういったそういった創薬が実現するかもしれない。
-
造血細胞移植後、幹細胞が生着する時期に一致して非感染性の発熱、肝障害、浮腫、体液貯留による体重増加、下痢などとともにGVHDに類似する皮膚病変が生じることがあり、生着症候群と呼ばれている。皮膚病変の病理組織は真皮上層の浮腫が主体で、拡張した毛細血管、小静脈内に顆粒球が出現し、内皮細胞と接着している所見を認め、ドナーの好中球による微小血管障害と考えられる。表皮細胞のアポトーシスはGVHDより少ない。なお、生着とは、好中球が3日間連続して500個/μL以上に増えることである。
生着までの期間は骨髄移植で2~3週間、末梢血幹細胞移植では約2週間、臍帯血移植では約3~4週間を要するらしい。治療はGVHDと同様でステロイドを用いることになる。
-
20歳代の女性。幼児期から数回、ウズラ卵の摂食後に発熱、咽頭違和感、全身のしびれ、呼吸困難をきたしている。ウズラ卵の白身、黄身でプリックテスト陽性。鶏卵の摂取は問題なく、卵白、卵黄の特異的IgE、プリックテストは陰性。ImmunoCAPRISACではオボムコイド、オバルブミン、コンアルブミン陰性。交差反応性なしと判断した。これまで国内で報告されているウズラ卵のアレルギーは消化管症状をきたした症例のみであった。
ちなみに、ImmunoCAPRISACとは、 ImmunoCAPRISAC(ファディア社)は、バイオチップ技術を用いた特異的IgE抗体の新しい測定方法で30μLの血清または血漿で、112種のアレルゲンコンポーネントに対する特異的IgE抗体を同時に測定することができるといった優れもの。25,000円でできるらしい。保険収載になるといいのだが。
-
眼科医を対象に、自身とその家族のアレルギー性結膜炎(AC)の有病率を調査した。3004名のうち、ACが48.7%、アレルギー性鼻炎(AR)が36.5%、アトピー性皮膚炎が7.0%、喘息が5.8%であった。ACの患者のうちARを合併する頻度は67.9%、AC単独が32.0%で、ACの中ではスギ、ヒノキの季節性ACが37.4%、通年性ACが14.0%であった。
耳鼻科医とその家族のスギ花粉症有病率の全国調査を見たことがあるが、それと同様のコンセプトで行われた調査。鼻炎よりも結膜炎が多いというのは意外だが、スギ花粉症としての結膜炎有病率は18.2%ということになる。
-
スギ花粉飛散時期に、室内犬を外で散歩させると、被毛に花粉が付着して、室内に持ち込まれることを実証した。付着部位は頭、頸部、背部だけでなく、地表に落下している花粉が付着する足蹠や腹部も多かった。帰宅後のシャンプーを用いたシャワー浴、ドライシャンプー、拭き取り用ウェットシートの使用でいずれも付着花粉は減少し、また静電気防止効果のあるペット用ボディーケア用品の使用も有効であった。
花粉飛散時期の犬の散歩に際しては、帰宅後に体毛や足の裏の花粉を拭き取らないと、室内に花粉を持ち込むことになる。ペットオーナーにはそのように伝えることにした。
-
1か月健診を行った548名のうち乳児湿疹と診断された児が73名(13%)を対象として、プロペトのみの外用を行い、3か月の時点でアトピー性皮膚炎と診断できる症例がどのくらいあるか、また、1か月の時点での湿疹病変がどのような状況だったかを検討した。3か月の時点で症状が確認できた51名のうち、アトピー性皮膚炎の発症ありと診断した児が28名(55%)あり、その児の1か月の時点での皮膚病変は、非発症群と比較すると、顔の湿疹の面積が広く、頬だけでなく額にも生じていたこと、顔に湿疹局面の形成があったこと(17vs4)、体にも湿疹局面の併発があったこと(9vs1)が特徴であった。
実際の臨床でも何となくは想像はしていたが、実際のデータが示された。ほかに家族歴なども参考にしながら、今後のムンテラに生かしたいと思う。
-
千葉大学予防医学センターで行っている出生コホート調査(こども調査)によると、生後4か月までに湿疹を認めた児は74%で、湿疹があった児の臍帯血TARC値は湿疹がない児より有意に高値だった。さらに10か月の時点でのアトピー性皮膚炎の有病率は、4か月までに湿疹があった群で30%、なかった群で8%、食物アレルギーは湿疹があった群で15%、なかった群で1%だった。臍帯血TARCが高値だと4か月での湿疹、さらに10か月でのアトピー性皮膚炎および食物アレルギーのリスクになる。
この調査は400組の家族が対象で、2014年から行われている。正式名称は「胎児期に始まる子どもの健康と発達に関する調査」で、HP(http://cpms.chiba-u.jp/kids/)も医師向けのデータが報告される予定とのこと。エコチルより多くの要因の検索が行われているので、こちらの知見にも期待したい。
-
ミルク蛋白含有繊維(ミルクレーヨン)を使った下着がある。4か月の男児が、それを着用して30分後に体幹に膨疹と潮紅が出現した。人工乳摂取後にも顔面の潮紅が出現することからミルクアレルギーを疑った。特異的IgEはミルクがクラス3、カゼインがクラス2。パッチテストでは乾燥した生地では陰性だったが、生食に浸した生地では20分後に赤みが出現し、1時間後にはそれが拡大し膨疹となった。発汗の多い時期には同様の症例があるかもしれない。
ミルク入りの下着があるとは驚いた。天然アミノ酸入りで肌ざわりがなめらか、ということらしい。寝具などにも使われているらしく、症例によっては疑ってみる必要があるかもしれない。
-
2010年に同定された、2型自然リンパ球(Group2 innate lymphoid cell:ILC2)は抗原や他の免疫細胞に由来しないIL-25やIL-33などのサイトカインに反応することで、多量の2型サイトカイン(IL-4、IL-5、IL13)を放出する。寄生虫疾患、真菌感染症、多くのアレルギー性疾患と関わることが最近注目されている。寄生虫感染ではIL-33によってILC2sが活性化し、積極的な排虫を促すが、虫体が体外に排出された後もILC2sが活性化し続けることは生体にとって危険な状態になるため、IFNやIL-27が出されることによって虫体の排出とともに炎症が収束することが明らかになった。また、IL-33-ILC2s依存的なアレルギー性炎症はIFNやIL-27によって抑制された。これらの知見は今後のアレルギー性炎症疾患の新しい治療戦略を考える上で有用である。
ウイルスや最近に比べると巨大すぎる寄生虫がどうやって排除されるかのメカニズムがおもしろい。IL-27は活性化樹状細胞から産生され、Th17の分化を抑制し、IL-10の産生を誘導するらしい。乾癬やアトピー性皮膚炎の治療にも結びつきそうだ。
-
環境省が企画する親子10万組を対象とした大規模な出生コホート調査があって、「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」と呼ばれている。胎児期から13歳までの子どもの健康状態を定期的にチェックし、環境要因が成長・発達にどのような影響を与えるのかを明らかにすることが目的。環境因子とアレルギーとの関連についても新しい知見が得られることが期待される。これまで、10万人の妊婦を対象とした調査で、気管支喘息の有病率が11%、アレルギー性鼻炎が36%、アトピー性皮膚炎が16%、食物アレルギーが5%であることがわかった。
2011年から全国15ユニットで実施されているそうだが、知らなかった。現在対象となる子どもは5歳から7歳ぐらいになっているので、これからは小児の新しい知見も出てくるだろう。詳しくはエコチル調査のホームページで閲覧可能(http://www.env.go.jp/chemi/ceh/index.html)。
-
ドキソルビシン(アドリアマイシン)、ダウノルビシン(ダウノマイシン)などのアントラサイクリン系薬剤は血管外漏出による組織障害が強く、少量の漏出であっても強い痛みが生じ、腫脹・水疱・壊死、潰瘍などの重篤な皮膚障害を生じる。デクスラゾキサン(サビーン)はその治療薬で、漏出後6時間以内に可能な限り速やかに1~2時間かけて点滴静注する薬剤である。トポイソメラーゼIIの作用を阻害することにより、細胞障害を抑制すると考えられている。
3日間の連続投与が必要で、薬価は1バイアル、\45,000とのこと。ステロイドの局注ではすまないらしい。
-
高齢男性。大動脈弁狭窄症に対し、経皮的弁置換術を施行された。術後2日めから足趾の紫斑が出現し、腎機能が急激に悪化した。コレステロール結晶塞栓症を疑って生検を施行したところ、真皮内の血管に淡い好塩基性の異物をみとめ、コロイド鉄染色で青く染まった。カテーテルのコーティングに使われている親水性ポリマーによる微小塞栓症と診断した。血液透析4日めで自尿あり。腎機能も10日で回復した。
血管内カテーテル療法後の微小塞栓は、コレステロール結晶だけでなく親水性ポリマーによるものがあることを知った。
-
糖尿病治療薬であるメトグルコはメラノジェネシスに関わる酵素の遺伝子発現を制御する主要な転写因子であるmicrophthalmia-associated transcription factor(MITF)の発現を低下させる。またプロトンポンプ阻害薬であるオメプラゾールがチロジナーゼの分解を促進しメラニン生合成を抑制する。いずれも既知の薬剤であるが色素増加に対する治療薬として用いることができるかもしれない。
いずれも使用頻度の高い薬剤である。報告とは反対にこれらの薬剤が脱色素斑の原因になるのだろうか。興味深い。
-
MRSAと緑膿菌に対し、5-ALAを添加しルミカライト(635nm)を照射することで菌量が有意に低下し、また創傷にMRSAないし緑膿菌を感染させたマウスの皮膚潰瘍に5-ALA外用後にルミカライトを照射することで上皮化が有意に早まった。難治性の皮膚潰瘍治療に利用できるかもしれない。
歯科では歯周病の治療にPDTが導入されている(ぺリオウェイブ)。安全で無痛の方法なので下腿潰瘍や褥瘡の治療に使えそうである。
-
20歳代男性、両前腕に生じた自覚症状のない不整形の貧血斑。上肢の挙上で消褪し、駆血と寒冷刺激で増悪する。臨床的にBierが1898年に報告した病変、multiple anaemic macules(Bier's spot)と診断した。皮膚毛細血管の緊張度の違いによる交感神経の反応性が皮膚の色調の差に影響を与えているために生じると考えられている。
よく経験するが、そういう疾患名があるとは知らなかった。禁煙で改善した症例があるとのことで、喫煙による毛細血管への影響も想定されている。今度症例があったら聞いてみよう。
-
複数の症例提示。共通する特徴として、使用開始から1~2週間後に生じる、腰部の発症が多い、一次刺激性のやけどのようなびらんを呈する、120mgより240mgの方が生じやすい。モーラスパップのケトプロフェン含有が0.5%なのに対し、XRは2.0%であり、また粘着力が強くなった。さらに水分を含むパップ剤の大型化で皮膚のふやけが増し、はがすときに剥離しやすくなったのではないかと考えた。
一目見て、「XR(青い袋の湿布)貼ったでしょ」といえるほど、同じ症例を多く経験するようになった。ふやけと粘着力アップによる皮膚剥離が原因だろうとする見解は、確かにその通りだと思う。
-
40代後半の女性。全身にやや持続期間が長い膨疹様紅斑を生じて来院した。月経の開始1週間前から出現し、月経開始とともに消退する。皮内テストを施行。estrogenで陽性、progesteronは陰性で、estrogen dermatitisと診断した。DDSの内服で症状が軽快する。月経に関連する皮膚病変はestrogen dermatitisのほか、auto-progesteron dermatitis(皮内テストでestrogen陰性、progesteron陽性)、月経疹(皮内テストは両者とも陰性)があり、鑑別が可能である。
そんなにシンプルだったか、という印象。周期的に遠心性だったり環状だったりの変な膨疹様紅斑が生じる女性患者を経験したことがあるが、月経との関連を聞いておけばよかったと思った。
-
持続する不明熱の原因として、血管内大細胞型B細胞性リンパ腫(intravascular large B cell lymphoma; IVLBCL)を考える必要がある。IVLBCLは節外臓器の微小血管内を閉塞性に進展する悪性リンパ腫で、全身臓器に虚血性病変をひきおこしすが、何らかの神経症状を呈することが多い。ランダム皮膚生検が診断に不可欠で、可及的速やかに行う必要がある。通常は上腕、大腿、腹部などからやや大きめの皮膚を脂肪織まで採取し、病理検体とするとよい。
これまでに触った経験がないのでわからないが、病理組織をみるとかなり多くの細胞集塊があるので、触診でわかるような気がする。実際に経験した皮膚科医に聞いてみたいと思う。
-
Helicobacter cinaediは1984年にホモセクシュアル男性らの直腸から分離培養された菌で、通常はAIDSなどの重症免疫不全患者に、敗血症を伴う再発性の蜂窩織炎をきたすことが知られている。血液培養では6-10日後にようやく出てくるので、早期に破棄しないことが肝要。H. cinaedi主要抗原タンパク質はH. pyloriの抗原タンパク質と相同性を有し、免疫的にも交差反応を示す。感染部位が胃粘膜に限局しているH. pyloriに比べ、本菌は血管侵襲性が強く、菌血症を介して全身に感染がおよぶ可能性があり、様々な疾患の病態に関わっている可能性がある。
最近では血清による診断が可能となっている。心房性不整脈や解離性大動脈瘤などの血管系の疾患との関連が指摘されている。高齢者で下肢にむくみがあり、時々蜂窩織炎を生じで改善に時間を要する症例がある。静脈性の循環障害だと思っていたが、H. cinaidiの関与があるのかもしれない。
-
dedicator of cytokinesis 8 蛋白をコードする遺伝子(DOCK8)の変異は高IgE血症を伴う副鼻腔・肺・皮膚のウイルス反復感染をきたす複合免疫不全症の亜型であるが、同時に重篤なアトピー性皮膚炎を発症することが知られている。DOCK8のknock out mouseも同様に重症の皮膚炎を発症し、IL-31の産生が著しく亢進する。そのメカニズムを解析したところ、DOCK8の下流で転写因子としてEPAS1が作動し、IL-31産生を誘導していた。EPAS1に対する抗体製剤がアトピー性皮膚炎の痒みに対する創薬標的になると思われる。
抗IL-31抗体製剤は実用化に向けて準備中とのことだが、これ以上の有効性があるかどうかはやってみないとわからない。生化学的な「痒み」の概念がよくわからないが、掻破行動の抑制につながれば、外用治療と組み合わせることによって悪化予防になるのかもしれない。
-
全身性強皮症患者159人における傍脊椎石灰化の有無をCTで検索した結果の報告。27人(17%)で傍脊椎石灰化がみられた。頸椎部が最も多く21人(78%)で、脊髄を圧迫する病変は7例(4%)にみられた。全身性強皮症は長期のフォローが必要だが、手のしびれ感や上肢の運動障害が出現した場合は精査が必要である。傍脊椎石灰化を合併した強皮症患者は男性が多く、手指潰瘍と手指末節骨短縮が有意に多いという特徴がみられた。石灰化の発症には血管障害が関連している可能性がある。
治療法は今のところないとのこと。抗セントロメア抗体陽性のlimited typeでみたれる皮下石灰化は高血圧症でCa拮抗薬を内服している症例に少ないとのことで、Ca拮抗薬の有効性が期待されるようだ。
-
高齢の男性で全身に生じた痒みが強い丘疹でステロイド軟膏外用治療中に両下肢を中心に丘疹性紫斑が続発してきた。皮膚生検の結果はIgA血管炎。その後疥癬であることが判明。イベルメクチンの内服を行い、疥癬の病変とともに血管炎の病変も消褪した。ヒゼンダニまたはそれが産生する何らかの蛋白が免疫複合体の形成に関与したと考えた。これまでの報告でも、他の感染症や発症を誘発する薬剤がなく、ANCA関連の自己抗体が陰性、そして疥癬の治療で軽快することが診断の根拠となっている。
疥癬の診断のためにも、ヒゼンダニ特異的な抗原蛋白が見つかればよいが、なかなか難しいようだ。質量解析などが進んでいると聞くが、今後に期待しよう。
-
関節リウマチとシェーグレン症候群のある50歳代女性。関節症状に対しアダリムマブ投与後、好酸球増をきたし、それとともに体幹に膨疹様の紅斑が出現。皮膚生検の結果、いわゆるleukocytoclastic vasculitisの所見で、薬剤性の蕁麻疹様血管炎と診断した。投与中止で軽快。原因として、血中のTNFとアダリムマブ、あるいはアダリムマブと抗アダリムマブ抗体のcomplexが血管壁に沈着したのではないかと考えた。
質問する機会を逸したが、IgAなどの免疫グロブリンやTNFの局在が毛細血管の血管壁いあったかどうか確認したかった。起こりうる、貴重な症例ではないかと思った。
-
成人アトピー性皮膚炎でも丘疹紅皮症と同様のdeck-chair signを伴うことがあり、マラセチア特異的IgEがクラス4以上の症例に多い傾向がある。アトピー性皮膚炎では発汗低下があることが示されているが、特に紅斑部ではこの傾向が強く、deck-chairの一見正常な皮膚では少ないながらも紅斑部より発汗が多く、角層内水分量も保たれていた。しかし、マラセチアのコロニー数は紅斑部で少なく、しわの部位に多かった。アトピー性皮膚炎で自己汗に反応する症例では、マラセチアに由来する蛋白が抗原であり、汗とマラセチアの関連を考えるうえで興味深い。
deck-chair signは、長期間ステロイド軟膏を外用している患者で、皮膚がたるんで合わさるしわに沿ってODTのような効果があるためではないかと思っているが、実際はどうなのだろう。発汗と角層内水分量が保たれているというのは想像できるが、マラセチアが多いから紅斑にならないというのは、逆のような気がする。
-
糖尿病に伴う肢端紅痛症の症例。肢端紅痛症は四肢末梢の潮紅、皮膚温の上昇、灼熱痛を三兆とする症候群で、真性多血症、本態性血小板増多症に伴うものが多いが、糖尿病でも起こりうる。一方で、近年、SCN9A遺伝子にコードされるNav1.7の変異に基づく常染色体優性の原発性肢端紅痛症が確認された。Nav1.7はナトリウムイオンチャネルで、変異によって疼痛シグナル伝達性ニューロンの興奮性が亢進し、痛覚過敏が生じると考えられている。古くは三環系抗うつ薬のアナフラニール、最近では抗てんかん薬のビムパットが治療に用いられている。
なかなか診断が難しい疾患である。糖尿病で手掌の潮紅をきたす例は少なくないと思うが、灼熱感を訴えることは少ないと思う。原発性の遺伝性疾患があることは知らなかったので、勉強になった
-
虚血性筋膜炎は寝たきりの高齢者に多いとされる皮下腫瘤で、仙骨部や四肢の加重部位に好発する。病理組織学的には中央にフィブリン変性と、その周囲の肉芽腫性の血管増生を伴い、偽肉腫性に増殖する線維芽細胞と筋線維芽細胞が帯状に配置する構造が特徴。文献的には男性に多く、大きさは平均4.7㎝、深部皮下から発生するが真皮下層、筋肉、および腱組織の浸潤が時に見られるため、軟部組織肉腫との鑑別が重要となる。
結節性筋膜炎と診断した症例はあるのだが、それとは違うようだ。在宅や施設の寝たきり患者で、そういった病変がある症例は経験していると思うが、生検をして、線維肉腫などと鑑別しようと考えたことはなかった。組織学的に中央の壊死組織と偽肉腫性の線維芽細胞増生が特徴とのこと。覚えておこう。
-
ローション基剤のステロイド外用薬や保湿薬をうまく使うと、アドヒアランスがよくなるという話題。特に男性で、保湿薬としてビーソフテンローションを好む人がいるが、ステロイドもローションを使うとよい。プロトピック軟膏がべたついて嫌いな患者には、ヒルドイドローションと直前に混合するとクリームのようになり、べたつきが減少する。
賛否両論あると思うが、塗ってくれないよりはずっといい。プロトピック軟膏に関してはそろそろ別の基剤の開発も勧めてほしいと思う。
-
薬剤抵抗性の心室性頻拍に対してニフェカラント(シンビット注)を持続静注。穿刺部位に一致して硬結が出現した。1週間ほどで自潰したが、内部から白色の固形物が排出されてきた。ニフェカラントは結晶性の粉末を生食で溶解して使用するが、溶解が不十分だと結晶が残り、異物肉芽腫を生じることがある。
生命の危険がある状態に対して使用する薬剤であるから、溶解が不十分になることもあるだろう。滅多に見ることはないが、以前から報告はあるようだ。一応、覚えておこう。
-
褥瘡などの慢性創傷では、創感染に移行しそうな状態、critical colonizationが創傷治癒遅延の大きな原因となり、対策が必要と考えられている。critical colonizarionの主たる原因は細菌によるバイオフィルムの形成であり、抗菌薬の抵抗性とも関連している。創面のどこにバイオフィルムが存在するかを同定する方法を開発した。まず創を洗浄し、生食に浸したニトロセルロース膜を創に10秒ほど当て、バイオフィルムの構成成分である酸性ムコ多糖類を吸着させる。そこにルイテインレッドないしアルシアンブルーによる染色を施すとバイオフィルムが染まるため、創面での局在がわかる。
バイオフィルムの形成が壊死の原因になるおそれがあり、バイオフィルムは外科的あるいは超音波を用いたデブリードマンが必要とのこと。biofilm-based wound managementということばもあるようだ。
-
アトピー性皮膚炎と発汗の関連をレプリカ法で検索した。掌蹠の汗管は皮丘に開口するが、健常人の体幹では皮溝から微量に発汗しているのが観察された。アトピー性皮膚炎では皮溝の発汗が減少している。ステロイド軟膏やワセリンはかえって発汗を低下させるので、アトピー性皮膚炎の乾燥肌はこれら外用薬の影響があるかもしれない。ヒルドイドクリーム3FTUの外用ないしODTは安静時の皮溝からの微量発汗を増加させるので、アトピー性皮膚炎の治療に有用である。
体幹の発汗が皮溝から、というのは知らなかった。発汗を増加させるためにはサウナなどの高温多湿環境よりも足浴がいいとのこと。ちょっと意外な感じがした。
-
重症で経過の長い慢性特発性蕁麻疹16例にオマリズマブによる治療を行った。12例は1回の注射後、1週間以内に改善がみられ、そのうち7例では4週間以内に無症状となった。1か月おき3回の注射で改善しない例があったが、投与を継続したところ5回目で改善した。欧州の臨床研究によると、3回の注射で改善した症例は、その後の治療を中断しても1/3は再発しないと報告されている。
血清中総IgE値が50IU/ml以下だとオマリズマブでよくならないらしい。とりあえず3回注射してみて、いったん終了。再発するようなら、再開するというのがいいようだ。もう少し安価だといいのだが、。
-
慢性特発性蕁麻疹の評価のためのツールとして、UCT(Urticaria Control Test)が有用である。現時点から過去4週間における蕁麻疹の①症状(痒み・膨疹)、②生活の質の障害の程度、③治療が不十分だったか、④全体としての症状の程度、をそれぞれ0点(非常に強い)、1点(強い)、2点(ある程度)、3点(わずか)、4点(全く)とし、合計0点が最重症、16点が症状なしとなる。12点以上だとコントロールが良好と考えてよい。評価の境目は8点で。日本人は控えめなため、一つでも「強い」をつけると7点以下になり、その場合は治療薬の変更、増量やオマリズマブの適応を考える必要がある。
評価ツールはやはり必要だと思う。前向き1週間を評価するUAS7(Urticaria Activity Score)を使ったことがあるが、それとよく相関するらしい。UCTの方が簡単で、待ち時間に書いてもらうことができそうだ。さっそく試してみよう。
-
自己免疫性水疱症あるいは全身性血管炎でアザチオプリン(AZA)を開始した2症例。2~4週後に全頭脱毛をきたし、発熱性好中球減少症を生じ、中止後も白血球減少は遷延した。チオプリン感受性遺伝子多型とされるNUDT15 R139Cの検索で、2例ともホモ接合体だった。アレルの頻度は日本人では10%と高く、AZA投与前に薬剤感受性遺伝子のスクリーニングを行うのがよい。
AZA内服後に急な脱毛があったら、重篤な骨髄抑制が生じていると認識する必要があるとのこと。薬剤感受性遺伝子の話題が最近は多くなってきた。
-
20歳代の男性で、12年前にSLEと診断されステロイドやタクロリムスで治療中。左腋窩から胸部に伸びる皮内の索状硬結が生じた。自覚症状はなし。生検の病理組織は真皮深層の膠原線維の変性とその周囲のリンパ球、組織球浸潤で、interstitial granulomatous dermatitisの所見。ステロイドの増量で消褪した。
SLEに伴う、膠原線維変性とアタック型の肉芽腫だった。モンドール病に似た索状硬結になることがあって、それをロープサインと呼ぶことは知らなかった。男性に多く、SLEの活動性と平行するらしい。
-
抗TIF1-γ抗体陽性の皮膚筋炎26例の集計。皮膚症状は顔面の紅斑、ゴットロン丘疹などの典型疹と嚥下障害をほとんどの症例で認め、17例に悪性腫瘍を合併していた。抗体価の経時的推移を検討した16例では、悪性腫瘍の合併のない5例では皮膚筋炎の治療で抗体価が減少し、1例で陰性化した。悪性腫瘍合併例では抗体価の低下は少なかったが、悪性腫瘍の治療が奏功した3例では抗体価が陰性化した。経過中に悪性腫瘍の再発や皮膚筋炎の病勢悪化があった症例では抗体価の上昇を認めた。抗TIF1-γ抗体を経時的に検査することで、皮膚筋炎および合併する悪性腫瘍の活動性を知ることができる。
貴重な報告だと思った。おそらく皮膚筋炎を疑ったら、タイプの確認のため最初の1回しか検査しないことが多いと思われる。経時的に変動をみれば、治療に反映させることができると知った。
-
20年前に皮膚筋炎と診断された50歳代女性。額に紅斑を伴う紅褐色の小結節が生じ、生検で結節性皮膚アミロイドーシスと診断。ケラチン陰性、L鎖κが陽性であった。シェーグレン症候群の合併はなし。同時期に筋症状の悪化があり、IVIg療法を3回施行。筋症状の改善とともに、額の結節は消褪し色素沈着となった。IVIgの投与により、病原性自己抗体が減少し、アミロイドの量が減少したと考えられる。
IVIgがアミロイド沈着に有効というと違和感があるが、B細胞の活性化にブレーキをかける作用があると言われれば、なるほどと思う。貴重な症例だった。
-
薬剤過敏症症候群(DIHS)は薬剤中止後も経過が遷延すること、HHV6の再活性化が特徴であるが、病初期には判断できず、播種状紅斑丘疹型薬疹や多形紅斑型薬疹との鑑別が難しいことがある。DIHSの発症後早期には血清中TARCが著明に高値を示すが、TENやSJSを含めたほかのタイプの薬疹では軽度の上昇にとどまることが示され、DIHSの早期診断マーカーとして有用である。Sysmex株式会社の全自動免疫測定装置HISCLがあれば、TARCが17分で測定できる。
現在は先進医療で行われているが、保険収載をめざして臨床研究が行われているとのこと。この装置が一般的であって、多くの病院の検査室で設置されているのかどうかはわからないが、早期診断に役立つのであればぜひ導入してほしい。
-
外用薬の基剤の話。乳剤性基剤には水中油型(O/W型:外側が水)と油中水型(W/O型:外側が油)があり、保湿薬を例に挙げるとヒルドイドソフト軟膏、パスタロンソフト軟膏が「油」、ヒルドイドクリーム、ケラチナミンクリームは「水」。「油」はべたつくが刺激が少ない。「水」は塗りごごちがさっぱりしているが、洗うと流れる。軟膏は「油」、ゲルは「水」。「油」は「水」との混合が不向きなので、ステロイド軟膏などと混合できるのは「油」。
何度も聞いてきた内容だが一番わかりやすかった。これまでの、O/W型、W/O型という呼び方だとどちらか迷うことがあったが、外側が水、外側が油というシンプルな呼び方がすっきりしていて理解が深まった。
-
長島型掌蹠角化症は常染色体劣性遺伝形式をとる遺伝性疾患で、蛋白分解酵素を阻害する作用のあるSERPINB7蛋白の変異で生じる。掌蹠は発汗が多く、角質の肥厚もあるためにおいが強いことが主訴になることがある。においに対する治療としてはベピオゲルの外用が有効である。
ナジフロキサシンなどの他の抗菌外用薬よりも効果があるらしい。これは是非試してみよう。pitted keratolysisにもいいかもしれない。
-
PsA=psoriatic arthritis(乾癬性関節炎):皮膚科医がこれまで用いていた関節症性乾癬という病名は死語になった。
SpA=spondyloarthritis(脊椎関節炎):乾癬性関節炎を含む、体軸関節、末梢の関節に炎症を来す疾患の総称で、HLA-B27との関連が深い。
AS=ankylosing spondylitis(強直性脊椎炎):bamboo spineが有名。概念は古く、1964年改訂New York基準が今でも健在。
IBP=inflammatory back pain(炎症性背部痛):SpAの特徴で、ASではほぼ100%、PsAでは40%~78%の患者でみられる。40歳以下、運動で軽快し安静や同じ姿勢で悪化、明け方に強い、NSAIDsの有効性が高い、という特徴がある。
最近聞くことが多くなった。少し前からIBPって何だろうと思っていたら、そういうことだった。開業医にとっては、ちょっとつかみがたい領域である。
-
処置をサボる、外用する量が少なすぎるといった外用療法がうまくできていない、アトピー性皮膚炎や乾癬の患者に対して、外用療法を充分に、適切に行ってもらうための殺し文句。次回の診察までに使い切った空のチューブを持ってくるように指導する。患者の心理としては、もったいないので中身を捨てることまではしないため、きっちり塗ってくるようになる。
さすが、エキスパートと感心した。個人的にはこういった情熱的なムンテラはしたことがないが、機会があれば試しにやってみようかと思った。
-
内服した薬剤は腸から吸収され、最初に肝臓へ移行して代謝された後に血液中へと移動する。これを初回通過効果という。肝臓を通るか通らないかで脳内への移行率も変化する。ケトチフェン点眼薬の使用後には脳内H1受容体が40~50%占拠される。オロパタジン点眼薬では占拠されない。
眼の結膜は脳に近いため、また初期通過効果がないために吸収された薬剤の脳内移行が起こりやすいらしい。注意しておく必要がありそうだ。
-
脳内への移行性を低下させるために、H1受容体遮断作用のある薬剤にカルボキシル基あるいはアミノ基を導入している。カルボキシル基がアレグラ、アレロック、タリオン、ジルテック・ザイザル、ビラノア。アミノ基がアレジオン、クラリチン・デザレックス・ルパフィン。向精神薬との関連が深く、ドキセピンにカルボキシル基をつけたものがアレロック、ミアンセリンにアミノ基をつけたものがアレジオン。
アミノ基がついたものの方が若干抗コリン作用が強いらしい。すぐ忘れてしまうので、メモっておこう。
-
内因性ADは血清中IgEが正常でフィラグリン遺伝子の変異が低率である。発症に金属アレルギーが関与している可能性がある。チョコレート負荷後の血中Ni濃度は内因性ADで高く、外因性AD、健常人の順であった。しかし、負荷前のNi濃度も内因性ADで3.48ng/ml、外因性ADで2.13ng/ml、健常人で0.40ng/mlで、内因性ADでは健常人に比べて8.7倍の血清Ni濃度であった。
内因性ADでは消化管のバリアに障害があって、Niの吸収が高くなっている可能性があるとのこと。外因性ADでも健常人よりは高いようだが、興味深い。
-
Palmar fasciitis and arthritis syndrome(PFA)は関節リウマチ類似症状を示すparaneoplastic syndromeである。卵巣癌が有名だが、乳癌や消化管の腺癌でも起こりうる。肩や膝の関節痛に加えて、手掌筋膜の肥厚と紅斑を伴った硬い有痛性結節、手のこわばり、指の屈曲拘縮が特徴で、woody handsと呼ばれる状態になる。癌の治療により、完全寛解することが多い。
paraneoplastic rheumatologic syndromesと呼ばれる、悪性腫瘍に伴うリウマチ類似疾患が色々とあるようだ。皮膚に置き換えればデルマドロームなので、リウマドローム(rheumadrome)と呼ぶべきか。意外にも皮膚病変が特徴的なので、覚えておく必要がある。
-
remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edemaの略で、60歳以上の高齢者に好発するリウマトイド因子陰性の対称性滑膜炎。関節破壊はきたさない。消化器系、前立腺などの固形癌や悪性リンパ腫などの悪性腫瘍、リウマチ性多発筋痛症、シェーグレン症候群、パーキンソン病、パルボウイルスなどの感染症と関連が指摘されている。HLA-B7が半数の患者で陽性。患者血清中のVEGFが著増しており、このVEGFによる血管透過性の亢進がRS3PE症候群患者の手足の浮腫の発現に関与している。発症は突然であり、対称性滑膜炎による末梢関節痛、両側手背・足背の圧痕を残す浮腫、手指屈筋腱の炎症による疼痛がみられる。
RAと鑑別すべき疾患。MMP3は高値になるようだ。略語は受け入れがたいが、悪性腫瘍に伴う反応性関節炎として重要。抗TNF-α製剤による治療の前に検討が必要。高齢者の血清反応陰性多関節炎で症状や経過が非典型的であれば血液悪性腫瘍、前立腺癌などの固形癌に注意する。
-
HIV感染症に対するHAART療法後、免疫機能が回復する過程日和見感染症の顕性化が生じることがある。これは免疫再構築症候群(Immune reconstitution inflammatory syndrome:IRIS)と呼ばれ、約20%に認められる。IRISはHAART療法開始前の免疫不全状態で増えていた病原体に対して、治療により回復したCD4+T細胞などの免疫応答が過剰になるために生じる炎症反応である。帯状疱疹はIRISとして生じる疾患の中で最も多い。通常の帯状疱疹と比較すると、38℃以上の発熱を来すことが多く、血清の抗VZV-IgG抗体が上昇しないことが特徴である。IRISと同様の病態はステロイドや免疫抑制剤治療の減量中やDIHSの際にも生じることがあり、この疾患概念を理解しておく必要がある。
ウイルス性発疹症に関しても、それ自体はウイルスそのもので生じるわけではなく、ウイルスに対する免疫反応をみているということ。大事な概念であることを再認識した。
-
バイクの事故で右大腿切断術を施行。2年後に切断部の感染症があり、ミノサイクリン200mg/日の内服を開始。4か月後に右大腿切断部と右肘頭に青黒色の色素沈着が生じ、その後側胸部、腰部などに拡大した。病理組織所見では真皮、皮下に鉄染色陽性顆粒の沈着がある。内服中止後、徐々に消退傾向。
ミノサイクリンの色素沈着は、一般的に外傷があった部位と関連することが多いらしい。側胸部、腸骨部、手背なども骨や関節の突出部で、機械的な刺激を受けやすい部位に生じやすいということ。
-
80歳代の男性。陰茎、陰嚢の黒色壊死と外陰部から右そけい部にかけての潰瘍。陰茎は海綿体に至る壊死組織があったが、病理組織学的には血行障害はなし。生活歴から、OTCのミズムシ用パウダースプレーを過剰投与をしていたことが判明。第4度の凍傷と診断した。
冷却スプレーは1回の使用で噴霧した部位の温度が5℃下がるという。使い続けるともっと下がると言うことか?ミズムシ用ではなくても、スポーツの時のうちみや、最近では暑さ対策で使われているので、気をつけないといけない。
-
30歳代女性。3回の流産の既往がある。1年前から両下腿から足背にかけて網状皮斑を生じた。抗リン脂質抗体は陰性。クリオグロブリンも陰性。病理組織では真皮中層の細動脈にフィブリン血栓を認め、livedo racemosaと診断。不育症の原因精査で第XII因子活性の低下があり抗第XII因子抗体が陽性であった。アスピリンの内服で挙児を得ることができた。
第XII因子欠乏症は通常出血傾向はなく、静脈血栓症、肺塞栓症などの血栓症状をきたすことが知られている。女性患者では不育症の原因となる。系統的に血栓が生じる疾患の原因として重要である。また、不育症の新しいリスクとして、抗phosphatidylethanolamine (PE)抗体と抗第XII因子抗体があり、血栓が生じやすいことのほかに胎盤の形成が阻害されることが原因とのこと。
-
50歳代の女性。子宮筋腫の術後から、顔のほてりや多汗が生じ、婦人科でエストロジェルを処方され、外用部位に接触皮膚炎が生じた。パッチテストでは主剤のエストラジオールが陽性。その後、婦人科から紹介されたエクオール(大豆イソフラボン)を内服したところ、播種状紅斑丘疹型の薬疹を生じた。エクオールはエストロゲンと類似の構造を有しており、経皮感作によってアレルギーが生じ、交叉反応によって薬疹が生じた可能性がある。
大豆食品中のイソフラボンであるダイゼインは腸内細菌によってエストロゲンと類似したエクオールに代謝される。エクオールは一般的なフラボノイドと同様に抗酸化活性を有し、さらに化学構造がエストロゲンと類似していて弱い女性ホルモン様作用を持つと考えられている。美容や更年期障害に有効との報告があり話題の食品だが、こんな副作用もあるということを認識した。
-
60歳代の男性例。手指に比較的急速に浮腫が生じ、関節の曲げにくさを自覚。股関節・膝関節の痛みを伴った。手指関節背面に母指頭大までの皮下結節が多発。皮膚生検では真皮の膠原線維の増生と弾性線維の減少をみとめた。手関節のMRIでは滑膜炎の所見あり。fibroblastic rheumatismと診断した。皮膚の線維芽細胞が関節の線維芽細胞と同様に、炎症によって活動性を増すことが原因で、治療はプレドニン、メトトレキセート、インフリキシマブなどが用いられている。
1980年ごろから提唱されていた疾患のようだが、初めて聞いた。未だに診断したことはなくいが、遭遇していたのかもしれない。急に発症する多関節炎と手指の皮下結節とその病理組織が診断のポイントのようだ。覚えておこう。
-
20歳代後半の男性。喫煙を再開して数か月後から。右こめかみに索状硬結が出現した。頭痛や視力障害はなく、血沈も正常。通常の側頭動脈炎は55歳以上の女性に多く、頭痛、咬む時の痛み、眼症状、さらに関節痛や筋肉痛などの全身症状を伴うが、若年者に発症するこれと近縁の疾患があり、若年性側頭動脈炎と呼ばれる。全身症状を伴わないことがほとんどで、病理組織学的に血管壁に好酸球の浸潤が多いことが特徴である。誘因としては喫煙や何らかのウイルス感染症が考えられている。
側頭動脈炎は、高安病とともに巨細胞性動脈炎という病名に変わったはず。高安病は若年女性に多い疾患だから、若年性巨細胞性動脈炎は、高安病のことを指す病名になってしまいそうだ。最近の血管炎の病名の変更は本当に困った問題だ。
-
40歳代の男性。熱発と同時に両手・両足の紅斑と腫脹が生じた。両腋窩や腹部などにも滲出性の紅斑があり、手掌には小水疱を伴う。病理組織学的には真皮中層から皮下脂肪織に多数の好酸球を含む細胞浸潤とflame figureをみとめた。末梢血好酸球は14,900/μLまで上昇。コクサッキーウイルスA6の中和抗体が8倍から128倍に上昇した。
感染症がきっかけになることはありそうだが、手掌の小水疱がなければコクサッキーウイルスの中和抗体までは調べないだろう。ほかに誘因があるかもしれないが、貴重な報告だった。念頭に置いておこう。
-
耳たぶのしわ(Earlobe creases)は耳垂を斜めに横断するしわで、以前から心血管イベントとの関連が指摘されている。今回は製造業に従事する腹部超音波検査を施行した398人の男性従業員を対象に検診結果をしわのある66人としわがない332人で比較した。その結果、収縮期血圧、AST、γGTP、中性脂肪、HDLコレステロール、脂肪肝の有無で有意差がみられた。耳たぶのしわは、検診医にも認知されるべき所見であると考えられる。
多くの対象者からの統計的解析なので、信頼性は高そうだ。女性ではどうなのかも知りたいところだ。明日からさっそく、耳たぶの所見の記載をしておこう。
-
脊髄炎の治療で用いた牛社腎気丸によると思われる滲出性紅斑から、粘膜病変を伴うStevens-Johnson症候群に進展しさらにTENへと移行した症例。ステロイドパルスと免疫グロブリンで加療を行ったが表皮剥離が拡大傾向。その後発熱性好中球減少症をきたし、抗菌薬とG-CSF製剤を使用したところ急速に上皮化が始まった。
たまたま、ではなく、過去にも同様の報告があるとのこと。機序については不明だが、薬剤による骨髄抑制が解かれて、骨髄幹細胞が復活し、先天性表皮水疱症と同様に、潰瘍化した皮膚の修復に関与したのだろう。
-
ライチ摂食後に膨疹、呼吸困難を生じた既往のある30歳代女性。マンゴジュースを飲んだ1時間後に膨疹、3時間後には全身に広がり、冷や汗と意識消失をきたした。特異的IgEはマンゴ:class3、ブタクサ:class6、ヨモギ:class6。プリックテストでウルシ科のマンゴ、カシューナッツ、ピスタチオで陽性。ライチ、ヒマワリの種、ハチミツも陽性。
接触皮膚炎ではなく、即時型のアレルギーで、花粉による感作、つまりpollen-food syndromeと考えてよさそうだ。キク科のヨモギはピスタチオとの交差反応があることはThermoFisher scientificのHPにも記載されている。ライチはウルシ科ではないが、同系列のムクロジ目ムクロジ科で、交差反応も報告されている。植物の分類は真菌以上に難しい。
-
間歇性跛行はその原因が抹消動脈疾患か脊椎疾患かの鑑別が重要。脊椎疾患では前屈で楽になるのが特徴。歩けなくなったらどうやって休むかを聞くとよい。座り込むのが脊椎疾患。PADでは立ったまま休むことが多いので、鑑別に役立つ。
とはいえ、間歇性跛行を主訴に皮膚科を受診する患者は多くない。皮膚科で診るPADは、足趾の潰瘍ができてしまったあと、つまりFounteinのⅣばかりである。
-
側腹部や四肢屈側に列序性に配列する点状紫斑を生じた症例に脳出血や脳梗塞が生じた。側腹部などは終動脈の穿通枝が分布する部位であり、脳血管障害を起こしやすい部位の血管に似ていることから、こういった紫斑が脳血管障害発症リスクのマーカーとして有用かもしれない。
皮膚生検は施行されておらず、病理組織は不明。急性期の脳血管障害の患者にこのような部位に紫斑があるかの検討が必要と思った。
-
40歳代の女性。顔面の腫脹、頭部にも同様の腫れと脱毛が生じた。頭皮は肥厚し浸潤がある。手指と口唇にしびれ感あり。採血ではWBCが8,500/μLで好酸球が20%。病理組織は好酸球が毛包周囲に稠密に浸潤し、周囲の真皮、皮下組織にも及んでいた。ステロイド局注で改善した。
アトピー性皮膚炎でもなく、掻破による影響でもないとのこと。好酸球が直接毛包に障害を与えたようだ。太藤病が頭皮に生じたと考えるのがよさそう。好酸球が浸潤する病態があれば起こりうる事象として認識しておこう。
-
乾癬患者で抗核抗体が陽性であった症例の解析の結果、4例で抗ヒストン抗体が陽性であった。この4例は皮膚病変は必ずしも重症ではなく、抗CCP抗体も陰性だったが、いずれも重症の腱炎・付着部炎を伴う乾癬性関節症であった。抗体価は病勢とも相関していた。
何らかの関連があるのかもしれない。開業医ではXPや関節エコーができないので、採血で関節症を評価できれば有用だと思う。機序の解明が待たれるところである。
-
疥癬の患者には多彩な皮膚症状が続発し、水疱性類天疱瘡(BP)や穿孔性皮膚症が生じることがある。BP様皮疹を伴った疥癬の症例が1990年代にいくつか報告されているが、病理組織学的には表皮下水疱で、蛍光抗体直接法でもIgG、C3の線状ないし顆粒状の沈着があり、BPと鑑別が困難であるが、ステロイド内服に反応せず、疥癬の治療で改善する場合が多い。時間的な経過としては両者がほぼ同時にあるいは随伴して生じている。
一方で、特に疥癬の既往のある患者にBPが生じ、それに対するステロイド内服治療を行うことによる免疫抑制のために疥癬が発症(再燃)、重症化する症例も報告されている。疥癬のBP様皮疹があるかないか、今後の検討を待ちたいと思う
-
クローン病のある若年女性。頭皮に膿疱とびらんが多発した。細菌培養陰性で抗菌薬も無効。クローン病に伴うErosive pustular dermatosisと診断した。インフリキシマブの投与で軽快した。Erosive pustular dermatosis of the scalpとして報告される症例が多いく、クローン病との関連が深いが、潰瘍性大腸炎や関節リウマチに伴う症例もある。
臨床はかなり特徴的で、一度見たら忘れられない皮膚症状。いかにもクローン病と関連がありそうな症状だった。開業医が遭遇することはまずなさそうだが、覚えておこう。
-
5歳の男児。ぬか漬けの摂食で口腔内アレルギー症候群。実家が精米店で、実家に行くと目の痒みと咳嗽が生じる。米ぬかのプリックテストで陽性で、米ぬかによるアレルギーと診断した。アレルゲンは、コメの52kDaグロブリンが主に米ぬかに、19kDaグロブリンが白米に存在し、それぞれに対するIgEが検出された。経皮感作が疑われるとのこと。
米ぬかも石鹸やパックに使用されていると聞く。食べられるものだから皮膚にとっても安全という神話は茶のしずくで完全に崩壊したはず。ちなみにイネ科花粉によるアレルギーとは関連がないらしい。
-
ケラトアカントーマ(KA)はKA like verrucaかKA like SCCしかない、という見解があったが、やはりKAという疾患は存在するという話。ただし、low grade のSCCとの臨床的な鑑別は難しい。KA自体があるとすれば、良性の腫瘍であり、KAと診断した症例がリンパ節に転移したという経過は、KAの中にSCCが生じた(悪性転化)と解釈するのが正しい。KAの組織像は、辺縁には核異型性があるが、中央に行けば行くほど、特徴である大型の細胞(large pale pink cell)が目立ち、これは毛包峡部の細胞に類似する。
結局は、切除をして組織を見るのがよさそうだ。1カ月間様子を見て自然消褪しないようなら切除する、という方針もあるが、顔や頚部の場合には、待っているのも気の毒である。
-
重度心身障害をきたす早期発症型の脳症。臨床症状は易刺激性、間欠的な無菌性発熱、頭位成長の低下、発達退行などの重症脳症の経過をとる。約4割の患者で手指、足趾、耳などに凍瘡様の皮膚病変を伴う。提示された症例は手足に胼胝様の病変もあった。近年ではより軽症な非典型例が存在することが明らかになってきている。変異する遺伝子により5型に分類され、TREX1の変異がもっとも重症になる。
SLEを合併することがあり、免疫学的検査で、補体低下、IgGおよびIgMの上昇をきたす例もあるようだ。神経学的には胎生期ウイルス感染様の表現型をとり、偽TORCH症候群とも呼ばれているとのこと。
-
ミルフィーHPによるセレン欠乏とてんかん予防のために使用されたケトンフォーミュラによるビオチン欠乏。いずれも脱毛とCK上昇を伴った。それぞれ、不足を補うことで症状の改善を認めた。特殊ミルクはそれぞれの組成を確認し、不足しがちな栄養素の補充を行う必要がある。
明治のHPでは、様々な「特殊ミルク」が紹介されている。先天性代謝異常症の栄養補給や治療には、国の助成事業として無償で提供される「登録特殊ミルク」と企業が無償で製造・提供する「登録外特殊ミルク」があるとのこと。
-
母乳栄養児のビタミンD不足が国際的な課題になっている。2016年夏・冬に採取した産後3~4カ月の母乳と1989年に採取した同じ時期の母乳に含まれるビタミンD2/D3と25- ヒドロキシビタミンD2/D3を九州、関東、北海道で比較した。食事からのビタミンD摂取と母乳中ビタミンDには有意な関連はなかった。季節による変化は夏に多く、冬に少ない。地域差はなかったが、外出時間と正の相関があった。経年的には1989年の母乳に比べて2016年の母乳中のビタミンDが有意に低かった。
児のアトピー性皮膚炎の発症にも関連しているといわれている。アレルギー発症の予防としてビタミンDをサプリメントとする効果については、一致した結果がまだないらしい。授乳婦もそれなりにUVに当たるようにすることが重要かもしれない。
-
・spiky keratoderma(keratoderma punctata):掌蹠に多発する点状角化性小結節で、37例のうち10例に食道癌などの悪性腫瘍があった。・Birt-Hogg-Dube(BHD)症候群:顔面と頭頚部の線維毛包腫(fibrofolliculoma)や線維性疣贅(acrochordon)に、多発性肺嚢胞と腎癌を合併する常染色体優性遺伝の疾患。・remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema(RS3PE):症状は手背の浮腫と関節リウマチ様の手指の変化。肺癌、前立腺癌、卵巣癌、乳癌、膀胱癌、消化管癌などの合併がある。・cancer-associated fasciitis panniculitis:両下腿の持続性脂肪織炎ないし筋膜炎で、女性に多い。血液、リンパ球系の悪性腫瘍の合併が多い。・Reed's syndrome:20歳過ぎから多発する四肢や体幹の皮膚平滑筋腫と単発性腎癌、女性では子宮筋腫を併発する遺伝性疾患。
どれも初めて聞く疾患名だが、皮膚病変は意外にもありふれた症状だった。見逃しているかもしれないので、すべて記憶に留めておこう。
-
医療分野の膨大なデジタルデータの利活用を進め、研究、医療システム、医療行政に資するアウトカムを含む多様なデータを大規模に収集・利活用する仕組みを設けるための法律で、平成30年5月11日に施行された。本法は個人の権利利益の保護に配慮しつつ、高い情報セキュリティを確保し、十分な匿名加工技術を有するなどの一定の基準を満たしそれを適正かつ確実に行うことができる業者を認定する仕組みを設けたことが特徴。
講演では医療情報も情報流通と空間の分離が進むとの見解だった。検査と予防は家庭へ、リハビリとケアも家庭へ、医療は社会へ、介護は施設へという流れだと述べられていたが、本当だろうか。
-
20歳代の女性、小児喘息の既往あり。感冒症状に喘鳴が加わり、ブデソニド/ホルモテロール吸入を処方された。2週間後から多形滲出性紅斑と舌、咽頭のびらんが出現した。スクラッチパッチテストでブデソニドが陽性。原因薬と判断した。
ブデソン軟膏によるかぶれをかつて多く経験した。喘息用の吸入薬としてはパルミコート、シムビコートがブデソニドが主成分で、多くの喘息患者に処方されている。さらにクローン病の治療薬として、ゼンタコートカプセルがあり、ブデソニドを小腸および結腸近位部にて放出するように設計された腸溶性徐放顆粒を充填した硬カプセル剤とのこと。今回のような症例が増えなければいいが、心配である。
-
ワセリン、ステロイド外用薬、保湿剤を健常部皮膚に塗布する前後で、微量発汗の定量をImpression mold法を用いて行った。安静時の有毛部皮膚における発汗は不感発汗として皮溝に分泌され、温熱誘発による汗は自覚できる汗で皮丘に開口する。6mg/cm2のワセリン、ステロイド軟膏、保湿薬と18mg/cm2の保湿薬を健常部皮膚に外用したところ、発汗滴数が7日後にはそれぞれ2.3倍、1.8倍、3.9倍、6.0倍に、14日後にはそれぞれ1.6倍、1.4倍、2.6倍、4.1倍に増加した。炎症性皮膚疾患の治療として保湿薬を用いることで不感発汗を増やし、角質水分量を増加させることは有用な方法である。
慢性の炎症性皮膚疾患の治療において、汗が多ければよいかというと、そうでない症例も経験する。ただ、微量発汗を定量するという方法は非常に興味深いと思った。
-
欧米ではすでにハチ毒をアレルゲンとした減感作療法が30年以上前から施行されていて、有効性(80~95%)と安全性が示されているが、年間20人がハチ刺症で死亡している本邦では未だに保険適応がない。ハチ毒アレルギーがあると、最終刺症から数年以内に再刺症を経験すると40~70%で全身症状が出現する。ハチ毒アレルギー患者はアウトドアワーカーや養蜂業者に多く、特異的IgE抗体の検査で、林業従事者の12.9%、電気工事業従事者の1.9%、建設業従事者の5.6%、養蜂業従事者の27.4%がハチ毒アレルギーと診断され、アレルゲン免疫療法の適応と考えられた。
Hollister-Stier社(USA)の治療用エキスを輸入して行っているそうだ。この会社のプロダクトリスト(http://www.hsallergy.com/products/)には様々な診断用、治療用アレルゲンがあって、驚いた。
-
Resolvinはω3脂肪酸であるEPAに由来する脂質メディエーターで、生物が持つ恒常性維持に必要な炎症収束機構に関わると考えられている。喘息モデルマウスにResolvin E1を投与すると気道への好酸球、リンパ球の集積を減少させ気道過敏性を抑制し、炎症を収束させることが示された。臨床応用の可能性がある。
EPAにはResolvin、DHAにもprotectinという抗炎症性脂質メディエーターが存在するようだ。魚油が皮膚のアレルギー性疾患にも有効ということに単純になるかどうかは今後の研究を待ちたいところだ。
-
腸内細菌と同様、腸内真菌もアレルギー発症・増悪の因子として注目されてきた。乳幼児期における抗菌薬の投与は腸内細菌叢の変容(dysbiosis)を介してアレルギーの発症リスクを高めると考えられているが、これに真菌が関与している可能性が示された。消化管にCandida albicansが長期間定着するモデルマウスでは、肥満細胞の活性化が生じ消化管粘膜の透過性を亢進させ、食物抗原の取り込みを増やし、結果として感作を促進すること、食物抗原による免疫寛容の誘導を阻害すること、消化管、皮膚、関節におけるアレルギー性炎症を増悪させることが報告された。
乳児期の抗菌薬投与は長期的な弊害があると考えた方がよいのかどうか、上気道炎は別にしても膿痂疹や中耳炎の治療はどうするのか、悩ましいところだ。
-
毛皮質線維が露出・断裂して、筆先を向かい合わせたようになる毛幹の形態異常。後天的には過度のヘアケア、ブラッシング、ドライヤーのかけ過ぎでが誘因のことが多い。頭頂部に粗毛をきたすこともある。肉眼的に頭髪は乾燥し光沢に乏しく、頭皮から2~5cmのところに白色点状物が混在し、同部位で容易に切断される。誘因となるヘアケアを中止することで約半年で症状は改善する。
成人のアトピー性皮膚炎患者で、頭頂部の粗毛を見ることがあるが、頭皮の過度の掻破も同様の症状を起こすらしい。毛の一本一本を見るようにしよう。
-
成長期脱毛は、円形脱毛症、抗ガン剤や放射線による脱毛症、瘢痕性脱毛症に分類される。休止期脱毛症は、急性休止期脱毛症(出産・発熱・薬剤・体重減少)、慢性休止期脱毛症(パターン型脱毛症:男性型・女性型)に分類される。抗ガン剤による脱毛症はアントラサイクリン系(ダウノルビシン・ドキソルビシン)を含む多剤併用療法やタキサン系薬剤では必発。投与後2-3週間めから脱毛が始まり、抜け始めると4、5日で全体の70-80%が脱毛する。
パターン脱毛症という疾患名はmale pattern hair loss、female patern hair lossから派生した和名。成長期毛の抜け毛の先はゴボウ状に萎縮していて、休止期毛の抜け毛の先は毛根が丸くなってくっついているらしい。機会があれば顕微鏡で観察してみよう。
-
プロカルシトニン(PCT)は全身性細菌感染症で特異的に上昇し、重症度を反映し、立ち上がりもCRPより早いバイオマーカーだが、壊死性筋膜炎と蜂窩織炎の鑑別に有用かどうかを検討した。PCTの中央値は45例の蜂窩織炎では0.15ng/ml、17例の壊死性筋膜炎では40.9mg/mlであった。PCTのカットオフ値を5ng/mlとすると感度100%、特異度95%、陽性的中率92%、陰性的中率100%であり、両者の鑑別に有用だった。
開業医にも役に立つ報告である。PCTが5ng/ml以上であれば、入院を強く勧める根拠になる。ただし、EDTAで採血して3時間以内に測定する必要があるようだ。開業医は検査が外注なので、検体の取り扱いと何日後に結果が戻るかを確認しないといけない。
-
H.cinaediはグラム陰性らせん状桿菌で、免疫抑制患者の胃腸炎や菌血症の原因となる。76例の菌血症患者を検討したところ、30%に突然の発熱とともに四肢に複数の紅斑が生じていた。特徴は圧痛を伴う軽度のcellulitisであった。H.cinaediは通常の血液培養では検出に時間がかかる(平均5日間)ため、これらの皮膚病変がH.cinaedi菌血症の、診断の契機になる。
大事な感染症である。皮膚症状から菌血症を診断できれば、皮膚科医の存在意義も高まるだろう。覚えておかないといけない。最近では健常者で生じることも報告されている。なお、治療はアモキシシリンやドキシサイクリンでよいらしいが、再発が多いため、4週間以上の長期投与が必要とのこと。
-
低γグロブリン血症がある患者の臀部に生じた膿皮症。広範囲の潰瘍と疣状に盛り上がった多数の結節。皮膚生検の病理組織像は表皮の肥厚と真皮内の巨細胞、好酸球浸潤。核内封入体を有する細胞があり、免疫染色でHSV-1、HSV-2がともに陽性で、Herpes Vegetanstと診断した。AIDSや悪性リンパ腫に伴うことが知られている。
臨床からの診断はなかなか難しそうだ。皮膚生検を行うことが大事である。覚えておこう。
-
帯状疱疹で入院した146例(男性65例、女性81例)のうち、汎発型を呈した11例のリスクファクターを統計学的に検討した。その結果、血清アルブミン低値、リンパ球数低下、女性で頻度が高く、中でも血清アルブミンが4.0g/dL以下の症例では、オッズ比4.19で汎発化のリスクファクターであることがわかった。
高齢者でやせ形、低栄養の患者に多い傾向はあると思う。内服治療ですませてしまうことが多いのだが、採血によるチェックは必要だろう。
-
帯状疱疹の入院患者71例のうち24例(34%)に低ナトリウム血症(平均129.8mEq/l)を伴っていた。女性患者での比率が高く、CRP高値、高齢、汎発疹ありで頻度が高かったが、罹患部位、腎機能には関連がなかった。低ナトリウム血症が進行する症例が4例あり、いずれも抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)の診断基準を満たしていた。SIADHを疑ったら、尿量の測定(必ずしも減少しない)、血漿浸透圧の低下、尿浸透圧が比較的高い(100mOsm/kg以上)こと、尿中ナトリウム排泄量が多い(20mEq/日以上)ことを確認する。
SIADHの原因は、教科書的には脳神経系の疾患、肺疾患、薬剤(ビンクリスチン、カルバマゼピン、クロフィブラートなど)であるから、帯状疱疹による軽い髄膜炎が原因だろうとのこと。今後も調べてみる価値がありそうだ。
-
乳房外Paget病111名のうち、リンパ節転移、遠隔転移を生じた症例の腫瘍マーカーを検索した。それぞれのカットオフ値は、CEAが4.8、CA19-9が22.3、CA125が13.6、CA15-3が20.1、CYFRAが7.2であった。中でもCYFRAは、7.2をカットオフ値とすると感度90%、特異度96%で、良好だった。シフラはサイトケラチン19のフラグメントで、肺の非小細胞癌のマーカーとして保険収載されている。
シフラは細胞の破壊による逸脱ではなく,腫瘍細胞内のプロテアーゼ亢進に起因するサイトケラチンフラグメントの分解によるため、手術、化学療法、放射線療法による細胞傷害の影響を受けないとのとのこと。サイトケラチン19抗体による免疫染色では、正常な重層扁平上皮では、基底膜に限局して発現。上皮異形成や癌化の際は、異型細胞に強く発現するらしい。
-
抗体と抗原の結合力の総和をavidityとよぶ。通常のELISAキットの数値と、8M尿素やドデシル硫酸ナトリウムなどの抗原抗体間の化学結合を切断する薬剤を使用したあとの数値の比をavidity indexとする。各種の感染症において、感染初期では抗原と低親和性の抗体が産生され、のちに高親和性の抗体が産生される。例えば、VZV感染症で初感染(水痘)か帯状疱疹かを明らかにする場合は、結合力の低い初感染=水痘と、結合力の高い再発=帯状疱疹との判別が可能となる。
ELISAのキットを2回使用すればできる検査ということだが、実験室レベルで通常の臨床に使えそうもない。一応、覚えておこう。
-
近年0.005%次亜塩素酸浴(bleach bath)を10分間行うことによってアトピー性皮膚炎の重症度が改善するとした複数個の論文のsystematic reviewがある。5本のうち4本の論文ではいずれかの時点でアトピー性皮膚炎の重症度がこれによって改善した。しかし対象とした通常の入浴との間で明らかに優位性が高かったのは2本の論文にすぎなかった。アトピー性皮膚炎には様々な標準外の治療があるが、引用された論文の対象や方法が正しければそのデータを信頼し個別化医療として実践してもよいが、結局信用するに値するのは大規模なランダム化比較試験である。
ちなみにこのレビューで対象とした論文では、黄色ブ菌の減少に関してbleach bathの方が通常の入浴より優るとしたものはなかったとのこと。患者に勧めるのは難しそうだ。
-
災害医療ACT研究所による研修会で聞いた話。災害時に医療拠点を立ち上げ、活動を開始する際に行うべきこと。Hellow(カウンターパートへの挨拶)、Location(本部の場所の確保)、Part(初期本部部員の役割分担)、Safety(安全確保)、Communication(通信手段の確保)、Report and Record(上位本部への報告と記録)、Equipment(機材の確保)、Assessment(状況把握)、Map(地図)。
2日間の研修と訓練を受けたが、現場が混乱する状況を身近に体験できた。災害医療では色々な頭文字を合わせた用語が出てくるが、すぐ忘れる。
-
1) Treponema pallidumは感染数時間後に血管・リンパ管を介して全身に広がる。この時期の血液には感染力がある。2) 潜伏梅毒の診断はTPHAが陽性でRPRが16倍以上のものであり、全例届出が必要。3) 神経梅毒は1期、2期でも起こる。治療していてもRPRが4倍より下がらなければ髄液検査を行う。3) 自動化によるTPLAはTPHAやRPRより先に上昇する(
感染7日後で30%、感染11日後で100%)。偽陽性として取り扱わないように注意。4) 神経梅毒は、内服治療では不十分でベンジルペニシリンカリウム(ペニシリンG)1回300~400万単位を1日6回点滴静注する。5) Jarisch-Herxheimer反応は投与1~4時間後から出現し始め、24時間で軽快する。
梅毒に関しては知っていそうで知らないことがある。通常行っているAMPC1500mg/日の内服が国際的に認められている治療ではないことは以前に聞いて驚いた。なお、当院が提出している検査会社では、TPHA定量をオーダーするとこれまで通りの希釈法を行って、TPTPHA定性をオーダーすると自動化のTPLAを行うということだった。
-
小児アレルギー学会が行ったアンケート結果の報告。患者 (保護者) の受診行動および小児科医と皮膚科医の連携について検討した。皮膚科医へ紹介したことのある小児科医は61.5%で、その理由は皮膚症状の悪化、他の皮膚疾患合併であった。反対に皮膚科医から紹介を受けたことがある小児科医は49.5%で、その理由は家族の希望、自院でできないアレルギー検査の依頼、他のアレルギー疾患の合併、成長障害・発達障害・自閉症であった。連携は重要であるが、どのような場合に連携をとるべきかの明確な基準についての記載をガイドラインで定めていくことが望まれる。
各々に紹介が必要とする基準を定めることは難しそうだが、当然ながら皮膚科医、小児科アレルギー専門医、それぞれの得意とする臨床経験をひとりひとりの患児に還元していくのが必要だ。こういった他科との連携の会は大切である
-
高齢者施設において、MRSA保菌者への対応が混乱している状況があり、広島県地域保健対策協議会が示した対応の目安が紹介された。1) 施設内での標準予防策(standard precautions)を実施する。2) 手指衛生については70%以上のアルコールを含有する消毒製剤を使用。3) 保菌がわかっている患者では、隔離までは必要ないが、コホーティング(同室配置)で対処する。4)回診・処置は保菌者を最後に行う。5) 褥瘡にMRSAが確認されている場合は処置の際に手袋を着用し、処置のあとには必ず手洗いを行う。MRSA保菌が確認されている患部はドレッシング材で覆う。6) 一律のガウンテクニックは必要ないが、処置の際に滲出液が飛び散ることが予想されるときはビニールエプロンを用いる。7) リネンは通常の洗濯・乾燥でよい。8) 病室の清掃・換気は通常通りでよい。9) 保菌者の手が頻繁に触れるところ(ベッド柵・ドアノブなど)は定期的(1~2回/日)に消毒用アルコールか中性洗剤で拭き取る。10) 保菌者に対する除菌は不必要、など。
MRSA保菌に関して若干軽視していたようだ。概ね同意できる内容である。他職種との連携のために、こういう指針があることを一応知っておく必要があると思った。
-
Boston exanthemaはEcho16ウイルスによる感染症で、本邦では1984年に岐阜県の笠原町で集団発生し、その詳細が報告されている。発熱が初発症状で、38~39℃が最も多いが、時に39~40℃に及ぶ例もある。熱発後2~3日経過して解熱する頃になり、発疹が出現する。発疹は突発性発疹に類似し、以下のような経過をたどる。Stage I(1~3日):頬部に対称的にまたは顔と四肢に丘疹を伴う紅斑が生じる。紅斑のみまたは数個の比較的大きい丘疹のみで、四肢は伸側に多い。躯幹には細かい丘疹が時に認められ、上胸部、上背部に強い。Stage II(2~4日):頬部、前腕、下腿に紅斑性丘疹が次第に増強する。躯幹の丘疹は消褪傾向となる。Stage III(3~5日):四肢の発疹が消退し始めるが、顔の引き方は比較的遅い。Stage IV(4~8日):顔の紅斑、丘疹も消褪していく。臨床検査成績では白血球減少を病初期に認めることが多い。
砂かぶれ様皮膚炎と同様に忘れ去られた疾患。ジアノッティーにも似ているが、経過はもっと短いようだ。これまでもみてきたかも知れないが、Echo16に注目したことはないので、今後検討してみたい。
-
ヒトパレコウイルス(HPeV)はエンテロウイルスやライノウイルスと同じピコルナウイルス科に分類されるウイルスで、1~16型の血清型/遺伝子型が報告されており、中でもHPeV-1~8型に関する報告が多い。HPeV-1、2、4~8は軽度の胃腸炎症状や上気道炎症状を呈することが多いが, 不顕性感染も多く、学童期の抗体保有率は80%を超えるとされている。その一方で、HPeV-3は生後3か月未満の新生児・早期乳児のsepsis-like syndromeや脳炎の原因となり、重症化することもあり、2014年以降、増加傾向である。典型的な症例は、高熱、頻脈、末梢循環不全で発症し、80%の症例で掌蹠に一過性の紅斑を伴う。紅斑は熱発後1~5日後に生じ、2~7日後に消失する。白血球数やCRPなどの炎症マーカーは正常範囲内であることが多い。
知らなかった。HPeV-3を皮膚科でみることはなさそうだが、掌蹠の紅斑で来院した小児に、軽症の胃腸炎や上気道炎を伴っていたら、疑わなくてはならない感染症なのかも知れないと思った。ちなみに検査はリアルタイムPCR法による微生物迅速診断しかないようだ。
-
VZVに対する抗体は帯状疱疹の痛みに関与する脳由来神経栄養因子(BDNF)と同様の作用があり、さらにVZVの抗体はBDNFの作用を増強することも知られている。VZVの抗体(IE-62)をマウスに投与すると痛覚過敏を生じることから、産生されたVZVに対する抗体によりBDNFの働きが高まり、痛覚に関連する脊髄の神経細胞を活性化させ、痛みが生じることがわかった。CF抗体価の値と痛みには関連があり、発疹を生じない痛みだけの帯状疱疹の患者でも、CF抗体価は16倍ぐらいに上昇することが多い。
片側性の痛みだけで来院する患者の対応は迷うことが多く、抗ウイルス薬の内服を見切り発車するか様子を見るかは患者に選択してもらうことが多い。CFも含めて抗体の変動はみておく必要があると思うが、発疹が出なかった帯状疱疹と確定診断できたことはないような気がする。
-
妊娠中に水痘に罹患すると胎児ないし生まれてくる子どもはどうなるかのまとめ。妊娠20週までだと、流産や先天性水痘症候群になるおそれがある。妊娠中期だと、生まれてくる児が乳児期早期で帯状疱疹を発症する。分娩5日前から分娩直前だと、児が重症の水痘を新生児期に発症する。ちなみに、妊婦がVZVに初感染する頻度は1,000人にひとりでまれ。先天性水痘症候群(CVS)は水痘罹患妊婦から2%の頻度で発症。症状は発達遅滞を伴う種々の神経障害、四肢の頭頸部や四肢躯幹の片側性の萎縮性瘢痕などの多発先天奇形である。
妊娠中期に罹患すると、児が胎内でVZVに感染し、VZVは脊髄神経節に潜伏し、母体からの移行抗体が児の血清中から消失し始める生後4カ月前後から帯状疱疹を発症するという機序が考えられている。
-
IgG4陽性形質細胞が皮膚に浸潤する、あるいはIgG4が皮膚に沈着する疾患をIgG4関連皮膚疾患と呼ぶ。その分類は(1)皮膚形質細胞増多症、(2)偽リンパ腫/木村病、(3)Mikulicz病、(4)乾癬様皮疹、(5)非特異的紅斑丘疹、(6)高γグロブリン血症性紫斑/蕁麻疹様血管炎、(7)虚血指趾。(1)~(3)はIgG4陽性形質細胞は病変部に多数浸潤する「原発疹」で、(4)~(7)はIgG4陽性形質細胞あるいはIgG4による炎症自体が間接的に病変を導く「続発疹」である。
眼瞼の腫脹が主訴の患者ではMikulicz病の鑑別が必要で、IgA血管炎類似の病変ではIgG4関連疾患による高γグロブリン血症性紫斑である可能性があるとのこと。見落としているかもしれないと思った。
-
下肢静脈瘤の外科的治療は、これまではストリッピング術が主流であったが、2011年から波長980nmの血管内レーザー治療による保険診療が適応になった。ストリッピング術より侵襲で術後すぐから歩行が可能で、疼痛や出血も少ない。抗凝固薬内服中でも施術可能。麻酔はエコーガイド下の大量局所浸潤麻酔が一般的。適応は伏在静脈に弁不全を有する一次性の静脈瘤で、深部静脈が開存している症例。径が4mmから10mmぐらいが最適。起始部に大きな瘤があったり、蛇行や器質化が強い場合は適応になりにくく、従来通りのストリッピングが行われる。
具体的な手技を見せてもらってわかりやすかった。外来で日帰り手術ができるようになったことは喜ばしいことだ。いずれにしても血管エコーの習熟が大事なのだが上達できない。
-
悪性リンパ腫の分類はWHOが定期的に改訂を行っているが、2016年の改訂では皮膚という臓器を特別扱いせず、全身あるいは他の臓器と統一した分類に当てはめることになった。例えばMALTリンパ腫は、他の部位に生じるMALTリンパ腫の免疫グロブリンがIgMが多いのに対し、IgGが90%を占める、さらに皮膚のMALTリンパ腫は他の臓器のMALTリンパ腫に対してきわめて予後がよいという特徴があるのだが、今回の分類では独立した疾患とは認められなかった。
分類のたびに新しい疾患概念が生まれて来る。治療に関しても新薬の開発のスピードが速く、まったくついて行けなくなった。この領域は深追いせず、大学病院に任せた方がよさそうだ。
-
分布が片側に偏る病変、Blaschko線に沿って出現する病変は母斑や母斑症だけでなく炎症性疾患や変性疾患でも遺伝的なモザイクが隠れている。ケラチノサイトに遺伝的なモザイクがあると、性質の異なるケラチノサイトの分布がBlaschko線という模様になる。メラノサイトにモザイクがあると左右に分かれる模様が生じ、チェッカーボードパターンになる。これらは生下時から見えているとは限らず、疾患が発症した時にあぶり出しのように現れることがあり、superinposeと呼ばれている。扁平苔癬、DLE、尋常性乾癬などでみる機会が多い。
ちょっと難しいが、新しい視点で勉強になった。分布が偏っている疾患はそれなりの理由付けを考えないといけない。以前に報告した化膿性汗腺炎の患者も演者の先生にたぶんモザイクと指摘された。まったく考えが及ばなかったので、感心した。
-
アレルギー性炎症の中心的な役割を担うTh2型サイトカインはIL-4とIL-13である。表皮細胞や気道上皮細胞においてIL-13が誘導する遺伝子に、ペリオスチンとSCC抗原(SCCA:扁平上皮細胞癌抗原)があり、アトピー性皮膚炎の診断、重症度、予後の予測、治療薬の反応性予測、再発の危険度などのバイオマーカーになりうる。血清ペリオスチンが高値(≧50ng/ml)の群では、ヒト化抗IL-4受容体α鎖(IL-4Rα)抗体であるdupilumabの効果が高いことが示された。
dupilimabがアトピー性皮膚炎の治療薬として承認されるが、どういった患者に使用するべきかが問題だと思っていた。ペリオスチンやSCCAが高値の患者を対象にするのがよいかも知れないと思った。なお、小児ではTARCとペリオスチンがもともと高値で、患児との差がつきにくいが、SCCAはしっかりと差がつくとのこと。
-
腋窩多汗症に対するボトックス、AGAに対するPRP(多血小板血漿)の局注に有用な医療材料の紹介。31Gと34Gがあり、針の根元がプラスチックのシールドで覆われているため、刺入の深さをそれぞれ1.5mm、2.5㎜、3.5㎜から選択できる。腋窩多汗症には34Gの1.5㎜ないし2.5㎜、AGAには31Gの3.5㎜がよい。刺入の深さが一定になることで、手技が簡単になり、疼痛も軽減できる。
これは知らなかった。腋窩多汗症のボトックス皮内注射では、たまに深く刺さってしまうことを経験する。高そうだが、よさそうである。
-
高齢者の難治性の痒みに対しては、根本的な原因の確定と是正を試みる必要があるが、基礎疾患治療薬の変更や、外用薬を塗布すること自体が難しい状況がある。実践的な治療として、ステロイド軟膏、抗ヒスタミン薬の標準治療に加えて、PSL 5mg/日の併用が有用な場合が多い。PSL 5mg/日の内服はvery strong クラスのステロイド軟膏を20g外用した時の全身への影響と同様と想定されている。
一度始めたら、なかなかやめられないという感じがあるが、患者のQOLを重視すればステロイド内服も有用かと思う。判断が難しい。
-
血液透析のための内シャントを前腕に増設した患者の拇指に生じる発赤、腫脹。疼痛を伴い、潰瘍を形成することもある。シャントの上流に閉塞が生じ、シャントの静脈を介して動脈血が流入する分枝があることを血管造影で確認した。シャントより末梢の手背や指背側の皮静脈の動脈性の拍動も重要な臨床症状である。治療は皮静脈の結紮が必要。
通常拇指に生じるが、それ以外の指にも生じることがあるようだ。shunt steal syndoromeと同様に静脈の高血圧が原因である。経験はないが、名前は覚えておこう。
-
液体が充填されているスマホケースがあり、それが漏れてchemical burnを負った症例が国民生活センターから5件報告された。5件すべてが10~20歳代の女性で、大腿、肩、腹部などに生じていた。キラキラとしたホログラムが液体中に浮いているタイプで、原因は揮発性の炭化水素類であった。
流行とはいえ、液体入りのケースがあるとは知らなかった。寝ながらスマホで、顔にかかったら大変だっただろう。最近ではオンラインから報告できるPIO-NETからの苦情が多いとのこと。
-
陥入爪は爪の切り方、不適合な靴、遺伝などの要因のほか、足関節背屈角の低下、膝内側傾斜歩行、第1趾可動域低下、下肢筋力低下、体幹筋力低下、体幹側方傾斜歩行などの筋骨格系の異常がある場合が少なくない。局所治療に加え、ストレッチや筋力アップの運動指導が功を奏することもある。
専門的な知識を有する理学療法士がいないとできない。診療報酬で評価されない現状では浸透は難しいが、皮膚科とPTの連携という観点からは注目すべき方向だと思う
-
グンゼのインナー用の生地素材、メディキュアの話題。木綿とレーヨンで構成し、縫い目がなくゴムを使用せず、生地のほつれが起こらない素材。乾燥型の皮膚炎に使用したところ、4週間後に皮膚病変の重症度、経表皮水分蒸散量、痒みのVAS、DLQIが改善した。日常のスキンケアのほかに肌着の選択も必要である。
当院では、四肢の病変に対して以前からチュビファーストを好んで使用してきた。肌着としての機能よりは掻破行動の防止を主たる目的としているのだが、今後、比較してみようと思う。
-
熊本地震の支援を経験し、被災地での支援のあり方を検討した。1)地域の支援を統括している組織に挨拶に行く。2)衣食住は自己完結で持って行った物と現地で調達した物を使用。3)余っていても支援物資には手を出さない。4)被災前の医療水準を超える行為は行わない。5)被災地外からの人・物への対応は被災地外の者が行う。
発災直後の医療支援はDMATに頼ることになるが、DMATも病院支援、広域医療搬送などのほか、いわゆる保健衛生業務に関わることになるようだ。平成28年にしっかりした避難所運営ガイドラインおよび福祉避難所運営ガイドラインが定まり、チェックシートが用意されたので、確認しておくとよい。
-
1)強皮症腎クリーゼ(SRC)高血圧を伴った乏尿性腎不全で発症し、急性尿細管壊死と高レニン血症を呈する。腎不全は強皮症の4~10%にみられ、週~月単位で急速に進行し、透析導入に至ることが多い。抗RNAポリメラーゼⅢ抗体と関連が深い。2)血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)破砕赤血球、貧血、血小板減少を主症状とする微小血管障害性溶血性貧血の所見を呈するTTP様病態を認めることがある。3)顕微鏡的多発血管炎(mPA)経過中にMPO-ANCA陽性の腎障害と肺胞出血が見られる症例があり、予後不良である。
TTP類縁疾患を伴うというのは知らなかった。報告された症例は抗トポイソメラーゼI抗体陽性で、長期間にわたり多量の胸水と腹水が持続し、Meigs syndromeを呈していたというが、卵巣の病変はなかったとのこと。
-
30歳代女性のDLEに対して、HCQを400mg/日で開始。17日目に薬疹が生じた。薬疹はHCQを中止し加療で改善。DLEに対してHCQが有用だったため、HCQの減感作を試みた。2mg/日から再開、22日かけて200mgへと増量できた。
HCQの薬疹はかなり頻度が高く、治療を継続したい場合の妨げになるが、少量か漸増すると克服できる例もあるようだ。HCQによる薬疹はアレルギー性ではない可能性もあるらしい。
-
皮膚型の結節性多発動脈炎の治療は、弾性包帯、弾性ストッキングの着用が有用である。血管内の血流が改善し、圧迫によって内皮細胞から抗血栓作用と線溶促進作用のあるtPA、NOなどの分泌が増えることが想定される。
動脈炎でも弾性包帯かと思ったが、確かに改善し、よい様態を維持できているようだ。さっそく試してみよう。
-
血栓性動脈炎は筋層が不規則束状で隙間があり、弾性線維に挟まれる。血管壁の弾性線維は豊富で内弾性板は認めない。筋層のフィブリノイド変性は少なく血栓は血管腔の中央に好発する。それに対し動脈炎では筋層は連続性で同心円状で隙間なく密に配列する。血管壁の弾性線維は乏しく、内弾性板のみがはっきりしている。筋層のフィブリノイド変性があり、血栓も内膜に面した血管腔側に好発する。下腿の静脈炎では内膜に生じた弾性線維が動脈の内弾性板と間違えられ、多発性浅在性静脈炎を結節性多発動脈炎に誤診されやすい。
HEに加え、Elastica-von Gieson染色が必須。言葉ではイメージが伝わりにくいが、標本をみると納得する。覚えておかないといけない。
-
3年間アトルバスタチンを内服中の50歳代女性に生じた皮膚筋炎。顔面や手指の紅斑、爪上皮の所見など皮膚症状は典型。両上腕の筋力低下があるがCKの上昇はなく、ALDが軽度上昇。間質性肺炎はなく、悪性腫瘍もなし。アトルバスタチンを中止後には筋症状は改善しALDも低下。皮膚症状にはDDSが有効であった。スタチン誘発性の皮膚筋炎と診断した。
スタチンによる薬剤介在性壊死性ミオパチーという疾患概念がある。嚥下障害を伴う例が多く、筋外症状として皮膚筋炎と同様の皮膚病変を伴うことがある。診断にはシグナル認識粒子(signal recognition particle, SRP)に対する自己抗体と、3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase(HMGCR)に対する自己抗体の測定が重要。保険収載はないがコマーシャルベースで検索可能とのこと。貴重な報告だった。
-
汗疹を生検すると、汗管の中にPAS染色陽性の無構造物質がある。表皮ブドウ球菌などの常在菌が汗管の中でバイオフィルムを作り、汗が汗管の外に漏れて炎症を生じる。1967年の報告では、ラップを貼り汗疹を誘発すると、その部位はその後の1週間は発汗がなくなり、3週間後にようやく回復したという。
汗疹はなかなか診断が難しい。典型疹を生検する機会もないので自分の目で病理組織を確かめたことがない。アトピー性皮膚炎でも汗管の外に汗が漏れて炎症を生じ、湿疹の悪化因子になると聴いたことがあるが、アトピー性皮膚炎でも汗疹と同様にしばらくは無汗になるのだろうか。
-
ほ乳類としてのヒトは、体毛で覆われていないため発汗によって恒温性を保つのだが、発汗のピークは12歳で、それ以降は徐々に減っていく。発汗が減る部位には順番があり、まず下肢から始まり、体幹後面、体幹前面、上肢、頭と減っていく。熱帯にすむヒトは発汗量が少ないが、寒冷地に住むヒトより汗をかく時間が長いことが知られている。
高齢になれば、乾皮症がまず下腿伸側に生じるという、ちゃんとした理論があったということ。なお、全身毛むくじゃらのイヌは汗をかかない代わりに、ハーハーと息を出して体温を下げている。多毛のヒトは発汗が少ないかどうか、ふと思った。
-
バチェラー・オブシューフィッティングの講義で聞いた、革靴が足に合っているかのチェックポイント。①踵はぴったりか(2~3mm)。②幅はきつくないか。締め付けても伸びる皮(ボール革)なら大丈夫。③つま先の捨て寸は1㎝以上あるか。母趾が上下に動くか。④足の甲の締め付けががないか。⑤マーチラインが合っているか。⑥トップラインが合っているか。
革靴の先端は型くずれを防ぐために芯が入っているので、足になじまないことが多いそうだ。革靴のチェックまでは仕事ではないが、コメディカルには知識として伝えておくことにする。
-
左外頸静脈の怒張とその周囲の丘疹状の毛細血管拡張が30年前から続いているという60歳代の女性。造影CTで外頸静脈の起始部に狭窄があり、胸郭出口症候群と診断した。胸郭出口症候群は一般的になで肩の中年女性に多く、肩を持ち上げる筋力が減少していることに起因し、前腕や手のしびれ、血行障害を来す疾患であるが、血管拡張を主訴に皮膚科を受診することはまれである。
長期間静脈の怒張が続くと、周囲に丘疹状の毛細血管拡張が生じるというところが面白い。それにしても怒張というのは不思議な用語だと以前から思っているのだが、誰が使い始めたのだろうか。
-
電撃傷は電流が組織を通過するために生じる損傷で、①通過する際に生じた熱により血管や神経、筋肉が損傷されるtrue electric injury、②電源に近接しアーク放電が起こり、そのスパーク熱により起きる損傷であるarc burn、③アーク放電やスパークの際に衣服などに引火炎上することで生じる熱傷であるflame burnの3つに分類される。電流が心臓を通過する際に生じる心室細動による心停止、筋や軟部組織の損傷で生じたミオグロビンによる急性腎不全、中枢神経に通電した際の呼吸筋麻痺など、急を要する合併症がある。
日本では発電された電気が配電用変電所で6,600Vにまで下げられて電柱や地中線を通して配電され、最終的には変圧器で100、200Vになって工場や一般家庭に配電されているが、この6,600Vの電線に触れておこる電気工事関連の事故が最も多いらしい。救急対応についてもたいへん勉強になった。
-
アレルギー性鼻炎と鑑別が必要な疾患がある。old man's dropは温かいものを鼻から吸引すると鼻漏が生じるもので、冬季に多く、鼻粘膜を温めておけば改善するため長期の抗ヒスタミン薬は必要がない。local allergic rhinaits(LAR)は局所に限局するアレルギー性鼻炎で特異的IgE抗体は陰性。通常のアレルギー性鼻炎になる可能性はあるが、一時的な血管運動性鼻炎として収束することもあるので、長期のフォローアップが必要になる。
old man's dropとは粋な症状名だと思った。確かにアレルギー性鼻炎だと思っている患者がありそうなので、鼻粘膜を温めるという指導をしてみよう。
-
体圧を常時測定しながら最適な内圧に自動調整するマットレスを開発した。体圧分散を妨げない体圧センサと最適な内圧調整アルゴリズムを開発し、臨床で求められる機能を持ったロボテックマットレス、LEIOS(molten)が完成した。搭載された機能は、①自動体圧調整、②自動背抜き、③睡眠状態モニタリング、④体位変換支援、⑤体動モニタリング。
産学協同で10年がかりだったそうだが、熱意があれば実現するということ。皮膚科ももっと理工学の専門家と一緒にできることがないか検討すれば、新しい領域に一歩踏み出すことができるような気がしているのだが。
-
collagen di-peptideを10g含有するゼリータイプの栄養剤。褥瘡患者に使用したところ、コントロールと比べDesignの改善が有意に高かった。総蛋白量などの生化学的検査では変動なし。褥瘡患者の栄養剤として補助的に用るとよい。
ペプチドであるということが、いわゆる栄養剤としてのコラーゲンとの違いらしい。評価が難しい領域ではあるが、説得力があった
-
額、上眼瞼、眉間、鼻、両頬に生じるnon-pitting edemaで、酒さの合併症と考えられている。自覚症状はないが、上眼瞼に生じた場合は視野狭窄をきたすことがある。リンパ浮腫に端を発する慢性の炎症で、病理組織学的にも肉芽腫性炎症を示す。肥満細胞の増加も指摘されていて、治療はミノサイクリンの長期投与が比較的有効である。
浮腫結合性肉芽腫、肉芽腫性眼瞼炎と診断してきた疾患のようだ。一応、名前だけは覚えておこう。
-
telangiectatic photoaging(TP)と毛細血管拡張性酒さとは区別されるべきである。酒さではflashingがあり、血管拡張はやや少なめである。TPはflashingがなく、紫外線による皮膚萎縮、色素斑、脱色素斑を伴う。病理組織でも光線によるダメージが強く現れ、MMP-3の遺伝子発現が酒さに比べて1/4程度と低い。
確かに、顔面に毛細血管拡張だけがあり、ステロイド外用の副作用かと思った患者で外用歴がない患者がある。炎症もないので、酒さとは違う診断をつけることに賛同したい。
-
症状が落ち着いている成人アトピー性皮膚炎患者に対し、P群(アンテベート軟膏週2回、1日2回外用+保湿剤を連日1日2回外用)とC群(保湿剤連日1日2回外用)に分け、治療開始8週後の皮膚症状スコア、VAS、DLQIで評価した。P群はいずれも改善、C群ではいずれも悪化した。両群の炎症収束維持率を比較検討したところ、P群はC群に比べて有意に高く、約70%の症例で60日以上維持しえた。
炎症収束維持率とは、一群の中で症状の悪化がなく、現状維持が続いている人数の割合とのことで、再発率の裏返しということ。初めて聞いた言葉だった。ちなみに、タクロリムスのproactiveは納得がいくが、ステロイド軟膏のproactiveは何となく不安である。
-
50歳代女性。左前腕にblaschko線に沿って線状に連なる扁平苔癬。薬剤の内服歴はなし。金属パッチテストでニッケルとコバルトが陽性。歯科治療後のクラウンあり。インタールの内服を開始したところ、発疹は消失した。
全身性金属アレルギーが病態として深く関わっている皮膚疾患にインタール内服が有効な場合があることを思い出した。今度使ってみよう。
-
マウス、ラットなどの動物を扱う実験助手に生じる即時型アレルギーをLAAと呼ぶ。40歳代女性で勤務歴は1年。既往歴はないがマウス咬創後に全身に膨疹が出現し、咳嗽を伴った。マウスの特異的IgE抗体陽性、ラット唾液のプリックテスト陽性。LAAは多くの症例が勤務歴3年以内に発症している。アナフィラキシー、蕁麻疹のほか、結膜炎、鼻炎、喘息など症状は多岐にわたる。労働衛生上の管理が必要である。各動物の主要なアレルゲンは以下の通り。マウス:Mus m 1 (prealbumin)/尿・毛・フケ、ラット:Rat n 1A (alpha-2 globulin)/尿・毛・フケ、モルモット:Cav p 1/毛・フケ・尿、ウサギ:Ory c 1/毛・フケ・唾液、ネコ:Fel d 1/毛・フケ・唾液、イヌ:Can f 1/毛・フケ・唾液
lipocalinという、疎水性の脂質などを輸送する糖タンパクが多くの動物アレルギーで関連しているらしい
-
凝固活性化のマーカーは以下の通り。1) トロンビン-アンチトロンビン複合体(TAT):凝固活性化の結果として最終的に産生されるトロンビンの産生量を反映するマーカー。トロンビンとその代表的な阻止因子であるアンチトロンビン(AT)が1:1結合したもの。2) プロトロンビンフラグメント1+2(F1+2):プロトロンビンからトロンビンに転換する際に、プロトロンビンから遊離するペプチド。TATよりもartifactが出にくい。ワルファリンの効果判定に用いることができる。3) 可溶性フィブリン(SF):フィブリノゲンからフィブリンに転換する過程で形成される中間産物。新規経口抗凝固薬(NOAC)の効果判定マーカーとして期待されている。4) Dダイマー:(DD):血栓(安定化フィブリン)が形成されてそれが溶解するとDDが血中に出現する。したがって、DDの高値は血栓が既に形成され、かつ溶解したということを意味する。上記の検査に比べartifactが全く出ない。線溶活性化のマーカーは以下の通り。5) プラスミン-α2プラスミンインヒビター複合体(PIC):線溶活性化に伴い産生される最終的な酵素であるプラスミンがα2PIと結合して生じる。PICの測定によってDICの病型を分類することができる。
呈示された症例は悪性腫瘍に伴うnodular migratory panniculitisで、凝固・線溶の亢進が証明された。下腿の血栓性静脈炎は皮膚科で診ることもまれではないし、慢性蕁麻疹でDDの上昇があるという報告もあるので、このあたりの病態生理学は、もう一回勉強しておかないといけない。
-
多発性骨髄腫の化学療法に続発した好中球減少症に対して使用したレノグラスチム(ノイトロジン)投与12日目から、顔面に丘疹が生じた。その後四肢にも同様の病変が出現し、8mm大までの充実性で硬く触れる結節となり、一部は潰瘍を形成した。病理組織学的に真皮の浅層から中層にかけて密な好中球浸潤があり、血管壁のフィブリノイド変性を伴った。レノグラスチムの中止で個疹は扁平化して治癒した。
造血幹細胞を末梢血中に動員し、好中球を増殖させるという薬理作用なので当然かもしれないが、血管炎、好中球性紅斑は副作用として添付文書に記載されている。臨床的には持久性隆起性紅斑に近いと思ったが、治癒後の瘢痕形成は目立たなかったようだ。
-
30歳台の女性、屋外のプール、温泉に入ると、水に浸かったところだけに膨疹が出現するようになった。膨疹は水からあがって30分で自然消褪する。花粉症やアトピー性皮膚炎はなし。寒冷刺激(アイスキューブ)では誘発できず、常温の生食水、水道水の貼付で膨疹出現。10分間の上腕水浴試験で、20℃で膨疹とかゆみ、41℃でかゆみが誘発された。水蕁麻疹と診断した。
30年近く皮膚科医をしているが、水蕁麻疹と診断した例はまだない。おそらくあったのだと思うが、温熱蕁麻疹や寒冷蕁麻疹と診断していると思う。ほかの物理性蕁麻疹を否定するのが難しそうなので、アプローチの方法は参考になった。
-
保管が不良でダニが繁殖してしまった小麦粉やミックス粉などを用いたお好み焼きなどの摂食後に生じる即時型アレルギーを、パンケーキ症候群と呼ぶことになった。国外の症例が、2009年にPancake Syndrome(Oral Mite Anaphylaxis)として報告されている。
いつもまにかそういう疾患名になっていた。日本ではパンケーキというよりはお好み焼きやたこ焼きで生じているというイメージが強い。消化器症状や呼吸器症状などの全身症状を伴うのでよいのかもしれないが、症候群と呼ぶのも若干違和感がある。
-
成人アトピー性皮膚炎患者を経皮悪化因子(金属・市販品などによる皮膚炎の増悪)の有無、経口悪化因子(食物摂取後の口腔症状の出現や痒みの増悪)の有無で4群に分類するという試み。質問票による集計で、いずれも7割の患者が悪化因子ありと回答した。群間の比較では経皮悪化因子あり+経口悪化因子なしのグループで、血清中IgE値が低かった。また、経口悪化因子でかゆみの増強があるサブグループで、カンジダに対する特異的IgEが下腿経口があった。
経皮あり、経口なしはいわゆる内因性アトピー性皮膚炎か。経口悪化因子があって皮膚のかゆみが増強する群にカンジダ特異的IgEga陽性が多いというのは、ちょっと意外に思うが、どういう理由か興味がある。
-
梅毒を治療せず、放置することで生じる結果についての検討。40年の長期観察の結果、399人の末期梅毒患者のうち、梅毒が原因の直接死亡が28人(7%)、梅毒の合併症での死亡が100人(25%)、パートナーへの感染が40人(10%)、期間中出生した40人の新生児のうち、先天梅毒が19人(48%)であった。
ということで、これはアメリカ合衆国公衆衛生局が1932年から40年にわたってアラバマ州で行った悪名高い人種差別的疾病人体実験であった。生命倫理上の重大事件として、知っておく必要がある。ちなみにクリントン大統領が1997年に被害者に対して正式な謝罪を行ったとのこと
-
ユリウス・ワーグナー-ヤウレックは1857年生まれのオーストリア人の医師で、専門は精神科および神経病理学。1927年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。その受賞理由は「麻痺性痴呆に対するマラリア接種の治療効果の発見」。当時、発症するとその60%が死に至っていた神経梅毒に対して、三日熱マラリアの原虫を接種し、42℃の発熱を誘発し、トレポネーマを死滅させる治療法を実践した。
これは知らなかった。100年前の医学・医療には驚くような視点がある。たまにはこういう話もためになって、ありがたい
-
症例は多発性骨髄腫由来の全身性アミロイドーシス。DFS(ダイレクトファーストスカーレット)染色で、前腕の紫斑からの皮膚生検でアミロイドの沈着が証明された。皮膚のアミロイドーシス、特にケラチン由来のアミロイドはCongo-red染色では強い陽性像が得られにくいため、DFS染色を行うとよい。
特殊な染色法も時々refleshしないと忘れる。ダイロン染色というのが以前はあったが、今はやらなくなったようだ。
-
抗リン脂質抗体症候群で血液透析中の患者。透析開始1カ月後から全身に紅斑が出現し、紅皮症状態となる。sIL-2Rは7,780と上昇。原因としてはダイアライザー(FDX150)から溶出するPVP(ポリビニルピロリドン)あるいは、BPA(ビスフェノールA)が原因と考えられた。
そういった化学物質が溶出している場合があるとは知らなかった。BSAはエポキシ樹脂の原料になるらしいので、エポキシ糊の接触皮膚炎の既往を確かめる必要がある。ちなみに血中のBPAを測定すると、透析患者では高値の場合があるようだ。
-
米国褥瘡諮問委員会(National Pressure Ulcer Advisory Panel:NPUAP)は2016年4月から、褥瘡にあたる用語をPressure UlcerをPressure Injuryに変更した。また、Deep Tissue Injury(DTI)をDeep Tissue Pressure Injury(DTPI)に変更し、Medical Divice Relatied Pressure Injury(MDRPI)、Mucosal Membrane Pressure Injury(MMPI)も付属的な褥瘡として新たに加えられた。
どうも用語は米国主導のようだ。潰瘍になる前の段階の褥瘡もあるので、Injuryの方が現実的ではある。
-
亜鉛欠乏があると創傷治癒が遷延し、亜鉛の投与によって改善することがある。高齢者の常用薬の中には、亜鉛とキレートを形成し、消化管からの亜鉛吸収を阻害するものがある(レボドパ、ニトラゼパム、ベラパミル、フロセミド、エナラプリル、ジルチアゼム、アムロジピン、アロプリノール、メトクロプラミド、アルファカルシドール、レボチロキシンNa、L-グルタミン、ペニシラミン)。19名の褥瘡の患者で、これらの薬剤の服用数と褥瘡の治癒までの期間を検討したところ、正の相関がみられた。薬剤の変更を考慮する必要がある。
これはなかなか面白い。カルシウム拮抗薬などは褥瘡患者で内服している頻度も少なくないと思われる。今後は、併用薬に注意して、血中亜鉛の測定も考慮したい。
-
回復期リハと療養型病棟に新規に入院した168人の患者。ほとんどが急性期病院を含む他院からの紹介。入院時の血中亜鉛濃度を検討した。正常値は80μg/dlだが、全患者の72%が低値で、全症例の平均は70.1μg/dlだった。また褥瘡があった11例では62.2μg/dl、スキンテアがある16例では55.2μg/dlと低値であった。
亜鉛の補正でスキンテアも改善したらしい。ちなみに、低亜鉛血症にはプロマック内服を行ってきたが、ウィルソン病治療薬のノベルジンという薬剤が2017年3月から低亜鉛血症治療薬として追加承認されたので、試してみようと思う。
-
IAD(Incontinence Assosiated Dermatitis)とは、失禁関連皮膚障害で、慢性的あるいはくり返し尿・便が曝露されることによって生じる外陰部、肛囲、臀部の皮膚病変をさす、看護学用語。本邦の高齢者ではその有病率は17%とされる。症状は発赤、びらんで、早期の褥瘡に類似することから、看護領域では褥瘡の鑑別疾患として重要と捉えられている。IADに対しては適切なスキンケアが必要で、その要点は、弱酸性の洗浄剤で丁寧にやさしく洗浄し、押し拭きをした後に、撥水と保湿効果のあるジェルを塗ること。微温湯だけの洗浄や、こすって拭くことは皮膚のバリアを損なうので、注意するようにと注意喚起を行っている。
本来は、ケアの他に接触皮膚炎やカンジダ症などの治療が必要な疾患があるのだが、訪問看護師に、「IADがあります」と言われた時に、「何それ?」とならないように、用語として覚えておくことにする。
-
馬事専門学校生に生じたケルスス禿瘡の症例。T.equinumが検出された。T.equinumは1972年に外国馬によって持ち込まれ、それ以降日本の競走馬にも蔓延しているが、ヒトへの感染はまれ。最近の動物糸状菌感染症の問題点は、 1) T. equinum感染が競走馬に蔓延しており、 M. canisも時に病馬から分離される。2) 牛のT. verrucosum感染は全国的で、集団発生が認められている。 3) 犬・猫にみられるM. canis感染も全国的で、発生症例数も増加し、保菌状態の動物も認められる。4) ラットではT. mentagrophytes感染が実験動物舎で蔓延し、対策に苦慮している。5) 豚では本邦での存在が知られていなかつたM. nanumの感染が認められた。
家畜飼育を営む患者がいない都会で経験することはほとんどなさそうだが、地域によっては問題となることもあるだろう。開業医も鏡検だけではなく、症例によってはやはり培養を行う必要がある。
-
手掌と手指の圧痛のある紅斑・硬結で来院。初診の1年前にタンザニアで足縁に外傷を負い、発赤を伴った。その後数カ月に一度の頻度で、四肢を中心に同様の発疹をくり返している。細菌培養から、メチシリン感受性黄色ブドウ球菌(MSSA)が陽性で、Panton Valentine leukocidine(PVL)が陽性だった。感受性検査ではPC、STに耐性。ST耐性のMSSAは本邦では稀だが、アフリカ諸国ではSTが安価なために使用頻度が高く、ST耐性になりやすい。
元気な若い患者に生じる再発性皮膚感染症ではPVL陽性市中感染型MRSAが多いが、MSSAでもみられるということがわかった。今後も注目していこうと思う。
-
10歳代男性の本邦初の症例。ブラジルから帰国後に発熱と播種状紅斑を来たし、ジカウイルス感染症と判明。ジカウイルスはデングデングウイルス同じフラビウイルス属に属し、いずれもネッタイシマカやヒトスジシマカが媒介する。中南米、東南アジアに蔓延しており、輸入感染症として重要。蚊に刺されてもジカ熱を発症するのは20%ほどだが、発症した妊婦から小頭症の児が生まれる確率が10%程度とのこと。ジカウイルスは発症後1週間は患者の尿から排泄され、また、精巣で増殖し感染から62日目の精液中に存在し、性交で男性から女性への感染が確認されている。
初めて発疹の臨床写真を見せてもらった。デング熱、チクングニア熱との鑑別は臨床からは難しそうである。2016年2月5日に感染症法上の4類感染症に指定され、全例報告になった。
-
爪白癬に対する抗真菌薬内服治療は、認可されてからすでに20年が経過し、いくつかの課題が見えてきた。①内服治療に抵抗し正常な爪の伸長がない症例がある、②内服治療で正常な爪の伸長が見られても部分的な白濁が残り完治しない症例、③内服治療で臨床的にも真菌検査でも完治した症例が1年後に同じ爪に再発する症例、④初回治療以降のドロップアウトが20%にみられる。①は爪切りの回数を聞き、伸びない場合は内服治療をあえて行わない。②はグラインダーなどで削る。③はおそらく休眠胞子の形で残っていたものが再発の原因。
確かに、皮膚科医側も抗真菌薬内服が発売された当初のモチベーションが落ちているようだ。最近発売になった外用薬がどこまで有効か興味があるが、①の伸びない爪に対する新薬の外用は行わないと決めた。
-
60歳代の女性。腹部に水疱様の外観を呈する黄白色の皮内結節があった。病理組織学的に真皮にアミロイドAL蛋白(IgG、λ)の沈着があり、汗腺周囲に形質細胞を混じる小円形細胞の浸潤があった。精査でSjögren症候群(SS)あり。本邦におけるANCAの40%はSSに併発し、患者の多くは中年女性である。
SSの皮膚症状は、1)SSを強く疑う皮膚症状として、環状紅斑、高γグロブリン血症性紫斑、虫刺様紅斑、2)稀だがSSと関連の深い皮膚症状に、ANCA、後天性無汗症、3)SSを念頭に置いて精査すべき皮膚症状として、凍瘡、薬疹、指端壊疽、蕁麻疹様血管炎があるとのこと。
-
眼瞼に生じた自覚症状のない小水疱。周囲にわずかな炎症があり、眼部の単純ヘルペスに似た臨床。鏡検ではひとつの小水疱に16匹の毛包虫が陽性で、水疱型毛包虫症と診断した。イオウの外用で改善せず、イベルメクチンの内服で改善した。
毛包虫が鏡検で、1カ所の病変から10~12個以上あれば、病因と考えてよいというルールがあるらしい。毛包虫は酒さに伴うざ瘡様発疹や小膿疱からも見つかることが多いが、10個まではないように思う。メトロニダゾールの外用が有効だったかもしれない。
-
アトピー性皮膚炎の大規模臨床研究。とくに男性と女性の臨床症状・検査値の違いを検討した。男性には白内障、網膜剥離などの眼合併症、結節性痒疹、Hertoghe徴候などの激しい掻破による病変、頚部の色素沈着が多く、女性には両手の湿疹が多かった。平均SCORADは男性50.7、女性47.7と大差はないが、血清IgE値の平均は男性が11,979 IU、女性が3,330 IUで男性が高値だった。金属アレルギー(Ni、Co、Cr)の合併は男性30%、女性42%と女性に多く、フィラグリン遺伝子変異はともに20%で性差はなかった。
納得のいく結果である。男性の方が強い力で掻破をすること、女性は家事、装飾品と関連する皮膚炎があることは、注目すべき点と思われる。女性の方がTh2サイトカインの産生能が高いらしいが、それが臨床症状の性差に反映されているかどうかは明らかではないようだ。
-
30代の女性。日本料理店で配膳の仕事を7年間続けていて、年に1回はスッポンを食べる機会がある。3年前からスッポン鍋の湯気があたるとくしゃみと顔のかゆみが生じるようになり、スッポンを食べた後の咽頭違和感を認めるようになった。prick to prickテストで、スッポンの生肉と水煮肉で強陽性。解析の結果、抗原はβ-Parnalbuminであったが、魚の摂取は可能だった。
感作経路はスッポン鍋の蒸気による経皮感作ないしは経気道感作ではないか、とのこと。飲食に勤務す人の経皮感作による即時型アレルギーは今後も色々な症例が出てきそうだ。
-
多発性筋炎/皮膚筋炎では急速進行性間質性肺炎(RP-ILD)が生命予後に関与するが、抗MDA5抗体陽性のCADMに多く、フェリチン値が高値で、それを指標に治療を決定することになる。呼吸器科に入院した39例の内訳は、PM 12例、CADM 19例、CADM以外のDM 8例で、RP-ILDはPM 7例、CADM 16例、DM 5例で、死亡例はそれぞれ0例、8例、3例であった。治療前のフェリチン値の中央値は、PM 117ng/ml、CADM 470ng/ml、DM 634ng/mlで、とくに900ng/mlを超える症例は全例死亡しており、予後判定の目安になる。
呼吸器科の入院なので、CADMの重症例が多いが、筋症状のある皮膚筋炎でもフェリチン値が高値だと予後が悪いということ。MDA5、Mi-2、TIF1-γの自己抗体測定も保険適応になったので、皮膚筋炎はかなり整理されてきた。
-
遅延型薬剤アレルギーでは、従来、薬剤反応性を細胞分裂で検出するDLSTが用いられてきたが、感度や特異度が高い検査とはいえない。近年、結核の診断には従来のツベルクリン反応に代わり、結核菌抗原に対するINF-γをELISpotで検出する、クォンティフェロンが用いられている。これと同様に、原因薬剤が明らかな薬疹患者10例の末梢血単核球を用いて、薬剤反応性のINF-γ産生をELISpotで捉えることができるかを確認した。10例のうち、DLSTが陽性の4例では全例、DLSTが陰性の6例では1例、合計5例で薬剤反応性INF-γの産生が確認できた。INF-γELISpotはDLSTと同等以上の感度で、原因薬剤を特定できる有用な方法である。
DLSTを行って、S.I=1.7という結果で、結局陰性なのか陽性なのかの判断に困る場合がしばしばある。INF-γELISpotがクリアーカットな結果を出してくれると助かるのだが、方法についてはまだ検討が必要らしい。
-
アトピー性皮膚炎の悪化因子のひとつに心理的ストレスがあるが、簡便で客観的な指標がない。ストレスを定量的に測定することを目的として、患者唾液中のコルチゾール、アミラーゼ、クロモグラニンA(CgA)を測定した。交感神経系はストレスに対して鋭敏に反応するとされ、CgAは交感神経ニューロンから分泌される主要な蛋白の一つである。アトピー性皮膚炎を軽症、中等症、重症、最重症の4群でこれらを比較したところ、唾液中アミラーゼは重症度に差はなかったが、コルチゾールとCgAは重症であればあるほど高値を示した。
以前から「あなたのストレスはこのぐらい」という客観的な指標があればいいなと思っていたが、CgAの測定が有用ということを初めて知った。アトピー性皮膚炎のほかにも慢性蕁麻疹の増悪時などで計測してみたい。ちなみにELISAのキットが入手可能である。
-
帯状疱疹は、神経後根に潜伏したVZVの再活性化によって生じるが、最初のイベントは増殖したウイルスによる神経根炎であり、発疹がない段階で痛みを感じることがしばしばある。この時点で、星状神経にも潜伏しているVZVが増殖し、唾液中に分泌されるため、唾液中のVZVをPCRで確認することが可能。その後は罹患した神経領域に発疹が出現するが、発疹が生じない場合もあり、それをsilent reactivationと呼ぶ。
片側性の痛みだけで、これから帯状疱疹の発疹が出てくるか、出てこないか、抗ウイルス薬による内服治療を見切り発車するか、待つかで悩む症例があるが、発疹がまだ出ていない時点でも唾液中のVZVをPCRで確認できれば、確信を持って治療することができる。ただし、日本の検査会社の使用しているプライマーでは偽陰性が多いらしく、まだ使えないとのこと。
-
沖縄のアタマジラミはフェノトリン抵抗性で、市販の0.4%フェノトリン外用薬が無効である。疥癬治療薬として承認された5%フェノトリンローションがこのアタマジラミに有効かどうか確認した。治療前の虫体が32匹、虫卵143個、1回の5%フェノトリンローション外用1週間後には虫体223匹、虫卵84個で、無効だった。その後、欧米で用いられている0.5%イベルメクチンローション(Sklice)の外用1週間後には、虫体0匹、虫卵178個となり、有効だった。
5%フェノトリンローションがアタマジラミに適応拡大されるといいと思っていたが、残念な結果である。もともとフェノトリン耐性なのでしかたがないか。今後はSkliceの保険収載をめざしてもらいたいと思う。
-
発端者は10歳代の女児で、頚部、体幹の褐色色素斑。父と1歳の妹にも同様の病変。母と父方の祖父母には病変なし。肥満や内分泌疾患の合併はなし。症状のある3名でFGFR3のコドン650にLsy→Thr変異があり、家族性黒色表皮腫と診断した。
家族性の黒色表皮腫があるとは知らなかった。皮膚症状以外にも軟骨低形成による軽度の四肢の短縮、低身長と低インスリン血症に伴う高血糖を伴うことがあるらしい。
-
20歳代男性、飲酒後に手掌に紅斑と腫脹を繰り返す。病理組織は固定疹。アルコール類のパッチテスト、プリックテストは陰性だったが、ビールとウォッカのDLSTが陽性。麦などの原材料の特異的IgEは陰性。ビールの内服テストで6時間後に紅斑出現。ノンアルコールビールの内服テストは陰性。日本酒の内服テストでは12時間後に紅斑が出現。原因はアルコールと考えた。
最近経験するの固定疹はムコダインばかりだが、まれにトニックウォーターやイクラなどの日常的な食品で起こることがあるので、いつも患者に尋ねるようにしていた。飲酒も原因になることは記憶に留めておこう。
-
皮疹部から採取した血液検体を用いて、診断の一助となる臨床検査を行うという提案。乾癬患者の皮疹内血は、血清中に比べてIL-8の濃度が高かった。また、肥満細胞腫では皮疹内血のヒスタミンが血漿中より高かった。皮膚疾患の病勢を把握する上で、皮疹内血の利用は有用かもしれない。
水疱性類天疱瘡の水疱内容で抗BP180抗体の存在を確認したり、汗腺嚢腫の内容液でCEA高値を確認したことはあるが、皮疹内血で病態を知るという新しいアプローチで、興味深かった。皮膚生検の際に出血した血液を利用するのがよさそうだ。
-
梅毒のビブラマイシンによる治療を再評価した。ビブラマイシンはこれまでもペニシリンの代替薬として用いられていて、1期では100mgX2の2~4週、2期では100mgX2の4~8週の内服が推奨されている。国外の統計によると、血清学的検査(Toluidine Red Unheated Serum Test:TRUST)による効果の判定は、1期では100%が陰性化、2期では97%で陰性化した。
ビブラマイシンを第一選択にしてもよいくらい有効性が高いとのこと。ちなみにTRUSTはPRPと同様にreaginに対する抗体をみる検査だが、TPHAの値も下がるらしい。今度、ビブラマイシンを梅毒治療に使ってみようと思う。
-
細菌68種、真菌9種のプローブ、プライマーを作製し、病理検体からの細菌・真菌の遺伝子を網羅的に検出する系を開発した。ホルマリン固定パラフィン包埋標本から、結核菌、クリプトコッカスなどが検出され、特染や免疫染色で確認できた。凍結サンプルからの検出も可能だった。病原体不明の病理検体から、細菌・真菌を検出する有用な方法で、皮膚科領域の検体にも応用できる。
変な肉芽腫や膿瘍ではやってみる価値がありそうだ。ただし、まず、組織をみて、感染症を疑うかどうかからスタートすることには変わりはないだろう。
-
Psoriasinは乾癬の皮膚に過剰発現している物質として同定された、分子量11kDaの分泌蛋白で、のちにS100蛋白ファミリーの一つ、S100A7であることがわかった。一方、乾癬の角層抽出物から、抗真菌作用を有する抗菌ペプチドを検索したところ、分子量11kDaのペプチドが単離され、質量分析の結果、それがPsoriasinであることが判明した。また、白癬の病変部では角層中に還元型のPsoriasinが増加していた。
乾癬や掌蹠膿疱症に対するステロイド外用中に、白癬が生じることは経験があるが、ピュアな乾癬の局面内に白癬の病変が併発していることが、あるかないか、多いか少ないかは、検討したことがない。理論的にはPsoriasinの抗菌作用で真菌は寄りつけないということになるが、実際はどうなのだろう。乾癬の発症に関わるIL-17が真菌感染の防御に関与しているということもあるので、複雑である。
-
ステロイド外用薬による治療に抵抗性のアミロイド苔癬、結節性痒疹は、その中心部の角層が厚く、正常の皮溝が損なわれ、さらに患部の発汗が低下している。保湿薬のODTを行うと、それ自体が有する発汗を促す働きよって、無汗部が減少し、皮溝が正常化して、やがて結節が改善していく変化が観察された。
保湿薬としては、ヒルドイドソフトよりもヒルドイドクリームの方が、発汗促進作用があるらしい。ODTを行うことによって、蒸れて発赤が生じたあと、病変が比較的早く消褪することもあるらしい。
-
黄砂飛来時に、主として露出部位の皮膚の痒み、皮膚炎の悪化を訴える患者がいる。黄砂にもその成分によっていくつかのタイプがあるが、大気汚染物質が少なく土壌ダスト主体の飛散がある日の皮膚症状は、飛散がない日に比べて、オッズ比が1.2となり、リスクの上昇が示された。また、皮膚症状を呈した症例で金属パッチテストを施行したところ、9割でニッケルが陽性となり、黄砂中のニッケルが皮膚症状を起こす可能性が示唆された。
砂やセメントによる接触皮膚炎は金属が原因であるということからすれば、当然の結果かも知れないが、それが、大気中にあるということが、問題だと思う。黄砂飛来時、ニッケルアレルギーがある患者には、帰宅時のシャワー浴を勧める必要がありそうだ。
-
ミノサイクリンを1年半にわたり継続し、総量が110gに達した高齢男性例。顔面にびまん性の褐色色素斑、四肢には境界明瞭な大型の暗青色色素斑を生じた。生検では真皮から皮下の血管周囲、付属器周囲に色素顆粒を貪食した紡錐形細胞浸潤があり、顆粒は鉄染色で青色に染まる。ミノサイクリンによる色素沈着typeⅡと診断。ミノサイクリンの色素沈着には4つのタイプがある。typeⅠ:青黒色の斑で顔面に多く、瘢痕や炎症を生じた部位に出現する。鉄染色陽性。短期間の内服でも生じることがある。typeⅡ:青褐色で下腿や前腕の正常皮膚に生じるびまん性の色素斑で、鉄染色陽性。長期の内服歴がある場合に生じる。typeⅢ:泥褐色の汚い色素沈着で、露光部位に生じる。メラニンの増加が主体で、鉄染色陰性。typeⅣ:typeⅢと同様だが、瘢痕などの上に生じる。
ミノサイクリンをダラダラと続けるのはやはり問題だと思う。色素沈着に関しては、厳密なtype分けは必要なさそうだが、鉄染色は必須と知った。鉄の由来は血清中のfreeの鉄由来とのこと。
-
カポジ水痘様発疹症(KVE)の治療が、口唇ヘルペスと同様の治療でよいかどうかは検討されていない。重症例では入院の上、抗ウイルス薬の点滴治療が行われる場合もある。そこで、KVEの重症度分類を試みた。①皮膚病変の範囲:顔面では手掌大以上が重症、以下が軽症。頚部・体幹・四肢では全体の5%以上が重症、以下が軽症。②全身症状・眼合併症:それぞれがあれば重症、なければ軽症。③細菌性の二次感染:あれば重症、なければ軽症。この基準にしたがって、重症例での治療を再考していく予定。
確かに、抗ウイルス薬内服5日間では心配な症例がある。症例を蓄積して、「症状によって適宜増量」などの添付文書の書き加えをしてもらいたいと思う。
-
開業医を受診する熱傷患者の統計。全体の男女比は1:2で女性に多いが、乳幼児では男児に多く、全年齢のうちでも1歳男児の受診が最も多い。30年前の同様の報告でも1歳男児が最多であった。やんちゃで好奇心旺盛な1歳男児の手の届くところには、熱い物を置かないように注意が必要。
自分の発表で恐縮だが、30年前の統計と同じ結果だったというところが面白かった。
-
BP230は表皮細胞内の蛋白で、抗BP230抗体は活動期の水疱性類天疱瘡(BP)患者の60%で陽性になる。抗BP180抗体がBPの発症に深く関わっていることは明らかになってきたが、抗BP230抗体の意義はよくわかっていない。活動期に抗BP180NC16a抗体が陰性で抗BP230抗体(コマーシャルで測定可能なリコンビナント蛋白が抗原)のみが陽性のBP症例は、掌蹠に水疱が多い傾向があった。国外の報告では、水疱が少数で軽症例が多いとされているが、全身に水疱をきたす例もあり、さらなる症例の蓄積が必要である。
まず、抗BP230抗体がコマーシャルで測定できることを知らなかった。保険適応ではないので持ち出しになるが、これからは抗BP180抗体と一緒にオーダーすることにした。これまでも、臨床からBPを強く疑ったが抗BP180抗体が陰性の症例があったような気がする。開業医では生検組織のDIFを行うことが難しいので、抗BP230抗体の測定の意義を明らかにしてほしいと思った。
-
臨床像から想像できなかった、意外な病理組織像を呈した病変の呈示。2種類以上の腫瘍が一つの切片に現れるcollision tumorには注意が必要。collision tumorは、同一臓器に組織学的に異なった腫瘍が発生したものとされ、その発生時期や臓器内での局在から、以下の3つに分類される。①相接型; 両者が接して存在し、渾然一体となっているもの。②衝突型; 両者が別個に発生し、互いに衝突または入り交じっているもの。③独立型; 両者が独立して存在しているもの。
臨床像から病理組織像を想像して、診断・治療を行うのは日常的に行っていることだが、主病変に隠れて存在する、主病変とは異なる異常所見に注目することが重要と再認識した。
-
小麦による即時型アレルギーでは、抗原特異的IgEのチェックを行うが、小麦、グルテン、ω-5グリアジンの3項目の組み合わせで、原因や感作経路を推定できる。経口感作による運動誘発アナフィラキシーでは、ω-5グリアジン > グルテン > 小麦の順に高値を示すが、経皮感作による加水分解小麦アレルギーでは、グルテン > 小麦 > ω-5グリアジンとなる。また、経粘膜感作と考えられるイネ科植物花粉症に合併する小麦アレルギーでは、小麦 > グルテン > ω-5グリアジンとなる。さらに、小麦粉に混入したコナダニが原因の場合も想定し、コナヒョウヒダニもあわせて測定するとよい。
接触する部位によって感作される抗原が違うというところが面白い。アレルゲンコンポーネントの検査でわかってくることがこれからもたくさんありそうだ。
-
尋常性乾癬ないし膿疱性乾癬の患者に生じる稀な病型で、多くはBlaschko線に沿う線状ないし帯状の角化性紅斑。通常の乾癬に先行して生じる。ステロイド軟膏外用などの治療に抵抗性で、ほかの部位が治癒しても、そこだけが残存する。Inflammatory linear verrucous epidermal naevusに似るが、単一遺伝子のモザイクで生じているわけではない。多因子疾患でも、より発症しやすいゲノム変化を持ったモザイクが存在すると、こういった病変を生じることがあり、segmental mosaicism of polygenic skin disordersという概念が提唱されている。
ちょっと難しかったが、多因子疾患と遺伝子モザイクの関連を考える上で重要とのこと。扁平苔癬、尋常性白斑、薬疹、アトピー性皮膚炎、環状肉芽腫、多形滲出性紅斑、皮膚筋炎、GVHDなどでも、同様の現象が見られるという。妙な分布の皮膚病に出くわすことは時々あるので、注意して診ていこう。
-
粉瘤に炎症を伴って切開を要する状況になることは稀ではないが、細菌培養を行っても半数では陰性となる、炎症はあるが、細菌感染ではなく、その原因は漏出した角質に対する異物反応と解釈した。皮下注用のステロイドを嚢腫内に注入しておくと、炎症が消褪し、嚢腫自体も縮小ないし消失することがあるので、臨床的に有用な方法と考える。
いかにも膿と思われても細菌培養で陰性であることは経験がある。細菌感染が少しでもある場合にはステロイド局注は気持ちが悪いが、確かに縮小している例もあるので、試してみたいと思った。嚢腫や嚢腫内の血腫が目立つようなニキビや膿皮症にも使えそうである。
-
女性のAGA(Female AGA: FAGA)はルードウィッグ型、クリスマスツリー型、ハミルトン型と3つのパターンに分類されている。ルードウィッグ型は頭頂部から後頭部の範囲がびまん性に薄くなっていくタイプ、クリスマスツリー型は生え際から頭頂部の真ん中が左右に拡がりながら薄くなっていくタイプ、ハミルトン型は、男性AGAと同様、生え際に剃りこみが入るタイプ。
知らなかったが、分類によって治療が変わるわけではなさそうだ。育毛サロンのホームページが詳細に記述しているのには驚いた。
-
ベピオゲルは2.5%過酸化ベンゾイル(BPO)を主成分とし、組織中に活性酸素を動員して爆弾のように細菌を死滅させるため、耐性菌の出現がないことが特徴である。一方、角層に対しては活性酸素の作用によって角層の剥離が促進する。アダパレンはレチノイド様作用で表皮角化細胞の分化を抑制するので、両者は作用点が異なっている。
配合薬を含めて色々なニキビ治療薬があるので、それぞれの薬理作用を知って適応を選ぶのがよいと思う。炎症性ニキビの初期治療としては、面靤が目立つときはアダパレン+抗菌薬、炎症が強いときはBPO+抗菌薬がよさそうである。BPOは接触皮膚炎の副反応もあるので、最初は狭い範囲からのお試しがよさそうである。
-
小麦による即時型アレルギーには、ω5グリアジンによる運動誘発性のもの、茶のしずく中のグルパール19Sによるものが知られてきたが、イネ科の花粉との交叉感作が原因の小麦アレルギーがありそうだ。イネ科花粉による鼻炎のある患者で、運動誘発性だが眼瞼に浮腫が生じた。抗原の解析からはこれまでとは違う可溶性分画中の蛋白が原因と考えられる。
果物や豆乳と同じ、いわゆるpollen-food syndromeだが、これまでは報告されていないようだ。うどんやパンをこねる人には小麦の経皮感作も起こりそうだし、それが、イネ科花粉症の原因になりそうで、複雑である。
-
下口唇から頬粘膜に至る潰瘍を主訴に来院した50代男性患者で、血清学的に梅毒と診断した。硬性下疳は、男性では冠状溝、包皮、亀頭部、女性では大小陰唇、子宮頚部が好発部位だが、口唇や手指などに発生することもあり、陰部外下疳と呼ばれている。頻度2~3%で稀であるが、臨床形態、病理組織像は典型的である。
古典に触れたような感じの病名である。このところ1期の梅毒を診ることが増えたが、これまでのキャリアでも陰部外下疳は診たことがなかったので参考になった。
-
原発性胆汁性肝硬変(PBC)は他の自己免疫疾患との合併が多い。中でも皮膚限局型強皮症との合併が最多で、PBCの3~50%とされている。また、PBC患者の9~30%で抗セントロメア抗体が陽性となる。反対に強皮症の25%で抗ミトコンドリア抗体が陽性となり、この2つの疾患の関連性が示唆される。PBCの診断に際しては抗ミトコンドリアM2抗体が感度、特異度ともに高いが、強皮症と合併する例では特異抗体を認めないものも多い。皮膚限局型強皮症で抗セントロメア抗体陽性、ALP上昇を認める場合はM2抗体が陰性であってもPBCの可能性が高いと判断するべきである。また、セントロメア抗体陽性例では門脈圧亢進症に進行しやすいと言われている。
抗セントロメア抗体陽性の強皮症は数例診ているが、ALPはさほど重要視していなかったので、勉強になった。
-
右外踝の胼胝が潰瘍化し、外用薬や被覆材で改善しないという経過。生検で有棘細胞癌であった。下肢の有棘細胞癌は、熱傷瘢痕を基盤とするものが最も多く、外傷瘢痕や慢性放射性皮膚炎なども基盤となるが、慢性の経過の鶏眼・胼胝にも注意が必要である。
臨床的には、有棘細胞癌とは思えないような小さな潰瘍だった。胼胝に対する治療としての頻回な物理的刺激が原因ということであれば、医原性もあり得るのだろうか。毎日行っている治療行為なので、ちょっと心配になった。
-
プロトピック軟膏は基剤のパリエーションもなく5gのチューブのみで使い勝手が悪く、四肢・体幹などの広い範囲に外用する際には患者のアドヒアランスが低下する。これを改善するために、保湿クリームと混和し、容器に入れて渡すことで、たっぷりと使用でき、患者のアドヒアランスも向上した。混合に不適との意見もあるが、経験上、臨床の現場では問題なく使用でき、効果も保たれていた。刺激症状も減り、経済的な負担も軽減した。
確かに、5gチューブの軟膏だけだと、顔専用という印象が強くなる。体幹・四肢にも積極的に使用できるような工夫をメーカーも考えるべきだと思った。当院でもこれに習って、少し始めてみよう。
-
抗癌剤の血管外漏出の既往のある患者に対して、他の部位からの再投与に伴って、漏出の既往がある部位の炎症が再燃する現象をリコール現象と呼ぶ。明かな血管外漏出の既往がない患者でも同様の現象が見られることがある。臨床症状を起こすまでに至らなかった、微小な漏出があったのではないかと考えた。リコール現象を起こす薬剤にはドキソルビシン、エピルビシン、ゲムシタビン、ドセタキセル、パクリタキセルなどが知られている。
点滴漏れがなくても、点滴スピードが速かったり、針刺しに手間どったりすることで、わずかな漏出が起こってしまうらしい。リコール現象という名前ぐらいは覚えておこう。
-
帯状疱疹が治癒した瘢痕部には、好酸球性皮膚症、肉芽腫など様々な皮膚病変が生じることがあり、post-herpetic isotopic responseと呼ばれることがある。基礎疾患にリンパ腫や白血病などの血液疾患があることが多い。ケブネル現象としての皮膚浸潤とは区別する必要がある。
ケブネル現象と考えてもよさそうだが、変わった反応である。これまで、そういった経験はないが、臨床的におかしいと思ったら、生検をしないといけないようだ。
-
糖尿病の既往のある水疱性類天疱瘡患者の治療で、プレドニンとレクチゾールを併用した。BSが250mg/dlでコントロール不良であったが、HbA1cは正常範囲内。その後プレドニンを減量し、レクチゾールを中止したところ、HbA1cが上昇した。レクチゾール100~150mg/日の投与で、80%の患者がHbA1cの偽性低下を示すという。このほかに偽性低下をきたす薬剤には、リバビリン、ヒドロキシウレア、少量アスピリン、ビタミンE、レトロウイルス感染症治療薬などが知られている。反対に、HbA1cの偽性上昇を示す薬剤には、大量アスピリン、大量ビタミンCがある。
HbA1cの値は赤血球寿命によって修飾されるとは聞いていたが、薬剤が関連することは知らなかった。レクチゾール+プレドニンの処方が行われる可能性がある水疱性類天疱瘡では、HbA1cの評価に注意する必要がある
-
患者から不眠の訴えを聞いたら、1) 不眠をきたしうる身体疾患(睡眠時無呼吸症候群など)、2) 不眠をきたしうる薬剤(降圧薬・高脂血症薬・抗パーキンソン病薬・気管支拡張薬・ステロイドなど)、3) 誤った生活習慣(極端な早寝・寝酒:カフェインの過剰摂取)の有無をチェックし、それがあれば、まずはその原因を除去する必要がある。次にうつ病を念頭におき、食欲低下、倦怠感、意欲の低下、興味の低下があるかを聞く。非専門医は、睡眠薬の使用は3か月以内とし、それでも改善しない不眠は、うつ病の可能性を考えて、精神科専門医に紹介するのを目標にするとよい。
3か月だったか。マイスリーをかなり長期間処方している患者がいる。困った。ロゼレム(メラトニン受容体作動薬:高齢者の睡眠リズム異常の改善薬)かベルソムラ(オレキシン受容体拮抗薬:寝つきが悪い過覚醒状態の改善薬)ならば、継続して使用が可能とのことで、明日からさっそく導入しよう。
-
内痔核(いぼ痔)は初期は自覚症状なし。脱肛があると便汁が漏れ、肛門周囲の皮膚炎の原因になる。浅い裂肛(切れ痔)は病変自体にかゆみを伴うことがある。また、裂肛の横には見張りいぼと呼ばれる出っ張りを生じる。痔瘻(穴痔)は初期に膿瘍の存在がかゆみの原因になることがあり、さらに瘻孔を通って便汁が流出すると、皮膚炎の原因になる。
以前から境界領域だとは感じていたが、肛門科医から詳しい話を聞いたのははじめてだった。今後は、痔の鑑別も念頭において、肛門周囲の病変をみることにしよう
-
非救急医は、患者が急変した時に、まず何をすべきか。病院内では「人を呼ぶ」ことが一番。そのためにも日頃から院内の救急体制を確認しておくことが重要。クリニックや市中では、「救急車の要請」が一番。訓練を受けた救急救命士がプロトコールに基づいた救命処置を行うので、「私は医者です。プロトコールに基づいて救命処置を行ってください」と実施指示を出すのがベスト。
医師としての誇りや見栄より、患者の命の方がずっと大切である。実践的な話でためになった。
-
フランスでは1986年から、国全体のシステムとして、SAMU(緊急医療援助組織)が構築され運用されている。SAMUは救急専用の電話番号15番の通報を、医学知識のあるオペレータが受信し、メディカルレギュレーション医師が適切なトリアージ、搬送や入院の調整を行う、救急医療の中枢である。生命危機が疑われる場合は救急医を中心としたMICU(移動ICU)チームが現場に出動する。さらに、大災害対応プランとして、Plan Rouge(入院前の段階における消防機関と医療機関双方の連携)とPlan Blanc(多数の傷病者の受け入れを調整する病院間の連携)があり、2015年11月13日の同時多発テロの際に、機能を発揮した。現場死亡が多い事件で厳しい状況だったが、パリ公立病院連合(APHP)傘下の病院に入院した負傷者356人のうち、1週間後までの死亡率は1.3%だったという。
災害時の病院間連携の構築、医療オペレーターの養成など、日本の大都市圏でも進めていかなければならないと感じた。
-
4歳女児に生じた多発性固定薬疹。ムコダインの再投与試験36時間後に発疹が誘発された。ムコダインは昼と夜では主要な代謝産物が異なり、昼はS-メチルL-システインに、夜は原因抗原となるチオジグリコールになると考えられている。ムコダインの固定薬疹は、1)多発性が多い、2)内服試験でも再現までに数日を要する場合が多い、という特徴がある。
ムコダインは使用頻度の高い薬剤で、遅発型の固定薬疹の原因になることは知っていたが、昼と夜で代謝産物が異なるとは知らなかった。パッチテストも一次刺激性の反応が多いので、診断には、こういったムコダインによる固定薬疹に特有な臨床経過を認識しておく必要がある。
-
糖尿病の管理不良の患者。包皮と亀頭に炎症をくり返し、仮性包茎となる。包皮輪には放射状に縦に走る複数のキレツが生じていた。経過が長くなると瘢痕となり、嵌頓包茎をきたし手術が必要になることもある。糖尿病性亀頭包皮炎と呼ばれることもある。
縦の放射状キレツが特徴らしい。尿糖との関連はないのだろうか。包皮亀頭炎を診る機会は多くはないが、いつもカンジダの鑑別だけで皮膚炎としての治療になってしまう。亀頭と包皮の疾患アトラス的な専門書があるといいのだが、。
-
脂腺癌は欧米の教科書には3/4が眼瞼に生じるとされている。眼科を含む皮膚科以外の診療科からの検体を扱う本邦の施設からの集計では、脂腺癌と診断した症例は、眼瞼が21例、眼瞼以外の頭頚部25例、頭頚部以外が14例で、眼瞼外発生例が2/3を占めた。人種による差がこの結果を反映していると思われる。
脂腺癌といえば、マイボーム腺癌だと思っていたので、眼瞼外、とくに鼻の周りが多いという印象はなかった。
-
トコジラミの吸血実験。吸血時間は7分から27分で、平均は15分。11回の観察のうち9回は1回の吸血だけで刺し換えなし。2回以上の刺し換えは2回。すぐ横に刺し換えがあると、刺し口が2つ並ぶという伝説の症状になる。なお、刺された回数と皮膚の反応に関しては、初回から3回目までは無反応、4回目は吸血の24時間後から紅斑が出現し、48~72時間後がピークの遅延型反応になる。通常の臨床では、刺されたあとに残った微量の抗原に対して、感作に6~15日を要するとされ、刺されてから2週間後に発疹が出現することがまれでない。
皮膚の症状は、蚊に対する反応と一緒で、最初は無反応、感作されてまず遅延型反応、刺さされ続けていると次第に即時型反応に変わってきて、最後は無反応となる。簡易宿泊施設で刺され続けていた利用者は、最後は刺されても症状が出なくなったとのこと。
-
米国南東部、テキサス州からカリブ海~大西洋沿いにメイン州までに分布するダニ媒介感染症があり、southern tick-associated rash illness (STARI)と呼ばれる。背中に一つ白い点があるlone star tickというダニが媒介するが、Lyme病の病原体であるBorreliaとは関連していない。症状は刺され口を中心に遠心性に拡がる紅斑で、Lyme病に似る。全身倦怠感、発熱、頭痛、筋肉痛を伴うこともある。日本ではタカサゴキララマダニ刺症後に遊走性紅斑が出現した例がある。Lyme病の原因となるシュルツマダニがいるのは北海道と本州中部の高地なので、その生息地以外で遊走性紅斑が生じた場合はTARI(tick-associated rash illness)と呼ぶのがよさそうだ。
ダニ媒介感染症も全世界的に色々とあるようだ。STARIは米国CDCのホームページ(https://www.cdc.gov/stari/)に解説があって、lone star tickや皮膚病変の写真も載っている
-
トコジラミが部屋の中に定着し繁殖すると、柱や障子の隙間に巣を作る。昼間はこの巣に潜んでいて、夜になるとモゾモゾと降りてきて、吸血する。巣に戻る時にフンをするので、茶褐色のシミになるのが特徴。
巣を見つけたら、成虫を殺虫剤で駆除するのだが、通常のピレスロイド系殺虫剤には抵抗性で、カルバメート系殺虫剤のプロポクスルが主成分の「バルサンまちぶせスプレー」かオキサジアゾール系殺虫剤のメトキサジアゾンを含んでいる「トコジラミゴキブリアース」、「ゴキジェットプロ秒殺+まちぶせ」がおすすめとのこと。
-
便秘の病態は一つではないので薬剤の使い分けが必要。上部消化管膨満感が強い場合はガスモチン、下部消化管の動きが悪いときはセンナ、プルセニド、便が固い時はマグミット、マグラックス(水を一緒に飲まないと意味がない)、肛門が締まっているときはレシカルボン坐薬がよい。
使い分けは意識していなかったので、参考になった。ちなみに、帯状疱疹後神経痛でトラマドールを用いるときには、便秘に対してセンナかプルセニド、吐き気にはナウゼリン最初から併用するとよいとのこと。
-
経験に基づくペイン専門医の、ザックリとした治療の提案。帯状疱疹後神経痛で、焼けるような、うずくような、締め付けるよう痛みには、トラマドールないし三環系抗うつ薬、電気が走るようなザーっと来るような痛みにはプレガバリンがよい。なお、トラマドール製剤の内容量はトラムセットだと1錠中、37.5mgなので、眠気、吐き気、便秘の副作用が出現することが多いため、最初はトラマール錠(25mg)を用いるとよい。徐放性剤で1日1回のワントラムは100mgで、トラマール4錠分にあたる。
「火」を想像させる痛みはトラマドール、「電気」を想像させる痛みがプレガバリンとのことで、わかりやすい。さっそく明日から使えそうだ。
-
創傷治癒においてはmoist wound healingの概念が推奨され、創を湿潤環境に保つことが必要だが、ここでいう湿潤環境とは適切にコントロールされた状態であり、過剰な滲出液は創底の浮腫や創周囲の浸軟の原因となり、乾癬の温床や上皮化の妨げになる。静脈瘤性下腿潰瘍など、創の面積や深さに比して滲出液が多い創傷では、ポリウレタンフォーム(ハイドロサイトなど)、ハイドロファイバー(アクアセルなど)、アルギン酸塩(カルトスタットなど)、ソフトシリコン/ポリウレタンフォーム(メビレックスボーダーⅡなど)のドレッシング材を用いると良い。
潰瘍自体は小さいのに、滲出液が多い下腿の病変にはたびたび遭遇する。褥瘡では周囲がふやけたときにイソジンシュガーを使ってきたが、下腿潰瘍では痛がることが多く使いづらい。もっとドレッシング材を積極的に使っていく必要がありそうだ。
-
外陰部のパジェット病の話。病変の辺縁が肉眼、あるいはダーモスコピーでも不明確なのは周知の通り。皮膚悪性腫瘍ガイドラインでは、通常は肉眼的な辺縁の1㎝外側、辺縁が不明瞭な場合は3㎝外側を切除マージンとすると推奨されている。切除した検体はそのまま病理に提出するのではなく、マクロで病変と思われる辺縁にメスを浅く入れておくとよい。病理組織では表皮に付けたキズがどこにあるかを確認することで、マクロとミクロの差を検証できる。
なるほどと思った。外陰部のパジェットには、術前にステロイド軟膏を外用し、局所の炎症をとることで、病変の辺縁が明瞭になるとのこと。ミノマイシン内服であぶり出せるというのも本当らしい。勉強になった。
-
70代女性。難治で経過の長い蕁麻疹様紅斑と膨疹様丘疹。抗ヒスタミン薬内服とステロイド外用で改善しない。好酸球数3,000/μL、IgE 4700IU/mL、TARC 36,000pg/mLと高値で、激しいかゆみを伴う。慢性疼痛に適応のあるサインバルタ(20mg/日)を投与したところ、3週間でかゆみが改善。膨疹様紅斑、痒疹丘疹も消褪。上記の検査異常も正常化した。サインバルタはセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)に属する薬剤で、脊髄中の下行性疼痛抑制系を賦活化するため、痒みに対しても効果を発揮する可能性がある。
多形慢性痒疹あるいはその類症と考える症例で、治療に窮することが少なくない。これまでも、ピロリ除菌(マクロライド系抗菌薬)や、レセルピンがよかったなど、いくつか報告があるが、もちろん全例に有効とはいかない。サインバルタがどの程度有効なのか、今後の検証を待ちたいと思う。
-
40代女性。前胸部から始まり、額、体幹に拡がった褐色斑。組織は表細胞の個細胞壊死と苔癬型反応で、ashy dermatosisと診断。金属パッチテストで重クロム酸カリウム(++)、硫酸ニッケル(+)。温泉水プールに週1~2回入る週間があり、温泉水のDLSTが陽性だった。温泉中の金属が原因の可能性がある。
ashy dermatosisは原因が見つからないことが多い。薬剤以外では金属のアレルギーを疑うことがあるが、たとえ陽性でも、なぜ病変が体幹に広く生じるのかはわからなかった。風呂やプールの水に含まれる微量金属が原因かもしれないというのは、新しい発想で、興味深かった。
-
TARC値の測定はアトピー性皮膚炎の管理上有用であるが、菌状息肉症や水疱性類天疱瘡などでも高値になることが知られ、疾患特異的なマーカーではない。最近、薬剤性過敏症症候群(DIHS)の初期に血清TARC値が特異的に異常高値となることが報告さた。DIHSの初診時のTARC値は平均で20,000pg/ml以上になり、他のタイプの薬疹や他の皮膚疾患との鑑別にも有用である。
皮膚のダメージを反映するマーカーと認識しているので、当然かも知れないが、発症直後に他のタイプの薬疹や感染症による中毒疹との鑑別に有用だとすれば、案外、役に立つかも知れない
-
消化性潰瘍にたいするH.pylori除菌の発疹症の集計。原因を検討できた8例中、DLSTではAMPCのみ陽性が5例、AMPCとCAM両方に陽性が3例、PPIはいずれも陰性だった。内服誘発テストは6例で施行、2例はAMPCで陽性だったが、ほかの4例はいずれも陰性で、DLSTの結果と一致しなかった。薬疹による機序以外の反応がある可能性がある。
1週間の除菌が終わる頃に発症する例も経験する。梅毒のJarisch-Herxheimer反応と同じように、抗菌薬で壊れたH.pyloriがアレルゲンとなって発症している例があるような気がしている。今後の集積に期待したい。
-
2歳の女児。入浴中に出現し、入浴30分後に消褪する膨疹が主訴。ブリキの金魚で遊ぶことを中止したところ、膨疹出現がなくなった。玩具を浸漬して得た溶液とパッチテスト用の金属を用いてプリックテストを行ったところ、玩具溶液とニッケルで膨疹が出現し、陽性で、金属による即時型アレルギーと診断した。
そういうこともあるのだ、という症例。入浴中に出現するというのがキーポイントだと思うが、ブリキの金魚を疑ったところがすごい。
-
78例の酒さ様皮膚炎患者。バックグラウンドはステロイド軟膏単独使用例が48例(62%)、タクロリムス単独ないしタクロリムスとステロイド併用例が28例(35%)。Japanese standard allergenを用いてパッチテストを行ったところ、Urshiol 17例(22%)、Nickel sulfate 16例(21%)、Fragrance mix 13例(17%)が陽性だった。パッチテストの結果と経過からアレルギー性接触皮膚炎と診断できた症例が64例(82%)で、原因の除去を行って酒さ様皮膚炎が改善した症例が57例(73%)あった。
酒さ様皮膚炎と診断した時点で、アレルギー性接触皮膚炎は否定しまっていたが、確かに、原因除去がうまくいかず遷延している症例も多いのかもしれない。若干多すぎるような気もするが、長くステロイドを塗るきっかけになっている、除去できていないアレルゲンの関与もあるのだろう。
-
ビールを一口飲んだ10分後に口唇のかゆみが出現。その後、顔の腫脹、全身の蕁麻疹、呼吸困難が出現した。特異的IgEはビール酵母でclass 2、バクガがclass 5、オオムギもclass 5。プリックテストでは各社ビールas is、オオムギで陽性。ビールによる即時型アレルギーと診断。ビアレストランでアルバイトをしていて、手にビールがこぼれた時にかゆみを感じていたことから、経皮感作による発症と考えられる。
ビールも経皮感作だった。食物が皮膚につきっぱなしになることを避ける必要があるかもしれない。バリア障害がある人は、食材を素手でさわること自体が、即時型アレルギーを引き起こす危険な行為になってしまうようだ。大豆や米ぬかなど、食物の成分が含まれている化粧品も危なそうである。
-
サケのホイル焼きで膨疹と呼吸苦、アミノコラーゲン入り栄養ドリンクでも膨疹が出現。タラ、ウナギ、ハモでも口腔内違和感が生じた。特異的IgEはサケで5+、プリックテストは生のハモ、タラでは陰性。加熱したウナギで陽性。コラーゲンがアレルゲンと考えられる症例のプリックテストは、生だと水に不溶のため陽性とならない。電子レンジで加熱すると、変性してα鎖がほぐれ、水に可溶になるため、陽性になる。
魚アレルギーの2/3はパルブアルブミン、1/3がコラーゲンである。料理用のゼラチンもコラーゲンだが、こちらはウシまたはブタ由来で、魚コラーゲンとの抗原交差性はないとのこと。ゼラチンアレルギーは、ウシないしブタコラーゲンアレルギーということになる。ためになった
-
60代男性。小麦によるアナフィラキシーで救急搬送。エピネフリン、ステロイドの投与で一旦軽快したが、5分後に胸痛、心室性頻拍を発症し、再度ショックとなった。アレルギー反応に続発して急性冠動脈疾患きたすKounis症候群と診断した。I型は冠攣縮によるもの、Ⅱ型はプラーク破裂に伴う血栓形成によるもので、本例はⅡ型だった。動脈硬化のリスクのある患者ではアナフィラキシーの初期治療後も、十分な観察が必要である。
Kounis症候群という病名を初めて聞いた。このほかにもアナフィラキシーによる血圧低下、心収縮力低下、徐脈が起こりのために冠動脈血流が低下し心筋虚血がおこるといった機序があるが、厳密にはKounis症候群に含まれない。アナフィラキシーによる心機能低下には、エピネフリンの単回投与は効果が乏しく、持続点滴(1mg/100mlを30-100ml/hrで)を推奨するものもあるようだ。
-
マイコプラズマ肺炎に関連する多形紅斑と診断した複数の症例。いずれも、紅斑出現前に内服していた複数の薬剤で施行したDLSTが陽性となった。マイコプラズマ感染により生じる紅斑症やStevens-Johnson症候群が薬疹と診断される可能性があるので、注意が必要である。
紅斑が主体の急性発疹症でマイコプラズマ感染症を疑うことがあるが、なかなか症例に当たらない。DLSTが何でもかんでも陽性になることがあるということは、リンパ球が活性化されているということか。念頭に置いておこう。
-
フランス製赤マカロン摂食後に生じたアナフィラキシーの症例。immunoblotでコチニール中に含まれるエンジムシ虫体由来の残留蛋白が原因と考えた。外国製の口紅による口唇のかゆみが既往にあり、経皮感作の可能性が高かった。コチニールアレルギーはなぜか日本人女性の症例ばかりで、フランス製マカロンによるものが多い。フランスからの症例報告はなく、人種差か、あるいは、幼児期からの摂食による免疫寛容かは不明である。
確かに、フランス人はフランス製赤マカロンを食べる機会が多いはずだが、発症しないのは、経消化管による免疫寛容が成立しているためかも知れない
-
コセンティクスは乾癬のキーサイトカインであるIL-17Aを標的とする生物学的製剤で、乾癬以外の他疾患では使用されていない。IL-17Aは当初は活性化T細胞(Th17細胞)が産生すると考えられていたが、近年では、T細胞以外にも好中球、単球、NK細胞などの自然免疫系の細胞からも産生されることがわかってきた。コセンティクスの副作用として、真菌(主にカンジダ)の感染症と炎症性腸疾患の発症ないし増悪が報告されている。治療経過中、β-Dグルカンの測定が必須で、消化器症状の出現に注意する必要がある。
IL-17はAからFまでの6つの遺伝子からなるファミリーで、IL-17AとIL17-Fは相同性が高く、同様の生物学的活性を持つらしいか、それ以外のBからEは別の免疫反応に関わっているらしい。かなり複雑で、ついて行けなくなってきた。
-
240人のざ瘡で通院中の患者で、径2mm以上の萎縮性瘢痕と径0.5~2mmのmini-scarsの有病率を調査した。acne瘢痕は60%で、mini-scarsは90%でみとめられた。mini-scarsの有病率は年齢が高くなると多くなり、罹病期間とも相関があった。初めてacneができた年齢は、scarのない患者と同じ時期だったが、初めて医療機関を受診した年齢に3年の開きがあり、早く医療機関を受診することがscarを残さないために重要であった。
これは、にきび治療の啓発に使えるデータだと思った。にきび治療も色々な薬剤が出てきて、どういう組合せがよいのか、悩むところではある。
-
ウルシでかぶれる人は、マンゴとギンナンに注意すること、は皮膚科医の常識である。マンゴのかぶれはウルシオールに似たマンゴールが原因である。ギンナンの外種皮に触れて起こるかぶれはギンコール酸が原因である。カシューナッツもマンゴと同様ウルシ科の植物で、種子はカシューアップルと呼ばれている。殻から取るカシューナッツオイルはウルシと同様に塗料として用いられていて、接触皮膚炎の原因となる。
カシューが塗料になっているとは知らなかった。またアレルギーもナッツによる即時型だけかと思っていた。ナッツにはウルシオールに似た成分は含まれていないらしいが、接触皮膚炎の既往も聞いてみることにしよう。
-
ベンゾフェノン誘導体(オキシベンゾン、ジオキシベンゾン)は紫外線吸収剤として多くの日焼け止めに配合されているが、同じベンゾフェノン基を持つ医薬品にケトプロフェンがある。さらに、高脂血症治療薬であるフェノフィブラート(リピディル・トライコア)も同じ構造を持ち、交叉反応が確認されている。
稀ではなく経験するモーラステープによる光かぶれの患者には、再発防止のために少なくとも1カ月は日焼け止めを塗るように指導してきたが、オキシベンゾンが配合されている製品は使ってはいけないということだった。これまで説明してこなかったので、ちょっと心配になった。フェノフィブラートによる日光疹型薬疹は経験していないが、モーラスとの関連を念頭に置いておこう。
-
舌の所見から全身疾患を疑う代表的疾患。舌全体が赤く腫れ、しかし一部に貧血性の変化を伴い、舌にV字型あるいはM字型の潮紅を認め、舌苔は萎縮し光沢がある。痛みを伴うことがある。Moller-Hunter舌炎といい、ビタミンB12の欠損すなわち悪性貧血に伴う症状。
忘れかけていた病名であった。舌痛があるとついつい亜鉛欠乏を考え、プロマックの投与になってしまうが、きちんと採血をして、必要があればメチコバールの投与も考えよう。なお、ビタミンB群の欠乏症では、ペラグラを含め、舌炎、口角炎、口唇炎をきたすことが多いことを再確認した。B2欠乏症では舌が赤紫色になるらしく、magenta toungeと呼ばれるそうだ
-
表皮ケラチノサイトは11βHydroxysteroid dehydrogenase 1(11βHSD1)とよばれる酵素により、中枢とは異なる機序で内因性グルココルチコイドを産生している。消化管や気道上皮細胞でも同様に内因性のステロイドホルモンが産生され、炎症局所での行き過ぎた組織障害を抑制している。11βHDS1阻害物質やノックアウトマウスを用いた検討では、ある条件下で内因性コーチゾールは、中枢性とは反対にIL1、IL6、TNFαなどのサイトカインを正の方向に制御し、バリア保持など皮膚の恒常性の維持に重要な役割をはたしている可能性がある。アトピー性皮膚炎では11βHDS1の産生が低下していて、ストレス下ではさらに減少している。コレステロールには11βHDS1の活性を増加させる働きがある。
ステロイドにもかかわらずサイトカインに対する正の制御があるというところが面白い。表皮でちょくちょく起きている炎症は、表皮が最前線で制御しているということか。
-
臨床検査を行った80万の検体から、好酸球数に注目して原疾患が何かを調査した。好酸球数2,000/μl以上(全検体の0.13%)では、薬剤性肝障害、固形腫瘍、皮膚疾患(好酸球性血管浮腫とアトピー性皮膚炎を除く)、血液腫瘍、気管支喘息、好酸球性血管浮腫、Churg-Strauss症候群(好酸球性肉芽腫性多発血管炎: EGPA)、好酸球性肺炎、アトピー性皮膚炎の順に頻度が高く、薬剤性肝障害、固形腫瘍、皮膚疾患の3つで50%以上を占める。好酸球数10,000以上(全検体の0.01%)では、non-episodic angioedema with eosinophilia(NEAE)、EGPA、好酸球関連腸疾患の順で多かった。好酸球数2,000以上が持続する場合には、特に心筋障害、弁膜症などの心疾患に注意が必要である。
重症の気管支喘息に使用可能な抗IL-5抗体であるmepolizumabは末梢血中の好酸球数を劇的に減らすらしい。アトピー性皮膚炎の紅皮症でも2,000を越えるくらいで10,000にはならないようだ
-
軟部悪性腫瘍は初回の不適切切除による増悪が多く、Oops excisionと呼んでいる。四肢における軟部腫瘍の生検では、皮切を長軸を縦にすること、無理な剥離はしないこと、被膜をきちんと縫合すること、確実な止血を行い、場合によってはドレーンを置き血腫を予防することが大事である。
皮切が横だと、再切除後の再建が大変になるらしい。脂肪肉腫などを疑ったら、最初からがんセンターに任せた方が無難というのが結論。
-
高IgE症候群は、1)黄色ブドウ球菌を中心とする細胞外寄生細菌による皮膚膿瘍と肺炎、2)新生児期から発症するアトピー性皮膚炎、3)血清IgEの高値を3主徴とする免疫不全症で、STAT3のmutationが原因である。STAT3は30種以上のサイトカイン・増殖因子のシグナル伝達に関与しており、この障害が疾患の発症に関与しているものと考えられる。その中でも、IL-17、IL-22などのTh17サイトカインの産生が低下していることが明らかにされた。ケラチノサイトと気管支上皮細胞においては、Th17サイトカインが好中球を遊走させるサイトカインや抗菌ペプチドの産生に重要であり、高IgE症候群の患児で皮膚と肺で黄ブ菌感染症を起こしやすいことと関連している。
Th17が活動しないと、Th2に流れていくようだ。易感染性は説明できたようだが、額の出っ張り、脊椎側弯などの骨・軟部組織の症状については関連がまだわかっていないらしい。
-
B型肝炎はHBVの初感染で、急性肝炎発症の際にHBs抗原が陽性化、その後HBc抗体が陽性となり、HBs抗原が陰性化して治癒し、通常は再燃しない。しかし、寛解後もHBVは核内に2本鎖閉鎖環状DNAとして残存している。B細胞性リンパ腫の化学療法(R-CHOP療法)を行った症例で、HBs抗原が再度陽転化し、劇症肝炎を発症することが報告された。リツキシマブはHBs抗体陽性既感染例でもその抗体価を下げ、HBVの再活性化を許す結果となる。また、HBV遺伝子にはglucocorticoid enhancement elementがあり、ステロイド投与がウイルス量を増加させることが知られている。この際の治療には、DNAポリメラーゼ阻害薬のエンテカビルが用いられる。
既感染であっても、中和抗体がなくなると再活性化が起きるということ。DIHSもそうだが、ウイルスの再活性化が関与する急性発疹症は、少なくないのではと思う。
-
局所陰圧閉鎖療法は褥瘡の早期閉鎖に有用だが、これまでは入院加療でしか扱えなかった。2013年以降在宅や通院でも使用が可能な機器が登場した。SNaP(米国Spiracur社製)、PICO(英国smith & nephew社製)はそれぞれ陰圧装置が手のひらサイズで、携帯が可能。
標準的には週2回のドレッシング材交換が必要らしい。意外に面倒で、価格も高く、普及はなかなか難しそうだ。
-
多くの症例で、アポクリン腺由来の原発性乳房外Pagetでは、CK7(+)、CK20(-)、GCDPF-15(+)、肛門管あるいは直腸由来のPaget現象ではCK7(-)、CK20(+)、GCDPF-15(-)、尿管上皮由来ではCK7(+)、CK20(+)、GCDPF-15(-)で、鑑別の補助となり、もはやルーチンで行うべき特染である。
専門医試験や国家試験にも出てきそうな基本中の基本。リンパ腫や皮膚腫瘍の鑑別に必要な特染のルーチンは、開業医も知っておかなければならない。
-
37歳の男性で、陰嚢に乳房外Paget病が生じた。父にも陰嚢とそけい部に同症があり、73歳の時に気づかれている。本邦ではこれまでに6家系の親子例の報告があり、親は60歳代に診断されるが、子はそれよりも平均17歳若く診断されている。乳房外Paget病ではdeleted in liver cancer 1 (DLC1)遺伝子の変異が関連するという報告もあるが、遺伝よりはエピジェネティックな要因が主体と考えられる。
親が乳房外Paget病であれば、自分も心配になって観察するため、早く気づくだけかもしれない。家族歴についてはしっかり聞いておく必要がありそうだ。
-
疥癬患者の末梢血好酸球の話題。検討した31例で、好酸球5%以上が19例(61%)であった。ストロメクトール錠2回内服後では検討した26例中、好酸球5%は12例(46%)となり頻度は低下した。一方、同年齢の皮脂欠乏性皮膚炎患者25例では、好酸球5%以上は7例(28%)であった。疥癬と皮脂欠乏性皮膚炎を比較すると、疥癬の診断は、好酸球5%での感度は58%、特異度は69%、好酸球3%では、感度77%、特異度34%、好酸球8%では感度35%、特異度96%であった。
ありそうでなかったデータだった。グレイゾーンの症例も多いので、補助的なマーカーになると思った。
-
Pterygium Inversum Unguisは、指の先端の爪床が爪甲の掌側にくっついている状態で、腹側翼状片とも呼ばれている爪の異常で、先天性(家族歴のある例とない例)と後天性がある。後天性の中では、全身性強皮症などの膠原病に伴う例や、神経線維腫症やハンセン病に伴う例、爪強化剤などの化学物質が関与する場合がある。痛みを伴う例があり、病理組織学的にグロームス小体、末梢神経の増加が確認できる症例がある。
このような疾患名で呼ばれているとは知らなかった。SLEの患者で典型的な病変を見たことがある。末梢循環障害が原因かと考えていたが、合併症からみれば末梢神経障害との関連もありそうだ。
-
両下肢の蜂窩織炎をきたした患者の血液培養から、グラム陰性螺旋状菌が検出され、Helicobacter cinaediと同定された。イミペネム、セファゾリンなどの抗生剤に対する反応は良好だが、再発をくり返した。H.cinaediは主に免疫不全状態の患者に再発性の蜂窩織炎を起こす菌として近年注目されている。菌血症にもかかわらずCRPは低値の症例もある。
基礎疾患のない整形外科領域からの報告もあるようだ。再発をくり返す症例ではこの菌も念頭に置く必要がある
-
水疱性類天疱瘡(BP)が平成27年7月1日から厚労省の指定難病となった。調査票では、BPDAIによる重症度分類が用いられている。皮膚では水疱・びらん、紅斑のそれぞれの部位と範囲を、また粘膜では水疱・びらんの部位と範囲を、別々に120点満点の点数で表し、皮膚の水疱・びらんが15点以上、紅斑が20点以上、粘膜では10点以上を中等症以上とし、医療費助成の対象とした。概要と調査票は厚労省のホームページで閲覧できる。
難病指定に重症度の概念が加わって複雑になった。BPDAIの点数表は手元に置いて、参考にしていこう。
-
水疱性類天疱瘡(BP)の症例。BP180のNC16a抗体は陰性だが、full-lengthのBP180抗原プローブに対する抗体が陽性だった。糖尿病のためにDPP-4阻害薬を内服中で、中止と少量のステロイド内服で改善した。DPP-4は生体内で広範囲に発現しているCD26と同一物質で、CD26陽性T細胞は免疫調整に関与しているため、BP発症の誘因になりうると考えられる。臨床的には緊満性水疱が主体で紅斑が目立たないのが特徴である。
膵からのインスリン分泌を促進するのがDPP-4阻害薬の重要な作用点であるが、わかっていないことも多いようだ。自己免疫性疾患との関連は今後も注目する必要があるとのこと。なお、国外ではDPP-4阻害薬とメトホルミンの併用例でBPの発症が多いらしい。DPP-4阻害薬を内服する糖尿病患者は今後も増加すると思われ、注目したい。
-
50代女性で、両肘と手指のPIP関節に結節性病変があり、白色で粘性のある排出物を認め痛風結節と診断。尿酸が12.2mg/dlと高値。腎結石を伴っていた。極度のるいそうがあり、10年前から神経性食思不振症と診断されている。極度のるいそうは高ケトン血症を伴うが、ケトン体は尿細管での尿酸再吸収を促し、高尿酸血症の原因となる。痛風はほとんどが男性で女性ではきわめて稀だが、エストロゲンが尿酸の再吸収に関与する尿酸トランスポーターの分解を促進するためと考えられている。女性の痛風は、男性より高齢で、腎障害や利尿剤が関与することが多いが、本例のように栄養障害に伴う例もある。
そう言えば、若い女性の痛風結節は記憶に残っていない。尿酸は抗酸化物質として働いている一面もあり、悪いことばかりではないらしい。ちなみに尿酸トランスポーター(URAT1)を阻害するのが、ユリノーム(尿酸排泄促進薬)の作用点である。
-
ペットボトル症候群は、潜在性2型糖尿病患者が、糖質を多く含むソフトドリンクを多飲することによって生じる一過性のケトアシドーシスで、肥満を有する若年男性に好発する。偏食と不規則な食生活が基盤にあり、ビタミンB1不足がケトアシドーシスを助長する。エネルギー代謝上はダイエットの際と同様、β酸化に依存した不飽和脂肪酸由来の過酸化脂質の増加があり、それが色素性痒疹の原因となる。しがって、抗酸化作用のあるミノサイクリンやDDSが有効である。
栄養と皮膚病変の関連を判りやすく説明してもらった。検査で重要なのは、血糖、HbA1cのほか、尿中ケトン体陽性、浸透圧利尿に伴う血球数の増加、総蛋白の上昇、低Na血症のを確認すること。
-
ボツリヌス毒は、局所皮弁の血行を改善し、低酸素によるストレスを抑制する働きがあるとされている。マウスの背部を用いた褥瘡モデルで、ボツリヌス毒の局注は潰瘍形成を有意に抑制した。褥瘡の予防に有用かもしれない。
コストも含めて現実的に使用されることはなさそうだが、面白い薬理作用である。多汗症と同じ薬効持続期限かどうかは、ヒトでの検証がまだとのことで、不明である。
-
体幹・四肢に散在する弛緩性水疱とびらんを認める高齢男性。病理組織は表皮下水疱で、蛍光抗体直接法では基底膜にIgG陽性。間接法も基底膜に陽性で320倍。1M生食によるsplit skinでは、IgGが表皮側に陽性。抗BP180 NC16a抗体は陰性で、ウェスタンブロットでは180kdの17型コラーゲン(COL17)リコンビナントC末端領域に陽性であった。Nc16a抗体添加の培養表皮細胞は、COL17量が減少したが、C末端抗体では正常血清とほぼ同等で、COL17の減少度と臨床的重症度が関連している。
高齢者の軽症あるいは限局性の水疱は時に経験する。最近はBP180Nc16a抗体が陰性だと、BP疑いで終わりにしてしまうことが多くなったが、以前のようにちゃんと生検をして、DIFをして、正常皮膚を基質としたIIFをやらないとダメだと感じた。
-
26例の慢性に経過する痒疹患者で、臨床診断を検討した。結節性痒疹とした5例、多形慢性痒疹とした5例を除く16例が分類不能であった。16例中、多くの症例では躯幹および四肢の比較的広範囲に、蕁麻疹様紅斑を生じ、これらの症例ではTARC値が古典的2型より高く、ステロイド内服歴がある患者が多かった。蕁麻疹様紅斑の消褪したあとに苔癬様の局面を形成し、さらに丘疹紅皮症(太藤)に移行する例もあり、治療の影響もあり、分類が混沌としている。
30年来のの懸案で、なかなか結論がつかないようだ。内臓悪性腫瘍が見つかれば、筋が通るのだが、決して多くはない。降圧薬、高脂血症治療薬などの薬剤の影響も否定できない。ただ、痒疹結節に至る理由が「掻破」であることは間違いないと感じている。
-
成人発症の多発性疣贅で肛門癌を併発。家族歴なし。肛門癌からはHPVのハイリスク型が検出された。骨髄異形症候群の合併があり、転写因子であるGATA2遺伝子に変異を認めた。常染色体優生遺伝によるGATA2変異が原因の疾患をEmberger症候群と呼び、感音性難聴、細胞性免疫不全、骨髄異形症候群あるいは慢性骨髄性白血病などの主症状に加え、皮膚では反復性で多発する疣贅が特徴とされている。
GATA2は造血幹細胞の増殖や維持に必須の転写因子で、GATA2異常症としては、単球減少と非結核性抗酸菌症を伴う免疫不全症として報告されたのが最初らしい。皮膚にも色々な症状を起こしてきそうなので、一応、覚えておこう。
-
バリア機能を定量的に表す指標を、テープストリッピングで得た角層内タンパクから検索した。角層中Galectin-7、HSP27は経表皮水分蒸散量と生の相関があり、角層内水分量と負の相関があった。Galectin-7は基底層に多く存在し、創傷皮膚で誘導される蛋白であり、HSP27は顆粒層に多く分布し、UVBや界面活性剤などの外的刺激で増加する。簡便に採取でき、ぶれの少ない結果が得られるため、角層バリアの状態把握に有用である。
患部の病変の有無や部位による差がありそうだが、同じ部位からの検体を治療前後で比較すれば、有用なマーカーになりそうだ。
-
皮膚の血管異常(vascular anormaly)は内皮細胞の増殖性変化による血管腫と、局所の形態異常を主体とする血管奇形に分類される。日本形成外科学会と日本IVR学会は、2013年に診療ガイドラインを策定した。国際血管異常研究機関(ISSVA)分類に基づく病名を踏襲し、莓状血管腫は血管性腫瘍の中の乳児血管腫、単純性血管腫は内皮細胞の増殖がないので毛細血管奇形、海綿状血管腫は同様に静脈奇形、リンパ管腫はリンパ管奇形となった。また、古典的には巨大血管腫においてKasabach-Merritt症候群の合併が知られているが、最近の研究ではこれを合併するのは乳児血管腫ではなく、Kaposiform hemangioendotheliomaやtufted angioma(別称angioblastoma of Nakagawa) など他の稀な血管系腫瘍であることが示されている。
血管炎がChapel Hill分類を踏襲して病名が変わってしまったように、血管腫の病名も国際基準に当てはめられることになるのだろうか。血管腫・血管奇形診療ガイドラインは医療情報サービスMinds(http://minds.jcqhc.or.jp/)で全文が公開されている。勉強しておこう。
-
サルコイドーシスの診断基準が改定される。日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会が担当。組織診断群と臨床診断群に分け、下記の基準にしたがって診断する。
【組織診断群】全身のいずれかの臓器で壊死を伴わない類上皮細胞肉芽腫が陽性、かつ、既知の原因の肉芽腫および局所サルコイド反応を除外できているもの。
ただし、特徴的な検査所見および全身の臓器病変を十分検討することが必要である。
【臨床診断群】類上皮細胞肉芽腫病変は証明されていないが、 呼吸器、眼、心臓の3臓器中の2臓器以上において本症を強く示唆する臨床所見を認め、かつ、以下の特徴的検査所見の5項目中2項目以上が陽性のもの。1) 両側肺門リンパ節腫脹、2) 血清ACE高値または血清リゾチーム値高値、3) sIL-2R)高値、4) GaシンチまたはPETにおける著明な集積所見、5) 気管支肺胞洗浄検査でリンパ球比率上昇、CD4/CD8比が3.5を超える上昇。
検査所見から、血清中Caとツ反陰性が消えた。難病法ではすべての指定難病に重症度分類を加味した認定基準の銘記が義務づけられ、それに対応した新基準とのことである。重症度分類もサルコイドーシス学会のHP(http://www.jssog.com/)で見ることができる。それにしても難病法の申請用紙は、以前より書きにくくなった。
-
異汗性湿疹や内因性アトピー性皮膚炎で問題になるニッケルによる全身性接触アレルギーは、内服再投与試験で証明することが必要。ニッケルの負荷は、リンツチョコレートの85%(1枚に470μgのニッケルを含有)を用いて、1日あたり1/2枚を4日間摂取することを標準としている。通常の食事で得られる量の2倍にあたる。
金属のパッチテストでニッケル、クロム、コバルトが陽性であれば、チョコレートは控えるようにと指導はしているが、負荷試験までは行ったことがない。チョコレートを使って患者にとって受け入れることが可能な金属負荷試験の標準があれば、参考になる。これなら開業医でもできそうだ。
-
野良ネコの寿命が長くなり、エイズを発症するネコが増えたことから、ネコに発生するスポロトリコーシスが増加している。原因菌はsporothrix globosaによる。臨床型はヒトと同様で、皮膚限局型、皮膚-リンパ管型および播種型がある。ネコでは難治性の皮膚潰瘍を呈するが、キズをなめるために口腔や鼻腔、爪に付着することがヒトへの感染拡大の原因となる。飼い主や獣医師は注意が必要。
スポロトリコーシスが人畜共通感染症だとは知らなかった。ペットの皮膚病は医真菌学会で時々講演を聴くが、ペットを飼う人が増えていく現状では、皮膚科医も注視が必要だと思う。
-
真皮内母斑あるいは真皮病変が主体の複合母斑で、続発性骨形成を認めることがあり、Nantaの骨母斑と呼ばれている。臨床的には通常の色素細胞母斑と変わらないが、ほとんどが顔面に生じる。骨組織は母斑細胞塊から少し離れた深部に認められることが多く、母斑細胞の増殖によって閉塞した毛包が嚢腫状に拡張し、嚢腫の破綻が異物肉芽腫を生じ、徐々に骨組織が形成されることが成因と考えられる。
確かに顔の色素細胞母斑の下に嚢腫があることは、よく経験する。名称からはもっと特殊なnevusかと思ったが、意外に身近にありそうだ。原著は1911年でNantaはフラン人。
-
クロムはさびにくい金属で、自然界では土中にクロム単体または3価クロムの形で広く存在しする。一方、クロムメッキには原料として毒性の強い6価クロムが多用されている。クロム皮膚炎は皮革(3・6価)、マッチ(6価)、塗料(3・6価)、ブリーチ剤(6価)、洗剤(3価)、染料(3価)、青インク(3価)、セメント(6価)が原因となる。パッチテストの試薬では、3価クロム化合物として硫酸クロム2%、6価クロム化合物として重クロム酸カリウム0.5%がある。皮革によるクロム皮膚炎は、皮なめし(天然の皮が腐敗し安くまた、乾燥すると板のように硬くなり柔軟性がなくなるという欠点を取り除く作業)に塩基性硫酸クロム塩を使用するために起こる。
2種類の試薬の違いを再認識した。3価と6価の両方あるいはどちらか一方が陽性であれば、それぞれある程度原因を絞れることになる。皮なめしについては、以前から疑問だったが、何が目的かよくわかった。ちなみに、なめしていない状態を「皮」と呼び、なめしたものを「革」と呼ぶらしい。
-
・VKA(Vitamine K antagonist):=ワーファリン。プロトロンビン時間国際標準比(PT-INR)のモニタリングによって治療効果を確認できる。逆に言えば、適正なINR値(1.6~2.6)になるよう、増減を調整する必要がある。コントロールの質を評価する指標として、TTR(Time in Therapeutic Range: 治療域内時間)があり、65%を保つことが推奨されている。
・DAPT(Dual antiplatelet therapy):アスピリン+チエノピリジン系抗血小板薬(パナルジン・プラビックス・エフィエント)による抗血栓療法。DAPTがアスピリン単独およびアスピリン+ワーファリンと比較して30日までのステント血栓症を有意に抑制することが証明され、DAPTはステント留置後の血栓症予防の標準治療となった。ただし出血性合併症にはVKAと同様に注意が必要。
・NOAC(non-VKA oral anticoagulants):DOAC(direct OAC)、TSOAC(target specific OAC)という用語も提唱されている。VKA治療中、適正なINRでも出血傾向の強い患者、内視鏡やポリープ切除を頻繁に行う患者ではVKAからの変更を考慮するが、腎機能障害のある患者には使いにくい、出血性の合併症があったときの拮抗薬がないなどのデメリットもある。現在以下の4種類がある。プラザキサ(トロンビン直接阻害薬)、イグザレルト・エリキュース・リクシアナ(第Xa因子選択的阻害薬)
作用機序の違う新薬が上市されるのはありがたいが、糖尿病や高血圧症、皮膚科領域ではニキビなど、同種同効薬の使い分けや既存の治療薬との併用の方法など、選択が難しい場面が多くなってきた。
-
トコジラミ(ナンキンムシ)による虫さされのまとめ。2000年以降、ピレスロイド耐性となり、2005年以降は日本でも増加している。トコジラミ刺症は、1~3回は無反応、4回目以降は遅延型の反応が起こり、毎回発疹を生じるようになる。感作には3~9日を要し、出張先や海外のホテルで宿泊してから1週間もたってから皮疹が出現してくることがある(spontaneous flare up)。反対に、くり返し刺されているうちに、反応の減弱が見られることもある。対策としては、現在は大半のトコジラミがピレスロイド系殺虫剤耐性であり、効果があるのはカーバマイド系(プロポクスル)とスミチオンを用いるのがよい。
虫刺されと診断しても、何に刺されたかといわれて、対応に困ることは多い。蚊の場合など、虫さされで「遅延型反応」があることは承知しているがせいぜい2~3日だと思っていた。1週間たって出現するとは思わなかった。
-
生来健康な女性。イタリア旅行から帰国後、四肢、体幹に複数のせつ、ようをくり返し生じるようになる。創部と鼻腔の細菌培養でMRSAが検出された。MINO、ST、GM、抗MRSA薬に感受性があり、経過から市中感染型MRSA(CA-MRSA)感染症と診断した。CA-MRSAは、特徴として、Panton-Valentine leukocidine(PVL)と呼ばれる白血球破壊毒素を産生し、IV 型のメチシリン耐性遺伝子領域(SCCmec)をゲノム上に持っている。皮膚の接触で感染が拡大すると考えられ、健康な小児や若年者の深在性の皮膚・軟部組織の感染症が特徴的である。
学校の寮、軍、刑務所、感染者のいる家庭などで、感染のリスクが高くなる。PVLが陽性だと、皮膚、粘膜に強く粘着し、症状としては、せつ、よう、皮下膿瘍をきたす。一方、伝染性膿痂疹からも20%ほどMRSAが検出されるが、PVL陽性はまれとのこと。
-
60代女性の両足蹠全体に、黄色調を帯びたやや赤い角化性局面が1カ月前から出現した。手掌はほぼ正常。同時にみとめられた顔面と両下腿の浮腫から粘液水腫を疑い、臨床検査上、T3とT4の低下、TSH上昇、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体陽性で、橋本病と診断。チラージンSの内服で軽快している。
足蹠の角化は色々と鑑別が必要だと認識している。遺伝性疾患、健康サンダルなどの物理的要因、薬剤性、内臓悪性腫瘍のデルマドローム、あるいは尋常性乾癬、接触皮膚炎などの皮膚疾患など。甲状腺機能低下でも起こることは、記憶にとどめておこう。
-
味覚異常を訴える患者で、口腔内のカンジダ症が原因のことが少なくない。抗真菌薬の含嗽、内服で改善する症例が、20%ほど存在する。味覚検査は皮膚科では一般的ではないが、テーストディスクRという臨床検査試薬があり、塩味、甘味、酸味、苦味について、濃度の低い順に鼓索神経領域(舌の先)、舌咽神経領域(舌の根元)、大錐体神経領域(軟口蓋)にあてて、味を感じる閾値をみることで治療前後の味覚を評価できる。
味覚の臨床検査があるとは知らなかった。ただ試薬の操作法をみると、1回ずつうがいで残味をとり、さらに1分以上おいて次の試薬をのせる、とのこと。1回の検査に1時間以上かかるらしい。
-
好塩基球を皮膚病理組織中に確認するために、好塩基球特異的なbasogranulinに対するモノクロナール抗体(BB1)を用いた免疫染色を行った。疥癬、マダニ刺症、トコジラミによる虫刺症、アトピー性皮膚炎患者のダニ抗原貼付部位など、寄生虫の関与する疾患では例外なく浸潤していた。また、慢性痒疹、持続の長い蕁麻疹、好酸球性膿疱性毛包炎、アナフィラクトイド紫斑でも病変部に好塩基球浸潤がみとめられた。痒疹丘疹を形成する疾患が多く、好塩基球が関与している可能性が高い。
皮膚の炎症においても、肥満細胞との役割の違いがあるということで、興味深い。好塩基球浸潤を抑制できれば、痒疹にいたる反応を食い止めることができるかもしれない。治療にも結びつきそうだ
-
interstitial granulomatous dermatitis(IGD)はもともとは関節症状を伴い、体幹・四肢近位の紅斑ないし索状の皮内結節が生じ、その病理組織は非感染性肉芽腫性炎症であるが、柵状配列はとらず、真皮の膠原線維を分け入るように浸潤するものをいう。また、類縁疾患であるpalisaded neutrophilic granulomatous dermatitisに比べると、好中球浸潤は少ない。通常は自己免疫性疾患や悪性腫瘍に伴って生じるが、近年は、薬剤によって誘発されることが報告され、降圧薬、高脂血症治療薬、抗ウイルス薬、抗痙攣薬などが原因となることがある。薬剤の中止で消褪する。
関節リウマチによる真皮結合織の変性によって生じると理解していたが、薬剤によって起こることがあるとは知らなかった。病理組織所見が臨床診断名になってしまうと、イメージがわかない。また、病理組織のバリエーションを受け入れられず、また新しい病名がついてしまう。
-
アレルギーハイリスク児の出生コホートの多変量解析の結果。1歳の時点での卵白感作は、生後6カ月までの顔の湿疹、母のアレルギー歴、4カ月までの母乳栄養、生後6カ月の顔の黄色ブドウ球菌の保菌が関与していた。卵白の経皮感作以外にも複数の因子が関与していて、単なるスキンケアだけではアレルギーマーチを抑制できるとは限らない。
確かにその通りだと思う。スキンケアを四六時中行っても、ほんの一瞬の接触が、感作を起こすこともあるだろう。結局、環境に慣れるのが一番の解決策に思える。
-
かゆみの評価はこれまで、VAS(visual analogue scale)やNRS(numerila rating scale)が臨床研究や治験に用いられてきたが、これらは単にかゆみの強さの一側面を評価するに過ぎない。「5D itch scale」はかゆみを5つの構成要素(Duration:持続時間、Degree:強さ、Direction:経過、Disability:QOL障害、Distribution:分布)から評価し、点数化する尺度で、成人のアトピー性皮膚炎患者に使用したところ、かゆみのVAS、皮膚病変スコア(SCORAD)、DLQIとの間に有意な相関が得られた。
5Dかゆみスケール日本語版が使えるようになったとのこと。VASより答えやすいと思われ、今後は治療薬の評価で使われることになるだろう。
-
20代男性例。手背、前腕に左右対称性に褐色の色素斑が以前からあり、鼻翼にも淡い褐色斑が目立ってきた。病理組織では真皮上層の真皮メラノサイトとメラノファージを認める。顔面四肢型後天性真皮メラノサイトーシスと診断した。本疾患はきわめて特徴的な臨床像で、一部に家族内発症を認めることから独立した遺伝性疾患の可能性が考えられる。
こういうタイプがあるとは知らなかった。後天性真皮メラノサイトーシスにはいくつかの亜型があって、背中に左右対称性の病変を伴う例や、中高年男性に生じ、悪性腫瘍に併発する例もあるという。面白い疾患である。
-
動脈硬化症では内膜にリンパ球、単球、樹状細胞などの炎症細胞浸潤があり、成因に炎症が関与すると考えられるが、その生物学的基盤は明かではない。無細胞系での高効率なタンパク合成技術で得られた約2000種類のタンパク質に動脈硬化症患者より採取した血清を反応させ、血清中の自己抗体を解析したところ、Th2サイトカインであるIL-5に対する抗体が高値であることが明らかになった。また、血中抗IL-5抗体価は有意に血中IL-5濃度と逆相関しており、患者血中の自己抗体がIL-5の働きを抑制している可能性が示唆された。抗IL-5抗体は、動脈硬化症の新規バイオマーカーとして、動脈硬化症の早期発見、早期治療に有用かもしれない。
皮膚科領域でのIL-5は、Th2反応を誘導する悪者的なイメージがあるが、IL-5の低値が動脈硬化をきたす、というのは意外な感じである。血中IL-5が高値で、好酸球増多がある人(アトピー性皮膚炎など)は、動脈硬化が生じにくいのか、検討の余地がありそうだ。
-
皮膚生検による円形脱毛症の診断とその要点の解説。4mmパンチで2カ所、毛球部まで円筒形にくりぬく。1つは通常の縦切り標本を作り、表皮基底層や毛包全体の構造変化をみる。もう1つは浅い部分から水平に4分割して水平面での状態の組織標本を作る(上から漏斗部、狭部、毛球上部、毛球部)。4mmパンチの生検では標準値があって、毛包は20本、毛周期の比率は、通常0~15%が休止期毛である。生検では、毛包の破壊が起きている部位の同定、terminal hairとvellous hairの割合(ミニチュア化)、anagen/telogen比を確認する。円形脱毛症ではミニチュア化した毛包は30%を超えない。また、急性期と慢性期で違いがあり、急性期では毛包周囲に炎症性細胞浸潤がみられ、慢性期になると次第に休止期の毛が増え、両者が混在した像をとる。なお、男性型脱毛症はミニチュア化した毛包の増加、休止期毛の増加があり、総毛包数は変化しない。また薬剤、産後、栄養障害などによる休止期脱毛は、休止期毛が増えるが総数は変化せず、ミニチュア化もない。
以前に、「白髪は太い」という話を聞いて、そうだったのかと思ったことがある。こういう数量的解析も面白い。
-
薬剤性の休止期脱毛の原因薬には、三環系抗うつ剤、SSRI、リチウムなどの向精神薬と、シンバスタチン、ベサフィブラートなどの高脂血症治療薬が多い。特に、向精神薬による休止期脱毛では高プロラクチン血症を伴うことがあり、女性では生理不順があるかどうかが参考になり、血中プロラクチン値の測定で確認する。プロラクチンには毛生長を抑制する作用がある。
一方で、高プロラクチン血症は多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)に伴う例があり、この場合には多毛を併発する。これは、下垂体LHの産生過剰による副腎性アンドロゲン(DHEA-S)の増加によるということ。先日、女性化乳房のある50代の男性患者が来院し、向精神薬による高プロラクチン血症を伴っていたが、髪の毛は年相応だった。かなり複雑である。
-
新生児TSS様発疹(Neonatal Toxic Shock Syndrome-like Exanthematous Disease:NTED)は新生児に生じる発疹症で、①生後7日以内に出現する紅斑、②皮膚症状に先行する38℃以上の発熱、③血小板減少(10,000/mm3以下)を特徴とする。MRSAがもつTSST-1による疾患であり、TSST-1がスーパー抗原としてVβ2細胞を活性化することが原因とされる。皮膚症状は成人のTSS同様、猩紅熱様、日焼け様紅斑で、苺状舌を伴う例があるが、成人のTSSより軽症で、経過も短い。新生児室でこのような症例があれば、施設にMRSAが蔓延していることを示唆し、また新たな発生をみた場合にはMRSA対策が必要となる。
新生児の発疹症は診る機会がないので勉強になった。SSSSのようなびらんにはならないらしい。
-
ウイルスに対する血清抗体価は種々の方法があるので、検査の原理を理解する必要がある。CF(補体結合反応)は患者血清とウイルス抗原に補体が結合し、消費されるため、本来起こるはずの溶血反応が起きなくなる現象を利用する。主としてIgGを反映する。VZVなど、通常は1年以内に消失するが、HSVでは生涯低下しない。NT(中和抗体)はウイルス粒子と特異的に結合して感染能力を失活させる抗体で、型別判定に用いられる。ただし、HSVでは1型と2型の間に交叉反応があるため、正確な診断はできない。
例外もあるので簡単ではないが、検査の原理は理解しておく必要がある。HSVのNTに関しては、交叉反応があるとは知らなかった。症例の蓄積がさらに必要だろう。
-
2010年に報告された米国で行われたSTEPP試験。結腸癌に対する抗EGFR抗体療法中に生じる皮膚障害に対して、以下の予防療法の有用性をオープンラベル無作為化試験で検討した。①保湿剤を起床時に全身に塗布、②外出時に日焼け止めを塗布、③就前に1%ヒドロコルチゾンクリーム(ロコイド)を全身に塗布、④ドキシサイクリン100mgを1日2回内服。予防を行った群では、全般的な皮膚障害が62%から29%に減少。治療の中止が必要となる重症の皮膚障害が21%から6%に減少した。症状ごとでは、ざ瘡様発疹、爪囲炎、かゆみがそれぞれ21%から4%に、6%から2%に、11%から2%に減少した。
副反応として皮膚症状が起こるのは薬剤が効いている証拠という考え。皮膚障害を軽減させ治療を中断せざるを得ない患者を減らすか、という観点である。かなり大がかりな予防法で、何となく受け入れがたい。日本ではここまでの対応はされていないのではないか。
-
粘膜類天疱瘡(mucous membrane pemphigoid:MMP)は以下の2つのタイプ、抗BP180型粘膜類天疱瘡と抗ラミニン332型粘膜類天疱瘡がある。抗ラミニン332型粘膜類天疱瘡は、胃癌、肺癌、卵巣癌、肝臓癌などの固形癌を合併することが多いため、両者の鑑別は重要である。1mol食塩水剥離皮膚を用いた蛍光抗体間接法検査を行い、表皮側に反応すれば抗BP180型、真皮側に反応すれば抗ラミニン332型と簡易診断ができる。他に、眼型MMPがβ4インテグリン、口腔粘膜MMPがα6インテグリンに対する自己抗体で生じるとのこと。
瘢痕性類天疱瘡と呼んでいた時代の知識しかなく、MMPという略語も知らなかった。どうやら、すべてが瘢痕になるわけではないというのが、名称がかわった理由らしい。なお、抗BP180型のMMPの自己抗体は、通常の水疱性類天疱瘡で検出されるN末端のNC16aではなく、C末端に対する抗体なので、コマーシャルの検査では陽性にならない。
-
形質細胞様樹状細胞(pDC)はヒト皮膚癌の排除に重要な役割を担うことが示された。日光角化症においても、病変部直下にpDCが浸潤している。ベセルナクリームによる癌免疫賦活化作用は、局所のpDCの浸潤を増加させるためと考えられている。実際、日光角化症病変部に浸潤するpDCは、ベセルナクリーム外用後に著明に増加していた(抗BDCA-2抗体を用いた免疫染色による定量)。また、外用開始7~10週後の病変内に浸潤するpDCの数と臨床的に日光角化症が消失するまでの期間には相関があり、pDC数が多いと消失が早く、少ないと消失までに時間を要することがわかった。
浸潤してきたpDCが産生するINF-αが癌抑制に働くらしい。ベセルナクリームのnon responderにはINF-αの直接的投与が有効かもしれない。説得力のある臨床研究だった。
-
魚摂食後の急性蕁麻疹40例の集計。年齢は8歳から76歳で平均55歳。性別は男性26例、女性14例。アニサキス特異抗体がclass 3以上が40例中24例で60%。摂食した魚は、サンマ、マグロ、メカジキ、サケ、アイナメであった。
アニサキスによる急性腹症や嘔吐などの消化器症状も、感作されたヒトに起こるらしい。胃粘膜を貫通して腹痛を起こすのかと思っていた。急性蕁麻疹だけの患者と腹症を起こす患者で何が違うのだろうか。いずれにしても魚による蕁麻疹患者では、アニサキスの特異的IgEを計測することは必須だと思った。
-
グミキャンディー摂食後の蕁麻疹と咽頭違和感。成分表にあったリンゴ、ゼラチンの血清中特異的IgEは陰性。グミキャンディーas is のプリックテストでは陽性。成分別ではコラーゲンペプチドで陽性。その他、ゼラチン、香料、光沢剤などでは陰性。この製品のコラーゲンペプチドは魚由来だった。
グミキャンディーといえばゼラチンを想像するが、この症例は魚のコラーゲンが原因だった。ちなみに、通常、グミキャンディーのコラーゲンは豚由来らしい。
-
複数の施設からの症例報告。イソチアゾリン系防腐剤のうち、メチルイソチアゾリン(MI)は2004年以降、leave-on 化粧品への使用が許可され、化粧水、乳液、美容液マスク、BBクリーム(オールインワン化粧品)による接触皮膚炎が最近増加している。国内製、外国製を問わず、化粧品による接触皮膚炎の原因成分として重要である。
覚えておく必要がある。メチルイソチアゾリンのほか、メチルクロロイソチアゾリン(MCI)による症例もあった。MCIは冷感タオルに含まれていた。なお、洗い流さなくてよい化粧品がleave-on で、その反対にシャンプーなどの洗い流す製品をrinse-off と呼ぶとのこと。
-
テグレトールによる薬剤性過敏症症候群の経過中、発症5日目にIgGが1119mg/dl、発症14日目には716mg/dlと低下、発症20日後に1294mg/dlと急速に増加(回復)したときに一致して、掌蹠に汗疱が生じた。神経疾患や川崎病などの際の免疫グロブリン大量療法後にも汗疱を生じることがあり、急激な免疫グロブリンの上昇が汗疱の原因ではないかと考えた。
これも意外な原因と結果である。多汗とは必ずしも関連しないようだ。高γグロブリン血症をきたす慢性疾患でも汗疱は出やすいのか。シェーグレン症候群では出そうもないが、多発性骨髄腫ではどうだったか。覚えておこう。
-
分娩3日後に授乳を開始。翌日の授乳直後から膨疹を生じるようになった。その後も数回、授乳時と搾乳時に膨疹。1カ月後には搾乳時に呼吸困難を生じた。Breast feeding anaphylaxisと診断。発作時の血漿中ヒスタミンは正常。自己乳汁によるプリックテストが陽性で、乳汁添加で末梢好塩基球からのヒスタミン遊離がみられた。乳汁が出なくなるとともに症状は消褪した。
そもそも、母乳は自身の血液が原料で、その過程のどこで、アレルゲン?が混入するのか非常に不思議だ。なお、治療は断乳と、母乳の分泌を抑えるための高プロラクチン血症治療薬のカベルゴリン(カバサール)という薬剤の内服とのこと。
-
30代の女性。ホットヨガののあと両下肢に浮腫が生じ、左大腿には圧痛のある発赤腫脹が生じた。生検ではリンパ何の周囲に平滑筋様細胞の増生。全身CTで肺に多発性の嚢胞があり、リンパ脈管筋腫症(lymphangioleiomyomatosis:LAM)と診断した。LAMは妊娠可能な女性に好発する希少疾患であり、遺伝子異常を起こした平滑筋様細胞(LAM細胞)が肺やリンパ節などで増殖する。LAMには遺伝性のない孤発性LAM(sporadic LAM:S-LAM)と遺伝性の結節性硬化症(TSC)に合併するLAM(TSC-LAM)の2種類がある。結節性硬化症の1/3にLAMが合併するとのこと。
リンパ浮腫の原因の一つとして覚えておく必要がある。LAMは、TSC1またはTSC2の遺伝子変異の結果、これらの遺伝子がコードするハマルチンおよびツベリンが複合体を形成できず、mTORの活性が抑制されず恒常的に活性化されるために発症する。最近、mTORの阻害作用を有するシロリムスがLAM治療薬として承認された。
-
IgG4関連疾患の包括診断基準。1) 臨床的に単一または複数臓器に、びまん性あるいは限局性の腫瘤、結節、肥厚性病変を認める。2) 血中のIgG4が高値(135mg/dl以上)。3) 病理学的に著明なリンパ球、形質細胞の浸潤と線維化を認め、IgG4陽性形質細胞浸潤があること。自己免疫性膵炎、硬化性胆管炎、Mikulicz病、腎症、呼吸器疾患については別に診断基準がある。
最近よく学会で症例報告を聞くが、どうもピンとこない。皮膚科的にはシェーグレン症候群、サルコイドーシス、形質細胞腫、悪性リンパ腫、木村病、高γグロブリン血症性紫斑と診断された症例の中にこの疾患が紛れ込んでいる可能性を考えておけばよいのか。勉強が必要だ。
-
製品評価基盤機構(NITE:National Institute of Technology and Evaluation)は、経産省系の独立行政法人で、国民生活の社会的リスクを低減するという使命のもとに活動していて、製品に含まれる化学物質による皮膚炎対策にも対応してきた。これまで、繊維製品のホルムアルデヒドや、ナフトールASの接触皮膚炎、デスクマットに含まれていた抗菌薬の接触皮膚炎などで関係省庁への情報伝達のかなめとなった。ただし関連する法規は消費生活用製品安全法(経産省)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(厚労省)、消費者安全法(消費者庁)と製品分野ごとに異なる。今後は基本となる法令を定める必要がある。
石鹸による小麦アレルギーで経験したように、皮膚科医も消費者の安全に留意して、被害情報を行政に速やかに伝達する必要がある。ちなみに、化粧品と医薬品による健康被害についてはNITEの仕事ではなく、薬事法に基づいて厚労省が管轄している。
-
ヘリコバクター・ピロリ除菌は、胃潰瘍・十二指腸潰瘍のほか、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後、慢性胃炎に適応があり、播種状紅斑丘疹型薬疹をきたすことが少なくない。多くはアモキシシリンが原因であるが、中にはランソプラゾールが原因の場合と、非特異的反応(抗菌薬によって破壊されたピロリ菌が抗原か)によって生じている場合がある。薬疹患者の血清グロブリンは健常者より低値(2.9g/dl以下)で、スーパー抗原となりうるHERV-K18の発現が末梢血単核球中に確認されるなど、複数の要因がありそうだ。
数例の経験があるが、臨床的にも間擦部中心の紅斑で、アモキシシリン単剤による薬疹に特徴的なので、全部アモキシシリンかと思っていた。確かに梅毒のJarisch-Herxheimer反応のようなことが起こっても不思議ではない。
-
慢性蕁麻疹でフォロー中の60代女性。鶏眼にスピル膏を貼付すると、その翌日に体幹・両下肢に膨疹が出現する。アスピリン負荷テストで再現性あり。アスピリン不耐症と診断した。スピル膏貼付試験では、貼付部位には皮膚症状は生じなかったが、1時間後に体幹の膨疹と顔面の発赤、2時間後には両頬、腹部に膨疹が生じた。サリチル酸が原因と確認できた。
アスピリン不耐症は、慢性蕁麻疹で念頭に置かねばならないと思いつつ、なかなか見つけることができていない。スピル膏の貼付テストは、アスピリン不耐症の診断に使えそうだが、どうだろう。
-
第65回日本皮膚科学会中部支部総会から(平成26年10月26日)
納豆アレルギーは、即時型アレルギーだが、摂食直後ではなく摂食12時間後に出現することが知られている。原因は、粘稠物質のポリγグルタミン酸(PGA)で、摂食後に消化管で徐々に分解され、アレルゲンとして作用すると考えられている。患者の多くはサーファーで、クラゲの摂食後にアナフィラキシーを併発した症例があった。クラゲの毒針にはPGAが含まれていて、刺傷時にクラゲPGAで経皮感作される可能性がある。納豆アレルギーの患者にはクラゲ刺傷の既往を問診する必要がある。
マダニ刺傷と魚卵・牛肉アレルギーに次ぐ、新しい経皮感作-即時型アレルギーの臨床例か。面白くなってきた。
-
第65回日本皮膚科学会中部支部総会から(平成26年10月26日)
加工食品には何らかの指定添加物(食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物)が含まれている。皮膚病変を起こす可能性のある成分は、保存剤としての安息香酸ナトリウム、パラベン(パラオキシ安息香酸ナトリウム)、抗酸化剤としてのブチルヒドロキシアンソール、漂白剤としての亜硫酸ナトリウム、そのほか、甘味料、香料、色素などがある。
基礎知識もなく法制も知らなかったので勉強になった。化粧品による接触皮膚炎で時々問題になるパラベンが食品にも入っているとは知らなかった。パラベンの遅延型反応が陽性の患者は、加工食品の摂取で何が起こるのか、気になった。
-
第65回日本皮膚科学会中部支部総会から(平成26年10月25日)
単球は血球の6%を占め、表面抗原CD14とCD16の発現によりclassical(CD14++CD16-)、intermediate(CD14++CD16+)、non-classical(CD14+CD16++)に分類され、健常人での割合はそれぞれ85%、5%、10%である。感染症、悪性腫瘍、関節リウマチなどで、intermediate、non-classical分画が増加する。また、膿疱性乾癬でも同様で、顆粒球吸着療法の有効性は、この分画の回収によると考えられている。実験的にはTGF-β1の刺激がintermediate単球を増加させる。
あまり話題にはなっていないようだが、肉芽腫を形成するような感染症との関連もあるのだろう。今後、さらに解析が進み、もっと面白い話が出てくるかも知れない。
-
第42回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成26年10月23日)
抗ARS抗体症候群は、筋炎、慢性の間質性肺炎、Raynaudやmechanic's handなどの非典型的皮膚病変、熱発などを主症状とする皮膚筋炎の亜型である。コマーシャルで計測可能な抗ARS抗体は主に抗Jo-1、抗EJ、抗PL-7、抗PL-12、抗KSのいずれかを反映し、抗OJは計測されない。抗ARS抗体陽性の165名を免疫沈降法で解析すると、それぞれの頻度は抗Jo-1が36%、抗EJが23%、抗PL-7が18%、抗PL-12が11%、抗KSが8%、抗OJが5%で、1例のみPL-7とPL-12の抗体が共存していた他は、互いに排他的であった。筋炎は抗Jo-1、抗EJ、抗PL-7に関連が深く、間質性肺疾患(ILD)は6抗体のすべてで関連した。皮膚筋炎様の皮膚所見は抗Jo-1、抗EJ、抗PL-7、抗PL-12の患者に頻度が高かった。したがって、臨床診断としては抗Jo-1、抗EJ、抗PL-7ではPM/DM、抗PL-12ではCADMまたはILD、抗KSと抗OJではILDとなる。
皮膚筋炎の臨床症状で、抗ARS抗体が陽性の場合は、抗Jo-1、抗EJ、抗PL-7、筋症状を欠くCADMでは抗PL-12が関連するということだ。抗Jo-1以外の抗体も個別に測定可能になれば、さらに理解が深まりそうだ。
-
第29回日本臨床皮膚科医会三ブロック合同学術集会から(平成25年11月24日)
抗MDA5(旧CADM140)抗体陽性の皮膚筋炎は全体の10~25%を占め、明らかな筋症状を欠くclinically amyopathic dermatomyositis(CADM)に多く、治療抵抗性で予後不良の急速進行性間質性肺炎が約70%と高率に出現する。間質性肺炎を生じた中の約半数は死亡しており、非常に予後の悪いサブセットといえる。関節痛を伴うことが多く、皮膚症状は、紫斑や穿掘性潰瘍などの血管障害を示唆する皮膚所見の存在が特徴的で、いわゆる逆Gottron 徴候も高頻度に認められる。抗MDA5抗体陽性患者では有意にIL-6、IL-18、M-CSF、IL-10が高値を示すことから、単球・マクロファージの異常活性化が病態の背景に存在すると考えられており、したがって、フェリチンが疾患活動性を反映する。
血球貪食症候群の時もそうだったが、フェリチンがマクロファージの活性化の指標であることが、皮膚筋炎でも出てきた。治療としては、シクロホスファミド間歇静注療法(IVCY)を含めた強力免疫抑制レジメンが必要だが、一度回復すると再発は少ないとのこと。
-
第139回横浜市皮膚科医会から(平成26年10月16日)
一次刺激性接触皮膚炎は、刺激物質が表皮細胞に細胞障害を与え、表皮細胞から放出されたアデノシン三リン酸(ATP)が炎症起因物質として働き、好中球を主体とした炎症反応が引き起こされて発症すると考えられている。亜鉛欠乏マウスは、正常マウスよりクロトンオイルによる一次刺激性皮膚炎が亢進するが、局所のATP量がより多く放出されることがその原因と考えられた。さらに、亜鉛欠乏マウスの表皮ではランゲルハンス細胞が著明に減少あるいは消失していた。ランゲルハンス細胞は、ATPを不活化する分子であるCD39を発現しており、ATPによる炎症の火消し役である。以上のことから、亜鉛欠乏症患者では表皮内ランゲルハンス細胞が減少あるいは消失しているために、ATPによる炎症を抑制できず、一次刺激性接触皮膚炎が増悪あるいは遷延化しやすいと考えられた。
生化学ではよく出てきたが、ATPが皮膚疾患と関連するとは思わなかった。亜鉛欠乏症における亜鉛補給の意義もよくわかった。亜鉛華軟膏の、皮膚炎に対する薬理作用にも関係するのではないかと思う。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成26年9月4日)
壊死性筋膜炎の起因菌はStreptococcus属、Vibrio vulnificus、Staphylococcus aureus、Enterococcus faecalisなどがありそのうちG群溶連菌は3.6%を占めている。これまでA群溶連菌では劇症例がみられる一方、G群溶連菌は皮膚や上気道に存在し病原性は低いと考えられてきた。しかし近年、基礎疾患を有する成人では壊死性筋膜炎やstreptococcal toxic shock like syndrome(STLS)などA群溶連菌による劇症例と類似した病態がG群溶連菌感染でも生じるようになった。G群溶連菌の多くを占めるStreptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis(SDSE)はA群溶連菌であるStreptococcus pyogenesが持つ病原因子との類似点が多い。A群では劇症型が54%、急性型が46%、亜急性型が0%、G群では劇症型が14%、急性型が56%、亜急性型が28%と報告されている。
G群溶連菌も危なくなったということは、念頭に置く必要ある。高齢化による社会全体の免疫低下状態が、色々な感染症の変遷と関係しているようだ。
-
第38回日本小児皮膚科学会から(平成26年7月6日)
Carney Complexは皮膚の色素沈着異常、粘液腫、内分泌腫瘍と機能亢進、神経鞘腫によって特徴付けられる疾患である。幼少時から、顔面や口唇、結膜、外陰部などに淡褐色から黒色の多発性色素斑を認め、思春期に数を増す。粘液腫は心の各房室に生じ、塞栓症をきたす。心以外にも皮膚、乳房、口腔にも生じる。内分泌腫瘍は原発性色素沈着性結節性副腎皮質病変(Cushing症候群)、GH産生性下垂体腺腫(末端肥大症)、精巣の大細胞石灰型セルトリ細胞腫、甲状腺濾胞性腺腫が特徴的。神経鞘由来のまれな腫瘍である砂腫状黒色神経鞘腫(psammomatous melanotic schwannoma: PMS)は約10%の患者にみられる。
これは難しい。ただ、口唇の色素斑はPeutz-Jeghers症候群に似ているようだ。体幹にカフェオレ斑を伴う症例もあり、色素異常をきたす先天性疾患の一つとしての認識が必要だろう。
-
第38回日本小児皮膚科学会から(平成26年7月6日)
メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症(Mendelian susceptibility to mycobacterial disease:MSMD)はBCGや非定型抗酸菌など弱毒抗酸菌に対して選択的に易感染性を示し、結核菌やサルモネラ菌などの細胞内寄生菌に対して重篤な感染症をきたす疾患。他の細菌や真菌、ウイルスなどに対しては易感染性を示さない。細胞内寄生菌に対する生体の防御機構は、主にIL-12/23、IFNγ経路であり、この経路に関わる分子異常により発症する先天性免疫不全症候群。IL-12受容体β1(IL-12Rβ1)とIFNγ受容体1(IFNγR1)が原因分子の症例が多い。MSMDではBCG接種後2/3の症例でBCG骨髄炎を生じる。
BCG接種後の結核疹は学会などで症例報告を見ることがあるが、MSMDという疾患については知らなかった。皮膚科医も覚えておく必要がありそうだ。
-
第38回日本小児皮膚科学会から(平成26年7月6日)
主として小児で2歳がピークで女児にやや多い。股部や肘窩に小紅斑で始まり、徐々に外方に拡大し、体幹の左右いずれかに残ることが多く、時に網目状になる。個疹は時間とともに淡褐色となり鱗屑を伴う。発疹の出現時に軽度の発熱、咽頭痛、リンパ節腫大を伴うことがある。発疹は数週続き、少なくとも3カ月以内に自然消褪する。Laterothoracic exanthemと呼ばれることもある。という疾患が、パルボB19感染症で生じる。成人例の報告もある。
報告例をみると、成人の体幹に出る、環状の蕁麻疹様紅斑に似ている。バルボB19のチェックはしたことがないが、興味がある。調べてみよう。
-
川崎市皮膚科医会・耳鼻科医会合同講演会から(平成26年6月28日)
アフタは病名でなく症候である。孤立性で癒合しないアフタは転移性アフタといい、細菌、ウイルスによる菌血症ないしウイルス血症による口腔粘膜への播種が原因である。細菌では腸チフス、ブルセラ症、ウイルスでは水痘、汎発性帯状疱疹、手足口病などで生じる。また、感染症の原発巣が明らかでない場合にも転移性アフタが生じることがある。この際には皮膚に膿疱や結節性紅斑が同時にみられることがあり、これをBehcet状態という。
転移性アフタもBehcet状態も、最近では使われなくなってきている疾患名であるが、どちらも病因と形態をよく表しているので、なくならないようにしたいと思った。
-
第854回日本皮膚科学会東京地方会から(平成26年6月21日)
長期にわたる血液透析患者に生じた下腿の有痛性潰瘍。組織学的にCalciphylaxisと診断した。チオ硫酸ナトリウム20gを透析後に点滴静注したところ、2カ月間で痛みはなくなり、潰瘍も改善してきた。チオ硫酸ナトリウムはカルシウムと結合してチオ硫酸カルシウムとなり、組織から遊離して血中に移動するため、異所性石灰化を改善させる。ただし、強い抗酸化作用から代謝性アシドーシスが必発であるため、血液ガスのモニターが必要である。
なかなかつらい疾患である。よい治療がないので、やむを得ないだろう。こういった治療があるとは、知らなかった。
-
第22回ALLIANCE HODOGAYA定例会から(平成26年6月14日)
高血圧治療ガイドライン2014(JSH2014)が発出された。高齢者高血圧への降圧薬治療はおおむねJSH2009が踏襲され、降圧最終目標は140/90mmHg未満、ただし75歳以上の場合はまず150/90mmHg未満を目指すことになる。高齢者に特徴的で降圧薬選択に影響を与える病態として、誤嚥性肺炎と骨粗鬆症が注目されている。ACE阻害薬は、咳反射を亢進することで高齢者での誤嚥性肺炎の頻度を減らすことが報告されている。また、サイアザイド系利尿薬はCa拮抗薬に比べると15%骨折の合併が減る。骨粗鬆症患者ではそれ自体の治療が重要であるが、降圧薬治療が必要な際にはサイアザイド系利尿薬が推奨される。
皮膚科に来院する高齢者では降圧薬の内服をしている人は多い。いくつかの選択枝のうち、なぜこの患者がその薬を飲んでいるのか、わかっているに越したことはない。こういった周辺の知識も必要である。ただ、日光疹が増えるのも困るのだが。
-
第113回日本皮膚科学会総会から(平成26年6月1日)
白斑が治りにくい理由のひとつに、病変部におけるカタラーゼの酵素活性が低下によって、過酸化水素や活性酸素が過剰に貯留し、その細胞毒性とメラニン重合体生成阻害作用により色素再生が起こらないことが知られている。したがって治療としてはカタラーゼや活性酸素分解酵素を皮膚に送り込めばよい。Vitixはこれらの酵素を多く含むメロンから抽出したエキスを椰子の実油で粒子化して皮膚に浸透しやすくした外用剤で、19人の白斑患者で6カ月間紫外線治療と併用し、白斑部の50%以上で色素の回復をみとめた例が78%に及んだ。
日本では、輸入代理店サンテナチュレルがこれを取り扱っている。日光浴の併用でも改善する例があるとのことで、指先など難治な例では試してみる価値があるとのこと。困った時には勧めてみよう。
-
第113回日本皮膚科学会総会から(平成26年6月1日)
補体結合反応(CF)で検出される抗体は、通常、罹患あるいはワクチン接種から1年あまり経過すると陰性化するが、単純ヘルペスウイルス(HSV)では、一度感染をおこすとCF抗体価が一生低下しない。したがってCF抗体陽性率は80歳代では90%に達する。HSVのCF抗体が陰性の場合は罹患歴がないと考えてよい。それに対して、帯状疱疹では、水痘罹患後に一旦水痘帯状疱疹ウイルス(HZV)CF抗体は上昇するが、罹患1年後には陰性化するので、帯状疱疹の発症直後のCF抗体は、2/3の症例で陰性である。ただし、帯状疱疹発症2週間後にはIgG抗体と同様にCF抗体も上昇するので、診断に利用できる。
片側性の痛みだけを訴え、しばらく経過を診ても帯状疱疹の発疹が出ない患者を年に数人経験する。発疹の出ない帯状疱疹と抗体価の変動から診断した例は、個人的には経験していない。単純ヘルペスのCF抗体は、他の疾患との鑑別には使えないということがわかった。
-
第113回日本皮膚科学会総会から(平成26年6月1日)
手術用具の解説。米国Delasco社のlocke Elevatorという名称の3X15mmの、剥離子が、爪甲を爪上皮や爪床から剥離するのに大変便利であるという話。陥入爪の爪廓形成術の際、予定切開線の外側にある余分な爪甲と爪上皮の間、および爪甲と爪床の間の狭いところに、それぞれ剥離子の先を滑り込ませて鈍的に剥離。爪甲を直線的に切り、ペアン鉗子で優しく引っ張ってくると爪と爪母を抜くことができる。爪上皮に生じるfibrokeratomaの摘除にも有用。
通販で入手可能とのことで、さっそくオーダーしたところ、2週間で届いた。Delasco社は医療機器以外にもシールやスタンプ、染色液やWood灯など、皮膚科関連の面白そうなグッズが勢揃い。ながめているだけで飽きない。
-
第113回日本皮膚科学会総会から(平成26年5月31日)
炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease:IBD)の話題。10~20代の若年者に好発し、原因不明で根治療法はなく、生涯にわたり再燃と寛解を繰り返す。ここ10年で倍増していて、将来は欧米並みの頻度(1万人にひとり)に達すると予測されている。治療の基本は薬物療法で、5-ASA製剤の内服が寛解維持、中等度以下の寛解導入に有効である。直腸や遠位結腸に病変の主座があれば、5-ASA製剤やステロイドの注腸が行われる。いずれも潰瘍部に到達してそこにとどまり、塗り薬のように効く。
5-ASAの内服は、通常の内服薬と同様の薬理作用だと思っていたので、少し驚いた。物理的に多くの量が必要なのもそのためだと理解した。他科の基本的な話もためになる。総会でこういった教育講演があるのも悪くない。
-
第113回日本皮膚科学会総会から(平成26年5月31日)
血管炎の病名はこれまでもChape-Hill分類を用いてきたが、2012年に大きな改定があり、小血管の血管炎については、病名が変わった。小血管の血管炎は、ANCA関連血管炎と免疫複合体性血管炎に分けられる。ANCA関連血管炎は、従来から顕微鏡的多発血管炎(microscopic polyangitis:MPA)、Wegener肉芽腫症、Churg-Strauss症候群に分類されていたが、Wegener肉芽腫症が多発血管炎性肉芽腫症(granulomatosis with polyangitis:GPA)に、Churg-Strauss症候群が好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(eosinophilic granulomatosis with polyangitis:EGPA)に変更された。ANCA関連血管炎としてまとめられているが、MPAはMPO-ANCAが90%で陽性、GPAはPR3-ANCAが30%で陽性、EGPAはMPO-ANCAが40%で陽性であり、陰性例も少なくない。EGPAはANCA陽性例と陰性例で臨床症状が異なる。ANCA陽性EGPAはMPAと同様腎炎を発症しやすいが、ANCA陰性EGPAは心・肺に好酸球による障害を生じやすい。
MPAに肉芽腫が加わるとGPA、さらに好酸球増多があるとEGPAという感じだが、それでよいのだろうか。EGPAは特にひどい。多発血管炎を伴う好酸球性肉芽腫ではないと思う。Wegener、Churg-Straussの名前を消し去るのも気の毒に思える。
-
第4回武蔵小杉皮膚フォーラムから(平成26年5月24日)
初夏になると、成人の、主として体幹に生じる環状の膨疹様紅斑をみることが少なくない。いずれも特別な誘因ははっきりしない。膨疹様紅斑は持続は1週間以上で、経過とともにわずかな鱗屑を伴う。組織もDarieの環状紅斑でみる細胞浸潤より浅く、軽い。ボレリアやHerpes simplexの感染もない。遠心性丘疹性紅斑の様に、外側には拡大しない。習慣性環状紅斑と呼称している。偏食の改善で軽快した例がある。
遠心性丘疹性紅斑とも少し臨床が異なるようだ。学会では聞いたことがないが、何となく、そういった患者がいるような気がする。遠心性丘疹性紅斑も、繰り返す患者が多い。局所に病原微生物がいるようには思えないが、いったい何が原因なのだろう。ジベルばら色粃糠疹の親戚か。集積してみる価値はありそうだ。
-
横浜市皮膚科医会学術講演会から(平成26年5月22日)
アトピー性皮膚炎の家族歴のある、生後1週間以内の新生児を対象として、全身に保湿剤を外用する群と、乾燥した部位に適宜保湿剤を使用する群に分け、生後4週、12週、24週、32週に、割り付けをブラインドされた皮膚科医がADかどうかを判断し、32週までのAD発症率を比較した。保湿剤を全身に使用した群では19/46(41.3%)、適宜使用した群では28/45(62.2%)がADと診断された。予防的なスキンケアでADの発症率を減らすことができた。
スキンバリアを正常に保つproactive療法が、経皮的なアレルギー感作を抑制し、ADの発症を減らすという、はやりの理論を実証した臨床研究である。さらに長期的に、喘息やアレルギー性鼻炎の発症も抑えられるか、フォローを続けるようだ。経皮感作を防ぐための保湿を四六時中行うことが赤ちゃんの一般的なスキンケアになるとしたら、母親は大変である。なお臨床試験には資生堂のドゥーエの乳液が使われたらしい。
-
第30回日本臨床皮膚科医会総会から(平成26年4月27日)
ストーマ周囲に生じ、ストーマとは連続しない有痛性潰瘍に対して、peristomal pyoderma gangrenosum(PPG)という疾患名を冠し、主として消化器外科領域から報告されている。炎症性腸疾患に伴う例が多いが、ストーマ増設に至った基盤の腸疾患は、炎症性腸疾患以外にも虚血性腸炎、S状結腸穿孔など様々である。治療は通常の壊疽性膿皮症と同様、ステロイド内服やタクロリムス軟膏外用が行われ、一時的には有効である。しかし、肛門を含めた残存する腸管の炎症巣に対する治療を行わないと再発が多いと報告されている。
消化器外科領域ではタクロリムス軟膏の外用が一般的になっているらしい。ストーマ周囲であれば、局所的な原因を想像するのだが、 ストマとは連続しないというのが不思議である。
-
第30回日本臨床皮膚科医会総会から(平成26年4月27日)
帯状疱疹患者と同居する水痘未罹患の家族が、水痘を発症する頻度を調査した。604例の帯状疱疹患者のうち、74例が水痘未罹患の小児と同居していた。74例中8例(10.8%)で小児の水痘発症が確認された。発症部位、帯状疱疹の重症度、小児との接触の濃厚さには一定の傾向はなかった。家庭内における帯状疱疹からの水痘感染は10%程度と考えられる。
顔面など、露出部位の患者に多い傾向があるのかと思ったが、部位は関係ないようだ。帯状疱疹患者の気道にウイルスがいるかどうかはいつも問題になる。空気感染の感染源として院内待合室での対応も考えないといけないかもしれない。
-
第30回日本臨床皮膚科医会総会から(平成26年4月27日)
糖尿病、高血圧、高脂血症のある高齢男性。眉間、両頬、鼻根部、下顎部に紅斑と血管拡張があり、両頬は丘疹、小膿疱を伴っていて、酒さと診断。アムロジピンをARBに変更したところ1カ月で著明に改善した。Ca拮抗薬の降圧の作用は血管平滑筋を弛緩させることによる血管拡張作用であるため、酒さの発症、増悪因子になる可能性がある。
これは気づかなかった。確かに高血圧症患者は赤ら顔が多い気がするが、高血圧症そのもののためだと思っていた。Ca拮抗薬を内服している患者に多いのか、確認が必要だ。
-
第30回日本臨床皮膚科医会総会から(平成26年4月27日)
ざらざらの皮膚が全身性溶連菌感染症の皮膚症状であることの警鐘。猩紅熱と診断できる間擦部の紅斑や、高熱、咽頭痛などの全身症状がともにあれば小児科を受診し、全身症状が軽く、皮膚症状も典型でない症例が皮膚科を受診すると思われる。皮膚症状は毛孔性の角化を伴う、炎症のないざらざらの皮膚だけの場合もあるが、抗菌薬の投与が行われていなければ口蓋扁桃から溶連菌が迅速診断キットで証明される例が多い。手足の紅斑、いちご状舌、扁桃の肥大・発赤は診断の一助になる。全身症状が軽くても、ざらざらの皮膚が急速に生じた例では溶連菌の検出を積極的に試み、さらに尿潜血の有無を検査する必要がある。
多くの症例が供覧されたが、皮脂欠乏やアトピー性皮膚と鑑別が難しいような症例もあった。いわゆるsandpaper-like skin rashと称される病変は赤みを伴う場合だけではないということ。確かに、本人や家族が気がつかないうちに症状がピークを過ぎてしまってから皮膚科を受診することもまれではないので、迅速検査は有用なツールだと思った。
-
第30回日本臨床皮膚科医会総会から(平成26年4月27日)
1986年、谷奥はチメロサールによる接触皮膚炎がツベルクリン陽性反応部位をさけて生じた症例の経験から、先に免疫反応が生じている部位には、あとから起こる免疫反応が抑制される現象を臨床的AC現象と呼んだ。遅延型過敏反応では、先に生じた接触過敏反応のためにその部位のランゲルハンス細胞が動員され、細胞数の減少ないし機能低下の影響で、次の反応が抑制されると考えられている。ウルシかぶれの既往のある被験者に対し、水痘抗原皮内注射で発赤を生じた部位とその周囲にウルシを塗布した際にも、この現象が見られたという。
面白い反応だ。ランゲルハンス細胞のほかにも、Tリンパ球も関連していると思う。多形紅斑型の全身性の薬疹が、ガン治療のために放射線療法を行っていた部位にだけは生じなかった症例の経験がある。
-
第30回日本臨床皮膚科医会総会から(平成26年4月27日)
水疱性類天疱瘡の水疱が上皮化したあとに、、褐色調の強い、一様に角化した局面が出現することがある。2002年に近藤らが、「類天疱瘡治癒部位に生じた黒色表皮腫様皮疹」として報告した。組織学的には表皮肥厚と乳頭腫で、創傷治癒過程における表皮の異常反応と考えている。数週から数カ月で自然消褪する。
BPに限ったことではないようだ。熱傷のあとでも、見たことがある。高齢者、あるいは糖尿病患者で見ることが多いような気がするが、基盤になる病態生理があるのではないか。
-
第19回糖尿病フットケア研究会から(平成26年2月22日)
病院内で発生する創傷は、褥瘡は減少傾向だが、最近では医療関連機器圧迫創傷(medical divice-related pressure ulcers)と定義されたキズが問題となっている。ギブスやシーネ、酸素マスク、各種チューブが当たってできる潰瘍で、特に小児病棟での頻度が高い。発症が想定される突出部位の保護とこまめな観察による早期発見が重要である。
新しい概念で、注目したい。原因が明白だし、予防の計画も立てやすいと思われる。日本褥瘡学会が調査を開始したとのことで、早々に対応指針が出るだろう。
-
第77回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成26年2月15日)
遠心性丘疹性紅斑は春から夏にかけて好発する、成人の体幹に生じる疾患である。発汗試験を行ったところ、病変部での発汗増加があり、皮膚生検では汗腺周囲にリンパ球浸潤がみられた。抗ヒスタミン薬内服とステロイド軟膏外用では効果がなかったが、サウナ浴の禁止、塩化アルミニウムローションの外用で発疹が消褪した。
汗腺周囲にリンパ球浸潤があると機能低下になりそうだが、病変部だけに発汗増加があるというのが不思議だ。塩化アルミの外用が効くとは知らなかった。時々経験するので、是非試してみたい。以前から気になっていた疾患なので、当院の患者の背景をいずれまとめてみたい。
-
第77回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成26年2月15日)
帯状疱疹の多数の入院例からの解析。帯状疱疹入院患者のHSVに対するEIA-IgG抗体陽性率は40~50代では52.4%で、同年代の健康人の陽性率70.9%より有意に低い。また、40~50代では、三叉神経領域に帯状疱疹が出現した患者のHSV抗体陽性率は36.1%で、他の部位の帯状疱疹患者の陽性率74.1%に比べると有意に低かった。
おもしろい、意外な結果である。HSVが星状神経節に潜伏していると、三叉神経領域のVZVが再活性化しにくいということか。
-
第77回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成26年2月15日)
自験例であるが、2013年の風疹流行時、18名の成人例を経験した。風疹は発熱とともに発疹が出現するので、発症して1~2日目に初診する。その後自宅安静を指示し、社会復帰してよいかどうかの判断のため、初診後3~4日すなわち発症して4~6日に再診することになる。初診と再診の2点で抗体価の変動をチェックした。採血の間隔が、たとえ3~4日と短くても、HI抗体、EIA-IgG抗体、EIA-IgM抗体の有意な変動が確認された。ただし、初診時に、あまりにも発症直後であるため、EIA-IgM抗体が陰性と判定される例が18例中7例にあった。初診時だけの採血では、風疹ではないと判断される可能性がある。また、発症後4~6日の再診時に、すでにEIA-IgG、HIが陽性となっている例も18例中7例あり、再診時だけの採血では、既感染と判断される可能性がある。
ウイルス感染症の診断に有用な抗体価の変動を確認するためには、2週間ぐらいの間隔をあけて2回採血をする(ペア血清)というように臨床検査学で習ったが、風疹の場合には3~4日でも十分変動するということがわかった。
-
第77回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成26年2月15日)
2007年に報告されたLegius症候群は、カフェオレ斑、小褐色斑を伴うためNF1と誤診されやすいが、神経線維腫は生じない。SPRED1遺伝子の変異による常染色体優性の遺伝性疾患で、頭蓋骨変形や神経行動や発達の異常を来すが、中枢神経症状、脊柱彎曲、虹彩の小結節はみられない。NF1と診断された5%はこの疾患である。
カフェオレ斑をみたら疑わなくてはならない大事な疾患だと思った。神経線維腫はないが脂肪腫を伴うことが多いとのこと。SPRED1とはどんな遺伝子なのか、調べておこう。
-
第39回横横会から(平成26年1月30日)
丘疹とは、炎症に基づく細胞成分の増加による(水だけではない)小さな盛り上がりで、病理組織を加味して以下のように分類する。1)紅斑性丘疹、2)膨疹性丘疹(痒疹丘疹の始まりで角層のすぐ下に小水疱があるので、てっぺんがびらんになる、3)漿液性丘疹(湿疹丘疹で、水疱は基底層に接する)、4)壊疽性丘疹、5)苔癬丘疹(表皮の変化が加わる)。
痒疹は膨疹性丘疹で始まり、個疹は癒合せず、多発しても正常の皮膚に境されている。7~10日たつと水が減って充実性丘疹となり、真ん中がへこんで色素沈着が加わり、さらに不規則な表皮肥厚が生じる、と教わった。学会などでは語られなくなったが、最近の教科書には書いてあるのだろうか。
-
第4回日本皮膚科心身医学会から(平成26年1月26日)
「泣けるビデオ」鑑賞中、前頭前野の血流にどのような変動があるかを光トポグラフィーを用いて計測した。泣く25秒ほど前の胸の高鳴る時に心拍数が増加し、泣く直前に血流増加のスパイクがあり、泣くと同時に心拍数が下がり、副交感神経優位の状態となった。心理テストではネガティブな気分尺度の改善がみとめられた。
涙は1歳までは出ない。1歳からはストレス伝達の道具となり、小児では自己に加わるストレスで悔し涙を流す。成人では自己のストレスとは別に、他者の行動に共感して流す感動の涙があるということで、それぞれに意味があるようだ。興味深い話だった。
-
第4回日本皮膚科心身医学会から(平成26年1月26日)
長島型掌蹠角化症は常染色体劣性遺伝で、掌蹠を中心に紅斑を伴う角化が主症状。多くは1歳までに症状が出現する。紅斑は手背・手関節屈側、足背・アキレス腱部に至り、しばしば多汗を伴う。手を水につけると、5~10分で紅斑部の角質が白色浸軟するのが特徴。全エクソンのDNA解析を行った結果、セリンプロテアーゼインヒビターのSERPINB7にホモの変異がみつかった。もっとも多いc.796C>T変異は、日本人ではおよそ50人に1人が保因者であり、1/50×1/50×1/4=1/10,000、1万人にひとりに発症する計算になる。
このほか抗コリン作用を有するパーキンソン病治療薬(アキネトン・アーテン)、抗コリン作用を有する第一世代抗ヒスタミン薬(ポララミン・ピレチア)などについてはガイドラインでの言及はない。プロ・バンサインは使ったことがないが、効果と副作用はどんなものだろう。
-
神奈川県皮膚科医会学術講演会から(平成26年1月18日)
ニキビの発症にはアンドロゲンが重要な役割を担う。第2指/第4指の長さの比(2D/4D)は胎生期アンドロゲン曝露を反映する(低比で高曝露)。16~40歳のニキビ患者251人(女性68%)、と健常者120人(女性73%)の2D/4Dを検証。ニキビ女性の2D/4Dは両手とも健常女性より有意に低く、ニキビ重症度、持続期間とも相関した。男性では有意差なし。
まず、胎生期アンドロゲン曝露と指の長さが関連する、という仮定が根拠なしと思ったが、マウスの実験で確かめられていて、2011年のProNASに報告されているとのこと。何人かで計ってみたが、傾向はよくわからなかった。
-
平塚市医師会講演会から(平成25年12月19日)
スキンテア(skin tears)は看護の現場からincident reportが必要な状況として報告されたものである。加齢と光老化による皮膚の脆弱性に基づく、摩擦・ずれにより発生する外傷で、高齢者の前腕や下腿に多く、高齢者施設での発生頻度は4%であった。日本創傷・オストミー・失禁管理学会ではオーストラリアで用いられているSTAR分類の日本語版を公表し、評価と治療のアルゴリズムを定めている。
高齢者では、体位交換で前腕を握っただけでもズルっと剥けることがある。incidentとして集積することは看護・介護現場では必要だろう。ステロイド薬外用、内服がrisk factorである。治療は剥離した皮弁を可能な限り元に戻し、ステリストリップを貼っておくこと。
-
第21回横浜臨床医学会学術集談会から(平成25年12月7日)
逆流性食道炎のため2カ月前からランソプラゾール30mgを内服中の70歳代女性。1日10~20回の水溶性下痢が連日続くようになったが、止瀉薬で改善しない。大腸内視鏡では空腸から直腸の全体に粘膜の肥厚があり血管透過性が低下し浮腫状。生検では粘膜の再生性変化と散在性に膠原線維の増生があり、膠原線維性大腸炎(collagenous colitis)と診断。ランソプラゾール内服中止1週間後から症状が改善した。血便を伴わない慢性水溶性下痢では、薬剤性の可能性を考えておく必要がある。
タケプロンによる症例が多いらしい。他のPPI、NSAIDs、アスピリンなどによる症例の報告もあるようだ。皮膚でも、真皮膠原線維の増生が起こる可能性があるのだろうか
-
第143回神奈川県皮膚科医会例会から(平成25年12月1日)
尋常性白斑と脱色素性母斑の鑑別に、ウッド灯が有効。尋常性白斑ではアイボリーホワイトの光を発するが、脱色素性母斑では発しない(off white)。脱色素性母斑ではメラニン細胞の数は正常、先天的に一部の皮膚メラノサイトに機能異常が生じるために不完全脱色素斑になる。辺縁は鋸歯状のことが多く、また患部から生える毛も黒い所があり、いずれもダーモスコピーで確認しやすい。
ウッド灯を白斑に当てて見たことがなかった。脱色素斑のダーモスコピー所見はかなり整理されてきた。ウッド灯を照らしてダーモスコピーで見ると、もっとわかりやすいかも知れない。
-
第29回日本臨床皮膚科医会三ブロック合同学術集会から(平成25年11月24日)
長島型掌蹠角化症は常染色体劣性遺伝で、掌蹠を中心に紅斑を伴う角化が主症状。多くは1歳までに症状が出現する。紅斑は手背・手関節屈側、足背・アキレス腱部に至り、しばしば多汗を伴う。手を水につけると、5~10分で紅斑部の角質が白色浸軟するのが特徴。全エクソンのDNA解析を行った結果、セリンプロテアーゼインヒビターのSERPINB7にホモの変異がみつかった。もっとも多いc.796C>T変異は、日本人ではおよそ50人に1人が保因者であり、1/50×1/50×1/4=1/10,000、1万人にひとりに発症する計算になる。
日本に1万人以上患者がいるということで、意外に多い疾患である。それにしても、全遺伝子解析を行おうと決めて、その結果、候補が一つだけだったというのが、すごい。
-
第29回日本臨床皮膚科医会三ブロック合同学術集会から(平成25年11月24日)
酒さの血管拡張に対して、欧米では2013年から血管収縮作用のあるアドレナリンα2作動薬の外用薬、Mirvaso0.33%gelが処方されるようになった。効果は外用後30分から見られるようになり、3時間持続、10時間後には元に戻るという対症療法であるが、とりあえず赤みをおさえたいという場合には選択枝の一つとして考えてよい。
知らなかった。ブリモニジン0.33%がその主成分である。緑内障・高眼圧治療薬のアイファガン点眼液はこれと同一の成分で、濃度は0.1%だが、皮膚に外用するとどうなるのだろう。
-
第65回日本皮膚科学会西部支部学術大会から(平成25年11月10日)
6カ月の女児で臀部・肛囲・腋窩・口囲に腸性肢端皮膚炎に似た病変が生じた。血清中亜鉛は低値だったが、SLC39A4の遺伝子変異はなし。兄も乳児期に同様の症状があったが離乳食を開始してから改善したという経過から、低亜鉛母乳が原因と判断。母の遺伝子変異を検索したところSLC30A2にヘテロの変異が見つかった。SLC30A2は亜鉛の輸送蛋白の一つで、乳腺以外には前立腺、膵、網膜などで発現しているが、母には低亜鉛母乳以外の症状はなかった。
発症する児には遺伝子変異がなく、その母の遺伝子変異が児に症状を起こすという、変わった遺伝性疾患。低亜鉛母乳による後天性亜鉛欠乏症の一部はこの疾患とのこと。亜鉛輸送の破綻は他の臓器にも異常を引き起こしそうだが、何もないのが不思議だ。
-
第65回日本皮膚科学会西部支部学術大会から(平成25年11月10日)
生物学的製剤による治療を受ける患者は、PASIが90%改善までいかないとDLQIの改善が見られないという。通常はレミケードを第1選択薬として使用するが、40週ぐらいで、効果が減弱する例があり、二次無効(レミ切れ)といわれている。これは、レミケードに含まれるマウス蛋白に対する中和抗体が原因と考えられている。二次無効を生じた例ではヒュミラ、ステラーラへの変更を余儀なくされ、使える薬剤が減ることへの不安が解消されない(バイオ難民)。
流行しそうなtermで印象的だった。PASI90%改善はかなりハードルが高いが、満足度の高い乾癬治療は、今後も生物学的製剤に頼ることになりそうだ。開業医としては、ちょっと寂しい気がする。
-
実地医家のための糖尿病治療を考える会(平成25年11月7日)
最近の大規模臨床試験の結果、罹病期間が長く血管が脆弱化した糖尿病患者では、厳格な血糖管理による大血管障害へのベネフィットは認められなかった。糖尿病治療は厳格な血糖低下を目的とするのではなく、個々の患者の状態に応じた質の高い血糖コントロールが必要である。薬物療法によって低血糖が頻発すると見かけ上のHbA1c低下をきたす。また薬物用法によって体重増加を生じることがある。これからは、血糖の変化がなるべく平坦で、低血糖や体重増加を生じさせない糖尿病治療が求められる。DPP-4阻害薬は患者の食生活に応じて血糖の管理が可能な薬剤として有用である。
なぜDPP-4阻害薬がこれほどまでに注目されているのか、少しわかったような気がする。ただDPP-4阻害薬はいずれも高価で、医療経済的にはメトホルミンが第一選択薬とのこと。たまには内科の勉強もしておかないと、浦島太郎になる。
-
第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成25年11月2日)
女性の外陰部に生じたPaget病に対して、手術、放射線、imiquimod外用などを施行され、残存病変の有無がわからない状態。ミノマイシンの内服を行ったところ、紅斑部2カ所に色素沈着が出現し、これがPaget病の病変だった。ミノマイシンによるPaget病のあぶり出しは切除範囲の決定に有用である。
ミノマイシンの副作用が役に立つとは意外である。機序はよくわからないが、全例で病変部に色素沈着が起こるのであれば試してみる価値がありそうだ。追試を期待したい。
-
第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成25年11月2日)
20代男性。家具の組み立てで金槌を使用し、手指、手背に痒みと浮腫が出現した。年に数回、同様のエピソードがあり、24時間以内に浮腫は消褪していた。補体は正常、D-dimerが2.7と上昇。前腕にサーモミキサーで10分間振動負荷を加えると、接触部位だけでなく前腕全体に浮腫と痒みを伴う潮紅が出現し、7時間持続した。Vibratory angioedemaと診断。国外では9例の報告があり、常染色体優性遺伝と孤立性がある。
面白い症例だった。生検はされていなかったが末梢の好酸球増多はないようだ。上肢のangioedemaではこの疾患も考えておく必要がありそうだ。
-
第9回神奈川皮膚免疫アレルギー疾患研究会から(平成25年10月12日)
太藤病は毛包とその周囲の真皮に好酸球浸潤があり、インドメタシンの全身投与が奏功する。インドメタシンはPGD2受容体CRTH2のアゴニストで、正常人末梢好酸球のCRTH2発現はin vitroにおけるインドメタシン処理により減弱した。また同時に好酸球上のCCR3発現も低下した。好酸球のPGD2単独またはPGD2+eotaxin(CCL11)に対する遊走はインドメタシン処理により抑制された。太藤病の皮膚病変部では造血器型PGD合成酵素陽性細胞が多数みられた。インドメタシンは局所でのPGD2産生抑制と好酸球のCRTH2発現抑制のため治療効果を発揮している。
好酸球増多をきたす太藤病以外の疾患、例えばアトピー性皮膚炎の紅皮症などでも同様の作用があるのか興味がある。ステロイド内服が末梢好酸球を減らす機序はどうなっているのかも調べておく必要がある。
-
第9回神奈川皮膚免疫アレルギー疾患研究会から(平成25年10月12日)
好酸球増多症候群(HES)は好酸球増多(1,500/μ3)が2回以上、組織の好酸球浸潤、臓器障害の3つを特徴とする疾患で、これまでは特発性と考えられていたが、最近は2つのサブカテゴリーが存在することが明らかにされた。1つは標識遺伝子であるFIP1L1-PDGFRA陽性のmyeloproliferative HES(M-HES)、もう1つは異常Tリンパ球によりIL-5の過剰産生が起こり、多クローン性の好酸球増多とともにIgEが高値となるlymphocytic variant HES(L-HES)である。M-HESは17:1で男性に多く、イマチニブが奏効する。L-HESは男女比が1:1で、従来からの治療法である副腎皮質ステロイドに加えて、抗IL-5モノクローナル抗体mepolizumabが有効である。
これは勉強不足で知らなかった。遺伝子検査が行えない場合でも、イマチニブが第一選択になっているようだ。L-HESはかなりまれな疾患なので、女性で、長期間持続する基礎疾患のない好酸球増多はlymphomaかChurg-Strauss Syndromeになるとのこと。
-
第1回疥癬研究会から(平成25年10月6日)
疥癬に対するイベルメクチンの作用点は表皮角層であるため、イベルメクチンの全身浴法を試みた。150Lの湯船にストロメクトールを4錠(12mg)で、80ng/mlの濃度が得られる。これは十分な有効治療域である。5分の沐浴で8時間皮膚中に残存し、血中からは検出されない。したがって、集団感染における、集団への投与経路として有用で、外用薬を塗る手間もいらず、さらに血中に入らないことから副作用も軽減でき、乳児や妊婦への投与も可能となるかもしれない。
これはうまくいったら面白い。5%のスミスリンが疥癬の治療薬として発売されるが、これも全身浴に使えるかもしれない。なお、国外では0.5%イベルメクチンがSkliceという名称で頭ジラミの外用薬として使用されているとのこと。
-
第1回疥癬研究会から(平成25年10月6日)
イベルメクチンの血中濃度と食事の関連について、国外ではGuzzoが、30mg服用時のデータを示した。空腹時ではTmaxが4.6時間、Cmaxが84.8ng/ml、t1/2が20.1時間、AUCが1538.4ng時間/mlだったのに対し、高脂肪食摂取後では、Tmaxが4.3時間、Cmaxが260.5ng/ml、t1/2が15.0時間、AUCが5951.9ng時間/mlで、AUCが2.57倍に上昇した。腸管糞線虫症では、腸管の糞線虫の駆虫が目的なので、薬が吸収されずに腸管内に移行した方がよいので食前投与が望ましく、疥癬では、皮膚角質中のヒゼンダニの駆虫が目的なので、薬が吸収され血中に移行、皮膚に到達するため、食後がよい、ということになる。
そういう話は以前から聞いていたが、しっかりとデータを示されると納得する。ストロメクトールの添付文書では疥癬に対しても用法は食前だが、改める必要があるかも知れない。
-
横浜小児医療懇話会から(平成25年10月5日)
1974年本邦で開発された弱毒生水痘ワクチン(Oka株)は、その有効性、安全性が高く評価され、1985年WHOで最も望ましい水痘ワクチンと認定され現在全世界で使用されている。日本では1987年から任意接種ワクチンとして使用されてきたが、接種率は30%と普及していない。米国では1995年に1歳での定期接種が導入され、その当時は2~6歳に多かったが、10年後の2004年には5歳から11歳に多くなった。2004年以降の5歳から上の年齢の発症はワクチン接種児がほとんどを占め、breakthrough varicella(BV)と呼ばれている。この結果を踏まえ、米国では2006年から2回接種(1回目:12~18カ月、2回目:4~6歳)とし、水痘の発症を95%減少させた。
水痘ワクチン接種後に20~30%が4年以内にBVを発症するというデータから、日本小児科学会では、1回目:12~15カ月、3カ月以上あけて1歳台に2回目:18~23カ月、を推奨しているようだ。このスケジュールでの5歳以降のBVの発生頻度はどうなっているのか。1回と変わらないのであれば米国のスケジュールの方がよいような気もする。定期接種になったあとの疫学に注目しよう。
-
第17回川崎市皮膚科医会から(平成25年10月2日)
ランゲルハンス細胞(LC)は全身の表皮を密なネットワークで網羅する生体最前線の樹状細胞である。LCの起源および表皮への動員機序はほとんど不明であったが、LC前駆細胞(pre-LC)を可視化することで、この細胞が骨髄の単球サブセットに由来することが明らかになった。Pre-LCはケモカイン受容体CCR2とCCR6に依存しながら毛嚢漏斗部と峡部を経由して表皮へと動員されるが、毛隆起部は動員を抑制する機能のあるCCR8のリガンドを多く産生する細胞があり、炎症が生じた際に樹状細胞の過剰な流入から幹細胞領域を守っていると考えられる。
骨髄由来であるということは何となく想像がつくが、わずかな刺激だけで、ものすごい勢いで集まってくる動画には感動した。手掌・足蹠の無毛部へも、LCは近くの毛嚢を経由して入り、横に移動していくとのこと。永久脱毛が免疫不全を起こすかもしれないと結んでいた。
-
第17回川崎市皮膚科医会から(平成25年10月2日)
無機物質の表面分析に用いられる質量分析顕微鏡(TOF-SIMS)を用いた観察で、角層がカリウム高・アルギニン低の外層、カリウム低・アルギニン高の中層、カリウム低・アルギニン低の内層の三層構造であることが証明された。上層は洗うと流れてしまう層で、様々な物質が浸透するスポンジ、中層は天然保湿因子に富み、一部の物質を通さないバリア、下層は多くの物質を通さない、2列目のバリアとして機能している。フィラグリン欠損マウスの皮膚では、下層のバリア機能が特異的に障害されていた。
これまでは半導体の分析などにしか用いられたことのないツールを駆使したというところにアイデアを感じる。面白かった。ところで、経皮感作がアレルギーを生じ、経口だとトレランスに働くという話をよく聞くが、粘膜のバリアはどうなっているのだろうか。
-
第850回日本皮膚科学会東京地方会から(平成25年9月28日)
7歳の女児で、両膝の固定性関節炎と間歇性の発熱。下肢に蕁麻疹様の紅斑を伴う。抗CCP抗体陰性、MMP-3高値。紅斑の病理組織は一部に膠原線維の変性を伴う好中球の浸潤があり、リウマトイド疹に合致する。若年性特発性関節炎(JIA)の多関節型と診断した。JIAは全身型(弛張熱が特徴で、かつての若年性関節リウマチ=Still病)、多関節型、単関節型に分けられている。
熱発が間歇的で弛張熱でないことが重要で、肝脾腫、リンパ節腫脹、心膜炎、胸膜炎などの合併が少ないことも考慮して診断されるらしい。JIA=JRA=Still病だと思っていたので、勉強になった。
-
第850回日本皮膚科学会東京地方会から(平成25年9月28日)
免疫不全のない30代女性の症例。微熱が続き、足蹠に暗紅色で圧痛のある小結節を認めた。臨床的、組織学的にOsler結節と診断。心内膜炎が証明され、原因菌は口腔内常在菌であった。細菌性心内膜炎に伴う皮膚症状には、指趾端に生じる圧痛のない紫斑(Janeway斑)と爪下の出血がある。また、網膜には中央が白色の出血斑をきたし、これをRoth斑という。いずれも、細菌による塞栓が原因。
Roth斑が網膜におこる病変というのがミソ。昔、内科で習った覚えがある。Janeway斑は結局Osler結節の初期病変あるいは出来そこない、ということであろう。久々に聞いた冠名のsignなので、印象深かった。
-
第77回日本皮膚科学会東部支部学術大会から(平成25年9月21日)
高齢女性の左足、外踝周囲の発赤、疼痛。蜂窩織炎の診断で入院したが抗生剤が無効。足関節穿刺液からピロリン酸カルシウム塩が検出され、偽痛風と診断した。NSAIDと補液で経過した。症状は痛風に似るが、痛風が圧倒的に男性に多い(95%以上)のに対して、偽痛風には男女差がなく、女性にもよくみられる。また、痛風が中年に多いのに対して、偽痛風は高齢者に多いことも違いの1つ。レ線ではカルシウム沈着が証明される。関節液の結晶が鑑別の決め手で、ピロリン酸カルシウム塩の結晶は単斜もしくは三斜結晶で、尿酸塩の針状結晶と形が異なる。
ピロリン酸カルシウムを下げる薬はない。肝障害があるとピロリン酸が上昇するらしい。加齢、肥満が誘因のようだ。皮膚症状をきたすこともあるということで、足関節部の皮膚病の鑑別疾患として覚えておこう。
-
第77回日本皮膚科学会東部支部学術大会から(平成25年9月21日)
高齢者女性の両下腿に生じたnecrobiosis lipoidica(NL)に似た紅斑局面。生検では類上皮細胞性肉芽腫が主体。アクネ菌に対する抗体を用いた免疫染色で肉芽腫内に陽性。臓器症状はなく、局面型皮膚サルコイドと診断した。両下腿では真皮内血管周囲の類上皮肉芽腫が循環障害の原因になり、真皮・皮下の変性からNLに類似した病変を形成するのではないか。症例は中年以降の女性に多いが、理由は不明。
高齢女性の例を当院でも経験した。アクネ菌の検察をしたところ、陽性だった。顔や上肢にも局面型のサルコイドが併発していたので、下腿伸側という部位が、特殊なのだと思われる。
-
第77回日本皮膚科学会東部支部学術大会から(平成25年9月21日)
体幹・四肢の数カ所に少数出現した環状紅斑で、痒みがある。3月に誘因なく初発し、7月、10月に再発。辺縁がわずかに膨疹様に隆起し、中央は色素沈着を伴う。それぞれ2週間で消褪。生検で真皮の好酸球増多と脱顆粒。DDS75mgの内服が有効であった。eosinophilic annular erythemaという病名で報告されている。
春先から初夏にかけて、成人の体幹に環状で辺縁が膨疹様、内側がやや褐色になる紅斑症を経験することがある。遠心性丘疹性紅斑と診断することが多かったが、丘疹は目立たないことが多いので、何だろうと思っていたが、これかもしれない。生検は多くないが過去にさかのぼって集積してみよう。
-
GSKIN SEMINARから(平成25年9月15日)
単純ヘルペスウイルスによる角膜病変の復習。通常は角膜上皮炎の形をとり、樹枝状角膜炎とよばれる。ウイルスに対する遅延型過敏反応は角膜実質を侵し、円板状角膜炎となる。角膜中央が白く濁って内皮側に出っぱる。角膜輪部炎(limbitis)は角膜の辺縁の浮腫が原因で、60%以上で眼圧上昇をきたす。角膜ヘルペス再発病型の14%を占め、少なくないが、診断が難しい。
輪部炎は霧視と異物感が自覚症状で、眼圧上昇が特徴。皮膚病変を伴う眼部単純ヘルペスに伴う場合もある。ただし、通常は三叉神経節に潜伏したウイルスの再活性化が角膜病変を単独で起こすので、皮膚科医が診ることがないうこと。
-
第22回神奈川県皮膚科医会在宅医療勉強会から(平成25年9月12日)
褥瘡のポケットは、尿取りパッドによる滲出の管理とゆるい保護だけである程度改善する。ポケットの奧に細菌感染ないしcritical colonizationがあるとそれに接しているところの肉芽が白くなるので、機械的に掻破したり、水圧式ナイフ(バーサジェットS)によるデブリを行う。ずれが解消しポケットが半分になったら少し保護、ポケットがなくなったらしっかり保護することが基本。ポケットの切開は出血の問題があり、あまり施行しない。
形成外科医で褥瘡治療のオーソリティーからの話で、意外だった。これまで、ほぼ全例切開してきたので、驚いた。確かに切開後の止血は大変だが、在宅ではジェット水流もないし、ポケットの奧を目視する必要もあるので、切開はやむを得ないというのが、私見である。
-
第22回神奈川県皮膚科医会在宅医療勉強会から(平成25年9月12日)
骨突出部の褥瘡が頻回のおむつ交換や褥瘡管理による体位変換で悪化している場合がある。褥瘡内褥瘡や肉芽塊による段差も擦れと圧が加わっている証拠。体位変換の際には、ポジショニンググローブ(モルテンのオレンジ手袋)を使って、骨突出部をしっかり支えて、残留擦れ力が残らないように動かすことが重要。
モルテンのオレンジ手袋は知らなかった。看護師、介護者にさっそく使ってもらうようにしよう。
-
皮膚アレルギーUpdate講演会から(平成25年8月3日)
アトピー性皮膚炎でフィラグリン遺伝子異常がある割合は30%ほどで、早期発症で重症、総IgEが高値、手掌の深いシワが多い(palmar hyperlineality)などの特徴があるが、遺伝子異常がなくても炎症によってフィラグリンの発現がタンパク質レベルで低下することがわかってきた。Th2サイトカインであるIL-4、IL-13ではフィラグリンが低下、Th1サイトカインであるINF-γではフィラグリンが上昇する。抗IL-4R抗体、ステロイド、タクロリムスでもフィラグリンが上昇する。
フィラグリンの発現レベルが恒久的ではなく変動する、というところがミソ。結果としてアトピー性皮膚炎の経過を反映することになりそうだ。フィラグリン発現を上昇させる創薬が注目されることになりそうだ。
-
第18回日本ラテックスアレルギー研究会から(平成25年7月28日)
柑橘類のOAS患者23例のまとめ。10代が多く、78%が女性。オレンジ、ミカン、グレープフルーツの他、ジュースや缶詰の加工品も半数以上で誘因となっていた。87%で花粉症の自覚があり、施行した全例でスギ花粉の特異的IgEが陽性。Immunoblotでは13kDa付近にIgEの結合がある症例が多く、15例中7例でスギ花粉によるImmunoblot inhibitionがみられた。柑橘類のOASではスギ花粉による感作が原因と考えられる症例がある。
ハンノキ、オオバヤシャブシ、シラカンバの感作ではOASが多いと知っていたが、スギ花粉はあまり関連がないと思っていた。スギ花粉症患者には、OASの有無も聞いてみないといけない。
-
第37回日本小児皮膚科学会から(平成25年7月14日)
生後2週間の男児で、右側胸部に褐色の局面がある。擦過刺激で皮膚の隆起が生じ、pseudo-Darier signが陽性だった。生後1カ月で軟毛が生えたところで、このsignは陰性となった。組織学的には平滑筋線維束の増生で、肥満細胞の増加はなかった。
これは気がつかなかった。ヒスタミンとは無関係で立毛筋が逆立つという現象か。毛が生えると消失するというのもおもしろい。なお、皮膚と子宮に多発性の平滑筋腫が生じる女性の遺伝性疾患があり、Reed症候群と呼ばれるが、この症候群でもpseudo-Darier signが陽性となり、診断的意義があるとのこと。
-
神奈川県皮膚科医会夏の勉強会から(平成25年6月29日)
性器ヘルペスの発症は、1)初感染初発、2)非初感染初発、3)再発がある。2)は過去に感染したときは無症状であって、何らかの誘因によって、初めて病変を経験することで、症状は初感染よりも軽いことが多い。HSV-1抗体陽性者はHSV-2の初感染が無症候性になりやすい。また、HSV-2抗体陽性者は、HSV-1の感染自体が起こりづらい。
非初感染初発は、まったく意識しておらず、再発性として扱ってきてしまった。再発性との臨床症状、抗体価の変動の相違について、調べてみる必要がありそうだ。
-
第62回神奈川医真菌研究会から(平成25年6月22日)
マラセチアは皮膚の常在真菌であるがM.globosaとM.restrictaはアトピー性皮膚炎(AD)の増悪因子の一つとして注目されている。AD患者血清IgEと反応するマラセチア抗原を検索した結果、M.globosaの42kDaのタンパクが主要アレルゲンとして検出された。さらにこの抗原はheat-shock protein 70(hsp70)ファミリータンパクの分解産物であるMGp42であることが明らかになった。ヒトケラチノサイトをM.globosaで刺激すると、IL-5、IL-10、IL-13などのTh2型サイトカインの分泌が認められた。また、M.restricta刺激ではIL-4のみの分泌が認められた。M.globosaとM.restrictaはヒトケラチノサイトに対してそれぞれ異なるTh2型サイトカイン応答を誘導し、それぞれのサイトカインが相乗的に作用することによりTh2免疫応答の誘導を介したアトピー性皮膚炎の増悪に関与している可能性が示唆された。また、M.globosaとM.restrictaがヒトケラチノサイトのThymic Stromal Lymphopoietin(TSLP)産生誘導を惹起することを見出し、このTSLP産生誘導を介したTh2型免疫応答もADの病態に関与しているものと考えられる。AD患者では、皮膚バリア機能の低下に伴い、皮膚菌叢の経皮侵入が起こりAマラセチアによるケラチノサイト刺激が惹起されるものと考えられる。
ちょっと難しいが、アトピー性皮膚炎が「バリア病」であるという、経皮感作とは別の側面を示しているようだ。ただ、癜風の病態をどう説明するのかが、よくわからない。
-
第112回日本皮膚科学会総会から(平成25年6月15日)
70代の女性で、幼少時から疎毛、爪の変形、歯牙欠損がある。5年前から足蹠、両下腿に小結節が生じて、乳頭種状の局面を形成した。生検では好酸性の小型な細胞が下方に増殖し吻合状構造を呈し、間質の増生もありsyringofibroadenomaと診断した。常染色体劣性遺伝でWntシグナル伝達経路の変異で生じるSchopf-Schulz-Passarge Syndromeである可能性が高いと考えた。
外胚葉性の形成異常をきたす疾患の一つとして覚えておこう。石灰化上皮腫もWntシグナル伝達系の異常と関係があるらしい。また家族性腺腫性ポリポーシスも同様の範疇だそうだ。
-
第112回日本皮膚科学会総会から(平成25年6月15日)
皮膚筋炎と関節リウマチ(RA)の併発した患者、MTXの内服1年後から両下腿に潰瘍を生じ、徐々に拡大、四肢に多発性の皮下結節が生じてきた。皮下結節の病理組織は柵状肉芽腫の像を呈し、リウマチ結節と診断した。MTXの中止で潰瘍、結節は改善した。MTX投与中にリウマチ結節が誘発されることがあり、MTX-induced accelerated nodulosisとよばれる。手指の関節に生じる小さな皮内~皮下の結節が典型疹である。原疾患はRAが多いが、性別、リウマチ因子の値、疾患の罹病期間、MTXの投与期間とは関連がない。またRA以外にも若年性特発性関節炎や関節症性乾癬などでも報告がある。
初めて聞いた。MTXでは間質性肺炎も起こることを考えると、線維に対する反応なのか。リンパ球増殖症もあるし、不思議な薬理作用があるようだ。
-
第112回日本皮膚科学会総会から(平成25年6月15日)
突然の片側性下腿腫脹で来院。膝膕から下腿にかけての筋膜下にエコーで液体の貯留があり、漿液性ないし血性の穿刺液を認めたため、ベーカー嚢腫の破裂と診断。関節リウマチなどの慢性炎症性疾患に併発する症例が多く、破裂するとDダイマー、CRPの上昇を伴うので、深部静脈血栓症との鑑別が必要になる。
これまでにあったかも知れない病態だと思う。整形外科との境界領域の疾患は判断が難しい。嚢腫の圧迫によって膝窩静脈に血栓性静脈炎を生じている場合もあるらしい。治療は穿刺と圧迫で、ステロイドの局注も行われるとのこと。
-
第112回日本皮膚科学会総会から(平成25年6月15日)
毛髪の成長サイクルについての検討。同一個人10名で4年間にわたって、頭頂部の1cm2をダーモスコピーで観察し、成長期と休止期にある毛髪の比率見たところ、12月が9.8%±1.8%だったのに対し、8月では11.6%±2.1%と最も多く、したがって秋に抜け毛が多くなり、密度が低くなることがわかった。温度、発汗、紫外線などの外的要因が関係しているようだ。
抜け毛の本数ではなく、ダーモスコピーでの観察というところがミソ。休止期毛が8月に増える理由は、外的要因というか、ヒトという生物としての環境への対応なのだろう。抜け毛を気にする患者への説明には使えそうだ。
-
第45回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成25年6月6日)
尋常性乾癬で生じる爪の病変は、病理組織像に対応している。爪甲の白斑、鱗屑を伴う陥凹はいずれもparakeratosisを示す。爪甲の肥厚はhyperkeratosis、爪下の点状ないし線状の出血はAuspitz現象そのものである。爪の赤みは爪床の慢性炎症を示す。また、尋常性乾癬では爪半月が大きいのが特徴の一つで、これは爪上皮の表皮細胞のturnoverが亢進していることを表している。
なるほど、わかりやすい。皮膚病変を見たら、その病理組織像を頭の中に描くことは、疾患の理解に非常に役に立つと改めて感じた。
-
第3回Dermatology WEBカンファレンスから(平成25年5月21日)
7カ月の乳児の足蹠に生じた異汗性(汗疱状)湿疹でニッケルのパッチテストが陽性。本人は母乳と少量の離乳食のみで、ニッケルを含む食物の摂取はない。母がチョコレートとココアを好むため、母乳経由の移行を考え、母にチョコレートとココアの摂食を禁止したところ、改善した。その後、母にチョコレートを負荷し母乳を与えたところ、乳児に湿疹が再燃。母乳経由の全身性金属アレルギーと診断できた。食物に含まれる金属は90~99%が便から排出されるが、残りの1%は腸管から吸収され、尿、汗、乳汁にも排泄されるとのこと。
もしかすると、肛囲の湿疹やかゆみも排泄物中の金属が原因である場合がありそうだ。これまで、肛囲の痒みを訴える患者に、金属アレルギーの有無を聞いたことはないが、調べてみる価値があるかもしれない。
-
エキシマクリニカルスタディーセミナーから(平成25年5月26日)
分節型の尋常性白斑のうち、治療に反応しやすいものは、FA:face、C:children、E:early stage、S:small lesionで、FACESと思えておく。ただし、顔では額正中部、内眼角、口角部は治りにくい。エキシマの線量は紅斑が2日続く程度がよい。
初期はやはりステロイドの外用が必要だというが、初診時に早期病変あるいは進行期の病変であると診断するのが難しいと思っている。多くの経験を積むしかなさそうだ。
-
第25回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成25年5月12日)
アスピリン喘息では末梢血の白血球周囲に血小板が多く付着し、システイニルロイコトリエン(CysLTs:LTC4,D4,E4)の過剰産生に関与していると言われている。負荷試験で確定診断したアスピリン喘息患者の安定期の血小板を材料として、活性化マーカー(CD62P、PAC1、CD63、CD69)を検討した。コントロールと比べ、PAC1及びCD63の発現細胞数が増加していた。
NSAIDs不耐症といわれる疾患はどうもピンとこないが、血小板が活性化していて、準備状態にある、ということはわかった。特発性蕁麻疹にもつながるデータだと思う。
-
第25回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成25年5月12日)
20代の女性。アトピー性皮膚炎のある美容師で、コラーゲンを含むヘアトリートメント剤を使った後に、手のかゆみと浮腫が出るようになった。その後、豚骨ラーメンを食べた後にアナフィラキシーを生じた。加水分解コラーゲン含有トリートメント剤のプリック陽性豚骨ラーメンのスープ、ゼラチンのプリックテスト陽性。ゼラチンのCAP-RASTも7.06と陽性。経皮感作によって成立したゼラチンアレルギーと診断した。
まず、ゼラチンが加水分解コラーゲンと表示されることを知った。ゼラチンアレルギーはグミキャンディーで起こると時々報告されているが、豚骨ラーメンでも起こるとは驚いた。ゼラチンは医薬品や栄養剤のカプセルにも含まれているものがあるので、注意が必要である。
-
第25回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成25年5月12日)
28歳女性、出産3日目から授乳を開始。4日目に授乳したあとに蕁麻疹が生じた。その後も授乳や搾乳の後に膨疹、耳鳴り、呼吸困難が生じた。さらに乳房の張りとともに授乳なしでも同様の症状を来した。断乳後に症状は軽快。搾乳した自己母乳のプリックテスト陽性、乳汁による末梢血好塩基球からのヒスタミン遊離がみられ、breast feeding anaphylaxisと診断した。
性交後の精子によるアナフィラキシーは聞いたことがあるが、母乳でも起こるとは知らなかった。抗原は何なのか、感作はどのように起こったのか、不思議である。
-
第25回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成25年5月12日)
卵白アルブミン(OVA)を腹腔内に投与し感作したマウス(喘息マウス)、OVAを2日間隔で2回吸入させてから感作したマウス(免疫寛容マウス)、OVA吸入時に6日間の拘束ストレスを加えた後に感作したマウス(免疫寛容+ストレス負荷マウス)にそれぞれOVAの吸入させ、気管支肺胞洗浄液のサイトカイン量と炎症細胞を解析した。喘息マウスでは好酸球、リンパ球の増加と、IL-4、IL-5、IL-13のTh2サイトカインの増加がみられた。免疫寛容マウスではこれらは抑制されていたが、ストレス負荷マウスでは気道炎症、Th2サイトカインが有意に上昇していた。ストレスによる免疫寛容の抑制が気道のアレルギーに関与することが示唆された。
皮膚のアレルギーにも関わっていそうだ。特に乳児や幼児のアトピー性皮膚炎の遷延にストレスの関与があるのではないかと思った。
-
第29回日本臨床皮膚科医会総会から(平成25年4月7日)
鼠咬症(rat-bite fever)は鼠による咬創の1~2週後に発症し、熱発とともに多関節痛、下痢などの腹部症状をきたし、敗血症、DICを生じることもある。皮膚病変は四肢・顔面の紅斑で、末梢には紫斑を混じることもある。2種類の異なる原因菌があり、鼠咬症スピロヘータ(Spirillum minus)と、モニリホルム連鎖桿菌(Streptobacillus moniliformis)が検出される。ペニシリン系抗生剤が第一選択であるが、投与期間の基準は定まっていない。
初めて聞く疾患で、経験もない。日本でも発症するようだ。犬咬創・猫咬創はPasteurella multocida、Mycobacterium chelonaeが有名だが、鼠の方が怖そうだ。
-
第25回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成25年5月12日)
H1-抗ヒスタミン薬(承認用量)による治療にもかかわらず症状が続く中等症~重症の慢性特発性蕁麻疹患者323 例に対し、ヒト化抗ヒトIgEモノクロナール抗体であるオマリズマブを75mg群、150mg群、300mg群、プラセボ群の4群に無作為に割り付け、4週ごとに3回皮下注射した。投与後、16週間の観察期間中、1週間の平均そう痒重症度スコア(0~21,スコアが高いほど重度のそう痒を示す)と膨疹出現数を評価した。12週目の平均そう痒重症度スコアのベースラインからの平均変化は、プラセボ群が-5.1、オマリズマブ75mg群が-5.9、150mg群が-8.1、300mg群が-9.8であった。血清中のIgE値とは関連なし。オマリズマブは遊離IgE抗体のCε3に結合し、IgE抗体とFcεRⅠの結合を阻害することで肥満細胞、好塩基球からの炎症性メディエーターの放出を抑制すると考えられる。
すでに気管支喘息に対し保険適応の薬剤で、血清中のIgEと関連しないというのがやや不思議だが、様々なH1-抗ヒスタミン薬や併用薬が効かない慢性蕁麻疹には、今後適応になるのだろう。
-
第25回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成25年5月12日)
エリスリトール(5g)を含有する低カロリーゼリーを摂食した5歳男児が、30分後に、咳、全身の蕁麻疹、眼瞼浮腫、喘鳴を生じた。prick to prick testは陰性。皮内反応では1~20mg/mlで陽性。再投与も低容量では出ず、3000mgでようやく陽性。ダイエット目的の飲料、食品にかなり使用されていて、二次原料として含まれている場合には表示の義務もないので、見落とされている可能性がある。
これは是非記憶にとどめておく必要がある。プリックテストでは陰性で、かなりの量の再投与テストが必要ということも重要。ダイエット飲料や低カロリー食品摂取の既往を確認する必要がある。
-
第29回日本臨床皮膚科医会総会から(平成25年4月7日)
かつて亜鉛華軟膏ないし亜鉛華単軟膏にイクタモールを混合し、イクタモールボチとして消炎と鎮痒目的に使用していたが、現在は使用されていない。またタール製剤として生き残っていたグリパスCも発売が中止され、現在はグリメサゾン軟膏が唯一のグリテール含有製剤であるが、特有の臭いから使用頻度は低い。しかし、グリメサゾン軟膏:亜鉛華単軟膏を3:7に混和して使用すると、亜鉛華単軟膏の伸びの悪さも改善され、グリテールの持つ抗炎症作用に若干のステロイドの効果も加味され、最弱のステロイド外用薬として乳幼児にも使用でき、ランクダウンにも有用である。貨幣状湿疹への貼布、褥瘡の最後のシメなどにも有効である。
大学医局のこだわりの外用薬は全国各地にあると思われる。こういったものを紹介してくれると実地医家としてはありがたい。たくさん集めてみると面白いと思う。OGZは知らなかったし、使ってみたいと思った。
-
第29回日本臨床皮膚科医会総会から(平成25年4月7日)
成人型T細胞白血病リンパ腫(ATLL)の治療薬であるモガムリズマブは、ヒトCCケモカイン受容体4(CCR4)に対するヒト化モノクローナル抗体で、ATL細胞に発現しているCCR4に特異的に結合し、ADCC活性によって抗腫瘍効果を発揮する。1週間隔で8回点滴静注を行うが、重症薬疹が5~8回終了後にみられることがあり、比較的頻度が高い。CCR4はATL細胞だけでなく、Th2細胞やTregにも発現していて、モガムリズマブ投与によりこれらの細胞が減少し、併用されている抗菌薬などの薬剤に対するアレルギーが制御不能となり、重症薬疹の発症、遷延化に関わっていると考えられる。
Tregを低下させ、抗菌薬などのアレルギーが制御できずに薬疹を誘導するという薬理作用が原因ということで、興味深い。ウイルス感染症の再活性化もおこりそうだ。
-
第29回日本臨床皮膚科医会総会から(平成25年4月7日)
新鮮な水疱を見つけ、鑷子で破り、スライドガラスを水疱底に圧抵し、ついでに水疱天蓋を、こすりつける。ここで熱を加えると細胞が落ちない。すぐに0.2%メチレンブルーを滴下し数秒染色。余分な染色液を裏返しにして流水で流し、水分が残っているうちに、カバーガラスを乗せて観察。保存にはカバーガラスを外して乾燥させる。
熱を加えると細胞が落ちない、アセトン固定はなしでもOK、カバーガラスを乗せてみた方がきれい、保存法の工夫など実践的だった。VZVとHSの鑑別は難しいが、VZVの方が巨細胞が大きい、炎症細胞が小さい傾向があるとのこと。
-
神奈川乾癬治療研究会から(平成25年3月28日)
ケブネル現象を起こした尋常性乾癬の病変部には、psoriasinとkoebnerisinが過剰発現している。両者ともS100蛋白ファミリーに属する表皮抗菌ペプチドで、IL-17によって誘導されるが、それ自体も走化因子やサイトカインとして機能しCD4+T細胞と好中球を動員し、炎症を増悪させる。ビタミンD3はpsoriasin、koebnerisinの産生を抑制させることによって、乾癬を制御する。
そんな冗談のような名前の蛋白があるとは知らなかった。S100蛋白ファミリーというのも意外だった。ただ乾癬に特異的ではなく、アトピー性皮膚炎、菌状息肉腫、ダリエ病でも過剰発現が観察されている。いずれも、ビタミンD3が効くことがありそうな疾患だ。
-
横浜市皮膚科医会医学研修の日から(平成25年3月9日)
災害救出現場では、救護所への搬送順位付けのため、まずSTART法を用いる。「おーい、みんなこっちに来て!」で集まった人は緑、来なかった人は呼吸と脈で評価。自発呼吸がない場合、気道を確保して自発呼吸が出なければ黒、あれば赤。自発呼吸がある場合、呼吸数が1分間で9回以下ないし30回以上で赤、10回から29回で、毛細血管再充満時間(CRT)が2秒以上は赤、2秒以内でも「手を握って、離して」に応じないときは赤、応じるときは黄色。赤と判断したらすぐ担架班に現場救護所に搬送させる。黄色は急変する患者が含まれているため、容態を観察。現場救護所はPAT法によるトリアージで詳しく赤と黄色を識別。さらに搬送トリアージで搬送順位と搬送先を決定する。
救出現場と救護所のトリアージの違いを初めて認識した。開業医として、災害医療には今後も注目していかないといけないと思っている。
-
第14回北里臨床皮膚フォーラムから(平成25年3月7日)
70代後半の女性で、数年前から水疱性類天疱瘡でステロイド内服中、糖尿病を併発し、αグルコシダーゼ阻害剤を内服中。突如、腹部膨満感が出現、右季肋部痛も認めた。腹部X-Pではfree airなし。CTにて、腹腔内遊離ガス像を認め、腸管嚢腫様気腫症(pneumatosis cystoides intestinalis:PCI)と診断した。高圧酸素療法で軽快。ステロイド内服による腸管壁の脆弱化とαグルコシダーゼ阻害剤による、腸管内炭水化物の増加と腸内ガス産生菌の増殖が関与したと考えた。
腸管内で発生したガスが、腸管壁を通して外側に出てきて、外膜が破れると腹腔内にairが漏れるという病態。高齢者のBPでステロイド内服中に起こりそうな合併症で、注意が必要と思った。必ずしもX-Pでfree airは確認できず、疑ったらCTが必須というところが大事。トリクロロエチレンの長期曝露でも発生するらしい。
-
神奈川アレルギーセミナーから(平成25年3月2日)
アトピー性皮膚炎ではかゆみ過敏があり、暖まるとかゆくなることが知られている。サブスタンスPによって真皮線維芽細胞から誘導される神経栄養因子の一つであるアーテミンは、正常皮膚では認めらないが、アトピー性皮膚炎病変部真皮に強く沈着していた。アーテミンの受容体(GFRα3)のノックアウトマウスではcompound48/80による掻破行動が生じなかった。アーテミンは皮膚末梢神経伸長に関与するとともに末梢神経のTRPV1発現増加に関与するが、TRPV1は42℃付近の温度を知覚する受容体であることから、アーテミンが温度知覚過敏性のかゆみと深く関連すると考えられる。
湿疹・皮膚炎のかゆみに対する新しいターゲットになるということである。このところ神経生理がずいぶんと皮膚科領域に入ってきと感じる。
-
神奈川アレルギーセミナーから(平成25年3月2日)
定量的軸索反射性発汗試験(quantitative sudomotor axon reflex test:QSART)はアセチルコリンを負荷した部位の発汗量を定量し、C-fiberの機能を評価するin vivoの試験であるが、これによるとアトピー性皮膚炎では発汗量が低下し、発汗に至るまでの反応時間が長かった。光コヒーレンストモグラフィーを用いると汗管を通る汗が観察できるが、ヒスタミンを投与するとアセチルコリン負荷による発汗が抑制された。2光子顕微鏡による観察では、ヒスタミンが直接汗腺に作用し、汗の分泌を障害することが確認できた。抗ヒスタミン薬の内服により、発汗が増加することも確認できた。
定量やイメージングを用いた手法で、わかりやすく納得できた。新規の機器を使った研究成果でこれぞ大学の研究という感じだった。ついでにあせもの研究もお願いしたいところだ。
-
第76回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成25年2月16日)
好中球が病原微生物を捕捉・殺菌する機序のひとつに、好中球がミエロペルオキシダーゼ(MPO)などの殺菌蛋白やDNAを細胞外に放出し、自らは死に至りながらも、周囲に張り巡らすネットの形成がある。この結合物を好中球細胞外捕捉現象(neutrophil extracellular traps:NETs)と呼ぶ。MPO-ANCAは感染がなくても好中球に作用してNETsを過剰産生させるため、MPO-ANCA関連血管炎(顕微鏡的多発血管炎:MPA)を引き起こす。NETs活性はMPAの活動性に比例し、またMPA患者では誘導されたNETsの分解活性が低いことがわかった。
ピンとは来ないが、病原体のない状態でも細胞障害性のある免疫複合体のようなものが形成されると言うことか。NETsとは病理の概念か、臨床検査上認識できるものなのか。もう少し勉強が必要である。
-
日本皮膚科学会第847回東京地方会から(平成25年1月19日)
ジェルカプセルタイプのOTC総合感冒薬内服後にアナフィラキシーショックを発症。カプセルに含まれていたゼラチンでプリックテストが陽性だった。ゼラチンアレルギー感作の経路は不明。ゼラチンアレルギーではカプセル薬の投与は危険。
以前から、気になっていたが、実際の症例を見たのは初めてである。ゼラチンを含む薬剤は多くのカプセル剤のみならず、一部の錠剤、散剤、トローチ剤、坐剤、注射剤、経腸栄養剤、貼付剤など幅広い薬剤に含まれている。他にも栄養剤や食品など多岐にわたる。ゼラチンは、かつてワクチンに含まれていたと聞くが、最近の感作経路はやはり経口か。
-
第20回横浜臨床医学会学術集談会から(平成24年12月8日)
眼科医からの報告。抗ヒスタミン薬、抗不安薬、抗うつ薬などは、緑内障患者には禁忌とされることが多いが、正確には狭隅角・閉鎖隅角の患者であって、その根拠は薬剤の使用による瞳孔ブロックにより、眼圧が異常に高くなり、急性緑内障発作、視神経萎縮を起こす可能性があるためである。緑内障という診断は緑内障性視神経症、つまり乳頭の変化がある場合に下される。瞳孔ブロックは開放隅角では生じないが、大規模疫学調査の結果から全緑内障のうちの88%は開放隅角であり、薬剤の使用はさしつかえないということになる。
抗ヒスタミン薬や抗不安薬はしばしば処方するが、ちゃんと眼科を受診し、眼圧が管理されている患者は大丈夫というような認識があった。逆に、狭隅角・閉鎖隅角の緑内障患者には、薬疹のアレルギーカードのようなものを持ってもらうのがいいのではないかと思った。
-
神奈川県皮膚科医会第140回例会から(平成24年12月2日)
足蹠の母斑細胞母斑のダーモスコピー所見は、場所によって異なるという話。①荷重部では皮溝・皮丘が縦にはっきりしているので、皮溝平行パターンあるいは、それが圧迫で斜めに流れた線維状パターン、②土踏まずは縦の皮溝・皮丘に直角に交わる横のラインが入るので、格子様パターン、③土踏まずの上、足の内側辺縁では、縦・横の皮溝・皮丘がさらに乱れるので皮丘網状パターンになる。
なるほど。走査電顕の写真と比較するとわかりやすい。覚えておく必要があると思った。
-
第35回川崎市皮膚科医会から(平成24年11月29日)
抗ヒスタミン薬が効かない痒みの一つに、内因性オピオイドとその受容体を介するものがある。βエンドルフィンとμ受容体が結合すると痒みが誘発され、ダイノルフィンとκ受容体が結合すると痒みが抑制される。血液透析患者では痒みが強いほどβエンドルフィンの濃度が高く、またβエンドルフィンとダイノルフィンの比が高い傾向にあった。また、アトピー性皮膚炎では皮膚のκ受容体とダイノルフィンの活性が低下していて、光線療法を行うと活性が上昇し、痒みが改善する。
すぐ忘れてしまうので、復習。βがμ、ダイノルフィンがκ。レミッチはκ受容体の作動薬。μ受容体の拮抗薬がナロキソンで、注射しかないが、外用をアトピー性皮膚炎に試みていることろ。
-
第64回日本皮膚科学会西部支部学術大会から(平成24年10月28日)
ムコダインによる固定薬疹は、中間代謝産物が原因のため、内服直後には出現せず、数日後に誘発される遅延型の経過をとることが多い。ムコダインそのものによるDLSTやパッチテストは陰性だったが、中間代謝産物のチオジグリコール酸を用いてパッチテストを行ったところ陽性だった。誘発に時間がかかる薬疹では、中間代謝産物を応用することが必要である。
ムコダインの固定薬疹は最近多く経験する。チオジグリコール酸が原因とのことで、すっきりしたが、用途を調べると酸化防止剤のようだ。パーマ液の還元剤にチオグリコール酸というのがある。内服薬が体内で毒性のありそうな化学物質に変わるというのも、恐ろしい感じだ。
-
第63回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成24年10月14日)
鼻の下1/3を横断する線条ないし浅いへこみをtransverse nasal stripe (crease)と呼ぶ。通常は無症状だが、線条に沿って面靤や稗粒腫を伴う例がある。10歳前後の女性に多く、急な鼻軟骨の成長が基盤にあるが、アレルギー性鼻炎などで鼻尖部を上に押し上げる癖が原因と考えられる。
これは、これまで気づいていなかった。癖が原因の皮膚病変でよさそうだ。主訴にはなりそうもないが、診察の際、思い出してみよう。
-
第63回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成24年10月14日)
皮膚筋炎に伴う間質性肺炎には急速進行型と慢性型の2種類があり、急速進行型は早急な治療をしても予後不良のことが多いため、見逃してはならない。間質性肺炎を合併する皮膚筋炎は抗CADM140抗体陽性のサブタイプと抗ARS抗体陽性のサブタイプに多く、それぞれで90%以上の症例に見られるが、抗ARS抗体陽性例では90%が慢性型、7%が急速進行型であるのに対し、抗CDMA140抗体陽性例では70%が急速進行型、23%が慢性型であった。抗CADM140抗体陽性例は筋症状がないことが多く、皮膚症状は典型的な皮疹に加え、紫斑、潰瘍、壊疽など血管障害性の皮膚症状を伴うことが特徴。フェリチンが症状進行のマーカーで、治療はエンドキサンパルスとタクロリムスを速やかに行う必要がある。
速やかに、治療が行える病院に紹介することがポイント。臨床的な意義が大きいので、抗CADM140抗体の計測を皮膚筋炎や間質性肺炎で保険適応にする必要があると思った。
-
第63回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成24年10月14日)
胸腺腫は重症筋無力症などの自己免疫疾患を合併することが知られている。胸腺は自己反応性T細胞の成熟を防ぐことで自己免疫疾患の発症を回避する免疫臓器で、胸腺腫による胸腺機能不全は、胸腺腫関連多臓器自己免疫と呼ばれる病態を引き起こす。皮膚症状としては扁平苔癬、円形脱毛症、落葉状天疱瘡があり、病理組織学的にCD8陽性細胞障害性T細胞の増加と制御性T細胞(Treg)の減少という、GVHDに似た免疫反応が起こっていると考えられている。また、同様の免疫反応はDIHSやTENなどの重症薬疹でも認められることから、これらの皮膚疾患の病態にT細胞の機能異常があることが示唆される。
胸腺の機能異常と自己反応性T細胞が関与する様々な皮膚疾患が関連しているという、貴重な報告で興味深かった。Tregの減少ないし機能異常は、様々な疾患と関連しているので、治療のターゲットになりそうだ。
-
第63回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成24年10月14日)
糖尿病性神経障害は、糖尿病患者の47%にみられる合併症で、そのうちの40%で自覚症状がない。最初に侵されるのが下肢末梢の感覚障害で、モノフィラメントを用いたタッチテストが有用である。モノフィラメントはナイロン製の細い糸で、これを足に当てて触れている感覚があるかどうかを確認する道具。なお、糖尿病神経障害の発症・進展に関与する危険因子には、血糖コントロールの不良、糖尿病罹病期間、高血圧、喫煙、飲酒、高身長がある。
できあがった神経障害ため、低温熱傷や外傷に気づかずに皮膚科に来る糖尿病患者があって難渋する。神経内科でなくてもタッチテストぐらいは皮膚科でもした方がよさそうだ。学生の頃に聞いたことがあったが、思い出した。
-
第63回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成24年10月14日)
足蹠にオレンジ色の色素沈着を生じて来院した複数の症例。無症候性で、受診は春と秋。色素は容易に取れないが、自然に脱落する。原因はクサギカメムシを踏んでつぶしたためと、再現試験の結果明らかとなった。クサギカメムシは北海道以外に分布し、10月下旬から11月上旬に越冬のため家屋に飛来する。強い悪臭を放つほか、マメ類や果樹の害虫である。
一度見たら忘れない色調であった。来院するかどうかはわからないが、こういう豆知識を発表してくれるとありがたい。
-
第133回横浜市皮膚科医会例会から(平成24年10月18日)
石けんに含まれていたグルパール19Sの経皮感作で発症したコムギアレルギーは、その後時間とともに改善していく症例が多く、小麦とグルテンに対する抗原特異的IgE値が著明に改善している。好塩基球活性化試験による検討でも、小麦蛋白による好塩基球の活性化が減弱してきていて、コムギ可溶性蛋白刺激によるCD203cの発現が10%以下となった症例では、小麦摂取を解禁している。グルパール19Sのプリックは即時型の陽性反応のほか、翌日に紅斑が生じ、3日で消褪する例があるのと、10カ月後に小麦の摂取をしたところ、プリックテストの部位だけが膨疹となった症例がある。
プリックの部位が摂食後に腫れる、BCGの部位が川崎病で赤くなる、など。固定薬疹もそうだが、皮膚にとどまる抗原を常に見張っているガードマンのような免疫担当細胞(Tリンパ球?)があると言うことか。
-
第17回横浜デルマカンファレンスから(平成24年10月11日)
口唇・口囲の皮膚炎は、化粧品、医薬部外品、マンゴなどの食物、歯磨き粉の界面活性剤が原因のことが多いが、経過が長い症例では金属アレルギーの有無を検討する必要がある。就眠中に歯科金属が溶け出し、金属が漏れてよだれかぶれのようになる症例がある。就前に口囲にワセリン等を外用することで、予防も可能。
確かに説明できない慢性の経過の口唇・口囲の湿疹病変がある。金属との関連は問診では尋ねていない。さっそく聞いてみることにしよう。
-
第16回川崎市皮膚科医会学術講演会から(平成24年10月3日)
皮膚筋炎の生命的予後は悪性腫瘍と間質性肺炎の合併に大きく左右される。悪性腫瘍合併皮膚筋炎で比較的特異的な自己抗体が近年同定され、その対応抗原がTIF-γというTGF-βシグナル伝達経路に関連する分子であることがわかった。抗TIF-γ抗体は皮膚筋炎は皮膚筋炎全体の10~20%、小児皮膚筋炎の30%で陽性で、40歳以上では75%以上が悪性腫瘍を合併していた。間質性肺炎の合併は逆にまれである。V-neck signを有する皮膚筋炎に多い。低力価(80Xまで)のspeckledないしhomogenousの抗核抗体として検出されるので、参考になる。
かつては抗p155/p140抗体と呼ばれていたとのこと。悪性腫瘍が皮膚筋炎を発症させる機序の解明に役立ちそうである。小児皮膚筋炎と悪性腫瘍合併皮膚筋炎に共通の病原というのが不思議である。
-
第16回川崎市皮膚科医会学術講演会から(平成24年10月3日)
ダーモスコピーは色素性病変の診断以外に、爪廓の血管病変の観察にもきわめて有用である。特に全身性強皮症では症状の進行に平行して変化が現れ、毛細血管の太さの不均一化、棍棒状変化、配列の乱れ、無血管化が観察される。また、爪廓の点状出血(nail fold bleeding:NFB)も強皮症に比較的特異的で、特に抗セントロメア抗体陽性の症例に高率に認められる。爪廓のダーモスコピーは、強皮症の早期例、軽症例を見出すことが可能で、積極的に行うべき検査である。
一次性レイノー症状を有する頻度は女性で2~9%、男性で2~6%といわれていて、その内の10%が膠原病と関連するとのこと。早期発見にダーモスコピーが有用だと知った。症例を集めれば、保険の適応拡大にも結びつくかも知れない。
-
第21回皮膚科在宅医療勉強会から(平成24年9月13日)
疥癬トンネルの検出は疥癬の診断上もっとも重要なポイントであるが、掌蹠や陰嚢・臀部の結節ではダーモスコピーでも確認可能な病変を見つけることができる。ただし、四肢・躯幹の痒疹丘疹では、ヒゼンダニを見つけることはできない。実際の寄生実験では、メスのヒゼンダニが少しだけ皮膚に潜ったあと、虫がそこにとどまらなくても、2日目には小水疱、丘疹が生じることを確認したので、ヒゼンダニのいない痒疹丘疹は虫がかつていたあと、あるいは、ちょっと潜ったあとで出てくると想像している。
痒疹反応は虫体や糞に対するアレルギーと解釈されてきたが、ちょっと潜って、そこに何らかの起痒物質を残していくのだろう。ちなみに、手掌・手指の疥癬トンネルは、フラットヘッドスキャナーに手を当ててスキャンをすれば、記録に残せるとのこと。他の手掌の疾患にも使えそうで、面白い。
-
第844回日本皮膚科学会東京地方会から(平成24年9月8日))
70代男性の多形慢性痒疹。腰臀部に膨疹様紅斑と丘疹が再燃した際にアポプロン0.2mgの内服を行い改善した。血圧の変動もなく、他の副作用もなし。抗ヒ剤と併用することで、かゆみに有効な症例があるので、難治例で試してみる価値がある。
確かに、再燃時には蕁麻疹様の紅斑が診られることが多い。衣類にすれる部分に一致するので、機械的蕁麻疹と同様の病変から始まり、掻破によって亜急性、慢性の経過に移行すると考えられる。難治例の蕁麻疹で有効例のあるレセルピンが多形慢性痒疹で有効例があるのもうなずける。オマリズマブもいいかもしれない。
-
第843回日本皮膚科学会東京地方会から(平成24年7月21日)
70代の男性で、糖尿病のため1年前からグリメピリドを内服している。臀部、左膝、左肘に大型の皮下硬結を生じた。病理組織では真皮深層と皮下脂肪織を中心とする非乾酪性類上皮細胞肉芽腫で、BHLとぶどう膜炎を伴い、サルコイドーシスと診断した。大型の皮膚サルコイドは糖尿病と関連が深く、膠原線維の変性とmicroangiopathyが発症に関与すると考えられる。糖尿病の治療により結節が縮小した症例もある。
意外な感じがした。環状肉芽腫になる症例と皮膚サルコイドになる症例は、どこが違うのか、興味がある。
-
第843回日本皮膚科学会東京地方会から(平成24年7月21日)
高齢男性で30年来の2型糖尿病。12年前からノボラピッド、ランタスなど腹部に注射していた。注射部位に一致して弾性やや軟の手拳大皮下腫瘤を認めた。組織では真皮深層に好酸性無構造物質の沈着があり、Congo red染色で陽性で、抗インスリン抗体を用いた免疫染色は陰性であった。インスリン注射部位に生じた医原性の限局性皮膚アミロイドーシスで、インスリンボールと名づけられている疾患。インスリン自体がアミロイドの前駆物質となるとのこと。
インスリンボールへのインスリン注射は吸収が低下し、効果が減弱する。また注射部位を変えることによって低血糖を起こしやすいので注意が必要とのこと。
-
第843回日本皮膚科学会東京地方会から(平成24年7月21日)
エキシマライトの有効性を検討した報告。白斑部をダーモスコピーで観察し、黒毛は生えていればエキシマライトが効きやすく、白毛のみだと効きにくいという傾向があった。
これは、観察しやすく、役に立ちそうだ。経過中にも毛に色が付いてきたかで治療の評価ができそうだ。さっそく取り入れてみよう。
-
第843回日本皮膚科学会東京地方会から(平成24年7月21日)
高齢者のアトピー性皮膚炎は、眼囲の病変が少ない、肘窩に苔癬化があるなど、小児や成人例と異なる臨床的な特徴を有する。しかし、IgEが高値の皮脂欠乏性皮膚炎との鑑別は明確ではない。病変部皮膚はIgE陽性の肥満細胞の増加と、CD11c、IgEがdouble positiveの真皮樹状細胞の浸潤がみられた。
定義が難しい。ただ、少なくとも20代から慢性の湿疹病変が50年以上継続している70代の患者を経験している。ステロイド忌避が問題となっていた1990年頃に30代、40代だった患者は現在60歳~70歳になっているわけだが、どうなっているのだろう。
-
第36回日本小児皮膚科学会から(平成24年7月15日)
生後4カ月の男児(第3子)で正常分娩、完全母乳保育、母は健康、兄弟に同症の既往なし。頚部の間擦疹から始まり、口囲、肛囲、外陰部などに典型疹が出現した。母の血清中亜鉛は78μg/dl(正常:65-110)と正常だったが、母乳中亜鉛は21μg/dl(正常:71-165)と低値。低亜鉛母乳の原因は、乳腺細胞における亜鉛輸送蛋白の異常のほか、初産婦の場合には乳汁の未成熟、経産婦の場合には加齢による血液から乳腺への取り込みの減少を考える必要がある。
治療はプロマックの内服でよいとのこと。この症例も内服開始4日目で改善している。母乳中亜鉛の正常値の基準として、記憶にとどめておきたい。
-
第36回日本小児皮膚科学会から(平成24年7月15日)
生下時は一見普通の毛髪が、成長とともに縮毛ないし乏毛が目立ってくる症例は、男女ともにあって、常染色体劣性遺伝が多い。そういった症例90%以上に、LIPH遺伝子変異が検出される。lipaseHの発現は毛包幹細胞の周囲に多く、毛髪の生育に重要な役割を果たしているらしい。なお、遺伝子検査はEDTAの採血で血球から行えるとのこと。
数例経験がある。今後は症例があれば、遺伝子検査も検討してみよう。遺伝子治療に結びつくとよいが、lipase Hの外用だけでは治療にならないのであろうか。新しいことがわかってきそうな分野である。
-
第36回日本小児皮膚科学会から(平成24年7月15日)
全身の無汗症の精査で入院。口渇、多飲、多尿を伴う。高Na血症、尿浸透圧が158mOsm/kgと低下、ADHは0.8pg/mlと低値。デスモプレッシン負荷テストで尿浸透圧は527mOsm/kgと上昇。MRIで下垂体炎があり、中枢性尿崩症と診断した。デスモプレッシン点鼻による治療後尿崩症は改善し、発汗も見られるようになり、運動後の熱感も改善した。
尿の出すぎで汗が出ないということか。皮膚科医がADH分泌異常症を考えることはまずないと思うので、貴重な症例であった。ステロイドパルスは無効。下垂体炎の治療はどうしたのか、討論はなかったが、無汗症の原因として、一応覚えておく必要がありそうだ。
-
第36回日本小児皮膚科学会から(平成24年7月15日)
てんかんの治療で内服していた臭化カリウムによるブロム疹の3歳女児の症例。左頬と左下腿に結節を生じ、bromoderma tuberosumと診断した。ブロム疹は鎮痛剤、鎮静剤、抗けいれん剤などに含まれる臭化カリウム、臭化ナトリウムなどの無機ブロム剤やブロムワレリル尿素(ブロバリン)などの有機ブロム剤の摂取によって生じる。メジコン、セスデン、ブスコパンなども臭化物を含んでいる。なお、臭素はハロゲン元素で、ブロム疹はフッ素(fluoroderma)、ヨウ素疹(iododerma)とともにhalogenodermaと総称されることがある。
臨床は壊疽性膿皮症に類似するというイメージがあるが、初期には結節性紅斑ないしはただの皮下結節でもよいようだ。OTCの総合感冒薬にも臭化物は多く使用されているとのことで、臨床から時には疑う必要もあるだろう。halogenodermaという病名は聞いたことがなかったので、勉強になった。
-
第42回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成24年7月15日)
慢性骨髄性白血病でイマチニブを2009年から内服中。3年後に頭部、眼囲、両頬に細かい白斑が複数生じてきた。四肢・体幹の皮膚も徐々に白くなってきた。イマチニブはフィラデルフィア染色体が有するBCR/ABL遺伝子のATP結合部位に特異的に結合し、白血病細胞が有しているチロシンキナーゼを選択的に阻害することにより治療効果をもたらすが、ほかにも血管内皮細胞の血小板由来成長因子レセプター(PDGFR)阻害、腫瘍細胞の KITレセプターチロシンキナーゼ阻害などがあり、多くの標的部位を有している。使用している患者の2~4割で脱色素斑がみられるとのことだが、完全脱色素斑は多くはない。
生物学的製剤は、その薬理作用から色々な種類の皮膚障害が想定できる。チロジナーゼが標的であれば、白斑・脱色素斑もうなずける。これからも色々な薬剤で、様々な皮膚病変が出てきそうだ。
-
第42回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成24年7月15日)
全身麻酔の導入後に生じたアナフィラキシーの症例。血圧低下、喘息発作、換気困難、全身の潮紅などがみられた。原因は静脈麻酔(鎮静剤)のプロボフォール(ディブリバン)、筋弛緩剤のロクロニウム(エスラックス)、筋弛緩剤拮抗薬のスガマデクス(ブリディオン)と多彩であった。とくにスガマデクスは手術の最後に使用される薬剤で、抜管後に生じることもあるため、注意が必要である。いずれもプリックテストや皮内反応で確認が可能で、皮膚科医でも知っておく必要である。
スガマデクスは確かに怖い。成分はただのオリゴ糖で、ロクロニウムと強固な複合体を形成するとのことだが、単独のプリックや皮内反応で陽性になるので、この場合はタンパク質の関与はなしということか。術中のアナフィラキシーの原因には、このほかに、ラテックスのアレルギーもあるとのこと。
-
第111回日本皮膚科学会総会から(平成24年6月2日)
10代の女児。震災後の不安神経症。鼻出血と指先の疼痛と紫斑で発症。指先の紫斑はダーモスコピーでは皮溝に沿う点状出血であった。その後指先が動かない、知覚がないなどと訴え、足趾や前腕にも点状紫斑や溢血斑が生じるようになった。末梢血液像、止血機能、補体などに異常なし。経過からAESSと診断した。ストレス後に発症する疾患で、患者の95%が女性である。かつて、Diamond症候群、心因性紫斑とも呼ばれていた。
疑ったことはあるが、診断したことはない。女性とストレスがキーワードのようだ。自己血の皮内反応は今でも診断に有用とのこと。
-
某製薬会社主催講演会から(平成24年7月1日)
臀部や大腿後面に再発性の単純性疱疹をきたす患者があるが、これは陰部ヘルペスを繰り返しているうちに、それらが移動してそこに出るようになったものである。なお、HSV-1抗体保有者はHSV-2に感染するが、不顕性になるか、あるいは症状が出ても軽症である。したがって、性器ヘルペスという認識のない無症候性排泄者が感染の蔓延に関与していると考えられる。反対に、HSV-2に先に罹患した患者はHSV-1に感染することは少ない。
当院にも数名、臀部に再発性のヘルペスを生じる高齢女性がいる。性器ヘルペスの既往は、若い頃にあったという。なお、臀部に初発するヘルペスも稀ではあるがあって、西洋式便器を介しての感染だったとのことである。
-
某製薬会社主催講演会から(平成24年6月30日)
アトピー性皮膚炎の眼合併症のうち、網膜剥離には注意が必要である。再周辺部に裂孔が生じることが多いため、自覚症状に乏しく、したがって発見が難しい。また手術も簡単ではなく、さらにかゆみのため、術後の安静も不十分になりがちで、再剥離を生じることが稀でない。
角膜の病変や白内障はよく聞くが、網膜剥離は詳しく知らなかった。いずれにしても眼合併症には注意しなければならない。
-
第842回日本皮膚科学会東京地方会から(平成24年6月16日)
HCV感染の証明されない40代女性の外陰部、小陰唇粘膜に生じた扁平苔癬。口腔粘膜は異常なし。男女とも外陰部は扁平苔癬の好発部位だが、外陰部に病変のある患者の半数で口腔内病変を伴い、また、口腔内病変のある患者の20%に外陰部病変があるといわれている。
男性の亀頭部ではたまに見ることがあるが、たしかに女性の外陰部の病変はあまり記憶にない。いずれにしても口腔内に病変があったら、ためらわず外陰部の診察をする必要がありそうだ。
-
第842回日本皮膚科学会東京地方会から(平成24年6月16日)
ポリカーボネート樹脂やエポキシ樹脂の原料となる、フェノール化合物のビスフェノールAの分包に携わっていた成人男性2名の前腕と項部に完全脱色素斑が生じた。接触皮膚炎の前駆症状はなし。業務から離れた後に、ビタミンD3の外用のみで改善した。フェノール化合物に職業的に接触する者に生じる白斑はoccupational vitiligoとして知られているが、局所の炎症を伴う例と伴わない例がある。作用機序はチロジナーゼ発現量の抑制ないしチロジナーゼに対する拮抗作用、メラノサイトそのものの障害が想定されている。
重要な発表だった。つい最近、美白化粧品に含まれていたロドデノールが、白斑を生じたということで商品回収になったが、同じフェノール化合物なので、経過や予後、作用機序を知る上で、参考になるだろう。ビスフェノールAでは先行する接触皮膚炎はなかったとのことだが、ロドデノールではどうなのだろうか。
-
第111回日本皮膚科学会総会から(平成24年6月2日)
莓状血管腫に対して、プロプラノロール内服療法を行った12例と過去の症例との比較。2mg/kg/日を半年間継続することで、全例で拡大抑制、早期退縮誘導がみられ、有効であった。副作用は便秘が1例にあったが、血圧低下や徐脈はなかった。βブロッカーによる血管収縮のほか、血管新生因子の阻害、内皮細胞のアポトーシスが作用機序と考えられる。
心血管機能への副作用がないのであれば、積極的に使った方がいいのではと思う。色素レーザーをするかしないかも意見が分かれているようで、最善の治療指針が定まるのを期待したい。
-
第111回日本皮膚科学会総会から(平成24年6月2日)
3歳の男児で、1年前から下腹部と胸部から腋窩にかけての両側のmilk lineに複数の白色の扁平な小結節が出現した。組織では基底層に大型で丸いpagetoid clear cellがみられ、それらはEMA、CK7、ムチンが陽性であり、clear cell papulosis of the skinと診断した。先天性三角形脱毛症、両腋窩の副乳、posterior helical ear pitsを伴っていた。
聞いたことがなかった。ear pitsも初耳だった。アジア人の報告が多く、nippleのclear cellと同じ由来とのこと。nipple表皮には、乳腺器官の一部として、非腫瘍性のclear cellが存在し、それが乳房Paget病のoriginであるとのこと。知らなかった。
-
第111回日本皮膚科学会総会から(平成24年6月2日)
50代女性に生じた出血を伴うlivedoと皮内結節。組織は小動脈のフィブリノイド壊死を伴う血管炎。全身症状はなく、皮膚型PNと診断。30代で輸血歴があり、HBs抗原陽性、HBc抗体陽性で、HBV-DNAが5.9 log copies/mlで慢性B型肝炎と診断。エンテカビルの内服を開始し、3カ月で皮膚症状は改善。1年後にはHBV-DNAも検出されなくなり、皮膚症状の再現もない。
きれいな症例だった。HBVに対する治療のみで改善し、再燃していないということが重要である。皮膚の血管炎の部位にHBVの局在が証明できれば、さらに完璧だった。
-
第111回日本皮膚科学会総会から(平成24年6月2日)
ざ瘡などでミノマイシンの内服歴のある複数の患者で、眼瞼結膜に点状ないし不整形の色素沈着が生じた。1例は結膜結石を繰り返していて、組織学的には白色の点状無構造物質で、自家蛍光を発することからリポフスチンと考えられた、ミノマイシンが副涙腺から分泌され、酸化されて色素沈着になり、さらにカルシウムとキレートを作り、結石になったと考えられた。
結石の組織はカルシウムではなく、リポフスチンで間違いなさそうだ。口腔粘膜の色素沈着はみたことがあるが、結膜にも注目してみよう。
-
第111回日本皮膚科学会総会から(平成24年6月2日)
発汗テストに用いられるヨードデンプン法は準備に時間がかかり、拭き取りも面倒である。ホワイトボードマーカーの中には水に触れると色が消える製品(パピエコのウォータークリヤペン)があり、発汗テストに用いることができる。微量な汗でも色が消失するので、多汗症の部位の診断にも応用できる。
すぐに乾き口に入っても安全とのこと。学術的ではないがこういった小道具の紹介は楽しい。塗るのが大変そうだが注文してみよう。
-
武蔵小杉皮膚フォーラムから(平成24年5月19日)
乾癬の治療法の歴史。1920年代のDr.William Goeckermanによる、コールタール軟膏と水銀灯によるゲッケルマン療法と、1950年代のDr.John Ingramによる、アンスラリン軟膏とUVBを組み合わせたイングラム療法。入院して4から6週間継続する必要があった。現在では米国内でもわずかな施設でしか実施されていない。
私も昭和50年代に経験したが、いい治療法だった。昨今の入院期間を短縮させる必要がある時代にはふさわしくないのだろう。
-
墨東病院オープンカンファレンスから(平成24年5月17日)
中年女性で、左そけい部の腫瘤を主訴に受診。下肢の痛みや血行障害はなし。CTでは右総腸骨および内外腸骨静脈は拡張。左総腸骨静脈は右総腸骨動脈と椎体に圧排され、完全に虚脱していた。これをMay-Thurner症候群と呼ぶ。この部位の血流障害があると左下肢の深部静脈血栓症をきたすので、左総腸骨静脈にステントを留置する必要がある。
皮下の腫瘤のみで、よく診断がついたものだと感心した。血管の疾患は奧が深い。ちなみにスペルはTurnerではなく、Thurnerが正しい。
-
横浜市医師会医学研修の日から(平成24年5月15日)
院内救急は、まずはBLS(Basic Life Support)からという話。1)倒れている傷病者を発見、2)自分の安全(手袋とマスクを着用)と周囲の状況把握、3)意識確認(両肩を叩いて「だいじょーぶですかー?」)4)119番に連絡する人、AEDを持ってくる人、人を集めてくる人、をそれぞれ指名。全員必ず帰ってくるように指示。5)胸郭の上下を見る、呼吸を聞く、頚動脈を触れて、脈と呼吸を確認、6)呼吸なし、脈なしなら心肺蘇生へ、胸骨下半分圧迫30回(強く、早く、絶え間なく)に人工呼吸2回、7)AEDが到着すればAEDの指示に従う、その間も胸骨圧迫。BLSをクリニックで対応できるような教育プログラムを今後稼働させていく予定とのこと。
AEDの設置もちろんだが、医院の待合室での事態を想定すれば、スタッフには毎日その日の役割を指示しておく必要があると思った。
-
第24回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成24年5月13日)
アトピー性皮膚炎(AD)の病勢マーカーであるTARCは、2歳未満では生理的に高値を示すため、有用性が評価されていなかった。アレルギー疾患で受診した175例の2歳未満の患者の診断は、ADが102例、食物アレルギーが133例、気管支喘息が18例、その他が2例で、それぞれのTARC値から、ADの特異度を検討した。乳児で1,221pg/ml、1歳児で652pg/mlを基準値とすると、AD診断の感度はそれぞれ70%と82%、偽陽性率は38%と24%。また、基準値を乳児2,626pg/ml、1歳児1,194pg/mlとした場合、偽陽性率はそれぞれ5%以下となった。年齢別のカットオフ値を設定することで、幼児でも病勢のマーカーとすることができる。
採血は必要になるが、データの集積は必要だろう。基準値以上だからADだというわけではないが、計測値の変動は評価でいるかもしれない。
-
第24回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成24年5月13日)
母乳中の卵アレルゲンの定量を行った。卵摂食後の母乳58検体のうち、3検体(5.2%)から、アレルギーを誘発する可能性のある量の卵白アルブミン(卵タンパク質換算でそれぞれ1.4、1.5、2.5μg/ml)が検出された。また、23検体(39.7%)からはng/mlレベルの量が検出された。マヨネーズ、プリン、クッキーなどの加工食品摂食後の母乳からは、検出されなかった。
母乳からの卵白アレルゲンが乳児のアトピー性皮膚炎の原因や悪化因子になるのか、悩ましいデータである。母乳中では卵白アレルゲンは分泌型IgAにとりかこまれ、抗原としては機能しないということだが、一部には遊離の形で存在しているらしい。これがアレルゲンになる可能性があるような気もする。
-
第61回神奈川医真菌研究会から(平成24年5月12日)
足の臭いの原因は主にイソ吉草酸が原因であり、これは悪臭防止法(1971)第2条に基づいて指定される「不快な臭いの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質」として施行されている22物質のうちの一つである。通常は環境中には畜産事業場や化学系工場などが主な発生源で、規制値が設けられている。これを発生させるのがcorytebacteriumなどの足の皮膚にいる常在菌である。
規制値まで設けられているとは知らなかった。なお、ダームライトⅡUvaという商品があり、今は手に入らないウッド灯のかわりになるという情報があった。
-
第10回皮膚膠原病研究会から(平成24年4月28日)
小児の顔面に生じた線状強皮症は、徐々に進行し整容的な障害を残すことが多く、早期の積極的な治療を考慮しなければならない。臨床的に炎症が強く急速に拡大していている場合、抗ss-DNA抗体が高値の場合にはステロイド内服の適応となるが、投与量の基準はない。最近、MTX併用の有用性が報告された。PSL1mg/kg/dayとMTX15mg/m2/weekの12週間投与で、80%で有効、副作用は吐き気、頭痛、肝機能障害などであったが重篤ではなかった。今後治療の時期、投与量、投与期間などについて、症例を重ねて検討する必要がある。
確かに、顔だと整容的に問題となり、四肢だと成長障害のため機能障害をきたす。MTXは小児には使いづらい薬剤だが、やはり必要なのだろう。小児科と連携できる病院に早めに紹介する必要がありそうだ。
-
第28回日本臨床皮膚科医会総会から(平成24年4月21日)
2008年から皮膚症状の激しい手足口病が流行し、コクサッキーウイルスA6による感染が原因であると考えられている。皮膚症状は、水疱の分布が広く、水疱も大きく、痂皮にいたるなど症状が激しいが、頬粘膜や舌のアフタ性の変化は少ないという特徴が示されている。しかし、よく観察すると口蓋垂とその周囲から咽頭後壁にかけての炎症は強く、いわゆる口峡炎(angina)を呈していて、ここにアフタを伴う例もあり、まさにヘルパンギーナと同様の症状である。コクサッキーA6もヘルパンギーナの原因ウイルスの一つであり、両者をまとめれば、皮膚症状も口峡炎もコクサッキーA6感染症ということになる。
コクサッキーA6は、このところ2年おきに手足口病の原因ウイルスの中での占める割合が大きくなっている。今年は口峡炎の有無にも注意して診ていく必要がありそうだ。
-
第28回日本臨床皮膚科医会総会から(平成24年4月21日)
アリに刺された後に、蕁麻疹、アナフィラキシーを発症した中年男性の症例。持参したアリはオオハリアリと同定された。通常は屋外の石の下や朽ち木に潜んでいるが、シロアリを補食するため、屋内でも風呂場や台所などの腐った木材に出現する。おしりの毒針で刺すためチックとした痛みを感じる。アレルゲンは蜂と同様と考えられる。このほか、山地に住むクシケアリ、屋内に巣を作るイエヒメアリも刺症を生じる場合がある。
虫さされの原因がアリかもしれないと思うときがあるが、名前や生態などは全く知らなかったので、参考になった。このほかアリに似たシバンムシアリガタバチの刺症も屋内で生じる。アリは咬むと思っていたが、どうやら毒針で刺すのが正しいようだ。
-
某製薬会社主催講演会から(平成24年4月1日)
アトピー性皮膚炎患者の多くは汗に対する即時型アレルギーを有している。タンニン酸がヒスタミン遊離性精製汗抗原を失活させる物質のひとつであることを見出した。そこでアトピー性皮膚炎のスキンケアを補完する目的で、タンニン酸を配合したエアゾールスプレー製剤(0.05%)を作製し、2~4週間連続して使用し、使用前後での臨床症状、かゆみスコアを対照群と比較した。タンニン酸スプレーはアトピー性皮膚炎の臨床症状の有意な改善と午後のかゆみの改善がみられた。有害事象もなく、アトピー性皮膚炎の臨床症状ならびにかゆみに対して有効かつ安全に使用できると考えられた。
汗抗原は陽イオンに吸着されるらしい。コマーシャルで使えるようになれば、汗で悪化する夏場のアトピー性皮膚炎の管理に役立ちそうである。少し臭いかもしれないが。
-
横浜皮膚悪性腫瘍研究会から(平成24年3月15日)
イミキモドは、細胞の受容体TLR-7あるいはTLR-8に作用し、INF-αやIL-12などのサイトカインの産生を促進し、自然免疫系および細胞性免疫応答を賦活化することによって日光角化症に効果を発揮すると考えられている。高齢者の顔面には、明らかな日光角化症の病変の近傍に、臨床的には明らかでない微小な病変が隠れていることが多く、これをField Cancerizationという。顔面全体にベセルナクリームを外用すると、あぶり出し効果によってこれらが明らかになることが多い。
5FUの外用でも同様のことがおこる。脂漏性角化症だけが残るのが、不思議だ。
-
第65回横浜市アレルギー懇話会から(平成24年3月14日)
C57BL/6マウスは、本来Th1優位でTh2型反応は起こしにくいが、抗原の腹腔内曝露とハプテンを用いない経皮曝露とが同程度にTh2反応を誘導することから、経皮感作による喘息モデルとなり得る。このマウスの背部に卵白アルブミン(OVA)を感作した後にOVAを吸入曝露し、その後の気道過敏性、好酸球数を測定し、腹腔内で感作した対照群と比較した。腹腔内感作群における気道過敏性と好酸球数は曝露翌日に最も強く、7日目にはほぼ完全に終息したが、経皮感作群では曝露7日目でも曝露翌日とほぼ同程度の好酸球増多が持続し、気道過敏性亢進は14日目まで遷延した。また、IL-17AおよびIL-23p19のノックアウトマウスを用いると、好酸球数と気道過敏性は、抗原曝露翌日では野生型と同等であるが、曝露7日目以降の好酸球数、気道過敏性は低下し、経皮感作による好酸球性炎症の遷延がIL-17依存性であることが証明された。
アトピー性皮膚炎に伴うバリア障害、あるいはフィラグリンの遺伝子変異が遷延する喘息の原因という流れか。スギ花粉飛散時に皮膚炎を生じる患者は、皮膚炎のない患者より遷延する炎症(鼻閉)が多いかもしれない。
-
神奈川アレルギーセミナーから(平成24年3月10日)
ミルクアレルギーのある乳児で、乳蛋白質消化調製粉末ニューMA-1で栄養管理を行っていたが、眼囲、口囲、臀部などに亜鉛欠乏症に似た紅斑、びらんをきたした。血中亜鉛は正常であった。ビオチンの投与で軽快。ビオチン欠乏症では血中ビオチン値は早期には低下せず、尿中3-ヒドロキシイソ吉草酸(3-HIA)の増加がマーカーとなる。ビオチン欠乏による同様の皮膚症状は経静脈栄養管理下でも発生する。また、抗けいれん剤の内服で血中ビオチンが低下することも報告されている。
脳血管障害で抗けいれん剤内服中の患者に脂漏性皮膚炎が多く、顔面の紅斑などの症状が強いと感じているが、ビオチンを投与してみたくなった。血清中のビオチンは様々な蛋白と結合し、測定が難しいとのことで、尿中3-HIAを測れるような体制になれば、さらに皮膚疾患との関連もはっきりしてくるのではないか。それにしても不思議な存在である。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成24年3月1日)
伝染性単核球症(IM)の診断に必要な、EBVの抗体の動き。1)急性期VCA-IgM抗体陽性、2)ペア血清でVCA-IgG抗体の4倍の上昇、3)急性期~早期回復期EA-IgG抗体の一過性上昇、4)急性期VCA-IgG抗体陽性でのちにEBNA抗体が陽転、5)EBNA-IgM抗体陽性/EBNA-IgG抗体陰性。なお、リンパ球50%以上、異形リンパ球10%以上の血液所見も参考になるが、CD8の増加が顕著で、CD4/CD8は1.0以下になる。
いつも忘れてしまう。以前から、乳児の砂かぶれ様皮膚炎で検討したいと思っている。IMと同じ初感染パターンとなるか知りたい。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成24年3月1日)
テレプラビルはHCVの複製に関与するNS3-4Aセリンプロテアーゼを阻害することにより、HCVの増殖を抑制する作用を有し、ペグインターフェロン(PEG-IFN)とリバビリン(RBV)を併せた3剤併用療法により、従来からの2剤併用療法を上回る治療効果が期待されているが、副作用として皮膚障害が80%に生じることが報告されている。治療開始にあたっては、皮膚科医との連携を確認することが示された。症状は播種状紅斑丘疹、多形紅斑から、SJSやTENに至る例もある。テレプラビルは継続しないと薬剤耐性変異を生じやすいため、発疹が体表面積の50%以下の場合で、全身症状がない(グレード1)、あるいは軽度(グレード2)の場合は、原則として3剤併用を継続し、症状に応じて抗ヒスタミン薬内服やステロイド外用で対処する。発疹が体表面積の50%以上では、速やかに中止し、皮膚科で対応することになる。
分子標的薬とちがって「発疹が出れば有効な証拠」ではないことに、注意する必要がありそうだ。詳細は日皮のHPにあるが、皮膚科医の任務と心得ておこう。
-
第75回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成24年2月19日)
大腸癌に対して、抗EGFR抗体であるパニツマブにて加療中。4週後から睫毛の伸長を自覚するようになった。セツキシマブ、エルロチニブでも同様の副作用があり、EGFR阻害による角化の異常と考えられている。時に乱生し角膜損傷をきたすこともあるので、副作用の一つとして認識する必要がある。
分子標的薬による癌治療では、皮膚の副作用が出てくれば効果が出てきた証拠と評価するのが通例である。睫毛も、伸びてきたら効いてきた、と考えるのであれば、治療前に長さを測っておけばよいのではないかと思った。ざ瘡様発疹にしても、再診のたびに、何個あるかを計測しておくとよいかもしれない。
-
第75回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成24年2月18日)
10代の男児。運動後の気分不快とほてり感、発汗の低下に気づき来院。温熱負荷でも全身の発汗がなく、塩酸ピロカルピンでも誘発されず。多尿があり血漿浸透圧の上昇、高Na血症を伴っていた。MRIにて下垂体炎を認め、中枢性尿崩症と診断。デスモプレシン点鼻治療で、多尿は改善、2カ月後には温熱負荷で全身の発汗がみられるようになった。
全身の無汗症といえば、即ステロイドパルスを考えてしまうが、そうでない症例もあるということで、勉強になった。
-
第841回日本皮膚科学会東京地方会から(平成24年1月21日)
80代の女性。高血圧症の治療で5カ月前からヘルベッサー、1カ月前からアダラートを内服していた。2週間前から下腹部から足背に及ぶ浮腫が出現した。アダラートを中止すると、多尿となり、2週間で8㎏の体重減少とともに浮腫はきれいに消褪した。循環器・高血圧内科的には有名であるが、皮膚科では以外と知られていない。
アムロジピンでも27%に下肢の浮腫が生じるといわれるほど、頻度が高い副作用である。末梢静脈よりも末梢動脈に対して強く血管拡張作用をきたすため毛細血管圧が上昇し、水分が血管外に漏出するための浮腫と考えられている。なお、ヘルベッサーなどの非ジヒドロピリジン系のカルシウム拮抗薬は、血管拡張作用より心収縮を抑制する作用が強く、下腿浮腫が出現したら心不全を疑う必要があるので、皮膚科医でも両者の違いには注意しないといけない。
-
第841回日本皮膚科学会東京地方会から(平成24年1月21日)
各種抗生剤、抗真菌剤、アロプリノール、カルバマゼピンなどの内服数日後に、38℃以上の熱発と全身の潮紅、多数の無菌性小膿疱をきたす重症薬疹。その発症機序は、病変部のT 細胞の解析により、通常の播種状紅斑丘疹型の薬疹と比較すると、本症では末梢血や皮膚病変組織にCXCL8(IL-8)を産生する薬剤特異的Tリンパ球が有意に多いことが指摘され、好中球性のⅣ型アレルギーと考えてよい。
名称にも同意できる。好中球を動員するサイトカイン産生のスイッチがどこにあるのかが興味深い。感染症が先行あるいは増悪因子となること、好中球が皮膚に動員されやすい基礎疾患(乾癬関節リウマチ、骨髄性白血病、潰瘍性大腸炎など)があるので、ホスト側の状況が関連していそうである。
-
第7回筑駒医師の会から(平成23年12月30日)
低線量内部長期被爆が人体に何をもたらすのかを呈示した事例。二酸化トリウムを主成分とする造影剤トロトラストは1930年にドイツのハイデン社により製品化された放射性の血管造影剤で、わが国では主として1932年から1945年にかけて使用された。その数は10,000~20,000人と推定されている。トロトラストは体内ではトリウム-232として肝臓、脾臓などに沈着し、主としてα線による内部被爆を引き起こし、20年から30年後に肝血管肉腫や白血病を発症させた。現在でも生存しているトロトラスト沈着症例について年に1回健診が行われている。
学生の時に習ったような気もするが、すっかり忘れていた。皮膚病変の総括などはなされているのであろうか。トロトラスト沈着者カードなるものもあるようだが、医者になって一度もみたことがない。
-
第840回日本皮膚科学会東京地方会から(平成23年12月17日)
梅毒再感染の症例報告。TPHAは10,280倍、RPRは1倍と乖離がみられた。梅毒再感染ではブースター効果でトレポネーマに対する抗体が過剰に産生され、凝集が抑制されるためにSTSが偽陰性となることがある(プロゾーン現象ないし前地帯現象)ので、検査の見方に注意が必要。
反対に抗原過剰の場合はポストゾーン現象と呼ぶ。いずれも梅毒に限ったことではないが、沈降反応や凝集反応の抑制を示す用語。なお、固相法とくに酵素免疫法では、抗原過剰の場合に結合がmaximumに達すると、検量線はピークから少し下がり気味になり、その形からフック(hook)現象と呼ばれるそうである。ちなみにかつてSTSに使われていた凝集法やガラス板法はそれぞれ平成20年3月、平成21年12月以降、測定試薬の製造中止で行われなくなり、STSは現在はRPR(カード法およびラテックス凝集法)だけになっていたと知った。
-
第137回神奈川県皮膚科医会例会から(平成23年12月4日)
皮膚外用剤は、基剤からの主薬の放出と、放出された主薬の皮膚への透過の2つの過程で効果を発揮する。同じ規格濃度であっても基剤に溶けている主薬の濃度は製品によってばらつきがあり、ジェネリック医薬品の品質の評価の際にも、考慮されるべきである。先発品では、主薬ができるだけ高い濃度で基剤に溶けように設計されていて、基剤に対して溶けにくい主薬の場合はプロピレングリコールや炭酸プロピレンなどの溶解補助剤を用いて高い濃度で溶解し、基剤中に均等に分散させた液滴分散型製剤として調製している。
プロトピック軟膏、ドボネックス軟膏、オキサロール軟膏、ボンアルファ軟膏、ステロイドではフルメタ軟膏、アルメタ軟膏がこの方式で調整されているとのこと。混合はおそらく不適と思われるので、覚えておこう。
-
第27回日本臨床皮膚科医会三ブロック合同学術集会から(平成23年11月23日)
痒疹についての総論から、定義・診断上の問題点を指摘した講演。多形慢性痒疹は中高齢者の体幹に生じ蕁麻疹様丘疹で始まり、褐色の充実性丘疹となる、経過としては亜急性の病変で、集蔟密生する傾向があることが特徴である。一部の症例では敷石状に集まった地図状の病変が、腹部のシワに沿った帯状の正常皮膚を残し(deck-chair sign)、太藤の丘疹紅皮症に移行する例がある。両者の関連について、今後も検討が必要である。
多形慢性痒疹は、印象としては、薬剤や悪性腫瘍などと関連している症例が多い気がする。これからも症例の蓄積とともに、ひとりひとりの経過を長く見る必要がありそうだ。deck-chair signはどうもステロイド外用薬の影響があるように思うが、実際はどうなのだろうか。
-
第62回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成23年11月19日)
乳癌治療中の2名の女性患者。それぞれタモキシフェンとアナストロゾールで治療を継続している。術前化学療法中に生じた脱毛がその後も数年間遷延していて、臨床と組織所見から男性型脱毛症と診断した。抗エストロゲン作用による副反応と考えられる。
なるほど、あってしかるべきの副作用か。症例が多くなれば、治療やその後のマネージメントのガイドラインも必要か。
-
第61回日本アレルギー学会秋季学術大会から(平成23年11月12日)
豚肉を食べて生じる口腔内アレルギー症候群、蕁麻疹、運動誘発アレルギーの症例では、ネコ上皮と交叉感作が証明される症例があり、Pork-Cat syndromeと呼ばれている。アルブミンのエピトープであるFed d2に対する特異的IgEが証明される。ハウスダストとしてのネコ上皮の吸入、ポーク、ビーフ、ラムの摂食、あるいはネコ上皮、肉の経皮感作で発症する可能性がある。
豚肉のアレルギーはPork-Cat syndromeとは別の、赤肉に含まれるα-galに対するIgEを介する症例もある。感作経路は摂食ではなく、ダニ刺傷がキャリアーになっているらしい。そもそもα-galのアレルギーはセツキシマブ(アービタックス)の副作用から存在が確認され、抗セツキシマブIgE抗体の有無で確認できるという。面白くなってきた。
-
第61回日本アレルギー学会秋季学術大会から(平成23年11月12日)
三重県津市からの報告。ダーラム型捕集器による実測で、毎年少数ながら10月中旬から秋のスギ花粉の飛散が始まり、11月中旬から下旬にピークとなり、その後減少する。春にスギ花粉症で耳鼻科を受診した281名に対しアンケート調査を行ったところ、秋冬に鼻炎が出現する患者は21%であった。また、秋冬にスギ花粉の飛散があることを知っていた患者は41%であった。
地域差があるかも知れないが、関東ではあまり知られていないのではないか。当院でも11月になると眼瞼炎の患者が若干増えるので、スギ花粉との関連があると考えている。もっと宣伝する必要がありそうだ。
-
第61回日本アレルギー学会秋季学術大会から(平成23年11月10日)
抗ヒ剤の内服で改善した後の蕁麻疹の管理の話。発症後2~6週の特発性蕁麻疹で、抗ヒ剤内服で一旦48時間以上の消褪が確認された93名の患者を、さらにアレグラを1カ月継続して中止した治療継続群と、内服を行わない無治療群に分け、3カ月後までの再発率を比較した。内服継続群が70%、無治療群では90%の再発率であった。改善した後の抗ヒ剤内服継続は、再発抑制に有用である。
逆に言えば、内服を1カ月継続しても、その後70%で再燃があるということ。10年以上つきあっている慢性蕁麻疹の患者もいて、いつになったら出なくなるのかと聞かれる。高齢者には慢性蕁麻疹が少ないと思うので、年をとれば少なくなると答えるが、本当かどうかは分からない。20年、30年の予後調査はどこかにあるのだろうか。
-
第8回血管バイオメカニクス研究会から(平成23年11月5日)
ACC/AHAの末梢動脈疾患ガイドライン2005が2011年アップデートされた。5年間の症例の蓄積から、65歳以上になれば、FontainⅠであっても心血管の重大なイベントの発生率が高まることから、ABPIが9.0以下を目安として下肢末梢動脈疾患(PAD)患者の早期発見、早期マネイジメントが必要とされ、65歳以上の全ての人に血管健診を行うのがよいと結論された。また、0.91から0.99までをボーダーラインとし、記載しておく必要があることも明記された。
なるほどと思う。ただ、ABPI以外の臨床検査などのマーカーがほしいところだ。PADの早期病変(アクロチアノーゼ、網状皮斑、足背の浮腫)の把握は皮膚科医の診察が大事で、積極的に介入しないといけない。重症血管イベント予防のためPADでも認可されるプラビックスの効果については、今後皮膚科的にも検証が必要である。どこかで臨床研究が行われるとよいが。
-
横浜市皮膚科医会学術講演会から(平成23年11月2日)
FDEIAでは食後1時間以内に運動して発症する症例が全体の70%であり、また運動をして1時間以内に症状が出現する症例が全体の90%である。しがたって、食事の後、少なくとも2時間は安静にするよう、患者に伝えておくことが無難である。
多くの症例の集積から得られた、大事なエビデンスである。さっそく実践していこう。
-
第8回相模原皮膚科学セミナーから(平成23年10月22日)
浅在性血栓性静脈炎は皮下組織の筋性小静脈を反応の場とする炎症性疾患で、病理組織学的には血管壁の炎症と内腔のフィブリン血栓が特徴である。下肢の浅在性静脈に好発し、索状を呈するもののほか、圧痛のある指頭大の紅斑が多発する例がある。後者は臨床的にも病理学的にも皮膚型結節性多発動脈炎と誤診され易い。修復期においては小静脈内膜側に新生した弾性線維が一見筋性動脈の内弾性板に見えるので注意が必要だが、豊富な弾性線維に挟まれ、やや隙間のある束状ないし同心円状の平滑筋層の存在が静脈の特徴を示している。
これはいい話を聞いた。欧米の教科書にPAN、つまり小動脈炎として掲載されている写真の多くは静脈であるらしい。Rook第8版のFig50.20は、間違いなく静脈だ。教科書の間違いを指摘できるとは、さすがである。
-
横浜市皮膚科医会第130回例会から(平成23年10月20日)
前向きの疫学調査から。1歳半でアトピー性皮膚炎(AD)と診断された幼児のTEWLを調査し、3歳になった時点でADがあるかを調べたところ、TEWLが高いグループにADの残存がみとめられた。TEWLが高いほど黄色ブドウ球菌が繁殖しやすい傾向があり、早期からの抗菌的スキンケアが、ADの遷延に対して有効な対抗措置と考えられる。
黄ブ菌が検出されるグループでは、表皮から分泌される角層内IL-18が高い傾向があり、これは総IgE値、LDH、TARC、TEWLと相関するという。抗菌薬の外用までは必要なさそうで、抗菌的スキンケアとして、クマザサやキシリトールなどが紹介されていた。衛生仮説と相反するような気もするが、一応、念頭に置いておこう。
-
神奈川県皮膚科医会学術講演会から(平成23年10月13日)
抗ヒ剤の排泄経路のおさらい。胆汁排泄がメインなのがアレグラ。腎排泄がメインなのがアレジオン、ザイザル、アレロック、エバステル、タリオン。腎・胆汁半々なのがクラリチン。腎障害患者、透析患者ではアレグラが無難ということ。
ついつい忘れてしまうので、しっかり記憶に止めよう。
-
第63回日本皮膚科学会西部総会から(平成23年10月8日)
子持ちガレイを食べた後に発症する即時型アレルギーがあり、蕁麻疹とアナフィラキシーを呈する。20名の患者があり、そのうち17名に牛肉や豚肉に対するアレルギーの既往があり、20名全員で牛肉と豚肉に対する特異的IgEが証明された。カレイ魚卵でプリックテストが陽性。ウエスタンブロットでは100kDaのカレイ魚卵中の蛋白に結合し、その結合は牛肉可溶性蛋白で阻害された。カレイ魚卵のアレルギーは牛肉・豚肉と交叉反応する。
経験がないが非常に面白かった。そもそも牛肉・豚肉のアレルギーを経験しない。これは見逃している可能性が高そうだ。あしたから、蕁麻疹の患者には、しっかりと既往を聞いてみよう。なお、交叉反応は四つ足動物の肉で、鶏肉にはないらしい。
-
第63回日本皮膚科学会西部総会から(平成23年10月8日)
Mycobacterium ulcerans、あるいはM. ulcerans subsp. shinshuenseが原因で発症する、皮膚病変を主症状とする感染症。多くの皮膚潰瘍患者がいたウガンダの地域の名をとって命名された。日本でも1980年に初めて報告され、これまでに30例ほどの報告がある。もともとは土壌や水中に存在する菌だが、水棲昆虫やザリガニなどからも検出されている。四肢に多く、外傷による創から侵入すると考えられる。初期には、虫刺様の紅斑から紅色丘疹で、徐々に直径数cm大の無痛性の皮下結節に進行する。その後、数日から数週間でその中心部が自壊し、潰瘍になる。痛みは無いか軽度だが、二次感染を伴う場合は疼痛を認める。発熱はまれで、全身状態は良好なことが多く、ブルーリ潰瘍が死因となることはまれだが、診断・治療が遅れると、関節の屈曲や皮膚に巨大瘢痕などの後遺症が残る。治療は抗菌薬内服(リファンピシンやクラリスロマイシン、キノロンなどを数種類内服)で、潰瘍が大きい場合には外科治療も必要。
潰瘍という名称だが、潰瘍になる前の皮下結節の時の皮膚生検、特染、培養が重要。培養の至適温度は30~33℃だが室温でも増殖可能。ただし発育は遅く、3カ月間の観察が必要とのこと。炎症性のあやしい皮下結節は、やはり生検、培養が大事だ。
-
第63回日本皮膚科学会西部総会から(平成23年10月8日)
2010年4月に宮崎で発生し、その後流行した口蹄疫では、8月の終息までに30万頭の家畜が殺処分となった。この防疫作業に伴って、消石灰、炭酸ソーダによるchemical burnの症状が相当数発生した。口蹄疫(foot-and-mouth disease)は主として偶蹄目に属する家畜に生じる感染症で、ピコナウイルス科に属する口蹄疫ウイルスが原因である。発熱、元気消失、多量のよだれが主症状で、舌、口腔内、蹄の付け根などに水疱が生じ、破れて潰瘍を形成し、蹄は脱落する。
手足口病のコクサッキーウイルスでも、爪脱落が生じる。コクサッキーウイルスもピコナウイルス科に属するということで、症状にも共通点があるようだ。
-
第63回日本皮膚科学会西部総会から(平成23年10月8日)
北海道のライム病の疫学調査、マダニ刺症を受けた患者の8%でライム病が発症していた。マダニ刺症の発生は6月に最も多く、咬まれた部位は頭頚部が1/3と最も多かった。シュルツマダニが80%をしめ、そのうち12%がボレリア菌陽性だった。患者の約半数は受診する前にマダニを自分で引き抜いていたが、自己抜去群のライム病発症率は16.1%で、非自己抜去群の0.81%と比べ有意に発症率が高かった。さらに、咬まれてから医療機関を受診するまでの期間については、ライム病を発症しなかった人は咬まれてから平均約4日で医療機関を受診したのに対し、ライム病を発症した人では受診までに平均約20日が経過していた。なお、ライム病の治療後、数週ばいし数カ月してから、関節炎、筋肉痛、顔面神経麻痺、心伝導障害のほか、認知症、食餌不振症などの精神症状を呈することがあり、post lyme disease syndromeと呼ばれている。
マダニ刺症は、外科的切除と早めの抗菌剤投与が必要という傍証であった。なお、BSK培地という培地を用いると、発熱期の血液からボレリアの分離・培養は比較的容易とのこと。
-
皮膚科学術座談会から(平成23年9月30日)
血清中IgEが正常ないし、正常より低く、特異的IgEが認められないアトピー性皮膚炎を内因性(intrinsic)タイプと呼ぶ考えがある。アトピー性皮膚炎の20%がこれにあたり、女性に多い(70~80%)。外因性のタイプとの臨床的な違いはないが、発症年齢が比較的遅いこと、症状が軽度であることのほかに、下眼瞼に見られるしわ(Demie-Morgan fold)が有意に高いことが特徴である。
Demie-Morgan foldは眼瞼の浮腫が原因と考えられているようだが、これと血清中IgEが高くないこととの関連が、よくわからない。女性に多いことが統計的な差異に結びついているのではないか。化粧やクレンジングが関与していそうである。
-
第75回日本皮膚科学会東部支部総会から(平成23年9月18日)
心房細動を基礎疾患とする高齢男性患者に生じた足趾の紫斑と潰瘍。皮膚生検ではコレステロール結晶の塞栓はなし。足趾アンプタ後の潰瘍が遷延した。血中ホモシステインが14.8nmol/ml(正常は3.7~13.5)とやや上昇。血中ビタミンB6が2.7mg/ml(正常は6~40)と低下。ビタミンB6を60mg/日投与し、7.2まで改善、断端部潰瘍も速やかに治癒した。
高ホモシステイン血症は以前からPADのrisk factorとして認識しているが、どういう症例でそれを疑うかがわからなかったので参考になった。ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸はホモシスチンがメチオニンに代謝される際に必要なビタミンで、これらの内服により血液中ホモシスチン濃度が低下することが知られている。
-
第75回日本皮膚科学会東部支部総会から(平成23年9月18日)
足背に生じた紫紅色結節。生検では好塩基性の菌塊の周囲を好酸球性の無構造物質が取り囲む、Splendore-Hoppi現象を認めた。組織の細菌培養で黄色ブドウ球菌が陽性。ボトリオミコーシスと診断した。皮膚のSplendore-Hoppi現象はスポロトリコーシス、マラセチア毛包炎、アスペルギルス症などの真菌感染症、ボトリオミコーシス、ノカルジアなどの細菌感染、鉤虫による幼虫移行症などの寄生虫症のほか、感染症以外では好酸球増多症でも見られることがある。
血管の疾患に解剖学はやはり大事だ。少し詳しく調べる必要がある。後脛骨動脈の分枝部の把握も必要で、血行の評価と治療法の選択に役に立ちそうである。
-
第40回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成23年9月1日)
体表は個々の部位の栄養を供給する動脈の分布から、約40のブロックに分けられ、それぞれをangiosomeと呼ぶ。もともとは形成外科領域で、皮弁形成のデザインのために考えられたconceptであるが、下肢の虚血性潰瘍の診断・治癒においても重要である。足には6つのangiosomeがあり、(1)前脛骨動脈→足背動脈(前脛骨angiosome:足の上半分)、(2)後脛骨動脈→内側足底動脈(内側足底angiosome)(3)後脛骨動脈→外側足底動脈(外側足底angiosome)、(4)後脛骨動脈→踵部分枝(踵部angiosome)、(5)腓骨動脈(腓骨angiosome:足関節外側前部)、(6)腓骨動脈の踵部分枝(踵骨分枝angiosome:踵からアキレス腱にかけて)に分けられる。血管内治療の方法、バイパス手術の適応を考える上で重要である。
血管の疾患に解剖学はやはり大事だ。少し詳しく調べる必要がある。後脛骨動脈の分枝部の把握も必要で、血行の評価と治療法の選択に役に立ちそうである。
-
第40回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成23年9月1日)
温熱刺激後に一過性の顔面片側の潮紅をきたす小児例。同側の発汗発作と反対側の分節型無汗症を伴う。潮紅と反対の第2・3胸部交感神経の異常と考えられるが、基礎疾患はなし。温熱、運動後の潮紅が顔面正中できれいに分かれるため、道化師の化粧を思わせることからHarlequin症候群と呼ばれている。自然治癒はなし。症候性のHarleqiun症候群は脊髄腫瘍、肺癌、神経線維腫症、シェーグレン症候群などが原因となる。
これまでに経験はないが、片側性の単純性血管腫と考えてしまいそうな臨床であった。幼児の場合は温度や情動による変動があることの確認が必要だ。
-
某製薬会社主催講演会から(平成23年8月28日)
アトピー性皮膚炎の外用治療の話。ステロイド軟膏の外用で改善したあとに保湿剤に変更する方法が一般的。しかし一見正常に見えても、わずかに炎症がくすぶっている状態では、保湿剤に変更すると皮膚炎が再燃するので、炎症のある部分からしか吸収されないプロトピック軟膏を、躯幹、四肢に対してもしばらく継続し、そのあと保湿剤に変更するのがよい。さらに、難治性病変である紅皮症と結節性痒疹に対しては、あえてデルモベート軟膏を外用し、表皮が萎縮した状態になってからプロトピック軟膏(10g/日を超えないように注意)に変更すると吸収がよくなり改善する。
個人的にもそうだが、プロトピック軟膏は、顔面、ないし頚部などの間擦部専用の外用薬としか使っていないのが現状である。躯幹・四肢の広い範囲に処方するには、5gチューブでは使づらい。30g、50gの容器にわざわざしぼって渡すと、患者は使いやすくなるそうだ。当院でも採用してみよう。
-
第13回日本褥瘡学会から(平成23年8月27日)
絆創膏の粘着剤の化学。ゴム系、アクリル系、アクリルゲル系、シリコン系があり、それぞれ長所と短所がある。また、粘着剤のテープ(指示体)への塗り方には、面状と球状があり、球状の粘着剤は柔らかいため、上から圧を加えると面状となり、引き上げると縦に伸びて点ではがれるため、皮膚へのダメージが少ない。
絆創膏にも色々あるわけだが、結局今でも20年前と同じ製品を使っている。シリコン系粘着剤を球状に塗ったテープが新規に開発されたとのこと。そもそも、絆創膏の新製品の情報が入ってくることも少ないし、評価を聞いたこともないので、たまには話題にするとよいだろう。
-
平成23年度日臨皮中国ブロック学術講演会から(平成23年7月31日)
足白癬に対する抗真菌剤内服治療のレジメン。イトラコナゾールでは、100mgを連日、4週から12週継続、ないし、200mgパルスを1週間+3週間休薬を3~4回、ないし、400mgパルスを1週間1回。テルビナフィンでは125mg連日を爪白癬同様6カ月まで、ないし250mgパルスを1週間+3週間休薬を3~4回。
爪白癬は治療が確立していて取り組みやすいが、足白癬の湿潤性病変や慢性の角化性病変での使い方が今ひとつピンと来なかったので、参考になった。これまでより積極的に導入してみよう。
-
第35回日本小児皮膚科学会から(平成23年7月23日)
砂かぶれ様皮膚炎の鑑別診断の文献的検索からたどり着いた、松本市の小児科医からの報告。1998年までに数回の流行を経験した。発症は6月と7月がピークで、単峰性ないし二峰性の発熱の解熱後数日で生じることの多い発疹症で、2歳児の罹患が最多で、4歳以下が80%以上を占める。発疹は顔面とくに両側頬部の紅斑性丘疹を特徴とし、四肢の中枢側や臀部にも紅斑が生じる。顔面の紅斑性丘疹は1~2週間ほど発疹が残存する。咳嗽や鼻汁などの感冒様症状は少ない。ウイルス分離の結果、エコーウイルス30型、18型、7型の検出頻度が高かった。
記載によれば、Gianotti症候群、砂かぶれ様皮膚炎とも若干異なる皮膚症状である。エコーウイルスが分離されることが多いとのことで、興味深い。これまで認識していなかったので、見逃しているかも知れない。1999年の報告以降、文献は見あたらないが、その後の動向も知りたいところだ。
-
第35回日本小児皮膚科学会から(平成23年7月23日)
けいれん発作のために入院した新生児。パルスオキシメーターを10日間足趾に装着していたところ、deep dermalの熱傷を生じた。国際規格では41℃以下に温度を維持するように定まっているが、局所的に圧がかかると、41℃以下の熱でも熱傷の原因になるので、注意が必要。
医療過誤といわれてしまうと対応が大変である。些細な医療行為だが、いずれにしてもこまめなチェックが必要ということだろう。
-
第35回日本小児皮膚科学会から(平成23年7月23日)
生後3週の男児とその母の症例。男児は四肢に小水疱、母は両下腿伸側に痒疹結節。両者ともCOL7A1に同一の変異を認めた。母の足趾の爪に萎縮がある。比較的高齢で初めて皮膚症状が明らかになることもあり、両下腿伸側の難治性の痒疹では、痒疹型栄養障害型表皮水疱症も念頭に置く必要がある。
下腿の痒疹から診断がつくというのはなかなかである。成人例では爪の萎縮が決めてとなるようだ。頭の片隅に止めておこう。
-
第35回日本小児皮膚科学会から(平成23年7月23日)
マイコプラズマ感染症は小児の市中肺炎の起因菌として重要で、全体の20%、6歳以上では40%以上を占める。エリスロシンが第一選択の治療薬だった時代は、体内動態の関連から4年に一度の流行が見られたが、クラリス登場後にはその傾向はなくなった。ただし、マクロライド耐性菌が増加し、全体の20~40%に達している。小児呼吸器感染症診療ガイドライン2011では、市中肺炎の治療開始後48時間以内に解熱しないなど、マクロライド耐性株の関与が疑われる場合には、オゼックスないしミノマイシン(原則8歳以上)が推奨されている。
なぜ敬遠されてきたのか、覚えていないが、キノロン系抗菌剤の小児への適応が認められたとは知らなかった。かつては多形滲出性紅斑や手足口病に類似した掌蹠の小水疱で、マイコプラズマ感染症が原因だった症例を時に経験したが、最近、サッパリ見なくなったのはどうしてだろう。
-
第41回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成24年7月16日)
乾癬の免疫学的異常のひとつが、Th17/Tregの不均衡である。乾癬患者の末梢血中のTh17細胞、Treg細胞をフローサイトメトリーを用いて、光線療法(PUVAバスないしナローバンドUVB)の前後で比較した。Th17/CD4比が正常コントロールよりも有意に高い症例(11例/59例)では、治療前が6.1±2.2%であったものが、治療後は2.9±3.0%と低下した。また、Treg/CD4比は3.5±1.4%から4.5±2.2%と増加した。光線療法がTh17/Tregの不均衡を是正することが示された。
全身への照射が乾癬、アトピー性皮膚炎、円形脱毛症に有効な理由として、理解できる。エキシマライトなどの局所的な光線照射でも、同様の不均衡是正が局所的に行われていると言うことか。
-
第41回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成24年7月16日)
乾癬の免疫学的異常のひとつが、Th17/Tregの不均衡である。乾癬患者の末梢血中のTh17細胞、Treg細胞をフローサイトメトリーを用いて、光線療法(PUVAバスないしナローバンドUVB)の前後で比較した。Th17/CD4比が正常コントロールよりも有意に高い症例(11例/59例)では、治療前が6.1±2.2%であったものが、治療後は2.9±3.0%と低下した。また、Treg/CD4比は3.5±1.4%から4.5±2.2%と増加した。光線療法がTh17/Tregの不均衡を是正することが示された。
全身への照射が乾癬、アトピー性皮膚炎、円形脱毛症に有効な理由として、理解できる。エキシマライトなどの局所的な光線照射でも、同様の不均衡是正が局所的に行われていると言うことか。
-
第41回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成24年7月16日)
血清中アミロイドA(SAA)は感染症、炎症性疾患、組織破壊性疾患などで上昇する非特異的炎症性マーカーだが、樹状細胞を活性化して、T細胞のTh17細胞への分化に関与することが報告された。尋常性乾癬では皮膚局所にTh17細胞が浸潤し、IL-17、22を産生して表皮の増殖を生じると考えられている。尋常性乾癬患者血清中、皮膚組織中のSAAはいずれも高く、SAAがTh17細胞を介して、乾癬の病変維持に関与している可能性がある。
SAAが持続的に高い他の疾患、たとえばRAの患者の皮膚組織にも、Th17細胞が多いのだろうか。RAに尋常性乾癬や角層下膿疱症の併発は少なくないように思う。関節症性乾癬や二次性アミロイドーシスとの関係も知りたいところだ。
-
第837回日本皮膚科学会東京地方会から(平成23年7月9日)
妊娠を契機に発症した下肢深部静脈血栓に対して、ヘパリンカルシウムの在宅自己注射を行っている患者。注射のあと2-3日後に、注射部位に紅斑が出現して、小水疱を伴った。パッチテストは陰性、皮内注射、皮下注射で48時間後、72時間後で陽性。スクラッチパッチテストで、96時間後に陽性。遅延型反応(DTH)と考えられた。静注では症状の出現はない。平成24年1月から、習慣性流産などで自己注射が認められるようになり、今後、特に妊婦での症例が増加することが危惧される。
低分子ヘパリンは近年開発が進み、クレキサン、アリクストラなどが発売されているが、海外ではこれらもDTHを生じることが報告されている。低分子にすると抗原性が増すというのは、加水分解コムギでの事例と同様か?
-
第837回日本皮膚科学会東京地方会から(平成23年7月9日)
好酸球増加症候群(HES)は、骨髄での好酸球増殖亢進による持続性の好酸球増多症で、しばしば臓器浸潤をきたし、半数に皮膚症状が見られる。症例は大腿に水疱性類天疱瘡に類似した緊満性水疱を生じた高齢者で、抗BP180抗体は陰性。HESの一部には、特異的な遺伝子異常(FIP1L1-αPDGFR融合遺伝子)があり、血小板由来成長因子受容体(PDGFR)チロシンキナーゼの恒常的活性化が原因で好酸球のクローン性増殖をきたすことが証明され、FIP1L1-αPDGFR陽性HESは慢性好酸球性白血病に分類された。治療としてはチロシンキナーゼ阻害剤であるグリベックが有効。症例の水疱もグリベックで消褪した。
平成24年2月から、グリベックが保険適応拡大の承認を得た。これまではステロイドにも抵抗性で、心筋障害による心不全で予後も不良だったが、治療の選択肢が増えたことは喜ばしいことである。
-
第136回神奈川県皮膚科医会例会から(平成23年7月3日)
トリメタジオン(ミノアレ散)、ワーファリン、エトレチナート、ビタミンA、コルヒチン、メトトレキサート、ミソプロストール(サイトテック)、抗ガン剤、ACE阻害剤は胎児毒性がある。経口血糖降下剤、麦角アルカロイド(エルゴタミン)、妊娠後期のNSAIDsも使用不可。
ミソプロストールは南米では非合法の妊娠中絶に使われているらしい。最近、食物アレルギーの治療に使われると聞くが、注意しなければならない。
-
第136回神奈川県皮膚科医会例会から(平成23年7月3日)
妊娠中期ないし後期に生じる病態で、主症状は、発疹を伴わないかゆみである。頻度は全妊娠の0.2%ほどで、原因は胆汁分泌におけるestrogen、progesteronの相互作用に関わる遺伝的な要因と、環境的な要因が考えられている。消化器症状はなく、肝不全に至ることもなく、分娩とともに消失する。検査上、血清中胆汁酸の増加と肝酵素の上昇がみられる。胎児仮死、早産などの合併症がまれではないので、注意が必要で、ウルソの内服が治療として用いられる。
かゆみを訴える妊婦さんは時に経験するが、こう診断したことはない。かゆみぐらいは我慢しなさいでは、すまないと知った。検査上の指標はビリルビンではなく、胆汁酸であるが、これまで測ったことがない。
-
第10回皮膚科EBMフォーラムから(平成23年7月2日)
胸腺髄質上皮細胞に発現するAIRE(autoimmune regulatory nuclear dot protein)をコードする遺伝子の変異で生じる常染色体劣性遺伝の疾患。AIREは自己抗原を胸腺髄質細胞に発現させる転写因子として働いていると考えられていて、その変異により自己抗原が胸腺で発現しないと適切なネガティブセレクションが起こらなくなり、自己抗原に強く反応するT細胞が成熟して末梢に流出し、多彩な自己免疫疾患を呈することになる。APECEDとはautoimmune polyendocrinpathy-candidiasis-ectodermal dystrophyの略で、アジソン病、副甲状腺機能低下症による低Ca血症、膵ラ島障害による1型糖尿病のほか、真菌感染防御に必要なIL-17などに対する自己抗体が産生されるため、慢性の皮膚粘膜カンジダ症が発生する。そのほかの皮膚症状として、爪形成不全、脱毛、白斑などを認める。
自己免疫疾患の病態に直接関わる遺伝子(分子)が同定されたのは、AIREが初めてであるとのこと。自己・非自己の識別機構は奧が深い。
-
横浜市皮膚科医会学術講演会から(平成23年6月23日)
尋常性疣贅で、液体窒素凍結が難しい症例には、以前からグルタールアルデヒドの外用が用いられる。表皮に浸透させ、硬くなったところをはがす、という方法であるが、時に、外用した疣贅の周囲が赤くなり、接触皮膚炎をきたした後に、疣贅の消失をみることがある。DNCBやSADBEと同様の接触免疫による機序があるかも知れない。
同様の経験がある。ただし全ての症例ではないと思う。医療従事者は、消毒剤として触れる機会があるので、用いない方がよいとのことである。
-
横浜市皮膚科医会学術講演会から(平成23年6月23日)
難治性の疣贅に、最後の手段的に0.5mg~1.0mg/kg/日のチガソン内服を用いて、有効だった。効果は2~3週で現れる。特に、鼻の中の疣贅に有効。ただし、0.3mg/kgを下回ると再燃する例もある。
鼻の中は呼吸が不自由という訴えもあり、液体窒素の綿棒も届かず、いい治療がなくて困っていた。高齢者では使えそうだ。
-
墨東病院カンファレンスから(平成23年6月9日)
生後3週間ではっきりしてきた両肩・大腿に生じたボコボコとした硬結を伴う萎縮性病変。難産でApgar scoreは6点。産道通過時の圧迫によって生じた、新生児皮下脂肪壊死症と診断した。組織では脂肪織のherniationがあり、皮下脂肪織の葉間結合織に接する脂肪細胞は変性し、中央に向かう様な配列の針状結晶を伴っていた。貪食する組織球が少ないのが特徴。
数10年ぶりにみた典型例であった。組織では、葉間結合織のすぐ隣の脂肪細胞に変性があり、一過性の血行障害が原因とするのが妥当と思われる。
-
第27回日本臨床皮膚科医会総会から(平成23年6月12日)
混合することにより、pHに変化が生じ、ステロイド含量が低下する組合せがあるので注意が必要。亜鉛華軟膏とは、グリメサゾン軟膏、ダイアコート軟膏、メサデルム軟膏、ロコイド軟膏、ロコイドクリームがダメ。亜鉛華単軟膏には、ジフラール軟膏、ネリゾナ軟膏、フルコート軟膏、ボアラ軟膏、マイザー軟膏、ロコイド軟膏、ロコイドクリームが合わない。
覚えられないので記載しておく。なかなか繊細である。
-
第27回日本臨床皮膚科医会総会から(平成23年6月12日)
宮崎県高千穂町の谷間の集落、土呂久(とろく)で、1920年から1962年にかけて、硫砒鉄鉱を焼いて猛毒の亜砒酸を製造する鉱山が操業し、大気、水、土壌が砒素によって汚染され、鉱山労働者や周辺の住民に慢性砒素中毒症が生じた。環境省は1973年、これを公害病に指定した。皮膚症状は多発性のボウエン病、掌蹠の角化症、色素沈着であった。その後被害者は、鉱山会社に健康被害の償いを求める裁判を起こし、1990年にようやく最高裁で和解した。世界中にはまだ、土壌や水が砒素に汚染されている地域がたくさんあって、健康被害に苦しむ人は数万人にのぼる。
恥ずかしながら、土呂久の名前は知らなかった。茨城県神栖市でも砒素の土壌汚染があり、今年になって和解が成立したと聞く。皮膚科医として、記憶に止めておかなければならない。立派なWEB musium(http://toroku-museum.com/)があるので、参考にしていただきたい。
-
第27回日本臨床皮膚科医会総会から(平成23年6月12日)
耳たぶに生じる、前方から斜め下に走る深いシワ(Diagonal earlobe creases)が、心血管病変のリスクであるという話。1989年のBritsh Heart Journalで報告された。303人(男性171人、女性132人)の剖検例を調査した。死亡年齢の平均は72歳。斜めの深いしわは男性で123人(72%)、女性で88人(67%)、合計で211人(70%)であった。冠血管病変の既往を有する人は、全体では90人(30%)であったが、しわがある人では74人(35%)だった。心血管疾患での死亡は、しわがある人の154人/211人(73%)、しわがない人では41人/92人(45%)で、危険率は男で1.55倍、女で1.74倍だったとのこと。
2006年にも520の剖検例で、同様の結果が示されている。ただの都市伝説ではないようである。光老化のサインとしか思えないが、どんな機序で発症するのか。自分の耳に出てくると困るが、今後は注意して見ておこう。
-
第27回日本臨床皮膚科医会総会から(平成23年6月11日)
Nd:YAGレーザー(波長1,064nm)は、深達度が深く、下肢の静脈や毛細血管拡張の治療に使用されるが、爪白癬に対しても効果が見られた。キュテラ社のGenesisを用いて、5mmスポットサイズ、0.3msec、14J/cm2、5Hzの設定で、罹患した爪甲とその周囲に100ショットの中空照射(1~2㎝浮かせて打つ方法)を施行。わずかに熱を感じる程度で疼痛はない。これを1カ月間隔で3回繰り返し、半年後には、11例中7名(33本中22本)で明らかな改善を認めた。Nd:YAGレーザーの熱が肥厚した爪甲に浸透し、白癬菌を叩くらしい。
これは予想外の展開である。欧米ではすでに行われているようだ。当院にも用意があるので、いずれやってみよう。
-
横浜市皮膚科医会学術講演会から(平成23年6月23日)
アトピー性皮膚炎(AD)の皮疹局所では、掻破に伴う出血がみられ、血小板が活性化していることが推測される。血小板は、さまざまなケモカイン、成長因子、炎症メディエータなどを豊富に含んでおり、止血や血栓形成だけでなく炎症反応にも重要な役割を有している。アトピー性皮膚炎患者では、血小板が凝集した時に放出されるセロトニンの血漿中濃度が高く、皮膚炎の重症度と相関しており、また、治療による皮膚炎の改善に伴って減少する。ADモデルマウスでも血小板を減少させると、炎症が減弱し、血小板の再投与によって炎症は回復する。また、抗血小板薬であるアスピリンやプラビックスをマウスに内服させると、IgEの遅発相が減弱することがわかった。
掻破の激しいAD患者では、血小板の凝集能が高まり、血栓を作りやすいということか。最近は中高齢者にもADは稀ではないし、皮脂欠乏性皮膚炎など掻き壊しだらけの高齢者も多い。掻破の程度-血小板機能-心・血管イベントの関連について、検証が必要かも知れない。
-
22nd World Congress of Dermatologyから(平成23年5月26日)
山本達雄先生が本邦初で報告した疾患についての報告が韓国からあり、hyperkeratotic lichenified skin lesion in the guluteal regionという病名で報告された。擦れによる高齢者の臀部の病変で、タタミが原因ではないかと考えている。ステロイド軟膏外用ではあまり有効でなく、チガソンのlow dose(10mg/日)が有効で、2~3週間の内服で軽快するとのこと。
これを主訴に来院する患者は決して少なくない。座位の際にふんぞり返らないように指導して、活性型ビタミンD3の外用を処方することが多いが、なかなか改善しなくて困る。チガソンは試したことがないが、使用経験のある先生はいるだろうか。有効性を尋ねたいところだ。
-
22nd World Congress of Dermatologyから(平成23年5月26日)
局所注射による皮膚障害の集計。異物肉芽腫、皮膚萎縮、脂肪織炎、非結核性抗酸菌症などに加え、Nicolau症候群と呼ばれる病態がある。主としてに筋肉注射後に生じる皮膚、皮下組織、筋肉の非感染性壊死とされ、注射局所に痛み、発赤、腫脹、リベド、硬結を生じ、最終的には壊死に陥ることもある。早期の診断が重要で、ステロイドやヘパリンの局注が必要である。原因薬としては、INF-α、エタネルセプトなどの生物学的製剤や酢酸リュウプロレリンが知られている。病因として、血管の炎症、閉塞、交感神経性血管攣縮、結晶析出など様々な要因が考えられている。
聞き慣れない病名だが、歴史は古く、1920年代に最初の報告があったそうだ。局所注射による皮膚障害をこの名称でまとめておくことは、病態解明のために有用かも知れない。
-
22nd World Congress of Dermatologyから(平成23年5月26日)
Canadaの皮膚科医の講演。新しく記載された薬疹として、太藤の丘疹紅皮症をpapulo-erythroderma of Ofuji(PEO)と紹介していた。皺壁を避けるように体幹に分布する苔癬化局面についても"deck-chair"signと称していた。内臓悪性腫瘍のデルマドローム、T細胞性リンパ腫としての側面の他に、薬剤が誘因の症例がある。
日本人の名前の付く診断名が国際的に認識されているというのは誇らしい。PEOという略称も初めて知った。臨床例を英文で紹介することもやはり大事なことだと思った。
-
第23回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成23年5月14日)
Aicardi-Goutieres(エカルディ-グティエール)症候群(AGS)はTREX1の遺伝子変異が原因で生じる常染色体劣性、まれに優性遺伝を呈する疾患で、寒冷刺激による発熱、繰り返す凍瘡、1歳未満で発症する脳症を特徴とし、検査上、基底核の石灰化、髄液中IFN-α上昇が見られる。軽症例も報告されており、難治性の凍瘡では考えておく必要がある。
神経症状を欠く、familial chilblain lupusという病名もあるらしい。今冬は患者が多かったが、家族歴についてはほとんど意識しなかった。見逃してはいないと思うが、一応念頭に置いておこう。
-
第23回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成23年5月14日)
IL-33はIL-1ファミリーに属するサイトカインで、上皮細胞や血管内皮細胞で産生される前駆体からcaspase-1で活性型に変換される。IL-33はTh2細胞を刺激してTh2サイトカイン産生を誘導する。以前から花粉症や気管支喘息患者で血清中のIL-33が高値であることが知られていたが、成人型アトピー性皮膚炎でも健常者に比べて有意に上昇しており、その値はSCORADによる重症度と相関していた。しかし血清IgE値、LDH、末梢血中好酸球数とは相関していなかった。治療による皮疹軽快後には減少していたことから、IL-33はアトピー性皮膚炎の病態と関連していること、重症度のマーカーになることが示唆された。
カテキン類は、茶葉中に11%~17%含まれており、その半分はエピガロカテキンガレート(EGCg)らしい。カテキンといえば抗アレルギー作用があると言われているが、アレルゲンにもなるということだ。
つい最近、花粉症の主要原因物質として話題になった。鼻粘膜上皮で産生され、鼻汁中にも多く含まれる。アトピー性皮膚炎の上皮中にも多いということであれば、汗の中にも多いかもしれない。汗で悪化する症例の、汗中の濃度がどうか知りたいところだ。
-
第23回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成23年5月14日)
果実とトマトによるOASで発症、のちにトマトでアナフィラキシーを発症。その後紅茶で消化器症状、頚部閉塞感。さらに緑茶、ウーロン茶でも同様の症状をきたすようになる。カテキン特にエピガロカテキンガレートによる食物アレルギーと考えた。
カテキン類は、茶葉中に11%~17%含まれており、その半分はエピガロカテキンガレート(EGCg)らしい。カテキンといえば抗アレルギー作用があると言われているが、アレルゲンにもなるということだ。
-
第23回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成23年5月14日)
食物アレルギー児に耐性獲得を目的として経皮免疫療法(EIT)を試みた。対象は2歳から10歳までの食物アレルギー児6名(鶏卵1名、牛乳3名、小麦2名)で、4名にはアナフィラキシー歴があった。鶏卵、牛乳、小麦をそれぞれ蛋白量として1mg/回を48時間ずつ週3回貼付した。貼付により皮膚反応を呈する場合には0.1mgまたは0.01mgと希釈して実施した。開始後8週以降に経口負荷試験を行い効果を判定したところ、4名(鶏卵1名、牛乳3名)では治療後の負荷試験で閾値が上昇した。経過中の全身症状はなく、経口免疫療法(OIT)に比して安全性の高い治療法の一つになりうると考えられた。
経皮的なアレルゲン負荷で耐性が誘導できるということになると、感作が経皮で起こり、経口でtoleransが誘導されるという、最近の流れに反するような気もする。さらにごちゃごちゃしてきた。
-
第23回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成23年5月14日)
conservativeな立場からのOITに対する課題のまとめ。1.安全性:急速法、緩徐法ともにアレルゲン負荷の増量中ないし維持期に誘発症状が認められ、有害事象発生率は高く、患者に覚悟や決意を促すほどで、現時点では医療に求められる安全性の基準を超えた挑戦といえる。2.有効性の限界:アレルゲン負荷を目標値までに増量できない症例が少なからず存在し、患者はその間も誘発症状を繰り返す。増量期だけでなく維持期にも負荷を少なくする必要があるため、増量法の改良では克服できない。3.明らかではないメカニズム:初期の一過性脱感作から真の耐性獲得にいたるメカニズムが不明で、自然経過による耐性獲得とOITによる維持療法到達に違いがあるか、検証されていない。4.社会的混乱:誘発症状が生じないレベルで可能な限り摂取させるという従来の食事指導との区別が不明瞭で、安全のために除去食指導を行う医師を非難する風潮になりつつある。
ピーナッツアレルギーのOITは現時点では時期尚早という論文(J ALLERGY CLIN IMMUNOL 126: 31-32, 2010.)があり、冒頭にヒポクラテスの言葉、「to do good or to do no harm」を引用している。このような考え方も大切だと思う。
-
神奈川県感染性皮膚疾患講演会から(平成23年3月12日)
HPVは表皮幹細胞に出会うとそこに侵入し、増殖させて疣贅を作る。治療後に、もとの疣贅の辺縁からドーナッツ型に再発することがあり、これをドーナッツ疣贅と呼ぶ。液体窒素で治療を行うと、局所的に一過性の免疫不全に陥るので、さらに潜伏しやすい。液体窒素の功罪の一つと考えられるが、これは汗管などに潜んだHPVが原因と考えられる。辺縁から数mm外側まではがすように液体窒素は当てないといけない。
ドーナッツ型の再発は時に経験する。液体窒素で疣贅より大きな血疱を作った場合、その大きさで再発してしまう例もある。また、爪囲の疣贅にに液体窒素を当てると、弓状の爪甲白斑を作ってしまうことがある。液体窒素の最も正解に近い施行方法は、何なのだろう。
-
神奈川県皮膚科医会第135回例会から(平成23年3月6日)
脂漏性皮膚炎からのマラセチア胞子の検出は、なかなか難しいが、染色に酸性メチレンブルーを用いると、比較的容易である。検体の採取は両面テープがよい。脂漏性皮膚炎では、癜風と異なり、小さく楕円形のものがほとんどである。
酸性メチレンブルーの方がズームブルーより染色されるのが早いと言うが、角質を溶かす必要がある場合には使えないようだ。もとは赤痢アメーバの染色に使われていたとのこと。サンプルをいただいたので、試してみよう。金魚の皮膚にカビが生える白点病の治療薬として、金魚屋にも置いてあるらしい。
-
横浜アレルギー治療講演会から(平成23年2月24日)
スギ花粉抗原で経皮的に感作させたスギ花粉皮膚炎マウスモデルを作成した。病変部皮膚には好酸球、肥満細胞が浸潤し、スギ特異的IgEの産生を伴っていた。肥満細胞欠損マウスでは皮膚炎は生じず、反応には肥満細胞が不可欠であった。しかし、この反応は、IgEを介するアレルギー性炎症と関わりの深い、STAT6の欠損マウスでは抑制されず、逆にプロスタグランディンD2(PGD2)のレセプターであるCRTH2欠損マウスで減弱がみとめられた。CRTH2はTh2細胞に特有な膜蛋白のクローニングから発見された膜蛋白で、Th2細胞以外にも、好塩基球、好酸球に発現している。抗原で刺激した肥満細胞がPGD2を発現すると、それに呼応してTh2細胞や好酸球の遊走性が亢進することが知られている。
意外だったが、アトピー性皮膚炎で想像されているIgEを介する免疫反応とは、発症機序が異なるということである。CRTH2に対する拮抗作用が確認されているramatroban(バイナス)が、このマウスモデルで細胞浸潤を抑制することも検証された。実際、スギ花粉皮膚炎の予防に有効か、確かめてみる必要がありそうだ。
-
第74回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成23年2月12日)
易感染性宿主の側腹部に生じた皮下膿瘍。切開すると乳白色の漿液の排出があった。細菌培養は陰性で、PDA、SDAでともにケタマカビ(Chaetomium属)が検出された。毛玉のような、ウニ状の子嚢殻が特徴で、穀類やナッツ類に付着する真菌であり、人体への感染は稀である。
初めて聞いた感染症だった。易感染性宿主の皮下膿瘍は、やはりただものではない。細菌と同時に、真菌や抗酸菌などの培養が重要だといつも思う。
-
第74回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成23年2月12日)
40代から顔面のcutis laxaによる、sad face appearanceと軽微な外傷による溢血斑と表皮剥離、発汗障害。家族歴あり。嚥下障害、発声障害、眼輪筋の脱力。生検では表皮基底層にアミロイドの沈着を認め、抗ゲルソリン抗体で陽性。角膜格子状変性があり、gelsolin遺伝子に変異を確認。遺伝性ゲルソリンアミロイドーシスと診断した。ゲルソリンはアクチンの機能を調節する(切断・重合阻止・重合核形成促進)蛋白で、家族性アミロイドポリニューロパチー(FAP)IV型の原因前駆物質である。常染色体優性遺伝で、浸透率は100%といわれている。
顔面のcutis laxaの鑑別として、覚えておこう。こういう症例を思い出し、スパッと診断して、神経内科医を驚かせたいものだ。
-
第74回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成23年2月12日)
幼少時から四肢の潮紅と腫脹が下垂時、起立時に生じ、熱感を伴う。挙上により速やかに消褪。gravitational erythemaと診断した。通常、血管の器質的な異常はないと言われているが、この症例では血管エコーで下肢静脈に脈波がみられ、サーモグラフィーでは上下肢とも末梢側の方が中枢側より温度が高かった。外踝に潰瘍の瘢痕もあり、微小血管での先天的な動静脈シャントが原因と考えられた。
動静脈シャントが原因であるとした結論に同意したい。足背や内踝・外踝の難治性潰瘍はそのサインであると認識している。一歩進んで、血管型のEhler-Danlos症候群の可能性はどうだろうか。
-
第74回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成23年2月12日)
白癬の臨床症状は白癬菌に対するT細胞や表皮角化細胞を介した免疫応答を反映している。すなわち白癬菌特異的T細胞がIFN-γを産生し、遅延型過敏反応を引き起こすとで、中心治癒傾向のある環状の病変を形成する。反対に白癬菌はそれらの免疫応答を回避する仕組みを有している。細胞壁の構成成分であるマンナンは、リンパ球の増殖抑制、角質増殖の抑制、マクロファージ貪食能の抑制の効果がin vitroで確かめられている。
マンナンというとコンニャクを想像してしまう。真菌の細胞壁にあって、免疫学的に重要な働きをしているとは知らなかった。
-
第74回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成23年2月12日)
高齢者に見られる皮膚の脆弱性、機能不全を皮膚粗鬆症(dermatoporosis)と称することが提唱されている。脆弱性の形態的特徴としては老人性紫斑、星芒状偽瘢痕、皮膚萎縮があり、機能不全としては軽微な外傷による皮膚剥離、創傷治癒遷延、皮下深部の血腫(deep dissecting hematoma)がある。高齢者女性の下腿に好発し、大きな血腫になると、内部からの圧迫のため皮膚壊死をきたし、難治性潰瘍を形成することになるので、切開して血腫を除去する必要がある。
長期のステロイド内服、動脈閉塞性疾患に対する抗凝固療法が基盤にあることが多い。在宅でワーファリン内服患者が、転倒してこの状況になり、植皮に至った症例を経験したことがある。dissectingとは、解離性と訳せばよいのだろうか。在宅での皮膚科的救急疾患として考えておく必要があると思う。
-
第74回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成23年2月12日)
慢性の手湿疹の治療に、alitretinoinの内服を試みていて、よい結果が得られている。alitretinoinは薬理学的にレチノイン酸受容体(RAR)のみでなくレチノイドX受容体(RXR)にも拮抗する。1,032人を30mg、10mg、placeboの3群に分け、12から24週の1日1回の内服を行い比較した。結果は、90%以上改善が、それぞれ48%、26%、17%であり、有効性が示された。副作用は頭痛、コレステロールと中性脂肪の上昇がみられ、また、口唇をはじめとする皮膚の乾燥も生じるが、etretinateに比較すると少なかった。催奇形性についてはetretinateと同様だが、半減期が1.3~2.3時間と短いことから、治療中断後の避妊は1カ月間でよいらしい。
今回のalitretinoinは、9-cis retinoic acidで、isotretinoinが、13-cis。etretinate(チガソン)はall-trans、白血病のベサノイドもall-trans。ニキビのadapaleneは合成レチノイドで、時々海外で話題になるtazaroteneがRARα、γ選択性が特徴と、同じようで違うのが難しい。手荒れなので外用ではどうかと思ったが、alitretinoin gel(Panretin)0.1%というのがすでにあり、Kaposi肉腫に対する外用治療薬としてFDAに認可されている。さらに、RXR選択性が特徴のTargretinはCTCLの内服、外用治療薬で、この領域のdrug lagはなかなかのものである。
-
皮膚病診療編集会議から(平成23年1月20日)
三橋善比古先生がLancetに報告した、項部のsalmon patchの頻度についての統計。10年間にわたり、各年代をあわせて計5,054人を観察した結果、1歳では82%にみられたが、9歳では4.5%に減少した。その後、思春期から20歳にかけて頻度が上昇し、20歳では31%に見られるようになる。その後も各世代で26%から39%の有病率となる。salmon patchは10歳で一旦消褪、性ホルモンの影響か、思春期以降に再発するようだ。
成人の有病率が30%というのは気づかなかった。記載を長期間にわたり継続し、残すだけでも大変な労力だっただろう。なかなか真似のできない調査である。
-
群馬アレルギー疾患カンファレンスから(平成23年1月13日)
中耳貯留液に多数の好酸球が存在する滲出性中耳炎および慢性中耳炎で、30~60代の女性に多く、難聴のリスクが高く、発症初期において、滲出性中耳炎と病態が類似しており診断基準が策定された。中耳貯留液に好酸球が存在することと、、(1)にかわ状の中耳貯留液、(2)ステロイド投与以外の治療に抵抗性、(3)気管支喘息の合併、(4)鼻茸の合併の4つの項目のうち、2つ以上を満たすものを確実例とした。気管支喘息の合併率は90%で、そのうち30%がアスピリン喘息であった。好酸球性副鼻腔炎の合併は75%で、62%に鼻茸が観察された。成人発症の喘息患者の1割に合併するという。
皮膚科にも病態として近い疾患があるのではないかと思う。一応、名称ぐらいは覚えておこう。
-
第6回筑駒医師会講演会から(平成22年12月29日)
流血中を流れる、無細胞性DNAがある。妊娠中の母体では、血中DNAの11.4%が胎児由来である。近年のゲノムサイエンスでは、血液中の壊れたDNAの配列を決定することが可能となり、採血のみでダウン症候群などの遺伝子異常の出生前診断ができるようになった。
DNAそのものが血中を流れているとは思わなかった。遺伝子のSingle Nucleotide Polymorphism(SNPs)の検査が、オーダメイド医療の核になるという話はよく聞くが、皮膚科領域でも進んでいくのであろう。
-
某製薬会社主催講演会から(平成22年12月16日)
蕁麻疹のエビデンス紹介。成人の慢性蕁麻疹では、12~33%に抗甲状腺抗体が陽性という報告がある。これらは抗ヒ剤の内服に抵抗性で、ただし、T4補充療法でそのうち17%が改善した。難治な慢性蕁麻疹では、これらを計測しておくとよい。
それ以外に、British Association on Dermatologists(BAD)のガイドラインでは、慢性蕁麻疹で行って、少しは意味があるとされた検査は、白血球数とその分画、および血沈の2つだけであったとのこと。当院でも成人例ではよく採血をしているので、negativeなデータは出そうである。
-
第18回横浜臨床医学会学術集談会から(平成22年12月11日)
不育症は不妊症とは異なり、妊娠はするが、妊娠早期の流産を複数回繰り返したり、妊娠中期以降の胎児死亡などで分娩に至らない状態で、その原因は感染症、内分泌異常、子宮形態異常、染色体異常など多岐にわたるが、その1/4は血液凝固異常が関連していると言われる。ヘパリンカルシウムの1日2回皮下注を行うことで、妊娠維持と出産が可能で、在宅自己注射を保険適応を求めていく予定とのこと。
不育症という名前は知らなかった。ヘパリン在宅自己注射の保険適応は、不育症の患者団体と産科学会の要望を受けて、平成23年12月21日の中医協で承認されたという。抗リン脂質抗体症候群の皮膚病変にも使ってよいのであろうか。
-
第40回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成22年12月11日)
2007年のJAADの論文紹介。24時間以上持続する蕁麻疹で、紫斑を伴い、臨床的に蕁麻疹様血管炎と考えた22症例の組織学的検討。好中球優位な細小血管炎をみとめたのは3例のみで、19例は種々の程度に好酸球を含むが、リンパ球浸潤が主体であった。21例では毛細血管内に炎症性細胞を認めた。紫斑を伴う、持続時間の長い蕁麻疹は、蕁麻疹様血管炎だけではないという結論。
Prolonged urticaria with purpuraを病名にするのは反対だが、印象として、確かにそういう範疇の病態がある。蕁麻疹より持続時間が長く、臨床的にも浮腫だけではなく、炎症性細胞浸潤を伴っていそうな症例は、蕁麻疹ではなくあえて蕁麻疹様紅斑と呼んで来た。その中には、特に下肢に紫斑を伴う症例が少なくない。皮膚生検を行うと、血管内に好中球中心の炎症性細胞を含むを充血性変化伴うことを経験している。原因は感染症が多いのではないか。
-
第134回神奈川県皮膚科医会例会から(平成22年12月5日)
DIHSの経過で、最初の山は薬剤アレルギー、二峰目はHHV6、そして、DIHS発症後4~5週目に生じる三峰目の症状はCytomegalovirus(HHV5)が原因だった。臨床症状として皮膚の潰瘍や胃穿孔を起こすことが知られ、CMVの再活性化を来した30%に見られるという。CMVの再活性化、すなわち3峰性の経過をとるDIHSは、高齢者に多い、男性が多い、HHV6のDNA loadが高い、急速は血球減少を来す、などの特徴がある。しばしば生命予後にも関わるが、Viremiaは4日で消失するため、γグロブリン製剤投与は有効ではない。
二峰目のHHV6のウイルス量が多いほど、経過の遷延化、三峰目の症状を含む症状の重症化があるようだ。HHV6のviremiaに先だって顔面の浮腫が生じるという。この際、血中VEGFが上昇するらしい。唾液を検体としてHHV6のDNA量を測定できると聞いたことがあるが、DIHSではどうなのだろうか。
-
第40回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成22年12月11日)
ヌカ漬けを3年前から日課としていたが、手に接触蕁麻疹が出るようになった。洗米のあとに前腕がかゆくなることもある。スペイン旅行中パエリアを食べた後に口腔内違和感と全身の発疹、顔面の腫脹が生じた。プリックテストでは米ヌカ、精白米、胚芽米で強陽性。炊いた後の精白米では反応の減弱があったが、パエリアは洗米せず短時間で炊くため、米ヌカの抗原性が残ったらしい。
これもまた、経皮感作と食物アレルギーの関連で、この経路ではますます色々なことが起こりそうである。調理で触れる食品の経皮的な感作も、即時型食物アレルギーの原因になることに注意しなければならない。
-
第40回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成22年12月11日)
口紅とアイシャドーで接触蕁麻疹の既往歴がある女性。サラミソーセージを食べた後に蕁麻疹が出たことがある。今回は、フランス製赤マカロンを食べた直後に、全身に膨疹が出現し、アナフィラキシーに至る。赤マカロンに含まれる、カルミンのプリックテストが陽性で、コチニール色素による即時型アレルギーと診断した。コチニール色素はメキシコのサボテンに付くエンジムシから取れる赤い色素で、カンパリ、イチゴ牛乳、カニかまぼこ、抗生剤の細粒などに含まれている。
非常に興味深い。茶のしずくによる小麦アレルギーと同じで、まず口紅やアイシャドー中のコチニール色素に経皮感作され、コチニール色素を含む食物によって、全身性の即時型アレルギーが誘発されたのであろう。さらに最近の化粧品や医薬部外品はミルクや豆乳が入っているものもあるので、心配である。
-
第40回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成22年12月11日)
10カ月男児で、顔面を中心とする湿疹が生後3カ月から出現し始め、生後6カ月から重症化した。母にステロイド忌避あり。筋トーヌスの低下があり、定頚・座位保持が不安定。脳血流SPECTで、前頭葉、側頭葉の血流低下をみとめた。ステロイド軟膏と保湿剤で治療を行い、1カ月で皮膚症状も改善。発達は月齢相当となり、SPECTでも血流は回復した。発達障害の原因として、湿疹が広い範囲に生じたため、低ナトリウム、高カリウム、低蛋白、ビタミンB1欠乏の可能性を考えた。
ステロイド軟膏外用の標準治療が必要であるという、ムンテラのよい材料になると思った。皮膚科医としても、乳児の発達状態の正常値を知っておかねばならない。今後、乳児のアトピー性皮膚炎では、筋の緊張状態ぐらいは確認しておこう。
-
第40回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成22年12月11日)
慢性蕁麻疹の経過中、治療効果が思わしくなく、他剤への変更を選択する場合がある。この際、構造式上、三環系とピペリジン・ピペラジン系それぞれに属する第二世代抗ヒ剤について、同系の変更と他系への変更のどちらが有効だったかを、過去の症例で比較した。第二世代同士の変更イベントは全部で25回あり、このうち、同系での変更が9回で、そのうち6回が有効、3回が悪化または不変。他系への変更が16回で、そのうち11回が有効、5回が悪化または不変であった。他系への変更が同系への変更より有効率が若干高い、という結果になった。
以前に紹介した、第二世代抗ヒ剤の使い分けを実証したデータで非常に面白い。慢性蕁麻疹で最初の薬剤で期待した効果がなかったときは、最近では増量がはやりだが、変更を選んだ場合は同系よりも他系への方がよさそうである。今後は、前向き調査のデーターが出てくることを期待したい。あるいは、自ら検証してみよう。
-
第40回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成22年12月10日)
20代女性、5カ月間にわたって消褪しない体幹・四肢の苔癬状丘疹。病理組織では異型性のないリンパ球の表皮内浸潤があり、慢性苔癬状粃糠疹と診断。ステロイド軟膏、活性型ビタミンD3軟膏外用の外用が無効で、シクロスポリン、メトトレキサート内服も効果なし。ブレディニン100mg~150mgの治療により3ヶ月後から発疹は消褪しはじめ、10カ月でほぼ消失した。ブレディニンにはTリンパ球の増殖や遅延型過敏反応を抑制する作用があり、そのために有効だったと考えた。
実は、滴状類乾癬が最近はこの病名で呼ばれているとは知らなかった。いつ変わったのだろう。それはそれとして、なかなか粋な薬の使い方である。ただしシクロスポリンが無効でブレディニンが有効と言うことは、T細胞増殖抑制以外の作用もあるかもしれない。おそらく急性痘瘡状苔癬状粃糠疹でも有効なのではないか。治療に行き詰まる症例があれば使ってみよう。
-
第60回日本アレルギー学会秋季学術大会から(平成22年11月25日)
スギ花粉の盲点。早朝に症状が出現する症例があり、洗濯物、特にふとんを屋外に干すことにより、室内に取り込んだスギ花粉が原因で、一旦室内に取り込むと、家具の裏などに残存し、飛散期終了後も症状を引き起こすことがある。また、秋にもスギ花粉飛散があり、特に翌年の花粉飛散が多く見込まれる前の年の秋に多く、鼻炎などの症状をきたす例がある。
残存花粉には気づかなかった。秋のスギ花粉症はやはり、という感じ。下着を外に干すことで、スギ花粉飛散時に外陰部がかゆくなる女児も経験している。
-
第26回日本臨床皮膚科医会三ブロック合同学術集会から(平成22年11月23日)
ダーモスコピーが各種脱毛症の観察にも有効という話。男性型脱毛症では、毛直径の不均一、毛孔周囲色素沈着、少数の黄色点がみられる。特に、毛直径の不均一性はプロペシア内服で改善するので、効果判定にも用いることができる。
プロペシア内服中のAGAの効果判定はすっきりせず、写真撮影による印象しかないかと思っていた。同じ部位の観察のみという簡単な方法なので、試してみたい。
-
第833回日本皮膚科学会東京地方会から(平成22年11月20日)
両手を水につけると1~2分で手がふやけて痛みが生じるようになったという主訴で来院。多汗症に伴う、Aquagenic Palmoplantar Keratodermaないしaquagenic wrinkling of the palmsという疾患。症状は、冷水より温水に浸したときの方が強く出現。20分ほどで消失するが、繰り返しているうちに手の皮がむけてくる。発症部位は手掌や指腹で、通常は同部位が乾燥し、軽度の鱗屑と角化があるが、浸水試験で1分後に白色のふやけた丘疹が出現する(hand in the bucket sign)。痛みや痒みを訴えるケースもある。
こう診断したことはないが、心当たりのある患者は少なくない。急な発症があるとは知らなかった。今後は念頭に置いておこう。治療は塩化アルミニウム液が有効な場合もあるが、通常は自然消褪するとのこと。何が発症誘因になるのであろうか?
-
第4回神奈川臨床皮膚病理組織検討会(平成22年11月13日)
Churg-Strauss症候群(CSS)の皮膚病理の総説。CSSは太さの異なる血管の血管炎と、血管炎を伴わない肉芽腫性炎症、組織eosinophiliaを様々な程度に伴うので、きわめて多彩な皮膚病変がみられる。血管炎自体も真皮細小血管では好中球性、好酸球性とその中間型が、筋性小動脈では好酸球性と肉芽腫性が入り交じって認められる。さらに膠原線維の変性を伴う血管外柵状肉芽腫も、好酸球性の赤いタイプ(Churg-Strauss肉芽腫)と好中球性の青いタイプ(Winkelmann肉芽腫)があり、多くはその中間型である。
red granulomaとblue granulomaというのは、よく特徴が出ている。それにしても、CSSは臨床も組織も難しい。これがわかれば、血管炎が全部わかるという話もうなずける。
-
大阪西部皮膚科学術講演会から(平成22年11月6日)
毒ヘビ咬傷における臨床検査からの鑑別診断。ヤマカガシはフィブリノーゲンがまず減少してから、血小板の減少が起こる。マムシはDICを発症し、数時間で急激に血小板が減少するタイプと、腫脹が激しく、それに伴って血小板が徐々に低下するタイプがある。ハブもマムシと同様。詳細は、Japan snake center(へび研)のHPに掲載されている。
ほんの数例しか経験がないが、患者が来たときの心構えは必要だと思った。コンパートメント症候群の予防として、筋区画内圧が40mmHg以上であれば、筋膜切開(減張切開)が必要という目安があるようだ。どうやって測るかは知らないが、救急のドクターなら常識か。委せた方がよさそうだ。
-
大阪西部皮膚科学術講演会から(平成22年11月6日)
中年の女性例。両大腿・両足がわずかに腫脹し痛みが強いということで救急外来受診。数時間前に、セアカゴケグモに手をかまれた。発汗がさされた部位に生じていた。下腿の深部反射の亢進がある。補液だけで数時間後には改善。セアカゴケグモ咬症では、このように、咬まれた部位以外に疼痛を伴う例が40%にあるという。
これは知らなかった。クロゴケグモとドクイトグモ(ブラウンレクルゼ)という2種類の方が、なおさら強毒らしい。クロゴケグモは岩国基地で見つかったことがあるらしい。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成22年11月4日)
乾癬型薬疹の集計とその特徴についての報告。原因がある程度確認できた20例の内訳は、男性12例、女性8例で、年齢は45歳から82歳で平均が65.8歳であった。原因薬剤は14例が降圧剤で、2例が生物学的製剤、NSAIDや抗リウマチ薬など、その他が4例であった。投薬から発疹出現までの平均期間は6.8カ月であった。パッチテスト、DLSTは全例で陰性。生検の病理組織で、好酸球浸潤、基底層の変性、限局した苔癬型反応など、乾癬として非典型的な所見す見た場合に、薬剤性を考えるとよい。
現在、私の最大の悩みの種といってよい。生検を積極的にした方がよいことはわかったが、薬剤を変更・中止するように頼むための、きれいな因果関係が、もっとほしいところだ。
-
神奈川県皮膚科医会秋の勉強会から(平成22年10月30日)
アトピー性皮膚炎とフィラグリンの関係に関するレビュー。免疫異常がバリア異常を起こすことは間違いなさそうだが、バリア異常が免疫異常を起こすかはまだナゾである。ヒトでは尋常性魚鱗癬の患者の40%で、アトピー性皮膚炎を伴わないが、フィラグリン欠損マウスは32週でアトピー性皮膚炎になり、血中IgE値の上昇もきたすことが報告されている。マウスでは表皮細胞が3層ぐらいで薄いために皮膚炎になるのではないかと考えられている。
薄いということであれば、ヒトのまぶたの皮膚はどうか。部分的アトピー性皮膚炎と考えている、スギ花粉飛散時の眼瞼炎の症例では、フィラグリンの発現低下があるかも知れない。
-
第54回日本医真菌学会から(平成22年10月17日)
足や腋のにおいの原因とされるコリネバクテリウムの菌相を、足白癬患者と健常人の趾間で比較した。同定にはPCR法を用いた。足白癬患者ではC. striatumが41%検出されたが、健常人では7.0%しか検出されなかった。また、健常人の93.0%に検出された、C. tuberculostearicumは、足白癬患者の25.6%からしか検出されなかった。
コリネバクテリウムは以前からなかなか捉えるのが難しく、しかし皮膚疾患に深く関わっていそうで気になる存在である。疾患特異的な菌種があるのではないかと思っているが、どうなのか。たとえばpitted keratolysisではどうか、大変気になるところだ。今後の発展に期待したい。
-
第54回日本医真菌学会から(平成22年10月17日)
63名の外耳道炎患者での検討。スメアからマラセチアが直接鏡検で陽性で、分離培養でも他の菌が検出されず、かつ抗真菌剤外用で改善した症例をマラセチア外耳道炎と定義すると、5例(7.9%)がそれと診断された。5例中4例は高齢者で、いずれの起因菌もM. slooffiae(スルフィー)であった。加齢に伴い、外耳道に遊離脂肪酸が増えるため、高齢者ではマラセチアが外耳道炎を起こすことがある。
脂漏性皮膚炎ではM.restrictaが多いと聞いている。外耳道炎は脂漏性皮膚炎と関連が深いと考えていたが、この菌種の違いはどこからくるのであろうか。
-
第54回日本医真菌学会から(平成22年10月17日)
カンジダが産生するファルネソールは、カンジダ自身が同種の存在密度を感知するシステムに関わる分子であるが、近年は病原因子の一つと考えられている。ファルネソールはメバロン酸経路の中間代謝物で、その上流にあるHMG-CoA還元酵素を阻害する、スタチンによって産生が阻害されることが明らかになった。さらに、播種性カンジダ症のマウスモデルを用いた実験では、腹腔内投与のみでなく、経口投与でも菌数の減少がみられ、フルコナゾールの併用で相乗効果を示した。
真菌とスタチンが関連するとは初耳であった。スタチンを内服中の人にはカンジダ症が少ないかどうか、疫学的に検討すると面白いかも知れない。
-
平成22年度社会保険診療懇話会から(平成22年11月9日)
湿布剤の適応疾患の話。RAの関節痛と腰痛に対して保険適応があるのは、モーラステープのみで、モーラスパップ、ロキソニンテープ、ボルタレンテープ、セルタッチ、アドフィードなどには適応がない。筋肉痛にたいしては多くの湿布剤は保険適応であるが、逆にモーラステープは保険適応がない(モーラスパップには適応あり)。ロキソニンテープ、ロキソニンパップは肩関節周囲炎、腱鞘炎に保険適応なしなど、混乱がみられる。
実際の返戻は受けたことがないが、それなりに覚えておく必要はありそうだ。
-
第14回横浜デルマカンファレンスから(平成22年10月28日)
クロピドグレル(プラビックス):血小板のP2Y12受容体拮抗薬。血行障害の改善のほかに、線維化を抑制し、NF-κβを介する虚血性炎症を抑制する可能性がある。ボセンタン(トラクリア):エンドセリン受容体拮抗薬で肺高血圧症に対して適応あり。レイノー症状や皮膚潰瘍に対しても有効で、線維化抑制の可能性もある。シルデナフィル(レバチオ):5型ホスホジエステラーゼ (PDE-5) の酵素活性を阻害する血管拡張剤で、肺高血圧症に適応あり。レイノー症状、指端潰瘍にも有効。メシル酸イマチニブ(グリベック):CML治療薬。TGF-β、血小板由来増殖因子(PDGF)受容体の活性を阻害する。線維芽細胞の活性化、増殖抑制の作用もある。スタチン(リピトールなど):高脂血症治療薬。強皮症では血管内皮が傷害されたときに起こるはずの、骨髄からの血管内皮前駆細胞(CEP)の動員が減弱しており、CEPを介した傷害血管の修復が見られないことが、末梢循環障害の原因と考える。スタチンにはCEP動員促進作用があり、末梢循環障害を改善させる。血管新生因子(VEGF、bFGF)、血管内皮傷害マーカー(可溶性VCAM1、可溶性E-セレクチン)も有意に改善した。PD98059、U0126:Ras K1/2の阻害剤。強皮症ではPDGF受容体を刺激する自己抗体があり、それがHa-RasおよびERK1-2のシグナル伝達を介してROSを誘導し、線維芽細胞の活性化および内皮細胞のアポトーシスを誘導する。この経路を遮断することで、線維化と循環障害を改善する。
色々と選択枝が広がってきたようだ。スタチンについては様々な循環障害を伴う皮膚疾患で有効性を検証してほしい。
-
第62回日本皮膚科学会西部支部学術大会から(平成22年10月24日)
耳鼻科Dr.との集談会での話題。慢性化膿性耳疾患には、ブロー氏液が有用である。原法は無水硫酸アルミニウム、炭酸カルシウム、酢酸、酒石酸、精製水の混和剤であるが、いくつか迅速調整剤の処方も工夫されている。グラム陰性桿菌、グラム陽性球菌、カンジダのいずれにも有効で、特にMSSA、MRSAの菌消失率はタリビッド点耳薬より勝っていたとの報告がある。さらに、メルクマニュアル家庭版では、汗疱を消褪させる効果があると述べられているとのこと。
米国のドラマERで紹介されていて以前から気になっていたが、確かに青い。中止、変更が難しいので、苔癬型反応が長期化するためであろう。
-
第62回日本皮膚科学会西部支部学術大会から(平成22年10月24日)/strong>
10代男児。頭頂部の馬蹄形の脱毛斑で、中央はやや陥凹し、周囲には紅斑を伴う。頚部から始まり、徐々に遠心性に拡大し、数年間持続した後に軽快していく。組織学的に、中央には脂肪織の萎縮、辺縁には非特異的な脂肪織炎がある。円形脱毛症の鑑別疾患の一つとして覚えておく必要がある。
難産の後に生じる新生児皮下脂肪壊死症と同様の組織反応のようだ。後天性だが、何らかの物理的な刺激が原因か。経験はないが、覚えておこう。
-
第62回日本皮膚科学会西部支部学術大会から(平成22年10月24日)
爪甲色素線条の鑑別診断の要点。ダーモスコピーでは、まず線条の太さで、lines(細線条)とbands(線条帯)に分け、色調、幅、間隔、平行性、境界の明瞭さを評価して、regularがirregularかを判断する。また、爪廓や指尖の黒褐色斑(Hutchinson徴候)については、足蹠の色素斑と同様に、皮溝平行か皮丘平行かを区別する。爪部メラノーマの抽出には、3つのダーモスコピー所見(背景の色調が多彩、不規則細線条・線状帯、皮丘平行パターンのHutchinson徴候)を各2点、3つの臨床スコア(年齢が30歳以上、発症から5年以内、最近3カ月での明らかな変化)を各1点とする6-point checklistが有用で、3点以上でメラノーマを強く疑う。なお、爪甲の線条は、夏に濃く、冬に薄い傾向があるので、季節変動も考慮すること。
重要な内容の講演であった。季節変動については気づかなかったので、実際に比べてみたい。
-
第16回アレルギー疾患治療座談会から(平成22年10月23日)
耳鼻科Dr.との集談会での話題。慢性化膿性耳疾患には、ブロー氏液が有用である。原法は無水硫酸アルミニウム、炭酸カルシウム、酢酸、酒石酸、精製水の混和剤であるが、いくつか迅速調整剤の処方も工夫されている。グラム陰性桿菌、グラム陽性球菌、カンジダのいずれにも有効で、特にMSSA、MRSAの菌消失率はタリビッド点耳薬より勝っていたとの報告がある。さらに、メルクマニュアル家庭版では、汗疱を消褪させる効果があると述べられているとのこと。
初耳であった。耳鼻科領域では有名な調剤らしい。それが汗疱に有効とは、知らなかった。自分のまわりに、これを用いている皮膚科医はいないと思われるが、試してみる価値はあるだろうか。
-
第6回神奈川皮膚アレルギー疾患研究会から(平成22年10月9日)
患者とのコミュニケーションスキルの総説。腕組みや脚組みはクローズな姿勢を示すので、診察時には慎むこと。また、腕組みや脚組みを患者がしていたら、それは患者が心を開いていない証拠。心のリセプターが開くと腕組み、脚組みをやめるようになる。
難しい症例では、ついつい腕組みをしてしまう。確かに、説明がうまくいかない時にも出てしまいがちである。自分の診療スタイルの指摘を受けたようで、焦った。そのほか「聞く」スキルとしては、沈黙(先取りをしない)、うなづき、ほほえみ(一緒に困った顔をする)、くり返し、言い換え、要約に心がけること。なかなか奧が深い。
-
某製薬会社主催講演会から(平成22年9月25日)
薬疹と診断した際には、法的リスクマネジメントの観点から、採血を行い、肝機能障害や顆粒球減少症がないか、確認しておく必要がある。この観察を怠ったために医師が敗訴した最高裁の凡例があるとのこと。
小児例や播種状紅斑丘疹型などの軽症例では採血をしないこともあるが、確かに皮膚の観察だけではわからない併発症状があるかもしれない。昨今では、医師-患者間のトラブル回避のためにも、必要なのだろう。方針を改めることにする。
-
第5回横浜市薬剤師会研修会から(平成22年9月11日)
外用剤の基剤の構成成分の話。油脂性軟膏剤は主として油性成分(白色ワセリン、ミツロウ、ステアリン酸、セタノールなど)からなり、添加物を混じるものは少ないが、中には界面活性剤(セスキオレイン酸ソルビタンなど)や抗酸化剤(ジブチルヒドロキシトルエンなど)を含むものがある。乳剤性軟膏剤(0/WクリームならびにW/0クリーム)は油性成分に加えて、水性成分(グリセリン、プロピレングリコールなど)や界面活性剤、防腐剤、抗酸化剤、pH調整剤の混和が必須で、それぞれの役割を知っておく必要がある。
長く皮膚科医をしているが、軟膏の製造現場を見たことはない。誰か見たことのある人はいるだろうか。乳化の過程、主剤の混和の方法など、本当は知っておく必要があるのではないかと、日頃から思っている。みんなで一度、外用剤の工場見学に行くのはどうだろう。
-
第5回横浜市薬剤師会研修会から(平成22年9月11日)
軟膏を人差し指の先から第Ⅰ関節の長さまで出した量が1FTUで、約0.5 gとなり、成人の手のひら2枚分の面積に塗布することができるということが最近では浸透してきたが、これは、もともと5 mmの口径の海外のステロイド軟膏を用いた海外の報告がもとになっている。日本のステロイド軟膏は口径が小さく、さらに先端に穴を開けたあとの内径はさらに小さくなる。たとえば5 gのアンテベート軟膏では口径が4.7 mm、開封後は3.7 mmで、1FTUが0.25 g、5 gのネリゾナユニバーサルクリームは口径が3.4 mm、開封後は1.8 mmで、1FTUが0.24 g、10 gのゲンタシン軟膏は内径が4.2 mmで、1FTUは0.33 gである。
ステロイド軟膏の5gチューブでは約半分と思っておいた方がよさそうだ。穴の開け方まではきちんと指導していないので、もっと少ないかもしれない。
-
第37回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成22年9月1日)
口角の皮膚病の総論。口角部は感染症の宝庫で、膿痂疹、カンジダ、Herpes simplexなどのほかにも、梅毒初期硬結、lepraなどが好発する。口角部の病変はすべて感染症と思って間違いない。
振り返ってみればそう思う。このように断言されると、すっきりする。治療方針の決定にもすぐに活かすことができ、ためになった。
-
第28回日本美容皮膚科学会から(平成22年8月8日)
陥入爪の治療にグラスファイバー製爪矯正器具を爪甲に貼り、痛みの程度をVASで評価した。装着後爪甲の彎曲度の改善とともに、痛みも1週間後から1/2に減り、8週後には1/3に改善した。簡便かつ非侵襲性で有用な陥入爪治療法である。
BSブレイスクイックという製品で、さっそく講習を受けた。爪甲に横に貼るので、短くて弾性ワイアーを使えない爪にも装着できる。爪甲をうまく削るのがミソで、厚い爪にはむかないようだ。症例を選んで使ってみよう。
-
第28回日本美容皮膚科学会から(平成22年8月8日)
AGAに対して発光ダイオード(LED)が使用されている。LEDの照射によって毛乳頭細胞から分泌される発毛に関与するサイトカインのmRNAの発現量を解析した。光源は、赤(638nm:0.6J/cm2)、緑(518nm:0.2J/cm2)、青(456nm:0.3J/cm2)を用いた。HGF(成長期を誘導)は赤は直後、24時間後、緑は4時間後、青は4、8、24時間後に上昇、IGF-1(器官形成促進・成長期維持)は赤で、4、8、24時間後、緑では8時間後に上昇。Leptin(成長期誘導)は赤の4、8時間後、緑の直後、4、8時間後、青の直後、4、24時間後に上昇。VEGF(毛包の血管新生)は赤の直後、4、8時間後、緑の直後、4、8時間後、青の直後、4、24時間後で上昇、TNFα(成長期抑制)は赤の4、8時間後、緑の8時間後に低下した。
赤は真皮浅層、青は真皮深層、緑はその中間をターゲットにしているらしい。LEDが美容以外の皮膚病の治療で使われるようになるのもそう遠くはなさそうで、楽しみである。
-
第37回皮膚かたち研究学会から(平成22年7月25日)
Nephrogenic systemic fibrosis(NSF)は、腎不全患者に生じる皮膚硬化で、MRIで使用されるガドリニウム造影剤が契機となる。強皮症や硬化性粘液水腫との鑑別が必要だが、組織中の線維芽細胞や膠原線維間に鉄染色陽性の顆粒を認めることが多い。ガドリニウムはキレートされた形で造影剤として使用されるが、NSFでは鉄代謝に異常があり、鉄がガドリニウムをキレートから遊離しやすくさせ、遊離したガドリニウムが組織障害を起こすとともに、鉄がキレート化されて不溶性になり、組織に沈着すると考えられる。
きれいな組織の写真だった。鉄代謝に異常があると、MRIのガドリニウムがNSFを起こすとも考えられる。腎不全以外にもヘモクロマトーシスや慢性肝炎でも起こるのであろうか。
-
第33回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成22年7月15日)
カネミ油症のざ瘡様発疹は、ダイオキシンによる皮膚障害として有名。これに有効な薬剤は何かin vivo、in vitroで色々と調べたところ、ケトコナゾールがもっとも有効であった。ダイオキシンは皮膚の芳香族炭化水素受容体(Aryl Hydrocarbon Receptor、AhR)という転写因子のリガンドで、これらの結合が、IL-8の産生を促すことがわかった。ちなみに、タバコの中のベンゾピレンもダイオキシンの一種で、IL-8の産生を誘導する。ケトコナゾールはAhRのbinderで、抗酸化作用を持つため、好中球の関与する疾患に有効かも知れない。
掌蹠膿疱症やニキビがタバコで悪化する理由もこれか。また、夏季になると乳児の頚部などに膿疱を混じるあせもをよく見かける。膿疱が乾いた後に小さな痂皮がぽつぽつと付いてくるが(あせもの黒ゴマ)、これが亜鉛華軟膏やオリーブ油などでなかなか取れない。これに対して以前からケトコナゾールローションを使用するときれいになることを経験している。カンジダは陰性で、なぜ有効なのかわからなかったが、ひょっとするとIL-8の産生抑制と関係があるのかもしれない。
-
第7回相模原皮膚科学セミナーから(平成22年7月24日)
水痘の発症予防のためのワクチン接種の目安。水痘患者との接触の後、3日以内であればワクチンは有効である。抗体の有無は血清抗体価の結果を待つと手遅れになる。抗体の有無を迅速に調べることのできる水痘抗原は、0.1mlを皮内に注射し、24時間後に5mm以上であれば陽性と判断し、その場合にはワクチンの必要はない。なお、水痘ワクチン(ビケン)接種後、小児では約20%に14日後から30日後に水痘様の発疹が生じ、接種後水痘も6~12%に見られる。成人では水痘様の発疹の発生は0.2%である。ワクチンによって水痘様発疹が出た人は、帯状疱疹に罹患しやすい(17/83)。
年に数回、母親からの問い合わせを受け、判断に迷うことがあったが、明確な基準があると便利である。常に1つは冷蔵庫に置いておこうと思った。
-
第7回相模原皮膚科学セミナーから(平成22年7月24日)
単純ヘルペスウイルス(HSV)のエンベロープにある糖蛋白質のgGは、型特異性がみられ、この抗体を測定することで、患者の感染しているHSVの型判定ができるようになり、診断や疫学に利用されるようになった。ELISA法では、初感染後約3か月で陽転化するが、偽陰性反応や疑陽性反応もみられる。gG抗体測定は、病変が治癒している場合にも判定できることが利点だが、陽性結果は過去のウイルス感染を意味し、現在の病変がどちらの感染かを示すものではないことに注意が必要。また、陽性結果は感染部位を示唆しないので、HSV-1の性器感染、HSV-2の口囲の感染の診断にも有用である。この方法を用いたHSV-2に対する抗体保有率のデータが報告されている(橋戸円ほか:医学のあゆみ,152:669-670,1990)。本邦の健常人で7.8%、妊婦で6.7%、特殊浴場接客婦で79%、STDクリニックに通う男性で23%、男性同性愛者で24%であった。
1型か2型かを知りたい時は、水疱部のDIFを利用しているが、病変が乾いていて行えないときも多い。抗体の測定で型判定ができるとは知らなかった。早くコマーシャルベースにはなってほしい。
-
第15回ラテックスアレルギー研究会から(平成22年7月9日)
DIHSにおけるHHV-6の再活性化は有名であるが、HSV感染後に発生する多形滲出性紅斑など、ヘルペスウイルス感染とアレルギー性皮膚疾患は関連が深い。さらに、一部の片側性の扁平苔癬では病変部の汗腺にVZVの抗原が発現していることがあり、また、固定薬疹の病変部に浸潤している細胞にもVZV抗原陽性細胞を多数認めることがある。ヘルペスウイルス感染による制御性T細胞(Treg)の機能不全が、続発・併発する皮膚症状の原因かも知れない。
固定薬疹と同様の水疱を伴う紅斑がHSV感染症に続発する症例がある。リンパ球に対するウイルスの働きには興味があるところだが、一方、麻疹や風疹など、ウイルス特異的な皮膚症状があるということをどうやって説明するのかが、以前から疑問である。
-
第15回ラテックスアレルギー研究会から(平成22年7月9日)
小麦アレルギーは、運動やアスピリンの投与で誘発されるが、これは消化管からのアレルゲン吸収を促進させるためと考えられている。アスピリンの内服により減少するプロスタグランディン(PG)を補う目的で、NSAIDsによる消化性潰瘍に使用する、PGE1誘導体であるサイトテックを抗ヒ剤とともに前投与したところ、症状の誘発抑制に効果があった。
運動誘発性の小麦アレルギーでは、サイトテック投与による運動負荷後の血中グリアジン上昇は抑制されず、インタールで抑制された。薬理学的におもしろい治療である。インタールとサイトテックの併用も有効な可能性があるだろう。
-
第133回神奈川県皮膚科医会から(平成22年7月4日)
表皮細胞は互いにタイトジャンクション(TJ)という構造によって結合し、先端側からの微生物や抗原の侵入と基底膜側からの水分蒸発のバリアとして機能している。TJバリアは顆粒層の上から2層目(SG2)の細胞間をシールしていることが、3次元可視化の技術によって証明された。また、通常、ランゲルハンス細胞(LC)はTJバリアの下に隠れているが、角層のストリッピングによってLCを活性化すると、LCはTJバリアを超えて樹状突起を伸ばし、角層を通り抜けて侵入した抗原を取りに行く。この時、LCはクローディン1というTJを構成するタンパク質をたくさん作り、LCの樹状突起と表皮細胞の間に、新しいTJを形成しながら突起をのばして行くので、抗原の体内への侵入を防ぐことができる。
いよいよ皮膚の生物学も3Dになってきた。臨床の写真も、やがて盛り上がりやへこみがわかるような3Dになるだろう。学会には赤青メガネが必需品になりそうだ。
-
某製薬会社主催記念講演会から(平成22年7月1日)
主として三叉神経支配領域に生じる難治性の潰瘍をtrigeminal trophic syndrome(TTS)と称する。前頭洞の手術などによる三叉神経節の損傷が原因とされていたが、三叉神経節より中枢あるいは末梢の神経障害でも生じることがあり、脳梗塞や帯状疱疹もその原因となりうる。帯状疱疹後の症例はherpetic TTSと呼ばれ、潰瘍は鼻翼部から鼻唇溝にかけて三日月型を呈することが多いとのこと。
お恥ずかしい話だが、trophicではなく、tropicだとずっと勘違いをしていた。trophicとは栄養の、という意味で、神経障害に基づく局所の栄養障害を表現した疾患名であると知った。
-
某製薬会社主催記念講演会から(平成22年7月1日)
米国で帯状疱疹の発症予防として使用されているVZVワクチン(ZOSTAVAX)は、2006年5月に、60歳以上での適応がみとめられた。岡/メルク株水痘弱毒化生ワクチンで少なくとも19,400PFUの活性を持つとされる。60才以上の健常人38,546例(ZOSTAVAX 19,270人、placebo 19,276人)を対象とした臨床研究(SPS:Shingles Prevention Study)では、60-69歳の年間発生率がZOSTAVAX 3.9/1000、placebo 10.8/1000で64%の発生率低下を、70-79歳では、66.7/1000と11.4/1000で41%の低減率、80歳以上では9.9/1000と12.2/1000で18%の低減率であった。現在日本では治験が進行中である。
帯状疱疹を英語でshinglesということは初耳だった。なお、最近、50歳から59歳の健常人を対象とした臨床研究(ZEST:ZOSTAVAX Efficacy and Safety Trial)が発表された。経過観察期間は平均1.3年で、11,211人のZOSTAVAX群では年間発症率が1.994/1000、11,228人のplacebo群では6.60/1000で、70%の発生低減率であった。これを受けて、50歳からのZOSTAVAX使用が承認されたとのこと。
-
第8回皮膚膠原病研究会から(平成22年6月26日)
ヘプシジンは鉄の代謝を調節するホルモンで、消化管からの鉄吸収を抑制し、また網内系マクロファージからの鉄放出をブロックする作用があり、遺伝性ヘモクロマトーシスの責任遺伝子の一つである。慢性炎症に伴う貧血(ACD:anemia of inflammation)では、感染や炎症による血清中のIL‐6やIL‐1βなどの上昇が、肝臓でのヘプシジン産生を亢進させる。ヘプシジンは体内を循環し、その作用により結果的に血清鉄の減少をきたし、造血に利用される鉄が不足し貧血をきたすことになると考えられるようになった。また、慢性C型肝炎では肝実質の機能不全によって(他の機序もあり得る)ヘプシジンの産生が減り、消化管からの鉄吸収が高まり、それがさらに肝障害を進展させたり発癌を起こすと考えられている。
C型肝炎に伴う口腔粘膜の扁平苔癬は、ヘプシジンと関係があるのではないかとひらめいた。活性型ヘプシジン-25の定量も可能とのことで、機会があれば検討してみたい。鉄以外の金属の吸収や放出を調節する他の分子があるかも知れない。金属代謝と皮膚疾患の関連は、おもしろそうである。
-
第8回皮膚膠原病研究会から(平成22年6月26日)
CRPはIL-6とIL-1βの共同作業で高値となるマーカーで、TNF-αは関与しない。血清中アミロイド-A(SAA)もIL-6とIL-1βの両者の存在下で著増するが、IL-1βとTNFαの組み合わせでも増加し、IL-6のみでもわずかに増加する。炎症性マーカーとしての血沈は血球表面のC3bと関連し、免疫複合体の関与する炎症で亢進する。また、β2-MGとフェリチンはサイトカイン誘導タンパクで、それぞれ、血中にINF-γ、TNF-αが増加している証拠である。
これは臨床で役に立つ。それぞれのマーカーの差異から、どのような炎症性サイトカインが病態に関与しているかが、想像できることになる。CRPとSAAのギャップがある症例は以前から注目しているが、今後まとめてみよう。
-
第8回皮膚膠原病研究会から(平成22年6月26日)
小児皮膚筋炎の少なくとも30%に合併するとされる異所性皮下石灰沈着は、時に患児のQOLを阻害する要因となる。大きな皮下の病変では、貯留液を伴うことがあり、その性状がらカルシウムミルク(milk of calcium)と呼ばれる。皮膚筋炎におけるcalcinosisの原因はまだ不明だが、カルシウムミルクの中には多くのマクロファージが存在し、また、IL-6、IL-1、TNF-αなどの炎症性サイトカインが大量に含まれていることが明らかとなり、マクロファージの活性化が異所性石灰沈着の原因と考えられる。治療としてはステロイドや免疫抑制剤は無効で、抗TNF-α製剤とサリドマイドが有効である。
サリドマイドもその薬理作用の一つがNFκBの阻害であり、マクロファージからのTNF-αの産生を抑制するということ。それにしてもカルシウムミルクとはなかなかの命名である。
-
横浜市皮膚科医会学術講演会から(平成22年6月10日)
入浴やプールの後は、皮膚の天然保湿因子が低下し、アトピー性皮膚炎の悪化につながることはよく知られている。また、外用薬はバリアが壊れた所からより多く吸収されることも事実である。したがって、慢性で難治性の手湿疹では、まずお湯に20分間浸すことで、一旦バリアを破壊し、そのあとにステロイド軟膏の外用ないしODTを行うと、よくなることがある。
ステロイド外用を単に行うだけでは一進一退の手湿疹の患者は多い。確かに、このような前処置によって浸透性が増した所に外用するという方法をたまに行ってもらうのは、QOLの改善に役立つかも知れない。一度試してみよう。
-
大分皮膚形成外科フォーラムから(平成22年6月5日)
マダニ刺症の話。マダニの成虫は蝕肢を広げて、鋏角と呼ばれる針状の構造物で皮膚を切開し、口下片と呼ばれる突起物(針状の歯を持つ)を差し込んで吸血します。口下片の鉤状の歯と鋏角により、マダニが皮膚状に固定され、吸血時に唾液とともに分泌されるセメント様物質でさらに硬く固定される。脱落しない場合には外科的切除が一般的だが、Veetと呼ばれるチオグリコール酸が主成分の脱毛クリームを外用すると落ちる場合がある。
これは面白い使い方だが、若干不安もある。多数の虫体があって手術が大変な時には試してみてもよいかと思った。
-
第36回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成22年6月3日)
黄色い皮膚病のまとめ。1) 沈着症(ビリルビン、カロチン、尿酸、トリグリセリド、コレステロール) 2) 角質の増加(掌蹠角化症など) 3) 好中球の集蔟(乾癬の爪など) 4) 脂腺の増加 5) 出血のあと(Ehlar-Danlos Syndrome、lichen aureusなど) 6) 弾性線維の変性(pseudoxanthoma elasticum、Pringle病など) 7) 膠原線維の変性(morpheaなど)
よくまとまっていて、覚えやすく、ためになった。黄色を見逃さず、しっかり鑑別しようと思った。
-
第26回日本臨床皮膚科医会総会から(平成22年5月30日)
IL-18はIL-3の存在下で肥満細胞や好塩基球を刺激し、IL-4やIL-13、ヒスタミンなどの産生を誘導することによって、IgEを介さずに皮膚炎を惹起すると言われている。アトピー性皮膚炎では健常に比べて、血清中IL-18が高値で、また、tape-strippingで採取した肘窩の角層内IL-18も高値であった。また、角層内IL-18は全身重症度、血清中のIgE、LDH、TARCとも相関しており、治療による皮膚症状の改善とともに、低下した。さらに血清IgEが1500IU/mLの症例では、黄色ブ菌の感染がある症例は感染がない症例に比べて肘窩の角層内IL-18が高い傾向があった。
結果を見ているに過ぎないような気もする。TARCも確かに湿疹病変の程度に比例するように思うが、アトピー性皮膚炎皮膚炎に限らず高値になる症例があるので、評価が難しく、未だにうまく付き合えていない。
-
神奈川県保険医協会第8回治験セミナーから(平成22年5月26日)
1957年、カリフォルニア控訴裁判所におけるサルゴ裁判で初めて用いられた法律用語。「医師が患者にインフォームした後で、患者から同意を得る行為」ではなく、「患者が医師からインフォームしてもらった後で、医師に同意を与える行為」であり、患者ないし被験者(研究対象になる者)が、治療ないし研究に関する説明を医師から受け、説明内容を理解した上で、その治療の実施ないし研究への参加に同意する、ということである。それは、患者ないし被験者が、(1)理解する力と決定する能力をもち、(2)他者の支配を受けず自発的に決定できる状況において、医師ないし研究者から、(3)十分な情報を開示され、(4)提案された治療を受ける、ないし研究に参加するよう勧められて、(5)説明された内容を理解した上で、(6)その治療を受ける、ないし研究に参加することに決めて、(7)その治療を受けること、ないし研究に参加することに同意を与える、という7つの要素からなる。
まさに、誤解の通りであった。治験は当然だが、今後は開業医の臨床研究でも、この辺をおろそかにできないと感じている。
-
第32回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成22年5月20日)
水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)は神経線維束に沿って、神経を傷つけながら下降し、神経支配領域で増殖して、帯状疱疹を発症する。これに対して単純性疱疹ウイルス(HSV)は神経線維の中を下降して神経終末で増殖し、その部分の皮膚に散在性の病変を形成する。したがって、VZVでは疼痛が生じ、HSVは神経線維束を損傷しないため患者はむしろ痛みに鈍感になる。また、VZVは再活性化に際し、VZV特異的転写因子immediate-early(IE)62が活性化してウイルス遺伝子の転写を促す。患者には、IE62に対する抗体が産生されるのだが、この抗IE62抗体は痛覚系に関与する脳由来神経栄養因子(BDNF)と交叉活性を示し、機能的には脊髄後角でのBDNFの働きを増強し、痛覚過敏と痛覚ネットワークを形成する。
HSVとVZVの通り道が、神経線維の中と外ということは知らなかった。抗IE62抗体の話も初耳だが、抗体の量と疼痛強さに関連があるとすれば、抗体価の測定で疼痛の予知が推測できるのではないか。
-
第32回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成22年5月20日)
顔面神経麻痺はBell麻痺(狭義のBell麻痺+HSV感染症)、Ramsay-Hunt症候群、その他に分けられる。Ramsay-Hunt症候群の中には、無疹性帯状疱疹(zoster sine herpete:ZSH)と呼ばれる病態があり、顔面神経麻痺全体の1割を占める。ZSHは耳鼻科・眼科領域でよく用いられる名称で、1) VZV再活性化による痛みがあるが、発疹がない、2) VZV再活性化による顔面神経麻痺があるが発疹がない、3) VZV再活性化による眼症状があるが発疹がない、4) 脊髄炎、神経因性膀胱などの神経疾患があるが発疹がない、と定義される。
ZSHは皮膚科ではあまり使わないのではないか。Ramsay-Hunt症候群も耳甲介腔の小さな痂皮や患側硬口蓋のびらんだけの時もあるので、皮膚科医がしっかり診れば、発疹は見つけられるような気がする。1割は多すぎるのではないか。
-
神奈川県皮膚科医会春の勉強会から(平成22年4月22日)
タクロリムスは感覚神経線維で細胞内カルシウム流入を増加させ、substance Pなどの神経伝達物質を放出させ、それを枯渇させることが知られている。同様の反応はカプサイシン処理時にも観察される。タクロリムスはカプサイシンの受容体であるTRPV1にも結合し、それがタクロリムス軟膏を外用した際の灼熱感と関連していると思われる。また、吸引水疱内容液を用いた実験では、タクロリムス軟膏を外用すると一時的に表皮内の神経成長因子(NGF)が上昇することがわかった。塩酸エピナスチンを投与するとNGFの上昇は抑制され、臨床的にも灼熱感の減弱がみられる。
確かにプロトピック外用初期の灼熱感はトウガラシを塗った時のようだ。アレジオンの内服でそれを減弱させることができるというのは、診療に役立つ情報である。ジルテックでも似たような臨床試験があったが、それ以外の第2世代抗ヒ剤でも同様だろうか。
-
第109回日本皮膚科学会総会から(平成22年4月18日)
大分と愛媛からの同様の報告。2009年に流行した、手足口病の罹患児に、発症6週~8週後から爪甲脱落症(onychomadesis)が生じた。原因ウイルスの検索を行ったところ(中和抗体ないし咽頭スワブからの分離)いずれもコクサッキーウイルスA6型であった。コクサッキーA6による手足口病は水痘様の分布を生じるなど、臨床型が異なるので、爪にも影響を来すと思われる。
当院でも2010年初夏に流行した手足口病に続発した同様の症例を複数経験した。エンテロウイルス71が原因と考えていたが、爪甲脱落を続発した症例の発疹の臨床も指摘の通りで、コクサッキーウイルスA6型だったのだろう。開業医ではなかなかそこまで検索できないが、臨床から、原因ウイルスの型をある程度推定でき、さらに1~2カ月後の爪の異常が生じるかも知れないことを指摘できることは、開業医にとってはexcitingである。
-
第109回日本皮膚科学会総会から(平成22年4月18日)
70歳代の男性患者。陰嚢前面に生じた持続性の潮紅とヒリヒリ感。臨床は血管拡張。Paget病との鑑別のため生検を施行したところ、組織でも真皮浅層の血管拡張とわずかな浮腫のみ。The red scrotum syndrome と診断した。この疾患は60歳以上に多く、30歳以下ではまれ。うつと関連があり、トリプタノールの有効例がある。
たまにみることがあるが、ステロイド軟膏外用による酒さと診断していた。あまり芳しい病名ではないので、単純に酒さという診断名を用いてもよいのではないかと思ったが、念のために覚えておこう。
-
第109回日本皮膚科学会総会から(平成22年4月18日)
慢性の下肢静脈瘤患者20例に単純XPを施行し、異所性石灰沈着の有無を検索した。13名で陽性で、病脳期間が長いほど高頻度に認めた。沈着のタイプは斑点型(punctate type)が9例、小柱型(tubular type)が1例、網状型(reticular type)が3例であった。小柱型、網状型は重症度の高い患者に多かった。皮下の石灰沈着は潰瘍の原因になるため、単純XPによる評価も重要なポイントである。
確かに潰瘍の周囲の皮内や皮下に硬い結節をきたし、自潰してくる症例がある。単純XPなら開業医でも連携機関があれば評価できる。是非行ってみたい。
-
第109回日本皮膚科学会総会から(平成22年4月16日)
Ⅲ度以上の褥瘡(黄色期・黒色期)では、TIMEコンセプトによる創面環境調整を図るのがよい。TIMEはT(Tissue non-viable or deficient:壊死・不活性組織の管理)、I(Infection or inflammation:感染・炎症の管理)、M(Moisture imbalance:滲出液の管理)、E(Edge of wound: nonadvancing or undermined:創辺縁の管理)という、創傷治癒を阻害する4つの因子の頭文字である。
創辺縁の管理とはポケットへの対応である。創底が赤色期になれば今度は湿潤環境に置いて上皮化を図るという流れで、大変わかりやすい。地域の訪問看護師への教育に使わせてもらおう。
-
第109回日本皮膚科学会総会から(平成22年4月17日)
後天性魚鱗癬は悪性腫瘍に伴う例が多く、尋常性魚鱗癬と異なり間擦部や四肢屈側にも大型の多角葉状の鱗屑をみることが多い。悪性腫瘍以外の原因としては、SLE、皮膚筋炎、MCTD、Crohn病、サルコイドーシス、真性赤血球増多症、腎不全、甲状腺機能低下症、副甲状腺機能亢進症、骨髄移植後、栄養障害などの全身性疾患に伴うもののほか、ハロペリドールなどの向精神薬、タガメット、チガソン、ザイロリック、リピディールなどの内服薬がある。
病態としてしっかり記載していないし、そう診断したとしても原因を明らかにできる症例がない。薬剤に関しては注目していなかったので、今後は内服歴を確認することにしよう。
-
第109回日本皮膚科学会総会から(平成22年4月16日)
皮膚に接触する食物アレルゲンによる感作が、即時型の食物アレルギーあるいはアトピー性皮膚炎の発症に重要な役割を果たしている可能性がある。経皮的なアレルゲンの侵入はTh2タイプの炎症を惹起しやすく、これに対して、経口的な侵入はトレランスへ進むことが多い。ピーナッツアレルギーでは、患者自身の摂食量より、世帯のピーナッツ消費量が相関するという報告もある。家屋塵中の食物アレルゲンの除去(食後の清掃)が疾患管理の上で重要である。
これはあり得ることで大変興味深い。乳児の口囲の湿疹病変については「ヨダレかぶれ」と診断することが多かったが、食物アレルゲンの経皮的な感作も考慮する必要がある。年齢の近い兄姉がいると乳児のアトピー性皮膚炎が多いという印象を持っている先生もいるので、今後の検討が待たれるところだ。
-
第125回横浜市皮膚科医会例会から(平成22年4月3日)
7カ月の男児。全身の痒疹丘疹と発熱。パッチテストでクロムが陽性。授乳中の母が、妊娠中からチョコレート、ココアを多く摂取していた。食物として口から入る微量金属は、90~99%が便から排泄されるが、1~10%は腸管から吸収され、血中に入り、その一部が汗や母乳にしみ出してくる。この症例では、母乳中のクロムが原因の全身型金属アレルギーが発疹の原因と考えた。
母乳のパッチテストをやるとどうなるのだろう。同様に異汗性湿疹でも汗のパッチテストが陽性の例があるのだろうか。なお金属塩負荷の代わりに行う誘発試験は、オートミール100g、大豆シチュー100g、チョコレートケーキ100gを連続4日摂取させ、増悪するかをみるとよいとのこと。なかなか、奧が深い。
-
第125回横浜市皮膚科医会例会から(平成22年4月3日)
むずむず脚症候群(restless legs syndrome:RLS)がビ・シフロールの適応取得によって注目されてきた。皮膚科にも来院する可能性があると言うことで、説明を受ける機会がある。足の不快感、かゆみ、虫がはうような、といった感覚の異常により、足を動かさずにはいられない状況に陥り、睡眠障害を来す疾患とされ、人口の2-5%が罹患しているという。皮膚科外来にも足がむずむずするという患者が来ることがあるが、はたしてドパミン作動性パーキンソン病治療剤の投薬まで必要な病態なのか、注目してみた。足のむずむずは妊娠後期に悪化して出産後に改善する、夜ふとんに入るとかゆくなる、冷え性が多いなど、循環系の異常が関与していると思われる症例があり、むずむず感がユベラの投与によって、50%の患者で改善傾向を認めた。
外来に100人患者が来れば2-5人はこの疾患、というのは信じがたい。足がむずむずする=むずむず脚症候群でないのは承知したが、紛らわしい。直訳の下肢静止不能症候群を使ってもらった方が、皮膚科医にとってはありがたい。
-
ベリナートP勉強会から(平成22年3月18日)
遺伝性血管性浮腫(HAE)の検査。まず発作時のC3正常、C4低値、CH50低下がある。C1インヒビター活性(保険適応)が低値を確認。次に病型の確認で、家族歴がある場合、C1インヒビター定量(保健適応外)が低値ならtype1、正常ならtype2。家族歴がない場合は血清C1q(保健適応外)を測定し、低値ならば後天性血管性浮腫の可能性がある。なお、C1インヒビター活性が正常の場合はtype3(きわめて稀)か薬剤性(降圧剤やエストロゲン製剤)を考える。
発作時の治療はC1インヒビターの補充療法(ベリナートP)が適応となり、喉頭浮腫には救命救急措置も必要となる。また長期予防にはトランサミンの内服が有効という。2010年に補体研究会がガイドラインを発表した。いつも疑ったときの検査の段取りに迷うので、しっかり覚えておこう。
-
第13回横浜デルマカンファレンスから(平成22年3月11日)
自分がHIVに感染していることに気が付かず、エイズを発症して初めてHIV感染に気付くことを「いきなりエイズ」という。HIV感染者全体における「いきなりエイズ」の発生率はは、2000年には41.6%、2009年は29.7%と年々減少しているが、報告件数は年々増加している。HAART療法でHIVに感染してもAIDS発症を抑えることが可能になり、生命予後は改善したが、AIDS発症前のHIV感染者の2年後の生存率が99%であるのに比べ、「いきなりエイズ」患者では80%であった。皮膚科医は「いきなりエイズ」患者を診る機会が稀ではないので、注意が必要である。
いまだに発症すると20%が2年で死亡するということ。患者にHIV検査を勧めることはあまりしてこなかったが、少し考えをあらためようと思う。
-
神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成22年2月25日)
STAT3は乾癬のヒト表皮で活性化していて、さらに表皮特異的な活性型Stat3トランスジェニックマウス(K5.Stat3C)にTPAによる接触皮膚炎を起こすと、乾癬が生じることから、乾癬の表皮病変の最終段階に関わっていると考えられている。これまで、STAT3 decoy核酸が乾癬モデルマウスで有効であることを確認したが、最近、低分子のStat3特異的阻害薬(Ochromycinone, STA21)が開発され、その外用がヒト乾癬に有効であることを確認している。
これは期待ができそうだ。STAT3が乾癬と同様に活性化している日光角化症にも有効とのこと。どんな形でSTA21が臨床に登場するか、楽しみである。ちなみに、日光角化症は乾癬の病変の上には出ないとのこと。確かに共存しているところはみたことがない。
-
第73回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成22年2月21日)
カンボジアでの生魚で生じた有棘顎口虫によるcreeping disease。抗寄生虫薬の内服でも腹痛と皮疹の出没が続いたが、発症5カ月後に切除でき、治癒に至った。皮下に移行した寄生虫は通常1日30㎝ほど移動するが、イベルメクチンの内服はその移動速度を遅くするので、虫を捕まえやすくする効果がある。
その場で虫が死ぬのではないとわかった。腸管を破って外に出たときの穴はどうなる?、皮内に入った虫の寿命は?、途中で死んだら異物肉芽腫になる?、など素朴な疑問もいくつか残った。
-
第73回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成22年2月21日)
家族歴のある31歳男性。指腹部、爪甲下の痛みで発症。指尖部から皮膚の萎縮が始まり全指に拡大していった。角質増生を伴った爪甲下の皮膚が延長し、爪狭に長く癒着するための剥離障害が原因。指腹側翼状爪を呈し、爪甲が下に引っ張られるため爪自体が白くみえる。痛みのため廃用を来たし、指自体が痩せていくという経過を考えた。
爪の各部位の名称が意外とわかっていない事に気づいた。爪下皮の延長はSLEの患者でみているが、循環障害が原因だろうと考えていた。爪と皮膚の剥離障害とは思わなかった。記載皮膚科的には教科書にも出ていないので、どの文献が参考になったか知りたいところだ。
-
北里真菌症研究会から(平成22年2月18日)
T. tonsurans感染症の話題。格闘技競技者に蔓延していることは周知の通りだが、どんなグループでも感染者は3割程度で、「オレはうつらない」という競技者がいて、菌に対するaffinityの違いがあるらしい。さらにコンタクトスポーツの出場停止の話へ。レスリングの国際ルールでは単純ヘルペス(herpes gladiatorum)とブ菌感染があると、競技への出場停止を定めているとのこと。
神奈川県レスリング協会は、県内で開かれる大規模な大会で医師による診断を選手に義務付け、2010年1月に行われた高校生のレスリング関東大会では、皮膚科専門医が参加全選手を診察し、感染が確認された1人が出場停止となった。平成24年度からは全国の中学校で武道が必修化されるとのことで、感染症に対する基準作りが必要と思った。われわれ皮膚科医も、コンタクトスポーツの国際ルールについて、少しは知ってべきかもしれない。
-
アトピー性皮膚炎治療研究会第15回シンポジウムから(平成22年2月6日)
アトピー性皮膚炎の皮膚症状(状態)からみた漢方治療についての総説。1)充血性の紅斑には清熱剤、15黄連解毒湯、34白虎加人参湯 2)うっ血性の紅斑には駆於血剤、25桂枝茯苓丸、105通導散 3)湿潤性湿疹には利水剤、18桂枝加朮附湯 4)乾燥した亀裂・鱗屑には補血潤燥剤、71四物湯 5)苔癬化には駆於血剤、25桂枝茯苓丸 6)かゆみには去風剤、22消風散、86当帰飲子。
何度聞いても覚えられない。しかも、治療に困ったときもひらめかない。根本的に苦手ということだが、患者が希望したときのカンニングペーパーということで、保存しておく。
-
第35回横々会から(平成22年1月28日)
液状変性という言葉の定義。SLEや皮膚筋炎の紅斑部では多糖類の沈着によって基底膜が厚くなり、それが下に垂れ下がってくるようにみえる状態を液状変性という。決して基底層が水疱のようにみえる状態を指す言葉ではない。これの証明にはPAS染色が有用である。
学会でも誤った使い方があるようだ。嫌われそうだが、若い皮膚科医の教育のため、その場で指摘する必要がありそうだ。
-
日本皮膚科学会第829回東京地方会から(平成22年1月16日)
マレーシア人男性の症例。臀部と陰股部の疣状褐色局面。肺結核あり。健康保険を持たず、医療から隔絶されていた。結核予防法に基づく保健所への届出とともに、医療費給付について確認し患者への情報提供を行った。
一般患者での医療と従業禁止・命令入院患者の医療では請求が異なると知った。また、一般患者では初診や再診料、内科的治療による入院料や結核菌のPCR、CT、MRIも公費負担にならないなど、結核予防法はなかなか難しい。
-
日本皮膚科学会第829回東京地方会から(平成22年1月16日)
成人男性の背部に生じた典型疹。外陰部以外に生じた場合は水疱形成と毛孔性角栓を伴うことが特徴で、ダーモスコピーではmilia like cystとcomedolike openingsがみえることが多い。
診る機会は多くないが、ダーモスコピーがこういった疾患にも有用だと知った。今後も腫瘍以外にも様々な疾患での観察が行われ、英語のやや複雑な表現が増えていくだろう。なかなか覚えずらく、大変である。
-
第30回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成22年1月9日)
強皮症では皮内や皮下に石灰沈着を合併することがあるが、2㎝以下であれば、ワーファリンの内服が有効である。0.5mgから1mgの低容量でよく、2~3週間で消えることもある。
出血傾向から血管壁に石灰沈着が逆に発生しやすそうだが、意外であった。なお、H2 blockerのCimetidineが、透析患者の石灰沈着症に有効という報告もあるようだ。いずれも機序は不明とのこと。
-
第30回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成22年1月9日)
動抗セントロメア抗体、抗Scl-70抗体がともに陰性で、抗tRNAポリメラーゼ抗体陽性の強皮症がある。日本人では6%の強皮症患者に陽性で、陽性例の多くはdiffuse型である。急激に発症する、広範囲に及ぶ、ステロイド内服に反応する、肺線維症なし、血管障害は10%と少ない、10%に腎クリーゼが生ずるという特徴がある。
一般的に強皮症の治療としてPSL15mg/日以上を使用すると腎クリーゼが起きやすいといわれているそうだ。上記のような症状を伴う強皮症にはもちろんのこと、治療でPSLを用いる際には、前もって抗体の有無を確認する必要があるとのこと。なお、検査は平成22年5月1日から保険適応になった。
-
第5回筑駒医師会から(平成21年12月29日)
動物実験ではカロリー摂取を抑制すると寿命が延び、この現象は酵母においても同様であることが知られている。その際、長寿遺伝子として知られているSIRT1が活性化し、インスリンシグナルに関連する遺伝子の発現が抑制され、長寿に結びつくと考えられている。SIRT1を活性化すれば、長寿に結びつくという構図だが、赤ワインに含まれているレスベラトロールという物質がその活性を持っていることがわかった。ただし大量に摂取しないとダメとのこと。レスベラトロール以上にSIRT1活性を高める薬剤は、2型糖尿病や肥満の治療に加え、長寿をももたらすかも知れない。
たくさん食べてもSIRT1活性化剤を補給すれば大丈夫という時代が来るのかも知れない。SIRT1は記憶力強化や脳活動の活性化にも重要な役割を果たしている可能性が高いとの報告があり、アンチエイジング剤としても使えそうだ。皮膚でも何らかの働きがあるのだろうか。
-
第5回筑駒医師会から(平成21年12月29日)
日本人若年女性の間に流行している不健康な痩せが、正期産2,500g以下の低出生体重児を増加させている。胎児が子宮内で低栄養状態に曝されると、これに適合するように代謝メカニズムの「プログラミング」がおこり、出生後に栄養状態が良好となったあとも、すでにプログラムされた倹約的な省エネ体質が持続し、その結果として2型糖尿病などのメタボリックシンドロームを発症するリスクが高くなる。
なるほど、次の世代にも影響していくということで、社会的風潮を変える必要もあるということだ。なお、女性は妊娠・出産・授乳という大きなイベントに対応できるように、皮下に脂肪をためている。閉経した後は、男性と同様に内臓脂肪に変わっていくとのこと。
-
神奈川県皮膚科医会第131回例会から(平成21年12月6日)
褥瘡などの創傷が遷延する場合、亜鉛欠乏があれば、それの補充療法を行うことがある。亜鉛は蛋白合成に関与する多くの酵素の発現に必要で、糖、脂質、拡散の代謝にも必須であるが、亜鉛の過剰摂取は銅や鉄の代謝に拮抗し、貧血の原因になることがあり、感染リスクの上昇や嘔吐などの合併症などの弊害もある。また、亜鉛の欠乏が褥瘡発生のリスクにはなっていない。
長期に漫然と投与するのはよくないようだ。面倒でも血中亜鉛値を時々モニターする必要がある。注意しておこう。
-
第35回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成21年12月3日)
TIP-DC(TNF-α、iNOS producing dendritic cell)は真皮に存在するCD11a陽性の奇妙なmyeloid DCで、Th17細胞の増殖維持に必要なIL-23を産生する。TNF-αはそれ自身もTIP-DCの活性化維持に必要である。これを抑制する抗TNF-α製剤や、IL-23のp40に対する抗体であるustekinumabが有効なことから、乾癬はTh17細胞依存性の疾患であると最近では考えられている。Th17細胞はIL-17のほかIL-22も産生し、このIL-22がStat3依存性に表皮細胞の増殖を引き起こすことがわかった。表皮細胞増殖を抑制するINF-γが乾癬で証明される理由も、Th17細胞による増殖に拮抗するためと考えられている。さらに、IL-17を産生せず、IL-22のみを産生する新たなヘルパーT細胞、Th22細胞が発見され、乾癬の病変部に存在することが証明された。この細胞の分化、活性化に関与すると考えられるのが、pDC(plasmacytoid dendritic cell)と呼ばれる細胞で、乾癬の初期病変に存在している。以上2つの経路で乾癬の病態が形成されている。
私が医者になった頃に比べて格段に進歩した。乾癬の病態の研究は、「なぜこの薬剤が有効なのか」の証拠集めから始まっているようだ。活性型ビタミンD3外用薬、シクロスポリン、抗STAT3デコイ、抗TNF-α製剤など。今後、開業医でもすんなり使える薬剤が出てくるとよいのだが、。
-
第25会日本臨床皮膚科医会三支部合同学術集会から(平成21年11月29日)
医療におけるwin-winとは、医師と患者の相互の利益を求める心と精神のことであり、お互いに満足できる合意や解決策を打ち出すことである。トラブル解決の最終的な目標として、それぞれの当事者が当初持っていた案ではなく、相手や自分の考え方に限定されない全く新しい第三案の存在を確信することである。また、トラブルの際に裁判手続に代替する解決法を、ADR(Alternative Dispute Resolution:代替的紛争解決)と呼ぶ。平成16年に12月に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が公布されている。ADRは紛争当事者の、合意に基づく自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ、公正かつ適正に実施され、かつ、専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図ることが目標である。
法律や精神論は苦手だが、何となく理解できた。win-winな関係は一つ一つの診療について、達成したいものである。
-
第51回神奈川医学会総会から(平成21年11月23日)
2007年の年度末に、横須賀で麻疹の大流行があった。小学校2年の8歳児がほとんどで、その6割はワクチン接種者であった。患者が2000年頃に接種した麻疹ワクチンの多くは千葉血清研究所製であった。このワクチンの接種者のPA抗体は74%が64倍以下で、特にC5-1のロットの接種者では、61%が16倍未満で、低効果の粗悪品だった。横須賀市は2008年に、8歳児に麻疹ワクチンの再接種を行い対応した。千葉血清研究所は2002年に会社を閉鎖している。
こんな事件があったとは恥ずかしながら知らなかった。多くの接種歴を効き、採血をし、それを集計するという労力が必要な仕事に開業医が携わったことに感銘した。責任問題はともかく、過信は禁物ということは、あらためて念頭に置いておこう。
-
平塚市医師会講演会から(平成21年11月19日)
創傷のcritical colonization(クリコロ)は、表在性の細菌負荷が増加し、創感染に陥りそうな状態で、臨床的には滲出液の増加、脆弱で膿苔を付ける不良肉芽の所見を示すと理解されている。クリコロの早期発見のためには、さらにサーモグラフィーが有用で、正常部に比べて高温になるため、赤くみえる。クリコロがあれば、バイオフィルムを取って通気性をよくし(ラップはダメ)、血流の改善を図る必要がある。
クリコロについては色々な意見があるようだが、個人的には、まずまず同意できると考えている。最近は簡易式のサーモグラフィーもあるので、導入は可能かもしれない。また、マイクロデブリードマンにはMIST Therapyという超音波による方法が有効とのこと。陰圧持続吸引も含めて、近頃は機器を使う慢性創傷の治療が、ずいぶん普及してきたものだ。
-
平塚市医師会講演会から(平成21年11月19日)
褥瘡を含めた創傷にハチミツを主成分とする外用剤が開発され、特に欧米で評判がよいらしい。抗菌作用があり、MRSAにも有効で、さらに壊死組織の除去にも働き、湿潤環境も維持できるらしい。ニュージーランドのCOMVITA社が地元のハチミツを用いて生産。MEDIHONEY Antibactrial Wound Gelとして販売している。
ホームページをみると、茶色のゲルで、ユーパスタ軟膏に似ている。日本にも支社があるが、ハチミツ入りのスキンケア用品だけで、創傷用の外用剤は取り扱っていないようだ。25年間にイソジンシュガーの話を聞いたときも、グラニュー糖がと思ったが、今後はハチミツも一般的になっていくのだろうか。
-
某社光線療法セミナーから(平成21年11月15日)
乾癬患者への生活習慣に関する生活指導の話。1) 喫煙は多いほど重症、2) 飲酒はその量と重症度が関係ありそうで、大酒は避ける、3) 栄養はバランスよく、EPA、リノレン酸、ビタミンD3を摂ること、4) メタボリック症候群が多く、心筋梗塞の合併もあるので、適度な運動を、と説明するのがよい。
さっそく明日から使えそうだ。メタボとの関連は興味がある。乾癬とアディポサイトカインとの関連などもいずれ明らかになってくるだろう。乾癬の病因が、どうもTregやTh17だけではないような気がする。
-
某社光線療法セミナーから(平成21年11月15日)
ナローバンドUVBは、MEDで比較すると、ブロードバンドUVBよりも発癌性は低く、1/3程度と考えられる。実際のこれまでの経験から、光線療法を受けていない正常人と比べると、基底細胞癌を少し増やすこと、有棘細胞癌は不変であること、メラノーマとは無関係であることがわかってきた。
話を聞く前には若干不安もあったが、これですっきりした。なお、エキシマランプは295nm以下の、光発癌と関連する紫外線が漏れるらしく、ここをカットするために、297nmと300nmの2枚のフィルターが付いていて安全性を確保しているとのこと。機会があれば使ってみたいと思った。
-
某社光線療法セミナーから(平成21年11月15日)
尋常性白斑が治療でよくなるか、ならないかの判断は、ミニグラフトをするとよい。白斑部にグラフトした正常皮膚の周囲から白斑が改善してくる場合には、ナローバンドUVBやエキシマライトでも改善するが、そうでない場合にはどんな治療に対してもきわめて抵抗性である。
今までは全く経験がない。効く・効かないの判断をしてから光線療法をすべきか、考えてしまった。ちなみに、ナローバンドUVBのMEDは一般的には0.6J/cm2ぐらいが目安。白斑の場合は、照射のあとで少しピンクになるぐらいでないと効果が現れにくいことを経験しているとのこと。大いに参考にしたい。
-
第827回日本皮膚科学会東京地方会から(平成21年11月14日)
HER2を過剰発現する乳ガンに対して、分子標的薬ラパチニブを使用。内服9日目から発熱を伴う紅色丘疹が出現した。発疹出現時には可溶性Fas ligandが上昇していた。ガンに伴うFasに、拮抗的に誘導された多くの可溶性Fas ligandが、皮膚のFasとも結合し、アポトーシスを起こした可能性がある。
分子標的薬が使われるようになって、薬疹もずいぶん認識が変わったものだ。大学や病院を離れると、皮膚科はまだしも、他科の医療の進歩にはついて行けなくなる。
-
第827回日本皮膚科学会東京地方会から(平成21年11月14日)
ミノマイシンによる色素沈着は有名な副作用であるが、沈着している物質により以下の3型に分けられる。typeⅠはヘモジデリン、typeⅡは鉄、typeⅢはメラニンである。組織の特染ではMasson-Fontanaで基底層を観察し、Berlin-blueで真皮を見ること。ミノマイシンは鉄とキレート結合するため、真皮に蓄積することが多い。
不勉強だった。何となく皮膚はメラニンだと思っていた。歯の黄変の原因は、歯の象牙質のカルシウムにミノマイシンがリン酸塩として沈着するため、つまり、ミノマイシンそのものの色とのこと。意外に複雑である。
-
第39回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成21年11月7日)
蕁麻疹の私見による分類。原因がはっきりしていて1日で終わる急性蕁麻疹。特発性の慢性蕁麻疹のほかに、10日以内に消褪し、小児によくみられる上気道の感染症に併発する蕁麻疹を10日蕁麻疹と呼んだ。
臨床ではよく遭遇する。感染症に伴う症例は慢性蕁麻疹とは違うムンテラをしている。10日もかからない印象があるが、こういう分類は悪くないと思う。さっそく、日常診療でこの言葉は使わせてもらおう。
-
第39回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成21年11月7日)
表記の一覧表が呈示された。ヒスタミン(ホウレンソウ・トマト・ナス・トウモロコシ・タケノコ・エノキ・ジャガイモ・鮮度の落ちた肉・チーズ)、セロトニン(トマト・バナナ・パイナップル・キウイ)、アセチルコリン(トマト・ナス・タケノコ・ヤマイモ・サトイモ・ピーナッツ)、サリチル酸化合物(トマト・キュウリ・ジャガイモ・イチゴ・メロン)、ノイリン(塩鮭・冷蔵タラ・古い青魚)、トリメチルアミン(イカ・カニ・エビ・アサリ・ハマグリなどの魚介類)、チラミン(チーズ・ニシン塩漬け・アボガド・オレンジ・バナナ・トマト)
別に覚えるつもりはないが、蕁麻疹の患者では一応、念頭に置いておきたい。トマトは仮性アレルゲンの宝庫と言えそうだ。
-
第39回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成21年11月7日)
アナフィラキシーは、肥満細胞-IgE抗体-ヒスタミンの経路のほかに、好塩基球-IgG抗体-血小板活性化因子(PAF)の経路で生じている可能性がある。マウスの実験であるが、ペニシリンでアナフィラキシーを起こすマウスから好塩基球を除去すると、ペニシリンを投与してもショックを起こさないことを確認した。ショックを起こしたマウスの好塩基球の表面には抗原と結合したIgG抗体があり、これがPAFを放出することが分かった。PAFは好中球のアポトーシスを誘導し、好中球が蓄積して炎症反応を増強すると考えられる。
ヒトではどうか。薬剤によるアナフィラキシーもプリックテストが陽性だと思う。やはり、IgEなのではないだろうか。
-
第39回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成21年11月7日)
通常、動物はマダニに刺された時、初回はたくさん血を吸われるが、2回目以降はその量が減少する。2回目以降のマダニ吸血部位の組織には多数の好塩基球が集まっているが、初回の刺し口周囲には見られない。好塩基球のみを欠損させたマウスでは、2回目以降のマダニによる吸血量に減少がみられない。マダニ抗体?で武装した好塩基球が血中にあると、マダニが付いた場合、その付着部位に集まり、マダニの吸血を阻止する。
マダニの抗原とは何かと疑問が残ったが、現象としては興味深いと思った。ダニの刺し口の組織をみる機会があれば、好塩基球の存在を調べてみたい。蚊など、ほかの吸血性の虫刺されも同じような仕組みがあるのだろうか。幼児の蚊刺症が大人に比べて重症化するのはよく経験するが、好塩基球が何らかの働きをしているかも知れない。
-
第39回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成21年11月7日)
薬疹の原因薬剤の同定に用いられるDLSTは、陽性になりやすい臨床型と原因薬がある。偽リンパ腫型(アムロジン、ディオバン、コニール)と丘疹-紅皮症型(バイアスピリン・ラシックス・ミオナール・プロスタール)は特に陽性になりやすく、有用である。他にも紅皮症型、DIHS、AGEPでも陽性率が高い。
臨床型を見ると、何の薬疹かが想像できる時もある。パッチテストの陽性率とも平行しているように思う。
-
第39回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成21年11月7日)
少量の食物の誤食でアナフィラキシーを生じる小児例に対して、tolerance inductionを根治療法と位置づける考え方が一般的になってきた。特に入院の上、閾値以下から毎回増量を図りながら、1日5回のアレルゲン食品を経口摂取する、rush SOTIを行い、鶏卵アレルギー12/12例、ピーナッツアレルギー4/5例で、長期的な経過を含めて有効だった。特異的IgEは急速期では変動はないが、6カ月で低下傾向、12カ月で優位な低下を認めたとのこと。
なお、経口感作はtoleranceを誘導し、経皮感作はtoleranceを遅らせることも明らかになったようだ。食事の後などに口囲に湿疹(接触皮膚炎)を起こす状態は避けるべきで、逆に摂食は積極的に試行するのが、よい食物アレルギーの治療と言えそうだ。食卓の上、床などには注意していても大人がこぼした食物アレルゲンが存在するという話もあるので、食事の後には掃除機をかけるのもよいらしい。
-
第12回横浜デルマカンファレンスから(平成21年10月22日)
ダーモスコピーは疥癬の診断に有用だが、乾いた鱗屑が付いていると、偏光のダーモスコピーで見たときに鱗屑が光って見えにくいことがある。このような場合は鱗屑をしめらせてから見るのがよい。エタノール綿でサーッと拭いてからゲルをのせるのもよい方法である。足蹠の色素性病変でも役に立つ、簡単な方法である。
足蹠に角化があるnevusで試してみたが、確かにこれは見やすくなる。これはみんなに紹介したい、ちょっとした雑学だ。
-
某誌誌上座談会から(平成21年10月16日)
薬理学の話。抗うつ剤には、ヒスタミンH1受容体に対する強い拮抗作用がある。第二世代の抗ヒ剤は抗うつ剤を改良したものがある。血液脳関門の透過性を低下させる官能基(-COOH、-NH2)を導入して、非鎮静性の抗ヒ剤が開発された。三環系抗うつ剤のドキセピンを改良したものがアレロック、四環系抗うつ剤のミアンセリンがアレジオンの元になっている。
患者に投薬する立場として、常に薬理学の基礎は大事だと思うが、構造式を見てイメージが沸くまではいかない。この話もかゆみに対する対応として、頭の片隅に入れておきたい。
-
第60回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成21年10月11日)
口唇ヘルペス発症の4日後、特に右三叉神経第2枝領域を中心に顔面全体に水疱と痂皮を生じ、体幹・四肢にも散発疹を伴った。上口唇、右頬の小水疱からはHSV1とVZVの両方が検出され、体幹からはVZVのみが陽性であった。カポジ水痘様発疹症に汎発性帯状疱疹が合併した症例と考えた。免疫異常、内臓悪性腫瘍は認めなかった。
臨床はカポジ水痘様発疹症で片側性の疼痛を伴った症例でもHSV1とVZVが同時に関与していたと、別の学会で報告されていた。状況によっては複数のウイルスが同時に再活性化するということは、考えておかないといけない。
-
第60回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成21年10月11日)
夏季に腋窩などの多汗部位に、魚が腐ったような独特の臭いを発する病態があり、魚臭症と呼ばれる。このうち、魚臭の原因となるトリメチルアミンの代謝酵素である、フラビン含有モノオキシゲナーゼをコードするFMO3遺伝子の変異のため、未変化体が尿、汗および呼気などに排泄される遺伝性疾患を魚臭症候群(fish odor syndrome)あるいはトリメチルアミン尿症と診断する。
報告の症例は疎毛と骨格の異常が主訴で、最終的にTRPS1遺伝子変異があり、trichorhinophalangeal syndrome typeIと診断された。FMO3に変異はなく、TRPS1も魚臭の原因になるとのこと。においも遺伝と再認識した。
-
第60回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成21年10月10日)
悪性腫瘍や重症の肝障害、脳血管障害などのカヘキシー状態にある患者の掌蹠に、小斑状の不整形な褐色~黒褐色の色素斑が多発することがあり、罹病期間や重症度に比例して出現頻度が高い。ダーモスコピーでは皮丘パターンで、組織でも皮丘に相当する表皮の厚い部分(crista profunda intermedia) に一致した色素の増加が認められる。
特養の入所者で見たことがある。Peutz-Jeghers症候群の色素斑と似ているということになるが、同様の機序か。ところで、Peutz-Jeghers症候群の色素斑の原因は、わかっているのだろうか。
-
第60回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成21年10月10日)
高齢者の白癬菌性毛瘡。飼い猫から感染したあごひげ部の紅斑と膿疱。Wood灯を当てるとヒゲ自体が黄緑色に光った。鏡検では毛包外小胞子菌寄生がを認め、培養ではMicrosporum canisが陽性。ラミシールの内服で皮膚症状は改善したが、ヒゲの蛍光は半年続き、菌要素も陽性だった。
Microsporumが光るとは知らなかった。滅多に見られない写真だった。鏡検に勝るとは思えないが、菌が死ぬと蛍光も消失するので、治療経過の目安になるとのこと。
-
第5回神奈川皮膚アレルギー疾患研究会から(平成21年10月3日)
日光蕁麻疹では作用波長と抑制波長があることが知られている。患者血清に作用波長を当て、皮内反応を行うと、31例中24例で陽性であった。作用波長と抑制波長の両方を当てた血清でも陽性を呈するので、抑制波長が血清に対してどのような反応を起こしているのかはまだよくわかっていない。なお、日光蕁麻疹は、ケガのあと、出血をしたような所に出やすく、何らかの物質の局所での濃度が問題なのかも知れない。
これも不思議な疾患である。ケガのあとに出やすいというのは知らなかった。慢性蕁麻疹では凝固系の異常を伴うことがあるとも言われているので、血清だけでなく、血小板や凝固因子などの関与もあるのかもしれないと思った。
-
第5回神奈川皮膚アレルギー疾患研究会から(平成21年10月3日)
サバの蕁麻疹は、1)アニサキスアレルギー、2)魚アレルギー、3)ヒスタミン中毒の3つの原因がある。3)では通常消化器症状を伴う。アニサキスは通常魚の腹腔内に寄生するが、サバ、サンマ、サケ、マス、ニシン、タラ、イカでは、魚肉内に侵入していることがあるので、原因となりうる。アニサキスアレルギーは35kdのトロポミオシンが主要抗原で、蛔虫と交叉する場合があり、豚ホルモンでアナフィラキシーを来たした症例を経験している。
アニサキスについては、実際はもう少しあると思われるが、確定診断に至った症例をなかなか経験しない。採血の際には特異的IgEの検査を忘れないようにしよう。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成21年10月1日)
RAに伴って生じた下腿潰瘍の症例。RAの活動性はactiveだが、臨床は静脈うっ滞性。各種外用で改善せず。白血球除去療法(LCAP療法)の適応を考慮したという話。LCAPは炎症性腸疾患での適応を想像するが、治療抵抗性で、全身症状の強い急速進行型RAで、腫脹関節数6ヶ所以上、ESR≧50mm/hあるいはCRP≧3mg/dLの場合、保険適応になるとのこと。
RAの下肢潰瘍は、1)関節の変形に基づく物理的障害、2)血管炎ないし動脈閉塞、3)静脈うっ滞性、4)結合織の変性に伴う経表皮性排泄、のほか、5)壊疽性膿皮症の合併を経験している。5)では炎症性腸疾患と同様、確かにLCAPが有効な例もあるだろう。またLCAP後にはCD34陽性細胞が増加することが知られていて、潰瘍部に骨髄の幹細胞が集まってくる可能性もあるとのこと。なお、顆粒球除去療法(GCAP)の保険適応は潰瘍性大腸炎とクローン病のみである。
-
ヒトパピローマウイルス講演会(平成21年9月17日)
HPVの遺伝子多型。HPV6型、11型は尖圭コンジローマの原因として知られているが、外陰部、肛囲、腋窩などの湿っぽい部位に付いたときには尖圭コンジローマになるが、下腹部などの乾いたところに付くと、脂漏性角化症になることが知られている。
老人性疣贅とHPVの関連は、あるようでないと思っていたので意外だった。最近はあまり切除せず、液体窒素で治療することが多いので、組織を見ることが少なくなった。なお、子宮頚癌ワクチンのガーダシルはHPV16, 18以外にもこの6,11を標的に加えた4価のワクチンである。
-
ヒトパピローマウイルス講演会(平成21年9月17日)
HPVの侵入経路の話。手・足の尋常性疣贅は初期の症状を見ると、皮丘に一致し、組織では表皮突起内のエックリン汗管周囲に発生していた。また扁平疣贅の一部や尖圭コンジローマでは初発疹は毛孔に一致している。病理では毛隆起部、いわゆるバルジ領域に発生していた。いずれも表皮ないし毛包の幹細胞の局在部位と考えられている。
HPV感染の標的が幹細胞である話は以前に聞いたことがある。今度ダーモスコピーのfurrow inkを使って、じっくり見てみよう。
-
第34回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成21年9月3日)
扁平苔癬の講演の中での話題。古典的な扁平苔癬では肝機能障害が多いといわれていた。その後角層を含めた表皮の変化が少なく、基底層の変化が強いものが多くなってきて、それらがエンボール、シンナリジンなどの薬疹が原因であった。それらの中には、皮膚生検で角層内に核がクリッと残るparakeratosisを認める例があり、UVとの関連を示す、photo-lichenoidの反応をきたすものがあった。
苔癬型薬疹は、最近ではあまりお目にかからないが、1980年代は確かにエンボール疹、シンナリジン疹という名称で呼ばれるほど多かった。時代の流れを感じる。ただ、病理を見るだけでUVとの関連がわかるというところは、若い世代にも伝えていかなければならない。
-
ネオーラルアトピー性皮膚炎治療講演会(平成21年9月2日)
サンディミュンではピーク値が内服後何時間で生じるか予測できなかったために、トラフ値をモニターしていたが、ネオーラルになってからはピーク値の再現性が向上した。現在、ネフローゼ症候群などではC1(内服1時間後の血中濃度)、C2(同2時間後)を用いて用量調節が行われている。C1がピークになる人が50%、C2がピークになる人が30%で、肥満や高TG血症があると遷延する。また食後内服だと10%の人がピーク値を示さないので食前1回投与がよい。C1ないしC2を800~1000ng/mlに持っていくように用量を調節する。具体的には、ある月はC1を測定、また翌月はC2を測定し、さらにいずれも700ng/ml以下だったら、C3を測定し、用量を決定する。
具体的な内容でとても参考になった。外来患者でC1、C2を2回同じ日に測定するのは難しいと考えていたので、なるほどと思った。有効性を発揮する用量設定についてもさっそく明日からの診療に役立つと思った。
-
ネオーラルアトピー性皮膚炎治療講演会(平成21年9月2日)
臓器移植後のシクロスポリン腎症の話題。シクロスポリンによる腎障害は、尿細管と血管への作用による。尿細管への機能的障害により、血清Mgの低下や血清K上昇となって現れる。また大量投与によっては、近位尿細管に巨大ミトコンドリア、空胞形成、Ca沈着などの構造的変化が起きるが、いずれも減量や休薬によって回復する。血管への作用は特に輸入細動脈の血管収縮が原因で、腎血流量の低下による血清クレアチニンの上昇が一般的であり、大量の場合にはangionecrosisを生じるが、頻度はまれで、休薬によって、remodelingにより改善することがしばしばである。低用量の使用では、急性腎不全の懸念は不要で、併用薬による血中濃度上昇、高齢者、高血圧症の合併、脱水、NSAIDsの併用などのrisk factorに注意すれば、慢性腎障害の発現は低下する。
乾癬、アトピー性皮膚炎での使用例が若干だが増えてきた。血圧とクレアチニンには注目していたが、Mgに関しては知らなかった。さっそく次回からは測定しよう。
-
北里大学皮膚科同門会から(平成21年7月19日)
シェーグレン症候群では白斑を伴うことが多い、同様に尋常性乾癬、膿疱性乾癬を伴う症例も報告されている。これらの皮膚症状は慢性甲状腺炎にも伴うことがあることが知られていて、シェーグレン症候群と慢性甲状腺炎の併発もまれではない。白斑、乾癬の皮膚症状とこれら2疾患の関連は、STAT3の過剰反応で説明できるかもしれない。
まったく関連しそうもない疾患や些細な症状を細かく記載することによって、思わぬ関連が見つかることもあると、感心した。なお、シェーグレン症候群では最近、抗αフォドリン抗体というのが高率に見つかるらしい。
-
第33回日本小児皮膚科学会から(平成21年7月4日)
生後3カ月から四肢、腹部に紫斑と小結節。生検では真皮から皮下に異所性の骨形成。血清Caは正常、血清Pは高値。外因性のPTH負荷に対し尿中cyclic AMP及び尿中P排泄促進反応の両者に障害が認められPHPⅠa型と診断した。母にも円形顔貌、低身長、鼻根部陥凹、短指症、肥満などの特徴的所見があり、同症と診断。皮膚骨腫は、低身長、テタニー発作、精神発達遅延などの症状に先立ち、もっとも早期に出現し、58%の症例で初発症状となるため、重要である。
昔の知識が少しよみがえった。PHPⅠ型は、PTH受容体からアデニル酸シクラーゼに情報を伝達するGs蛋白活性の低下を認めるⅠa型、アデニル酸シクラーゼのcatalytic unitの異常が想定されるⅠc型と、これらに異常を認めないⅠb型に細分される。Ⅰa型ではGsαサブユニット遺伝子(GNAS)の変異が原因とのこと。
-
第33回日本小児皮膚科学会から(平成21年7月4日)
ソフトキャンデー摂取後10分後に呼吸苦、全身の膨疹、血圧低下をきたした。ワクチンアレルギーの既往はなし。ゼラチンのプリックテスト、IgE-RASTがともに陽性だった。通常ゼラチンアレルギーはゼラチンの経口摂取によって感作されることはほとんどないとされているて、この症例でもいつ、何によって感作されたかは不明であった。
ゼラチンは多くのカプセル剤、一部の錠剤、散剤、トローチ剤、坐剤、注射剤、経腸栄養剤、貼付剤など幅広い薬剤にも含まれていることがわかった。ゼラチンアレルギー児に対するカプセル剤等のゼラチン含有経口剤の使用にも慎重な対応が必要そうだ。
-
第33回日本小児皮膚科学会から(平成21年7月4日)
12歳の女児。右手の乾燥を自覚していたが、その3か月後に右手のしびれ、疼痛が始まった。ほかに右前腕のわずかな浮腫と軽度の熱感を伴っていた。精査の結果CRPS(複合性局所疼痛症候群)typeⅠと診断。CRPS typeⅠでは疼痛のほか、交感神経の関与を想像させる発汗の異常(亢進ないし低下)、浮腫、血流の変化(皮膚温の左右差)、皮膚や爪の萎縮を伴うことがあるので、皮膚科でも診る可能性がある。
皮膚科からの報告はすべて女性で上肢の病変とのこと。皮膚病変がなくて、疼痛だけを伴う症例は、つい神経だから整形へ行くようにとムンテラする。整形へ行ったが何もなかったという患者には、この疾患が当てはまるかもしれないと思った。
-
日本皮膚科学会第824回東京地方会から(平成21年6月20日)
風俗業の女性。頬粘膜に発赤・びらん、歯肉の発赤・腫脹、舌には厚い白苔。鏡検で回転するトリコモナス原虫を多数確認。口腔内のトリコモナスは正常でも20%、歯周病があると60%で陽性。女性の外陰部そう痒症のほか、腋窩にも皮膚病変をおこすことがあるとのこと。
粘膜の病変については、診断をつけたことがない。詳しく聞かなかったが、腋窩にはどんな病変を起こすのだろうか。
-
日本皮膚科学会第824回東京地方会から(平成21年6月20日)
SLEに伴う多発性痛風結節の症例。高尿酸血症の原因として、ループス腎炎に対するループ利尿剤の長期使用によると考えられた。臨床は灰白色の結節で典型だが、痛みはなかった。低補体血症があると、補体の活性化が生じず、痛風発作が起きにくいと言われているとのこと。
必然的な組み合わせにも思える。痛くない痛風結節を見たら、SLE→腎炎→フロセミドとつながる訳である。こういう連鎖がおもしろい。
-
日本皮膚科学会第824回東京地方会から(平成21年6月20日)
発熱と両側耳下腺腫脹でムンプスと診断された男児。3病日から胸骨前部に淡い赤みを伴い、圧痛のある腫脹を生じた。臨床からは皮下軟部組織の浮腫と考えられた。無治療で経過を見たところ5日目には自然消褪。これを、Gellis signといい、ムンプスの1~6%にみられる症状であり、顎下腺腫大のために生じるリンパ浮腫が原因と考えられている。
聞いたことも見たこともなかった。耳鼻科や小児科のドクターはたびたび遭遇しているのであろうか。近所の先生に聞いてみて、もしあったら紹介してもらおう。これは是非、触れてみたい症状である。
-
第7回皮膚膠原病研究会から(平成21年6月13日)
シェーグレン症候群の下口唇生検における病理所見の時間的経過の報告。発症初期に分泌部周囲のリンパ球浸潤があるのは周知の通りだが、20年後にあらためて生検を行った数例の症例では、1)現在でも細胞浸潤がある例、2)細胞浸潤が少なく導管が拡張している例、3)小葉が完全に萎縮している例に分類できた。ステロイドの内服がdry mouthの発症や増悪に有効であったと考えられる症例もあり、下口唇生検を複数回行い、組織反応の変化を見ることも、臨床上有用であると思われた。
指摘の通りであろう。初回の診断の時にしか行わない施設がほとんどではないだろうか。どんな疾患についても当てはまるので、長く経過を見て、臨床と病理を比較していくのが皮膚科臨床医の努めと感じた。
-
第7回皮膚膠原病研究会から(平成21年6月13日)
従来、CNS lupusと呼ばれていた経過中に神経・精神症状をきたすSLEを、最近ではNeuropsychiatric SLE(NPSLE)と呼ぶ。主たる症状は、歩行障害を含む局所的な運動神経障害、うつ、認知障害、けいれん、頭痛などで、SLEの40%ほどに認めるという。髄液中のIL-6の上昇(4.3pg/ml以上)のほか、自己抗体としては抗リボゾームP抗体、抗グルタミン酸受容体(NR2)抗体、抗ニューロナル抗体などと関連が深いとされるが、疾患活動性の指標、たとえば抗DNA抗体や血清補体価とは相関しない。ステロイド精神病との鑑別が重要である。治療はステロイドパルス、エンドキサンパルス(IVCY)に加えて、最近ではリツキシマブの有用性を指摘する報告が多い。
あまり皮膚科の文献でもお目にかからず、古い知識で固まっていたので、ドキッとした。若い先生に教えてもらうこともたくさんあるものだ。病棟勤務の頃の悩み・迷いを思い出した。
-
第7回皮膚膠原病研究会から(平成21年6月13日)
SLE、シェーグレン症候群、MCTD、皮膚筋炎を基礎疾患とし、臨床的に好中球性紅斑、滲出性紅斑、あるいはやや浅めの結節性紅斑が生じた場合、これを生検すると、真皮中層に膠原線維の変性があり、それを取り囲むように、一見好中球の核破砕にも似た細胞浸潤(CD68陽性のマクロファージ・組織球系の細胞が主体)を認めることがあり、これを膠原線維attack型組織反応と称した。この紅斑は、発熱とともに生じることが多く、通常2週間で消褪する。反応の機序は不明であるが、ウイルス感染などが引き金になり、マクロファージの活性化が起きて生じるのではないかと考えている。膠原病に伴う皮膚症状の一つとして、認識しておく必要がある。
何度かみたことのある組織だった。RAに合併する手指の皮内結節(rheumatoid papule)も同様の組織反応だと思う。おそらく、いわゆるcollagen diseaseの、まさに真皮collagenが、病変部組織反応のターゲットなのではないかと感じた。今後のさらなる検討が楽しみである。
-
神奈川県天疱瘡講演会から(平成21年6月11日)
ステロイド抵抗性の天疱瘡ないし類天疱瘡に、Th2型の免疫状態をTh1に戻すことを目的として、インターフェロン-γが用いられていた。ビオガンマの200JRUを7日間点滴静注、あるいは、オーガンマ100万単位を5日間連日筋注を2クールという治療指針があって、有効であった。いずれも菌状息肉症、ATLの適応を有していたが、残念ながら現在は製造中止になっている
腎癌に適応のある、イムノマックス-γが、現在では唯一のインターフェロン-γ製剤である。これが自己免疫性水疱症に有効かどうかは報告がなかった。かつてあった治療、消えていく治療も記憶にとどめ、記録に残しておく方がよさそうだ。なお、犬のアトピー性皮膚炎の治療には、現在インタードッグというインターフェロンγの注射剤が用いられていると知った。さらに、インターキャットというのもあるが、これは猫の風邪(猫カリシウイルス感染症)の治療薬だそうだ。
-
第4回北摂皮膚科病診連携の会から(平成21年5月30日)
成人のアナフィラクトイド紫斑の症例28例のうち、根尖病巣があった患者が14例、なかった患者が14例であった。根尖病巣のない症例では、腎障害が5例、腹部症状が5例であったのに対し、根尖病巣のある症例では、腎障害が12例、腹部症状が9例といずれも多かった。抜歯を7例に施行したところ、紫斑のflare upが5例にみとめられた。歯根部のα-streptoccoccusがアナフィラクトイド紫斑の重症化に関連していると考えられる。
RAなどの合併症がなく、咽頭炎・扁桃炎のない成人例では検討する余地があると思った。今後は積極的に歯科受診を勧めよう。
-
第26回日本臨床皮膚科医会総会から(平成21年5月10日)
虫の話。ツチハンミョウ、アオカミキリモドキは、その体液が皮膚に触れると、痛みとともに水疱を形成し、2日後には潰瘍となり、上皮化に3週間を要する。カンタリジンという有機化合物がその主成分である。以前はツチハンミョウを乾燥させて作ったカンタリスという生薬が日本医薬品集にも収載されていた。皮膚に水疱をきたす働きをあえて利用して、イボの治療や植皮などに用いていたとのこと。
メルクマニュアルをみると、イボの治療の一つにカンタリジンの名前が挙がっていた。まさに「イボにハンミョウ」である。
-
第26回日本臨床皮膚科医会総会から(平成21年5月9日)
当院における湿布かぶれのまとめ。約2年間で82例の症例があった。処方箋医薬品が原因だった58例の湿布かぶれのうち、モーラステープないしモーラスパップによる光接触皮膚炎が32例と過半数を占めた。年齢的には10歳代が12例、20歳代が6例と両者で過半数となり、屋外のクラブ活動などによる日光暴露を受けやすい若年に生じていた。さらに、10歳代の12名のうち、整形外科で診察の上、モーラスの処方を受けた患者は1名のみで、ほかの11例は、自宅にあった、祖母からもらったなど、使いまわしが原因であった。
整形外科医に対して、お年寄りの患者さんにモーラスの処方をするのはかまわないが、余ったものをお孫さんのうちみや捻挫への使いまわしはしないように伝えてもらうよう、働きかけていく必要があると考えている。
-
第26回日本臨床皮膚科医会総会から(平成21年5月9日)
当院における湿布かぶれのまとめ。約2年間で82例の症例があった。処方箋医薬品が原因だった58例の湿布かぶれのうち、モーラステープないしモーラスパップによる光接触皮膚炎が32例と過半数を占めた。年齢的には10歳代が12例、20歳代が6例と両者で過半数となり、屋外のクラブ活動などによる日光暴露を受けやすい若年に生じていた。さらに、10歳代の12名のうち、整形外科で診察の上、モーラスの処方を受けた患者は1名のみで、ほかの11例は、自宅にあった、祖母からもらったなど、使いまわしが原因であった。
整形外科医に対して、お年寄りの患者さんにモーラスの処方をするのはかまわないが、余ったものをお孫さんのうちみや捻挫への使いまわしはしないように伝えてもらうよう、働きかけていく必要があると考えている。
-
第108回日本皮膚科学会総会から(平成21年4月25日)
ATLLの病型は、1.急性型、2.リンパ腫型、3.慢性型、4.くすぶり型に分けられている。皮膚のみに病変が限局する皮膚型は、くすぶり型に含められており、未だに明確な基準は示されていない。しかし、皮膚病変を伴うくすぶり型は皮膚病変のないくすぶり型より予後が不良で、皮膚型でも腫瘤型の方が紅斑丘疹型より予後が不良である。皮膚型ATLLを、白血病、節性リンパ腫および皮膚以外の節外性リンパ腫がなく、臨床的に認められた皮膚病変にHTLV-1 proviral DNAが証明されることを診断基準とすると、HTLV-1抗体が陽性でproviral DNAが証明されない菌状息肉症があることがわかった。
なんとも複雑だが、HTLV-1の感染が原因で発症するT-cell lymphomaはATLLだけではないということである。厳密な診断にはサザンブロットが必要ということは認識しておこう。
-
第108回日本皮膚科学会総会から(平成21年4月25日)
貴重な症例報告。顔面・手指背などに生じたかゆみを伴う紅色小結節。生検では真皮、皮下組織にムチンの沈着を認めた。慢性C型肝炎の合併があり、ペグインターフェロン・リバビリン併用療法でかゆみは速やかに消失、皮膚病変も軽快した。甲状腺疾患を伴わないpapular mucinosisでは21例が肝疾患を伴っていたが、そのうち16例がC型肝炎であった。
C型肝炎の肝外症状として認識しておこう。ちょっとした皮膚病変なので見落としている可能性がある。積極的に皮膚生検を行う必要がありそうだ。
-
第108回日本皮膚科学会総会から(平成21年4月26日)
掌蹠の色素性病変の鑑別には、皮溝・皮丘と色素細胞の関連が重要で、ダーモスコピーでの観察もその点にもっとも注意を払う必要がある。特に、皮溝を目立たせたい時には、ホワイトボードマーカーをさーっと塗り、乾いたティッシュペーパーで拭き取ると、インクが皮溝部のみに残るので、観察が容易になる(furrow ink test)。
これは確かに見やすくなる。色は赤がいいようだ。皮膚科医に広く知ってもらう必要があるだろう。
-
第108回日本皮膚科学会総会から(平成21年4月25日)
4歳以下で発症するまれなサルコイドーシスがあり、若年性サルコイドーシスと呼ばれている。皮膚、関節、眼病変を3主徴とし、肺、肺門リンパ節は侵されないが進行性で、失明、関節拘縮、内臓浸潤を来す。皮膚病変は播種状の小結節が多く、組織は典型的な類上皮細胞肉芽腫。また、これと同様の症状を呈し、常染色体優性遺伝の疾患はBlau症候群と呼ばれている。いずれも領域は異なるが、クローン病と同じ、常染色体16番にあるNOD2遺伝の子変異に基づく疾患であることがわかった。Nod2は細菌の細胞壁成分(muramyl dipeptide:MDP)を認識し免疫反応を活性化させる機能があるが、これらの疾患では、MDPが存在しなくても、Nod2の変異自体がNF-κBの活性化を引き起こし、肉芽腫が形成されると考えられている。
なかなかお目にかかれないが、肉芽腫の発生に関連する分子機構を少し理解できた。通常のサルコイドーシスでは、巨細胞内にMDPが存在することが確かめられていて、アクネ菌や抗酸菌が発症に関与する可能性が指摘されているそうだ。顔面播種状粟粒性狼瘡でもおそらく同様だろう。
-
第108回日本皮膚科学会総会から(平成21年4月25日)
開業医の工夫の話。pincer nailの治療では、硬く厚い爪に40%尿素軟膏を外用して爪を柔らかくすると、ゆがみが改善して痛みもなくなり、7-8割は弾性ワイアーなどの矯正を行わなくても改善する。
これは造影剤との関連に、よく気がついたと思う。すでに2009年9月に、日本医学放射線学会・日本腎臓学会合同で「腎障害患者におけるガドリニウム造影剤使用に関するガイドライン」が定められている。透析患者の重要な皮膚症状として、常に念頭において診察しよう。
-
第108回日本皮膚科学会総会から(平成21年4月25日)
2例の症例報告でいずれも腎不全で透析中。四肢の硬化と膝・足関節の拘縮が徐々に増悪してきた。既往にガドリニウム造影剤(オムニスキャン、マグネビスト)を用いたMRI検査を受けており、腎性全身性線維症(Nephrogenic Systemic Fibrosis)と診断した。進行は緩徐であるが、皮膚、関節以外にも肺、心筋、横隔膜の線維化を来す例もあるので、不必要な造影剤使用は避けるべきである。
制御性T細胞、Th17陽性T細胞はホットな領域で、これからも様々な皮膚疾患との関連がわかってくるにちがいない。なかなかついて行けないので、簡単な総説がほしいものだ。今後はFOXP3を治療に応用する流れになるかもしれないと思った。
-
第108回日本皮膚科学会総会から(平成21年4月24日)
真性多血症では、特に水に触れる、風にあたるというありふれた刺激のあとに、全身にかゆみが生じることが知られている。増多している流血中の好塩基球がヒスタミンを放出するためと考えられているが、抗ヒスタミン剤は無効なことが多い。症例によってはアスピリンなどのCOX阻害薬が有効であることから、プロスタノイド、特にトロンボキサンA2、プロスタグランディンE2が起痒因子ないし、かゆみの増強因子として働いている可能性がある。
逆に、プロスタグランディンD2はかゆみを抑制する働きがあり、NSAIDでかゆみが増強する場合もあるとのこと。帯状疱疹後神経痛が、のちにかゆみに変わる症例があり、神経痛が軽くなったもと説明しているが、NSAIDとの関連もあるのだろうか。
-
第122回横浜市皮膚科医会から(平成21年4月4日)
採血や手術の際に神経を損傷することによって生じる難治性疼痛。タイプⅠは神経損傷が明かでないもの、タイプⅡははっきりした神経損傷のあるものをいう。症状としては原因となる刺激に不釣合いな強い痛み、皮膚に触れるだけでも感じる痛み(アロデニア)で、消炎鎮痛剤は無効である。早期に判断し、受傷直後から局所への神経ブロック、上肢の場合は星状神経節ブロックなどの適切な処置を行わないと治癒が遷延する。早急にペインクリニックへの紹介が必要である。
覚えておかなければならない疾患で、早期の対応が必要だと知った。採血時の正中神経損傷によるCRPSは6.000回に1回の頻度で起こるといわれていて、臨床検査技師賠償責任保険の最重要項目になっているそうだ
-
第2回横浜皮膚病免疫治療研究会から(平成21年4月2日)
かゆみの対応として有効な冷刺激は20℃前後であって、冷やしすぎると毛細血管の収縮の後に反応性の充血が生じ、かえって処置前よりかゆくなることがある。かゆみに対しては氷や冷凍した保冷剤より、ぬれタオルの方が有効である。
今までは氷嚢や保冷剤をタオルでまいて、などと薦めていたが、ちょっと考え直さなければならない。実際はどちらがよいのだろうか。自分自身で虫さされなどのかゆみに対してくらべてみよう。
-
第2回横浜皮膚病免疫治療研究会から(平成21年4月2日)
中等度以上の成人および小児のアトピー性患者で、16週のプロトピック外用を継続し寛解した197名で、寛解後に週3回のプロトピック外用が再燃予防に有効かを白色ワセリンを対象に行ったRCTの結果。flare-freeの平均期間は、プロトピックで177日、白色ワセリンで134日であった。また、初回再燃の中央値は、プロトピックで169日、白色ワセリンで43日であり、プロトピック軟膏外用はアトピー性皮膚炎の寛解維持に有用である。
これは、何となく想像はしていたが、しっかりしたRCTが行われたことは開業医にとってもありがたいことだ。具体的には、改善した後もいつも湿疹病変が出てくるhot spotに対して、患者さんに週3回の外用を継続してもらう、というのがよいらしい。
-
第10回北里臨床皮膚フォーラムから(平成21年3月5日)
糖尿病と睡眠時無呼吸のある成人男性。熱発に続発し両下腿に皮内~皮下の小結節を混じる紫斑を呈した。組織では小動脈の血管炎で、好酸球浸潤を伴っていた。皮膚科的にはPNCに近い病態。最近、C. pneumoniaeが血管に慢性感染を起こし、動脈硬化性疾患に関わる疑いが指摘されている。 また、内科から全身性血管炎、結節性紅斑がC. pneumoniae感染症で生じた症例の報告がある。
C. pneumoniae肺炎は、飛沫感染で伝播して非定型肺炎の病態を示すらしいが、不顕性感染もあるらしい。血管に病変を起こすことがあるので、PNCや結節性紅斑では原因として念頭に置く必要がありそうだ。診断には上気道からの病原体検出が試みられるが、分離は困難で、酵素抗体法やPCRが用いられる。通常は血清中の抗体価をペア血清で比較する。STIの原因となるC.trachomatisとは別の種で、C.pneumoniaeは、1999年から、Chlamydophila pneumoniaeと種の名前が変わったとのこと。
-
第10回北里臨床皮膚フォーラムから(平成21年3月5日)
立ち仕事の長いパン職人の内踝に生じた褐色のなだらかに隆起する局面。組織では毛細血管拡張と線維芽細胞の増生、ヘモジデリン沈着があり、pseudo-Kaposi sarcomaと診断。arteriovenous malformation(AVM)はなく、慢性の静脈性循環障害が原因と考えた。AVMのないpseudo-Kaposi sarcomeをMali syndoromeと称し、AVMがあるものをStewart?Bluefarb syndromeと呼ぶ。治療としてシャント後のpseudo-Kaposiに有効だったと報告のあるエリスロシン内服を試みた。
確かに静脈うっ滞だけでも起こりそうな病態である。Mali syndromeという病名は初めて聞いた。覚えておこう。なお、エリスロシンには血管拡張を押さえる薬理作用がある?ということであった。別の病態でも使えるかもしれない。
-
皮膚病診療医会取材(NDC)から(平成21年3月14日)
開業医の工夫の話。pincer nailの治療では、硬く厚い爪に40%尿素軟膏を外用して爪を柔らかくすると、ゆがみが改善して痛みもなくなり、7-8割は弾性ワイアーなどの矯正を行わなくても改善する。
これは簡便でよい方法だ。pincer nailは末節骨が変形し、上にとがっているのが原因で、骨を削って平らにする手術をしないと根本的にはなおらないと思っていた。40%尿素軟膏をさっそくためしてみよう。まずは院内製剤用の材料を手配をしないといけない。
-
第7回日本フットケア学会から(平成21年2月27日)
603例のPAD患者の生命予後の話。平均年齢は71歳で観察期間の中央値は7年5カ月。死亡は204例で、全体の5年生存率は62%、10年生存率が38%であった。BMI別に比較すると、低BMI群(18.5未満)では、5年生存率が41%、10年が13%と低く、正常BMI群(18.5以上25未満)では5年が66%、10年が40%、高BMI群(25以上)では、72%、52%と生命的な予後がよく、BMIは死亡率と負の相関が認められ、太っている方が予後がよいと言う結果だった。
逆に、重症虚血肢で栄養状態が不良だと、さらに生命予後がよくないという結論になる。往診患者でも栄養状態の評価が必要だが、体重などのフォローができないことがほとんどだ。それにしても多くの症例でたくさんのfactorを解析した、貴重なデータだった。
-
第72回日本皮膚科学会東京支部学術大会から(平成21年2月21日)
帯状疱疹の既往が2回ある中年男性。鼻孔部の単純性疱疹罹患後、2週間で右大腿に多形紅斑を生じた。単純性疱疹後多形紅斑と診断してアシクロビルの内服を行い、約1週間で色素沈着を残し消褪した。病変部の汗腺に免疫組織学的にVZV抗原を認めた。紅斑の原因としてHSVだけでなくVZVの関与も示唆された。
汗腺にVZVが陽性だと紅斑に至るかが不明。しかし病変部以外の皮膚ではどうだったか知りたい。帯状疱疹罹患者すべての患者で、汗腺にVZV抗原があるとも思えず、不思議。こういった、「まさか」が時がたって常識になることもあるかもしれない。
-
第72回日本皮膚科学会東京支部学術大会から(平成21年2月21日)
ハプテン反復塗布による慢性接触皮膚炎モデルで、ブスルファン投与によって血小板を6万/μlから1万/μlに減少させたマウスでは、皮膚の肥厚、掻破回数、血清IgE、白血球浸潤、Th-2リンパ球に関連する遺伝子発現レベルがいずれも低下した。ここに血小板を静注すると、すべてが増加したが、P-セクレチン欠損血小板の静注では増加がみられなかった。血小板が慢性接触皮膚炎の白血球の遊走に関連していると考えられる。
意外な話であった。アトピー性皮膚炎など、血小板と臨床が関連するか、念頭に置いてみていこう。
-
第72回日本皮膚科学会東京支部学術大会から(平成21年2月21日)
接触過敏反応は樹状細胞とTリンパ球による免疫反応と考えられてきたが、Bリンパ球も一連の反応に重要な役割を持っていることがわかった。CD19はBリンパ球に特有のシグナル伝達分子で、抗原と接触することにより、活性化シグナルを増強させる機能がある。したがってCD19の過剰発現は自己免疫を引き起こし、反対にCD19の欠損では、免疫不全となる。しかしCD19欠損マウスではハプテン外用後の接触過敏反応が、正常よりも長く遷延し、耳介腫脹が72時間後でも残っていた。遷延した反応は、脾臓のmarginal zone B cellを移入することによって抑制された。以上から接触過敏反応を抑制する働きを持つBリンパ球(regulatory B cell)が存在することがわかった。
おもしろい発見である。regulatory B cellとeffector B cellのバランスが乱れることで、色々な疾患や病態が起こってきそうである。やはり自己免疫疾患の方に向かっていくのであろうか。
-
某製薬会社主催講演会から(平成21年2月10日)
発熱で救急外来を受診した小児(平均年齢1.7歳)の統計。熱性けいれんが認められた群では、抗ヒスタミン薬を45.5%が内服しており、発熱はあったが熱性けいれんを認めなかった群の抗ヒスタミン薬の内服率22.7%の約2倍であった。脳内ヒスタミンは覚醒↑・認知↑・運動↑・摂食↓などの機能を有するが、またGABAとならぶ代表的なけいれん抑制物質である。したがって、特に脳内H1受容体占拠率の高い、眠くなる抗ヒスタミン薬では、けいれんを誘発する可能性があるので、注意が必要。
これは日頃から念頭に置かねばならない大事な話だった。2歳未満でも安心して使用できる、味のよい非鎮静性の抗ヒ剤の開発が望まれるところだ。
-
アトピー性皮膚炎治療研究会第14回シンポジウムから(平成21年2月7日)
アトピー性皮膚炎の精神療法の話。患者の生き方に注視する森田療法を外来で実践している。失敗をおそれ、現実の問題に取り組めず、不安や心理的ストレスがかゆみと掻破を増強させ、皮膚炎が悪化する症例には、変えられないものは変えようとせず、変えられるものだけを変えていくという生活を促すよい。具体的には、1) まあいいや(完全主義からの脱却)、2) とりあえず(行動本位の生活)、3) 幸せさがし(観照)を提案することで、自己肯定感、自己実現、感謝の念、貢献が生まれ、皮膚に対する執着・こだわりから解放され、皮膚炎改善の一助となる。
個人的には、毎日の診療の中で、患者の生き方にまで目をむける時間的、精神的余裕があったことが一度もない。こういった診療にはあこがれるが、私には到底できそうもない。
-
2008年度東京支部主催教育セミナーから(平成21年2月1日)
MMPsと呼ばれる酵素が、様々な疾患と関連している。皮膚ではMMP-2(gelatinase A)とMMP-9(gelatina B)およびそれらの内因性特異的阻害蛋白であるTIMPsが重要である。湿疹の局所ではMMP-2、MMP-9がともに上昇している。その際、血中のMMP-2、MMP-9は正常であるが、寛解期には血中TIMP-1が上昇する。また接触皮膚炎の感作刺激の後には、表皮のLangerhans細胞はMMP-9を強く産生する。
結局すべての疾患、病態と関連がありそうでつかみにくいが、炎症にしても腫瘍にしても、組織の障害と修復の過程に関与すると言うことだろう。MMPs阻害薬で組織の障害を減らす、というのが臨床応用への道筋か。
-
2008年度東京支部主催教育セミナーから(平成21年2月1日)
ムチンの話。バセドウ病に伴う甲状腺機能亢進症でまれにみられる前脛骨部粘液水腫は、線維芽細胞にあるTSH-receptorとそれに対する自己抗体の作用により、ヒアルロン酸が過剰に産生されるために生じる。これに対しては、ソマトスタチンのアナログ製剤である酢酸オクトレオチド(サンドスタチン)の局注が有効。サンドスタチンは局所の線維芽細胞に働き、ヒアルロン酸の産生を抑制し、併せて甲状腺ホルモンの分泌を抑制することが、その理由と考えられる。
通常はアクロメガリー、内分泌産生腫瘍、消化管内外分泌抑制の目的で使われる薬剤であるが、薬理作用からはまさにこの疾患に効きそうだ。名前ぐらいは忘れないでおこう。
-
某製薬会社主催講演会から(平成21年1月28日)
閉塞性動脈硬化症の下肢虚血では、その初期症状として間歇性跛行があるが、ABPIによるスクリーニングとあわせて、歩行機能の主観的評価も重要であり、WIQが国際ガイドラインで推奨されている。WIQは痛みの程度、歩行距離、歩行スピード、階段を上る能力の4項目を患者が回答するもので、WIQのスコアーが低値だと心血管イベント発症率が高く、生命的予後も悪く、これらはABPIとも相関している。また、アンプラーグ300mg/dayの内服を24週間継続させ、WIQの変化を見たS-WIQスタディでは、WIQの4項目はすべて改善し、30~40%上昇した。
数値で表すことのできる主観的評価法は、薬剤の有効性の評価として、様々な分野で盛んだ。治療の有効性=QOLの改善、ではない気もするが、世の中の流れのようだ。なおWIQ日本語版は日本脈管学会のHPからダウンロードが可能である。
-
第823回日本皮膚科学会東京地方会から(平成21年1月17日)
生後20日男児の典型例。ステロイドスルファターゼ(STS)遺伝子領域に欠損。デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)もこの酵素の器質であり、STSの欠損により、胎盤内でのエストロゲン生合成障害が生じ、子宮内膜の成熟が阻害されるため、児は難産になることが多いとのこと。
STSの役割を久々に思い出した。エストロゲンと関連する子宮内膜癌や乳癌で、STSの阻害剤による治療が試みられているらしい。治療を受けた女性に魚鱗癬の症状が出るかもしれないので、覚えておこう。
-
第823回日本皮膚科学会東京地方会から(平成21年1月17日)
アカコッコマダニ刺症は頭頂部や頚部に発生することが多い。このダニは主に伊豆諸島などに生息するアカコッコという鳥に寄生している。アカコッコは、冬期になると本土に渡って越冬するが、まれに寄生しているダニが飛んでいる間に落下し、それがヒトに寄生するために、頭や頚部に多いと考えられている。
ダニが空から降ってくるとは思わなかった。鳥が運ぶため、市街地でも発生する可能性があるらしい。どのくらいの確率で生じるのだろうか。
-
第28回神奈川皮膚科免疫アレルギー疾患懇話会から(平成21年1月10日)
細胞膜のミクロドメインである脂質ラフト(lipid raft)はスフィンゴ糖脂質とコレステロールに富み、細胞のシグナル伝達に関わっている。高親和性IgE受容体(FcεRI)もこのlipid raft内に存在する。外来性コレステロールの添加で、lipid raftを不安定化させると、IgE依存性TARC産生が抑制された。試みにアトピー性皮膚炎患者に10%コレステロール軟膏を外用させたところ、皮膚症状の改善がみられた。lipid raftを修飾する医薬品でアトピー性皮膚炎が治療できる可能性がある。
コレステロールの外用でアトピー性皮膚炎が改善する可能性があるとは、初めて聞いた。第一三共ヘルスケアのロコベースリペアは5%コレステロール含有とのこと。機会があればためしてみよう。
-
神奈川県皮膚科医会新春勉強会から(平成21年1月8日)
理美容師の職業性接触皮膚炎についてのアンケートとフィールド調査。理容師1.058名のうちの115名(10.9%)、美容師675名のうちの166名(24.6%)に手の湿疹があるとの回答があった。悪化因子となる作業は洗髪、パーマ、染毛の順で、洗髪の際の手袋着用率が、髪に絡まって痛がる、温度がわかりにくいなどの理由で7.4%と低いためと考えられる。パッチテストではパラフェニレンジアミンが73.5%に陽性でもっとも多く、次にシャンプーに含まれる界面活性剤であるコカミドプロピルベタインが39.6%、パーマ液の還元剤であるシステアミン塩酸塩が18.8%であった。
理美容師の洗髪作業による手の接触皮膚炎の原因が、多くはコカミドプロピルベタインだと知った。被髪頭部のかぶれの症例でもこれに感作されている場合があるのだろう。
-
第822回東京地方会から(平成20年12月20日)
糖尿病では様々な生体内タンパク質が血糖値のに比例して非酵素的な糖化をうけることが知られている(HbA1cもその結果をみている)。一方、糖尿病に伴うperforating collagenosisではAGE(advanced glycation products)レセプターとして知られているCD36が、表皮細胞に発現していることが酵素抗体法示された。AGE化したI型collagenがAGEレセプターを介して経表皮排泄される可能性が示唆された。
糖尿病性腎症についても、AGE化したⅣ型コラーゲンがメザンギウムに蓄積した結果であるという報告がある。皮膚のⅣ型コラーゲン(表皮基底膜)が厚くなる病態も、糖尿病に合併しておこるのであろうか。
-
第128回神奈川県皮膚科医会から(平成20年12月7日)
金製剤の投与後に生じる口内炎で、上皮の肥厚が主体で浸軟性。炎症は比較的軽く、しっかりした角質増殖もまれ。頬粘膜では縫合部に沿った、境界不鮮明で縦じわが目立つ、白色の混濁した病変を呈する。この状態を真珠母口内炎(Perlmutterstomatitis)という。カンジダ症、粘膜苔癬、後口角部白板症との鑑別が必要。
初めて聞いた。粘膜苔癬の角化とは異なる、白く浸軟した病変が特徴とのこと。よくよく注意深く観察しないとその違いはわからないだろう。頬粘膜を見て、内服している薬剤がわかるという達人の観察眼に感動した。粘膜は奥が深い。
-
第2回神奈川臨床皮膚病理組織検討会から(平成20年12月6日)
潰瘍性大腸炎の患者の手指に生じた圧痛のある皮内結節。同時に手指の腫脹と多関節痛を伴っていた。病理組織はdebrisを伴う好中球浸潤と膠原線維の変性があり、一部には組織球の浸潤を認めた。症状が進行するとpalisading pranulomaに移行する病態の早期病変と考えた。
いかにもアメリカンな、聞いたことのない病名だったが、rheumatoid papuleやrheumatoid neutrophilic dermatitisに近い病変と思われた。記憶にはとどめておこう。不思議な臨床と組織である。
-
第58回日本アレルギー学会秋季学術大会から(平成20年11月27日)
乳癌や子宮頚癌の術後に生じることの多い、リンパ浮腫は、特にリンパ管炎を繰り返すような状況では、動脈硬化と同様に、リンパ管硬化症が生じ増悪する。通常は弾性ストッキングなどの圧迫で治療することが多いが、難治例では顕微鏡下リンパ管静脈吻合術が有効である。
つなぐだけで改善するとは驚いた。もちろん0.5mmのリンパ管を探してつなぐテクニックがあっての話だが、困っている症例も多いので、場合によっては紹介しよう。リンパ管硬化症という病名については反論もあるだろうが、考え方としてはとてもおもしろいと思った。
-
第58回日本アレルギー学会秋季学術大会から(平成20年11月27日)
大分での検証。10/1~12/31の間にダーラム型捕集器で計測した実測値。平成15年以降の総飛散数は5.4個~37.0個/cm2で、飛散が確認された日数は3カ月のうち14~47日であった。秋にもスギ花粉が少数ながら飛散することが実測された。
これは参考になるデーターだった。まぶたの皮膚炎が11月に増えることを経験しているが、一部の患者は、おそらくスギ花粉に対するhigh responderなのではないかと確信した。
-
第58回日本アレルギー学会秋季学術大会から(平成20年11月27日)
魚によるⅠ型アレルギーの抗原は何かという話。特異的IgEとプリックテストから魚アレルギーがはっきりしている3例のうち、2例でコラーゲンに対する陽性反応が証明された。欧州のタラアレルギーなどで原因抗原の主体と考えられているパルブアルブミンよりも日本の魚アレルギーにおいては重要な抗原と考えられる。
魚のアレルギーはアニサキスが主役と考えていたが、コラーゲンにも注意が必要だとわかった。ただし魚のコラーゲンには牛・豚・鶏のコラーゲンとの交叉反応はないとのこと。また、コラーゲンは低温では抽出できないため、RASTやプリックの抗原抽出液には含まれていない可能性が高いらしい。RASTや試薬を用いたプリックの評価が難しくなると感じた。
-
第821回日本皮膚科学会東京地方会から(平成20年11月15日)
眉のアートメイク(人工眉)を6年前から3回施行。その部分に一致して黄褐色の肉芽腫性結節を生じた。組織は類上皮細胞性肉芽腫。その後背部や外陰部にも結節が生じ、両側肺門リンパ節腫脹(BHL)もあり、皮膚のサルコイド反応だけではなく、全身性のサルコイドーシスと診断した。国外の症例で、入れ墨を除去したら、サルコイドーシスの肺所見とBHLが改善した症例や、ぶどう膜炎が軽快した症例の報告があり、それと同様、注入した色素に対するhostの特殊な免疫反応が発症の原因と考えた。
不思議な症例であった。確かに局所的な異物反応、皮膚サルコイドではないようだ。アートメイクは表皮直下の0.01~0.03mmに色素を注入するので徐々に色が薄くなり、数年ごとに繰り返し施行する必要があることが、入れ墨との違いで、また入れ墨のような金属は使われていないらしい。
-
第821回日本皮膚科学会東京地方会から(平成20年11月15日)
テトラサイクリンとニコチン酸アミドが有効であった、肺結核の既往のある68歳の落葉状天疱瘡の症例。アクロマイシンV(テトラサイクリン)1000mg/日、ニコチン酸アミド900mg/日を使用した。水疱性類天疱瘡の治療のファーストラインは、この両者の併用療法で、ミノマイシンを用いることも可能だが、間質性肺炎の併発の懸念から、最近はアクロマイシンVが主流になっているとのこと。
高齢者、特に施設入所者や在宅患者の水疱性類天疱瘡では、いままでミノマイシンを使ってきた。副作用の経験はないが、施設や在宅の寝たきり患者では、息切れなどの自覚症状を聞くことも難しく、胸部X線も撮れないので、アクロマイシンに変更するべきなのだろうと考えた。日皮の皮膚科Q&Aでもアクロマイシンの使用を勧めていることに気づかなかった。
-
第821回日本皮膚科学会東京地方会から(平成20年11月15日)
24歳の男性の外陰部に多発性に生じた黒褐色結節。組織はBowen病に類似し、bowenoid papulosisと診断した。組織のPCRから、子宮頚癌のハイリスク群として知られるHPV16型が検出された。パートナーから感染したかどうかは不明。
HPV16型陽性の異性からの感染が疑われる。少なくとも現在のパートナーには、HPVのワクチン投与ができるとよいだろう。ちなみに、メルクのガーダシル、GSKのサーバリックスの2種類が日本でも承認待ちの段階で、まもなく使用できるようになるらしい。また、子宮頚癌の健診でも細胞診に加えて、HPVの定性テスト(PCR)を行った方がよいという意見もあるようだ。bowenoid papulosisでも定性、型判定が必須ということがわかって、よい報告であった。
-
平塚市医師会講演会から(平成20年11月6日)
踵やくるぶしのⅠ度褥瘡に対して、振動が有用であり、ベッドのマットの下に置く機器を開発したと言う話。振動は四肢末梢では、逆に血行障害を起こすイメージがあるが、血管エコーと酸素分圧の測定から、傷害を起こさず血行を改善する振動条件(600mV、47Hz、変調周期15秒)を定めた。下肢の筋肉あるいは皮膚を刺激したことで軸索反射やシアストレスによって生じたNOによる血管拡張作用により、血流が改善すると考えらた。臨床的には1日3回、15分の加振で、足のⅠ度褥瘡が平均3.3日で改善した。
超音波検査では静脈の還流改善が示されていた。治療に困っている静脈うっ滞性の皮下脂肪織炎によいのではないかと考え、導入した。現在、週に1回通院していただいている患者さんに使用中で、少し良さそうな感じである。症例を増やして報告したい。なおこの機器はマツダマイクロニクス株式会社からリラウェーブの商品名で販売されていて、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業で評価されている。
-
平塚市医師会講演会から(平成20年11月6日)
褥瘡の経過を評価するDESIGNは個別の評価には有用であるが、別々の患者の絶対的評価には使用できなかった。DESIGNPのそれぞれに重み付けを行うことで、この問題点を解決したDESIGN-R(R:rating)を作成した。3601例の症例の経過から、Eが6まで、Sが15まで、 Iが9まで、Gが6まで、Nが6まで、Pが24までの点数をつけた。ポケットのあるなしが、重症度に大きく影響することが証明された。なお、D(深さ)はほかのすべての要素と関連するため、評価には含めないことになった。また、Deep Tissue Injuryを考慮し、深さ判定不能(DのU)が加わった。
深さが関連しないというのは意外だったが、ポケットの有無が大きいことは予想通りだった。ポケットの切開によって、S(大きさ)が大きくなっても、ポケットがなくなれば総合評価としては点数が減るというのも、実際の臨床にあった重み付けになった。評価表は真田弘美先生のHPにPDFが用意されている。
-
第121回横浜市皮膚科医会から(平成20年11月1日)
高齢者で乾癬を見たら、まず薬疹を疑うべきという話。薬剤が中止されないまま、難治な病変として経過が長くなっている症例が多い。特にCa拮抗薬、β遮断薬には注意が必要。乾癬型薬疹には、①薬剤の投与で発症し、中止によって消褪する症例、②薬剤投与で発症し、中止で軽快はするが、完全には消失しない症例、③乾癬の既往があり、薬剤の投与で増悪する症例、の3種類がある。特に、②、③は乾癬の素因が発症や悪化に関与し、徐々に増悪した場合は薬剤の関与がいつからかが明らかでない症例もある。
最近は特養の超高齢者でも乾癬と診断することが増えたような気がする。確かに多くの症例で、高血圧治療薬が投与されているかもしれない。ダラダラと内服している場合が多いので、因果関係を見落としている。薬剤中止を指示しないといけない症例があるに違いない。
-
第121回横浜市皮膚科医会から(平成20年11月1日)
金属部品などについた油脂に対する脱脂洗浄剤として、町工場などで使用されている、有機塩素化合物。発癌性の問題から徐々に使用されなくなってきたが、中国や東南アジアではまだ使われているらしい。働き始めて1ヶ月ぐらいから症状が出現し、肝障害、発熱などを伴い、皮膚症状もDIHSに似る重症例があり、HHV6の再活性化も1/4で見られるとのこと。
1980年代には日本にもあって、急性中毒による死亡例もあったようだ。貴重な写真を見せてもらった。
-
第121回横浜市皮膚科医会から(平成20年11月1日)
当院の集計を報告した。pitted keratolysisは、多汗のある人に生じる足蹠の点状角質欠損で、夕方になると靴下に足が張り付く、においが気になるなどの主訴で来院する。表在性の細菌感染症で、原因菌としてはCorynebacterium属、Streptomyces属などといわれている。決してまれな疾患ではなく、当院での3年間の集計では、101例の症例があり、男性が75例、女性が26例。年齢分布では10代が11例、20代が30例、30代が29例、40代が17例と若年成人男性に多かった。細菌培養が陽性だった症例が14例あり、混合感染が目立つが、その内訳は、Corynebacterium sp.が3例、Staphylococcus epidermidisが7例、MSSAが3例、そして、Acinetobactor sp.が7例と半数もあり、疾患との関連があるのではないかと考えられた。治療は、表在性細菌感染であるから当然だが、アクアチムクリームの外用が有効で、切れ味がよい印象を持っている。
教科書的にはCorynebacteriumだとばかり思っていたが、Acinetobactorとは、一体何者?今後も細菌培養の検討は続けていこう。なお、真菌との混合感染もあるが、その際は、イミダゾール系の外用抗真菌剤を用いると、細菌に対してもある程度抗菌活性があるので、併用はしなくてもよいかもしれないとのこと。
-
第4回神奈川皮膚アレルギー疾患研究会から(平成20年10月11日)
アトピー性皮膚炎と精神的ストレスの話題。85人のアトピー性皮膚炎患者に対して、不安の高さを定量的に評価できるstate-trait anxiety inventory(STAI)を用いて、健常人との比較、さらにストレスと皮膚炎の程度、血中IgE値などの各種ファクターとの相関を調べた。アトピー性皮膚炎患者では、変化するストレス(SA)、持続するストレス(TA)の両方とも健常人より高く、特にTAの値が高かった。また、SAが高いと、IgEが低い傾向があり、また、TAが高いとIgEが高かった。TA/SA比とIgEには正の相関があり、TA/SA比が高いほどTh2にシフトしていると考えられる。
結果と原因の関係が理解しにくい感じがした。症状の強さと特性不安の数値が相関しそうな雰囲気も、日々の診察から何となく伝わってくる。心理テストも時間があったらやってあげたいところだ。
-
第4回神奈川皮膚アレルギー疾患研究会から(平成20年10月11日)
ヒアルロン酸は生体内において、水分を引き込む作用があると考えられている。接触皮膚炎の病理学的特徴である、海綿状態では、局所でのヒアルロン酸の増加とヒアルロン酸合成酵素活性の増強があることが証明された。また、培養表皮細胞にIL-4、IL-13、INF-γを添加すると、ヒアルロン酸の産生が増強した。接触皮膚炎局所に浸潤するT細胞が分泌する炎症性サイトカインがヒアルロン酸産生に関わっていると考えられる。さらに、海綿状態では、E-カドヘリン、アクアポリンも局所的に減少しているが、これらも炎症性サイトカインの調節を受けている。
ヒアルロン酸といえば真皮のものという認識があったが、表皮細胞が合成しているとは知らなかった。接触アレルゲンに対する合目的的な反応だとすれば、局所での抗原を希釈する働きだろうか。
-
第38回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成20年10月8日)
リップクリームないし口紅による接触皮膚炎の症例で成分パッチテストを施行した2演題。いずれもリンゴ酸ジイソステアリルが陽性だった。また1例ではイソステアリン酸グリセルが陽性であった。いずれもエモリエント剤(皮膚柔軟剤)として多くの化粧品に使用されているとのこと。
リップクリームや口紅のかぶれは多いが、いつも何が原因なのかわからず、興味があった。l-メントール以外にも色々ありそうで、開業医にはパッチテストは難しそうである。
-
第38回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成20年10月8日)
DIHSの症例報告2演題。1例はアロプリノールによるDIHSで、経過中外陰部に潰瘍を生じた。生検ではウイルス性巨細胞があり、単純疱疹ウイルスの局在が証明された。単純疱疹ウイルスのIgG抗体の上昇を伴っていた、同時に、HHV-6とサイトメガロウイルス(CMV)のコピー数増加した。もう1例は、ゾニサミドによるDIHSで、CMVだけのコピー数増加を認めた。CMVの再活性化による症状としては皮膚潰瘍、消化管出血、心筋炎が知られているが、それらの症状はなかった。DIHSでは、HHV-6以外のヘルペス属ウイルスについても再活性化されることに注意する必要がある。
DIHSを見たときに注意すべき臓器障害、行うべき検査が付け加えられた、大事な報告であった。
-
第38回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成20年10月8日)
進行性腎癌に2008年1月から使用が認可された、ソラフェニブ(ネクサバールR)という経口抗癌剤。内服4日目から口腔内の違和感、6日目には手足のしびれ、圧痛。7日目には指尖、手掌に水疱を伴う紅斑が出現し、手足症候群(hand-foot skin reaction)と診断した。同様の副作用は、5FU、UFT、カペシタビン(ゼローダR)などが有名だが、その他、ドキソルビシン(アドリアシンR)、メトトレキセート、エトポシド(ラステットSR・ペプシドR)、ドセタキセル(タキソテールR)、シタラビン(キロサイドR)でも報告されている。
最近の抗癌剤はどうも手足の皮膚にトラブルが多いようだ。汗、末梢循環、機械的刺激、角層の厚さ、などが関連するのか。何故手と足なのか知りたいところだ。
-
第38回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成20年10月8日)
お好み焼き摂取後の口腔内違和感、喘息発作、膨疹、アナフィラキシーショックなどの即時型アレルギー症状。CAP-RASTで小麦、グルテンは陰性、ダニ類に強陽性。プリックテストでも小麦は陰性でダニが陽性。持参したお好み焼き粉で強陽性。新しく開封したお好み焼き粉では、陰性。持参した粉には、コナヒョウヒダニの死骸が無数確認された。同様の報告を集計すると、ほとんどが常温で数ヶ月以上、輪ゴムで止めるなどして保存された、ミックス粉で、コナヒョウヒダニ、ケナガコナダニが検出された。なお、すべて加熱したお好み焼きで症状が起こっていて、熱ではダニの抗原性が消失しないとのこと。
これは見過ごすことができない。製品の裏に、「長く室温で放置するとダニがわき、アレルギーの原因になることがあります。」と注意喚起が必要だと思った。一度開封したお好み焼き粉は水を通さないパックに入れ変え、冷蔵庫に保管する必要がある。
-
某製薬会社主催講演会から(平成20年10月20日)
病原体含んだ患者の咳・くしゃみなどの飛沫が他人の粘膜に付着、侵入することで感染が成立するのもが飛沫感染。飛沫核感染は、飛沫より小さな微粒子(直径5μm以下)が原因。放たれてから2~3時間は空気中を漂い、いわゆる空気感染をきたす。飛沫核感染(空気感染)を起こす病原体は、水痘・麻疹・結核である。
恥ずかしいが忘れていた。覚えかたは以下の通り。「空気が乾いたら、水(水痘)をま(麻疹)け(結核)!」それ以外の多くの急性発疹症は飛沫感染。伝染性紅斑や突発性発疹も?
-
保土ヶ谷区医師会災害医療講習会から(平成20年9月25日)
災害時は、傷病者が医療資源を上回り、医療の供給が需要に満たない。災害医療で重要なことは、Command(指揮命令)、Safty(安全)、Communication(情報伝達)、Assessment(評価)、Triage(トリアージ)、Treatment(治療)、Transport(搬送)である。トリアージは災害医療の一つの要素に過ぎないが、最大多数に最良の医療(Best for Most)を供給するために重要。災害現場では歩行、呼吸、循環、意識の評価のみで、1分以内に行うSTART(Simple Triage and Rapid Treatment)が用いられる。まず歩行可能なら緑、気道開放後に自発呼吸がなければ黒、呼吸数が10~29でCapillary Refill Time(爪床5秒圧迫後の毛細血管再充血時間)が2秒以下で、簡単な命令に答えられるが、歩行ができない時が黄色、それ以外が赤となる。
災害医療は地域医療を担う以上、避けて通れない。以前に比べると格段に系統立って、分かりやすくなった。
-
第820回東京地方会から(平成20年9月20日)
右頚部リンパ節廓清術の1年後から、咀嚼時に右の頬がぬれる感じが出現。耳下腺から唾液の分泌を促す耳介側頭神経が、再生の際に汗腺と連絡してしまうために生じる状態で、Frey症候群と呼ばれる。耳下腺腫瘍の術後合併症として有名であるが、同様の症候性味覚性発汗は外傷、糖尿病、帯状疱疹後にも発生することもある。
発汗異常は医者にとっても、患者にとっても発見が難しい。帯状疱疹後に起こる事があるとのことだが、今までは訴えを聞いたことがない。今後は頚部の帯状疱疹ではしっかり聞いていこう。
-
Foot-and Leg Conferenceから(平成20年9月13日)
皮膚の厚さやメラニンの量は表皮細胞ではなく、その直下の線維芽細胞が決めると言う話。そもそも足蹠に大腿の皮膚を分層で植皮するとうすいままだが、suction blisterを作って取った表皮だけを植えると、しっかりした足蹠の表皮に変化する。掌蹠の表皮直下にある線維芽細胞はDickkopf 1(DKK1)のレベルが他の場所の皮膚線維芽細胞より高い。DKK1は発生学的に頭部、骨・関節の形成に重要な因子であるが、厚い表皮の形成にも重要な因子で、表皮細胞に対し、掌蹠に特有のkaratin 9の発現を誘導する。また、メラノサイトの機能を抑制する働きもあり、メラニンの受容体として知られてるproteinase-activated receptor-2(PAR-2)の発現を抑制し、さらに毛包、脂腺系への分化に重要なβ-cateninの発現を抑制する。以上から、線維芽細胞のDKK1が高いことが、表皮が厚く、毛がなく、色が白い、掌蹠型の皮膚と深く関連している。
これはおもしろかった。削ってもすぐにもとの大きさになる胼胝のできる人がいるが、その直下の線維芽細胞のDKK1はどういうレベルなのだろうか。よほど高いようなら、真皮まで切除しないと再発すると言うことか。
-
Foot-and Leg Conferenceから(平成20年9月13日)
もう一つ、足趾の潰瘍の治療の話。末梢にできた潰瘍の壊死組織のデブリードマンの際に末節骨などの潰瘍の下にある骨を砕き、骨髄を露出させる。それをフィルムで閉じこめておくと肉芽形成が起こってくる。骨髄中の幹細胞が筋線維芽細胞や血管内皮細胞に分化するためで、一種の骨髄移植と潰瘍閉鎖療法を組み合わせた方法である。
やや過激な感じもするが、理論に基づく実践的な方法だと感心した。在宅のPADの潰瘍は難治なので、機会があれば試してみたいと思う。
-
Foot-and Leg Conferenceから(平成20年9月13日)
PADなどの重症虚血肢に対する血管再生治療。骨髄幹細胞ではなく、G-CSF投与後の末梢血中からCD34陽性細胞を選択的に集め、それを用いる方法。末梢血幹細胞を採取しやすくするために、まず、患者に4日間G-CSFを10μg/kgを投与する。その後、10?の血液を遠心し、CD34陽性細胞を1000万個ほど得る。それらを血管造影などで虚血のある部位に筋注し、その後痛みのscale、ABPI、経皮酸素分圧などを指標として評価する。なお、悪性腫瘍、糖尿病性網膜症、心・脳の不安定プラークの存在が疑われる症例は適応にならない。いままで16例で試み、4例で有効だったとのこと。
骨髄からでは大変だが、末梢血中から取るというのは優れた方法だと思った。末梢血管再生治療研究会という集まりがあり、もっと多くのretrospectiveな調査が行われているようだ。治療の一つとして、頭に入れておこう。潰瘍の周囲に局注したら難治の潰瘍がよくなるのであろうか。
-
神奈川県皮膚科医会在宅医療勉強会から(平成20年9月11月)
在宅での褥瘡管理上、皮膚科医が往診をして介入したケースと介入しなかったケースの群間試験。皮膚科医が介入した方が早く治る、designが減少しやすい、患者・家族の満足度が高いという結果が出た。またdesignが下がりやすい状況は、Eが小さい場合、Iが大きい場合、皮膚科医が介入した場合であった。
褥瘡管理に在宅を診る皮膚科医の役割が小さくないことが証明できて、よかったと思う。もっと在宅患者をみる皮膚科医が増えて欲しいものだ。
-
横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成20年9月4日)
頚部・腋窩などに類円形、小判型で、辺縁にやや浸潤が強い紅斑局面をきたす脂漏性皮膚炎のタイプを古くからウンナ型と呼ぶ。体部白癬、ジベルバラ色粃糠疹、癜風との鑑別が必要。なお、眼瞼など、好発部位でないところに生じた脂漏性皮膚炎を見たら、薬剤性を考える必要がある。原因となる薬剤はアンタビュース、D-ペニシラミン、金製剤、カルバマゼピンなど。
確かにこういうタイプがあるが、今後はUnna型としてまとめておこう。マラセチアの関与につては知りたいところである。まずは鏡検で調べてみよう。
-
北里大学皮膚科同門会から(平成20年7月20日)
ストレスに対する皮膚反応の性差をラットで検討した。成熟個体のラットに急性ストレスとして電気のフットショック、慢性ストレスとして3ヶ月間の隔離飼育を行った。その後背部皮膚を採取し、ELISAによりsubstance P(SP)および神経成長因子(NGF)を測定した。急性ストレス下のオスではNGF量は直後から増加、3日後および5日後にも増加傾向が見られ、常にメスより高い値を示した。慢性ストレス下でも同様の変化が見られた。SP量はオスにおいて急性ストレスの3日後から減少し、5日後も減少は続いた。メスも同様の経過を辿ったが、オスの方がより顕著な変化を示した。慢性ストレスでも同様に、SP量はオスで顕著に低下した。ストレス負荷による皮膚SP量の減少は、皮膚神経からのSP遊離が亢進し、neutral endopeptidase(NEP)などの分解酵素によって即座に分解された結果であると考えられる。皮膚NGF産生とSP放出でみる限り、オスはメスに比べてストレスに対する皮膚の反応性が高いことが示された。
かゆみとストレスの関連が言われている。人でも同様であれば、ストレスによる痒み、さらには掻破行動がより男性に起こりやすいということか。
-
第27回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成20年7月17日)
乾癬の生物学的製剤による治験の経過報告。infliximab(レミケード)TNF-α、adalinumab(ヒューミラ)TNF-α、etenercept(エンブレル)TNF-α、efalizumab(ラプティバ)LFA-1 α sub-unit(CD11a)、alefacept(アメビブ)LFA-3、ustekinumab IL-12/23についての報告。この中ではefalizumabとalefaceptが厳しい状態。infliximabとeternerceptは連続しようで効果が落ちる懸念。ustekinumabはPASI75が59~81%と有効率が高く、皮下注で効果がすみやか、単回投与で34ヶ月まで有効例があるなどかなり有望とのこと。
いよいよ市場に登場しそうだ。ただし胸部レ線などがフォロー中必要と思われ、開業医はちょっと手を出しづらいかも。
-
第819回日本皮膚科学会東京地方会から(平成20年7月12日)
Churg-Strauss症候群の症例報告。多発単神経炎を伴う典型例。ステロイドにプログラフの内服を併用した。ネオーラルを用いなかった理由は、ネオーラルには血管の収縮作用(これが副作用である高血圧の発症機序と考えられている)があるので、血管炎には使いづらいためである。
細かい配慮で、大切な事だと思った。ネオーラルの血管内皮細胞への作用として、トロンボキサンやエンドセリンを分泌し、末梢動脈を収縮させ、腎血流量や糸球体濾過量が低下し、腎血管抵抗や平均血圧が上昇すると考えられているらしい。
-
某抗ヒ剤学術講演会から(平成20年7月5日)
第二世代抗ヒ剤は、化学物質としての構造から、三環系とピペリジンないしピペラジン系に大別できる。ケトチフェン(ザジテン)、アゼラスチン(アゼプチン)、エピナスチン(アレジオン)、ロラタジン(クラリチン)、オロパタジン(アレロック)が三環系、エバスチン(エバステル)、フェキソフェナジン(アレグラ)、ペボタスチン(タリオン)、オキサトミド(セルテクト)、セチリジン(ジルテック)がピペリジン・ピペラジン系に属する。慢性蕁麻疹などで、効果が不十分であった場合には、同系の薬剤に変更するより、別の系の薬剤に変更した方が有効性が高くなるかもしれない。
蕁麻疹やアレルギー性鼻炎などの慢性疾患では是非心得ておきたい。数多くの症例を蓄積すれば、結論が出るだろう。なお、ピペリジン・ピペラジン系に属する5剤の覚え方が紹介された。「アレグラい、エバった、ジーさん、セは、タリん」である。五七五でたいへん調子がよい。
-
第32回日本小児皮膚科学会から(平成20年6月28日)
発熱を伴う小児の急性感染症の多くは気道感染症であるが、それらを咳の有無で2つのグループに分け、咳があれば下気道、なければ上気道の感染症を考える。咳のない高熱では、溶連菌感染症、アデノウイルス、各種エンテロウイルス、単純ヘルペスウイルス、突発性発疹を考える。咳のある高熱では、インフルエンザウイルス、RSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、ライノウイルス、麻疹を考える。夏季にはエンテロウイルス感染症が多く、小児科では「夏かぜに、咳なし」といわれている。また、主に夏季に、頬と四肢に小紅斑をきたす「顔四肢発疹症」という疾患群があり、これはエンテロウイルスの中の、特にエコー、コクサッキーA9が原因らしいとのこと。
小児の感染症の鑑別に有用な話だった。顔四肢発疹症と仮称された疾患には、当院でも心当たりがある。2歳以下がほとんどで、指趾間などに紅斑性丘疹が出現し(いわゆる砂かぶれ様)、時に手背・足背・膝蓋部・両頬にも紅斑性丘疹が出るが、ジアノッティーほどしっかりした丘疹にはならない発疹症を経験する。冬季に多いような気がするが、いずれまとめてみよう。
-
第32回日本小児皮膚科学会から(平成20年6月28日)
表皮は病原体との接触や表皮自体の損傷に際し、いくつかの自然免疫システム(非特異的防御機構)を発動させるが、その中の一つに内因性の抗菌ペプチドの産生がある。表皮が産生するhuman-cathelicidin(hCAP18)はプロテアーゼにより切断され、通常ではC末端の37アミノ酸残基が抗菌活性を持つペプチドLL-37を遊離するが、rosaceaにおいてはプロテアーゼインヒビターが壊れ、cathelicidinが多くの細かい産物となって出るようになり、それが炎症と血管拡張の原因になると考えられる。
抗菌ペプチドの産生は、アトピー性皮膚炎で減少し、乾癬では過剰発現しているという報告もあるらしい。皮膚疾患の原因としてどれだけ重要かは、まだはっきりしていない。
-
第818回日本皮膚科学会東京地方会(平成20年6月21日)
抗セントロメア抗体陽性の75歳、女性の原発性シェーグレン症候群。足趾に難治性の潰瘍があり、MR-angiographyで末梢動脈の閉塞を認めた。肺高血圧症を伴う。抗セントロメア抗体陽性原発性シェーグレン症候群は、抗SSA抗体陽性群よりも平均年齢が10歳以上高齢で、レイノー症状の合併頻度が50%と高く、高IgG血症の合併はまれで、白血球減少の頻度が低い、という特徴がある。
シェーグレン症候群でも抗セントロメア抗体を調べておく必要がある。なお、この症例では、肺高血圧症があるので、末梢動脈閉塞に対しボセンタンの使用が可能であるとの意見があった。強皮症の足趾潰瘍の予防・治療に有効という報告があるとのこと。
-
第20回日本アレルギー学会春季臨床大会から(平成20年6月12日)
男子学童、入浴後、情動変化時の蕁麻疹と運動後の意識消失発作。脳波(てんかんの鑑別)、頭部MRI、頭部MR-angiography(もやもや病の鑑別)、心電図、ホルター心電図(房室ブロックや不整脈の鑑別)、心臓超音波検査(心筋症の鑑別)、立位負荷血圧測定(起立性低血圧の鑑別)では異常なし。head up tilt test(頭部挙上試験)で、失神様誘発があり、血管迷走神経性失神と診断。また、Treadmill excercise test(運動負荷試験)で、は、10分後に一瞬の失神発作と血圧低下があり、運動中止数分後から上半身に小型の膨疹が出現し、コリン性蕁麻疹と診断した。運動、緊張、情動変化などの交感神経優位の状態でコリン性蕁麻疹が生じ、その後の交感神経の緊張離脱で血管拡張が生じ、血管迷走神経性失神が起こったと考えた。
どんな検査をすればよいか、きれいにまとまっていて大変参考になった。失神が交感神経興奮のあとの離脱症状というのは、なるほどと思った。
-
第5回相模原皮膚科学セミナーから(平成20年6月14日)
日本では茶あざが1~5個であれば、扁平母斑(Nevus spilus)、6個以上であればカフェオレ斑と定義し、カフェオレ斑は神経線維腫症(NF1)やAlbright症候群に伴う皮膚症状とされるが、欧米ではこれらの母斑症の有無にかかわらず、ひとつの茶あざもカフェオレ斑と呼ばれている。また、欧米でNevus spilusと定義されている疾患は、Speckled Lentiginous Nevus、すなわち日本の点状集蔟性母斑をさすことが多いので、注意が必要である。
確かに、国外のアトラスを見るとその通りの写真が掲載してあって驚いた。Nevus spilusが、欧米ではメラノーマの発生母地になるが、日本ではならない、というのも釈然としない。最近の傾向から、結局は欧米の定義に変わってしまうのだろう。
-
第30回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成20年6月5日)
アトピー性皮膚炎のduty neckに似た皮膚病の鑑別診断。1. dyskeratosis congenita(Zinsser-Cole-Engmann症候群):粘膜の白板症、爪のdystrophy、貧血、2. dermatomyositis:特に思春期の症例、3. 全身性強皮症、4. 扁平苔癬ないしlichen pigmentosus:高齢者の男性に多い、5. リール黒皮症(pigmented contact dermatitis)、6. 先天性ポルフィリン症、7. 黒色表皮腫:若年男子に多い、8. Darier病、などの鑑別が必要。
なるほど、色々あるものだ。特にdyskeratosis congenitaは見落とさないようにしないといけない。有名なtriasだがすぐ忘れる。
-
第24回日本臨床皮膚科医会総会から(平成20年5月24日)
cutis laxaはエラスチンの遺伝子異常で生じる先天性の疾患であるが、まれに、多発性骨髄腫などに伴う後天性の症例がある。さらに、慢性に繰り返す蕁麻疹の患者で、顔面・腋窩・腹部などに皮膚の弛緩、しわの増加、弾力性の低下をきたす例が報告された。また、腹部や腰部などに多発する、毛孔一致性の柔らかい小結節で、細かいしわが表皮にみられ、組織学的に真皮中層と真皮乳頭層の弾性線維の欠如がある、mid-dermal elastolysisという疾患も、蕁麻疹や多発性環状肉芽腫に続発して起こることが知られている。いずれも浸潤する好中球などの炎症性細胞が放出するelastaseが皮膚の弾性線維を破壊したために生じると考えられている。
そういう症例があっても不思議ではないが、cutis laxaのようなびまん性の皮膚弛緩症にまで至るのは、遺伝的な素因があるのではないか。mid-dermal elastolysisの症例は探せば見つかるかもしれない。
-
第107回日本皮膚科学会総会から(平成20年4月20日)
小児科入院患者の全身管理で用いられることの多い、パルスオキシメーターのプローブによる低温燃焼が、装着部位の手指・足趾に発生することがある。これらのプローブの光源はLEDであり、正常に装着された状態では、発光部直下の温度上昇は1~2℃であるが、環境温度が高かったり、発熱等で装着部位の皮膚温度がもともと高い場合や、プローブの上から必要以上にテープで巻いたりすると、表面からの発熱が妨げられ、局部的に熱傷を起こす温度となる場合がある。プローブは発熱源であることを認識し、装着部位の変更を心がける必要がある。
LEDによるやけどは今後は外来でも診る可能性がありそうだ。注意していこう。
-
第107回日本皮膚科学会総会から(平成20年4月20日)
ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)はヘパリンの使用中に血小板減少をきたす、ヘパリンの副作用で、ヘパリンの血小板直接刺激により投与2~3日後に発症するtypeⅠと、一過性に出現するヘパリン依存性自己抗体(抗ヘパリン-血小板第4因子複合体抗体:HIT抗体)が血小板を活性化するために、投与5~14日後に発症するtypeⅡに大別される。重篤な合併症を引き起こすのはtypeⅡで、その臨床上の特徴として、①ヘパリン(未分画、低分子分画を問わない)を投与中(血液透析のように間歇的投与や、点滴回路のヘパリンロックも含まれる)に発症する、②血小板数が急激に減少する、③ヘパリンの投与中止により血小板数が急速に回復する、④しばしば、動静脈血栓を合併する、ことがあげられる。血栓は静脈に多く、カテーテル刺入部に起こると皮膚潰瘍の原因になるので、注意が必要。検査上、HITでは、血小板の活性化に伴ってトロンビンが産生されるために種々の凝固分子マーカー(D-ダイマー、プロトロンビンフラグメントF1+2、トロンビン・アンチトロンビン複合体など)が異常に増加し、あたかもDICを思わせる所見を示す。最近では抗ヘパリン-PF4複合体抗体(HIT抗体)の検出も可能となっている。治療は抗トロンビン剤であるアルガトロバン(ノバスタンR)が第一選択で、ワーファリンはプロテインC系の抑制のため皮膚壊疽を引き起こす可能性が高く、急性期での投与は禁忌である。
開業医が診ることは少ないかもしれないが、透析患者では注意が必要であると思った。
-
第107回日本皮膚科学会総会から(平成20年4月20日)
自然免疫シグナル機構の遺伝的な異常によって、好中球、単球・マクロファージの機能が亢進する全身性炎症性疾患を自己炎症性疾患とよぶ。自己炎症性疾患の代表的な疾患である遺伝性周期熱症候群においては、多くがIL-1の産生機構に関与する遺伝子の変異であることが明らかとなってきた。若年性特発性リウマチやベーチェット病に類似する病態を呈するので鑑別疾患として重要である。さらに皮膚科的には、家族性地中海熱(FMF)では丹毒様の紅斑、高IgD症候群(HIDS)では血管炎による丘疹・結節、TNF受容体関連周期熱(TRAPS)では遠心性遊走性紅斑をきたすことがある。また、クリオピリン関連周期熱(CAPS)と総称される疾患には、家族性寒冷蕁麻疹(FCU)、Muckle-Wells症候群(MWS)、CINCA(Chronic Infantile Neurological Cutaneous Articular)症候群があり、いずれも皮膚症状としては蕁麻疹ないし持続性の紅斑をきたす。治療としては、CAPSではアナキンラ(IL-1R抗体)が特効薬で、FMFでも有効例が報告されている。
疾患群の雰囲気は十分伝わってきた。凍瘡様紅斑に限局性脂肪萎縮を伴う日本人だけに見られる遺伝性周期熱症候群(中條-西村症候群)というのもあるらしい。
-
第107回日本皮膚科学会総会から(平成20年4月19日)
ここ数年、高校生や大学生の罹患が社会問題となった麻疹は、そもそも1966年から、不活化ワクチンと生ワクチンの併用法(KL法)によって予防接種が開始された。しかし不活化ワクチンによって感作された後に自然麻疹に罹患すると、カタル症状が乏しく、発疹は四肢末端に強く、肺炎や胸膜炎を合併することがあり、これを異形麻疹と呼んだ。1969年以降はKLの併用方式は中止となり、その後は高度弱毒生ワクチン(FL)の単独接種に切り替えられた。1978年10月から開始された定期麻疹ワクチン接種はFLワクチンが採用されている。一方、母体由来の移行抗体が残っている乳児や、ヒトγ-グロブリンを投与された場合、また最近では麻疹ワクチン接種後数年を経過するに従い抗体が低下し、Secondary vaccine failureをきたした場合など、軽症の不全型麻疹を発症することがあり、これを修飾麻疹と呼ぶ。修飾麻疹は潜伏期が14~20日に延長し、前駆期症状は軽いか欠落し、コプリック斑は出現しないことが多く、発疹の癒合傾向も少なく、通常合併症もなく、経過も短いという特徴がある。
恥ずかしながら忘れていた。麻疹ワクチンの歴史を知らないといけない。2006年6月からは1歳と小学校入学前の1年間の2回接種となり、さらに2008年4月からは中1と高3の何れかで接種をし、18歳以下では全てで2回接種となったわけである。
-
第107回日本皮膚科学会総会から(平成20年4月19日)
小児の帯状疱疹の統計的な話題。15歳以下の帯状疱疹を年齢別にみると、1歳未満が33%、小学校入学前が56%、それ以上が11%であった。乳児期に発症する帯状疱疹は、母体が妊娠中に水痘に罹患した症例が63%、乳児期に水痘に罹患した症例が30%であった。乳児期に水痘に罹患すると、母体からの移行抗体の影響で抗体の上昇が悪いためか、小児期の帯状疱疹発症につながるrisk factorとなる。
乳児の帯状疱疹はちょくちょくあるわけではないが、既往歴や水痘ワクチン接種歴の把握はもちろんのこと、抗体価の変動もみていく必要がありそうだ。
-
Mycology Initiative Forumから(平成20年3月22日)
主に白人男性の糖尿病患者を対象とした統計の解析。1285名の患者を平均3.38年、フォローアップし、そのうち216名に足潰瘍が生じた。足潰瘍のrisk factorは、糖尿病の罹病期間が長いこと、インスリン治療を受けていること、HbA1cが高いこと、間歇性跛行の既往、知覚障害の合併、足潰瘍ないし足切断の既往、足の変形、足の浮腫、視力障害、網膜症の既往、爪白癬であった。足白癬では潰瘍の有無に有意差はなかった。
趾間型足白癬に細菌感染をきたす症例がたまにあるので、足白癬の方が爪白癬より潰瘍のriskが高いと思っていた。糖尿病患者の爪白癬も積極的に治療をした方がよいということだろう。
-
Mycology Initiative Forumから(平成20年3月22日)
Evidence-based consensus guidelineを用いることにより、医師の診療内容、患者のアウトカム(生存率、罹患率、症状、身体機能障害、満足度、コスト)が改善することが多くの調査で示されるようになった。例えば米国の気管支喘息では、ガイドラインができた1995年以降では、それ以前に比べると、ICUに入院した人が41%減り、在室時間が50分減り 、医療費が39万ドル減った。しかしこれらの推奨されるべき医療が施される患者は全体の60~95%と言われ、この格差(Evidence-Practice Gap)を少なくすることが課題となる。そのためには医療提供の構造、医療の経過と結果を測定する必要があり、これは医療の質を表すため、質指標(Quolity Indicator:QI)と呼ばれている。今後は皮膚科の診療にもこのQIを取り入れることになるだろう。
日本も医療の質の公開を強制するような流れになっていくのだろうか。疾患ごとのQIをみて、患者がクリニックを選ぶ時代もそう遠くはないかもしれない。患者にはわかりやすいだろうが、医者側にはまだ多くの反発がありそうだ。
-
第10回関東皮膚脈管懇話会(平成20年3月16日)
RAに伴う皮膚症状の総論。結合織のnecrobiotic conditionによる病変(リウマチ結節、superficial ulcerative rheumatoid necrobiosisなど)、中小動脈の血管障害(リベドなど)、免疫複合体の関与する細小血管炎などに加え、爪の点状陥凹、縦線を伴う斑状のアクロチアノーゼ、ミベリの被殻血管腫も多く、特に凍瘡の既往のないミベリをみたらRAが疑わしいとのこと。
ミベリは普通は凍瘡を考えるが、RAとの関連については知らなかった。今度から気にしてみていこう。
-
日本臨床皮膚科医会東北支部総会(平成20年3月9日)
皮膚の機能検査としては、角質水分含有量と経表皮水分喪失量が有名だが、それぞれは恒温恒湿の部屋で行わないと意味がない。それ以外にも皮脂量を計測する機器や皮膚の弾力性を計測する機器(痒いと感じる閾値を調べることもできる)など、様々な機器が利用可能である。
話にはよく聞くが、実際の機器は目にしたことがなかった。東北大学皮膚科のHPに製品の多くが紹介されているので参考になる
-
第7回横浜みなと・東部皮膚科懇話会から(平成20年2月28日)
月経前に顔面に紅斑を生じる患者の報告。紅斑は約1週間続き、また3週後に再発するという経過を繰り返す。estrogen 0.1%の皮内テストで即時型の反応が陽性。文献では、月経前に小水疱、湿疹が増悪する5例の患者でestrogen皮内テストの遅延型反応が陽性、慢性蕁麻疹の患者2例で即時型反応が陽性で、そのうち5例ではtamoxifenによる抗estrogen療法が有効だったとの報告があるとのこと。
estrogenの皮内テストはやったことがないし、実際こういう症例がいても乳癌に対する抗癌剤は使う気にならない。反対に更年期障害の治療薬であるル・エストロジェルという製剤があるが、一度女性の外陰部の硬化性萎縮性苔癬に外用で使ってみたいと思っている。
-
第9回横浜デルマカンファレンスから(平成20年2月21日)
足白癬を俗称では「みずむし」というが、この歴史は、江戸時代頃から、水田で仕事をする時期になると足にぽつぽつと水疱ができて痒いと記載された資料から始まる。これを水に虫がいて、皮膚が侵されるのに似ているところから「みずむし」と呼ばれるようになった。ただし当時はまだ頻度としては少なく、増えてきたのは明治に入ってからで、これは軍隊が靴を導入したことと関連が深い。また、「みずむし」の原因が白癬菌であると判明したのは、1910年で、日本では、太田正雄先生が1918年に「みずむし」から白癬菌を分離培養することに成功したのが皮切り。なお、1914年に長井新蔵先生が、製糸工場の女性に「みずむし」が多発したことを報告した。これが職業性皮膚疾患の始まりと言われている。
たまにはこういう話もよい。教科書には書いていないことだが、疾患を理解するということからすれば、大事なことであると思った。
-
第5回皮膚膠原病研究会から(平成20年2月16日)
MCTDの患者に生じる皮膚病変のまとめ。抗U1-RNP抗体単独高値の24症例の皮膚症状は、Raynaud症状が96%、手指の腫脹が71%、acrocyanosisが50%、網状皮斑が33%であった。また、熱発を契機に不定の紅斑(滲出性紅斑・虫刺様紅斑・蕁麻疹様紅斑)をきたす例が6例(25%)あり、組織は全てに共通で、真皮中層に急性線維素性炎症に見えるような、好中球・組織球の浸潤があり、膠原線維は好塩基性に変性している。これを膠原線維アタック型反応と名付け、MCTDに特異的な変化であると思われた。
確かにMCTDに特異的と思われる反応があると思っている。同様の反応はシェーグレン症候群でも見られるらしいが、今後は自己抗体との関連から、なぜそういった組織の変化が起きるかの検討が必要だろう。
-
第6回日本フットケア学会から(平成20年2月10日)
閉塞性動脈硬化症(下肢動脈疾患:PAD)のFonteinⅡ度、間歇性跛行の患者から、重症虚肢を早期に見いだすための検査法の話。ABPIを運動負荷をかける前後で測定し、ABPIが20%以上低下した場合、あるいは下肢の動脈圧が20mmHg以上低下した場合は、重症になる可能性が高い。運動負荷は、トレッドミルを12%の傾斜で、2.4km/h、5分間あるいは、つま先立ち運動(toe raises)50回がよい。運動負荷後は2分ごとにABPIを測定し、ABPIが運動負荷の前の値に回復するまでの時間を計測することも有意義である。
最近の苦い経験から、当院では下肢のPAD患者の早期発見を心がけている。さすがにトレッドミルはないので、toe raisesで検討してみよう。
-
第6回日本フットケア学会から(平成20年2月10日)
下肢末梢の温痛覚障害がある糖尿病の患者に生じる、荷重部位である趾腹部や踵部に生じる難治な乳頭腫状角化性結節をこう呼ぶ。しばしば角化とともに血腫を伴い、角層を取り除くとその下には潰瘍になっている。糖尿病の管理やインナーソールを用いても、各種外用治療に抵抗性で、角質削りを定期的に行うことが、やはり必要である。
同様の皮膚病変はハンセン病でも以前から問題になっているようだが、末梢の温痛覚障害があるとなぜ乳頭腫状になるかはわかっていないようだ。また、papillomatosus citis carcinoides Gottron、epithelioma cunicuratumとの異同についても検討の余地があるだろう。
-
第6回神奈川MMC研究会から(平成20年2月7日)
ペントシジンはAGEs(advanced glycation end-products)の一種で、高血糖や酸化ストレス下において、糖から変化したカルボニル化合物と生体蛋白との非酵素学的反応によって生成される。つまり、生体蛋白質が糖化及び酸化されたことを反映するマーカーである。特に腎機能の低下に比例して産生が増加し、血中濃度が上昇するため、慢性糸球体腎炎や腎硬化症等の診断に有用である。また、RAや重症アトピー性皮膚炎でもペントシジン高値の報告がある。皮膚・硬膜などの組織中のペントシジンは年齢とともに蓄積することが確認されていて、老化との関連が示唆される。また、皮膚のペントシジンが増加すると、動脈硬化のマーカーである脈波伝播速度(PWV)が上昇する。
ペントシジンが酸化ストレス、老化のマーカーとは知らなかった。120点の保険適応があり、糖尿病性腎症を除く腎機能低下が疑われた場合に、3ヶ月に1回算定できるとのこと。PADはもちろんのこと、他の皮膚病にも使えそうだ。
-
アトピー性皮膚炎治療研究会第13回シンポジウムから(平成20年2月2日)
乳児期のアトピー性皮膚炎の話。妊娠後期から授乳期にかけての母親に対する食物アレルゲン除去は、乳児期のアトピー性皮膚炎の発生率を低下させるが、幼児期以降の発生率には影響がなかったとのこと。母親が卵を食べたあとに、母乳中に出てくるovoalbuminは、摂取後3~6時間で認められ、4時間後がピークとのことであった。なお、アレルゲンとは無関係に、アトピー性皮膚炎の母親から出る母乳中のTGF-β値は正常より少なく、乳酸菌(lactobacillus)を投与するとこれが上昇し、乳児のアトピー性皮膚炎の発生率を低下させると言われている。
乳酸菌であれば、妊娠後期でもOKか。母乳中にアレルゲンが出ることはわかっていたが、ピークが4時間後というのは知らなかった。まだ、卵を食べたことがないような4ヶ月以下の乳児で、卵白・卵黄のプリックテストが陽性になる例があるが、これも母乳経路の感作だろうと考えている。
-
第29回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成19年12月6日)
下腿の皮下硬結の総論。lipogranulomaの原因として、考えられる疾患は、1)Weber-Christian症候群:組織に好中球が出る。2)Rothman-Makai症候群:原因不明で、いくつかの結節が集まって局面をなす。3)sclerosing lipogranuloma:炎症の結果で生じた硬化。4)lipogranuloma due to oil injection 5)addiponecrosis:lipaseが逸脱するような急性膵炎による、lipolysis。6)post-steroid panniculitis 7)cold panniculitis 8)外傷性 である
上記のいくつかは自らの最近の診療では鑑別診断から消えていた。静脈性の循環障害に伴う高齢者のlipogranulomaが近頃は多い気がする。大根足に生じやすいと教わったがそうでなくても起こっているようだ。
-
アトピー性皮膚炎治療研究会第13回シンポジウムから(平成20年2月2日)
血清IgEが極めて高いアトピー性皮膚炎では、家屋中のダニの関与がある。屋内に生息するダニは、新しい家を建てると、まず最初にケナガコナダニが増え、数年でヒョウヒダニに入れかわり、この傾向が以後長く続く。屋内のダニが増える状況は、1) 気温が20℃前後、2) 湿度50%以上、3) 人が住んでいること、4)空気がよどんでいること、5) 産卵できる繊維の隙間があること、があげられる。屋内のダニ相はMBA法(Methyleneblue agar法)で分析が可能で、専門の業者もある。なお、ケナガコナダニの分泌物として検出されるα-acaridialは強力な強力なprimary sensitizerであり、パッチテスト陽性部が数ヶ月後も痒疹として残るとのことであった。
なかなか、ダニ相の検出まで試みようとは考えなかったが、治療上あるいは予防上、大事なポイントなのかもしれない。とにかく、カーペットなどを強力な掃除機できれいにすることは、やって損はないだろう。
-
アトピー性皮膚炎治療研究会第13回シンポジウムから(平成20年2月2日)
チベットで、中学校1年生の皮膚科健診を行い、日本人と比較した。西宮では4.26%あるアトピー性皮膚炎の有病率は、チベットでは0%でであり、角質水分量が気候の特性のためか有意に低下しているにもかかわらず、経費水分蒸散量は日本人よりも低かった。ドライスキンがあるにもかかわらず、バリアー機能が保たれていることがわかった。入浴の回数を調査したところ、日本人の平均は週7.7回、石鹸を使う頻度も週7.3回であったが、チベットでは月に2.2回、石鹸を使用するのも月2.1回と極端に少なかった。アトピー性皮膚炎がチベットにない理由は、このことに加え、大気汚染がなく、ばい煙がないこと、ダニが少ないこと、伝統的な食事が関与しているかもしれない。
洗いすぎがアトピー性皮膚炎の悪化因子であることは、時々経験する。今後、チベットが発展していく中で、アトピー性皮膚炎を発症する子供が何年後に出てくるか、興味のあるところである。
-
第44回日本小児アレルギー学会から(平成19年12月8日)
小児用プロトピック軟膏とロコイド軟膏を、2歳から15歳までの、小児アトピー性皮膚炎の顔面の病変に使用し、寛解状態がどれくらい維持できるかを比較検討した。治療は治癒状態まで、それぞれを1日2回外用し、その後1週間は1日1回を継続し、中止。その後の再燃(治癒状態から、皮膚の症状が治療前の30%にまで悪化)までの期間を調査した。結果はロコイド軟膏では.2日めから再燃する症例があったのに対し、プロトピックでは26日目の再燃例が最初で、それぞれ7週間目の再燃率を見ると、ロコイドでは47.6%であったのに対し、プロトピックではわずかに8.8%であった。プロトピック軟膏で治療した方が、ステロイドで治療するよりも寛解を維持できる期間が長いことがわかった。
悪化までの期間を、治療をがまんしてもらって調査するという、ご家族の協力を得るのに大変な労力を使われただろうと敬服した。臨床に役立つ、貴重なデータである。プロトピックをたまに塗れば、寛解を維持できるという使い方もこれでうなずける。
-
第33回横々会から(平成20年1月31日)
尋常性狼瘡の組織は、真皮主体の類上皮性肉芽腫で、肉芽腫の境界は明瞭だが、不規則であり、周辺に向かって増殖する傾向がある。表皮の変化を伴うことがサルコイドーシスとの違いである。肉芽腫内の壊死は軽く、乾酪壊死が見られることは多くない(乾酪壊死はそもそもリンパ節の病変が典型である)。また類上皮細胞は核がはっきりしない、eosinにぼーっと染まるなど、元気がなく、この点もサルコイドーシスと違う。また肉芽腫内の壊死が激しかったらLMDFを考えないといけない。
なるほど、元気がない、はその通りだと思う。結核菌との死闘を物語っているのであろう。乾酪壊死についても、もともとリンパ節の話というのは知らなかった。
-
神奈川県皮膚科医会編集委員会講演から(平成20年1月24日)
帯状疱疹に関連した論文の紹介である。非汎発性の通常の帯状疱疹患者から感染した乳幼児水痘の解析した。7例が秋冬に、1例が夏に発症した。感染経路から、従来は起こらないとされている接触感染や、帯状疱疹皮疹部あるいは帯状疱疹患者上気道からの水痘・帯状疱疹ウイルスの飛沫感染もあると考えられた。秋冬に感染が多かったのは、部屋を閉めきるためと推定された。
帯状疱疹の上気道からウイルスDNAが検出されるとの報告もあるらしい。日頃は覆っておけば大丈夫と話しているが、VZV抗体を持たない乳幼児への感染には注意が必要そうである。少なくとも痂皮になるまでは別室で寝るようになど、指導するようにしよう。
-
第817回東京地方会から(平成20年1月19日)
ハンセン病の経過中に、らい反応と呼ばれる急性の炎症反応が起こる場合がある。1)1型らい反応(境界反応):B群の病像の経過中に急に紅斑が増強し、神経症状の増悪がある。Th1型の免疫応答の増強の結果と考えられている。2)2型らい反応(らい性結節性紅斑):LL型およびBL型に見られる反応で、病変部や正常に見える皮膚に、発赤と疼痛を伴う浸潤性紅斑が出現する。らい菌の菌体成分と、これに対する抗体との免疫複合体が血管壁に沈着して起こる症候群と考えられてる。
ハンセン病の分類、経過、合併症はもともとなかなか頭に入ってこないが、らい反応については知らなかった。
-
第817回東京地方会から(平成20年1月19日)
潰瘍性大腸炎の経過中に、消化器症状の増悪に伴って、臀部に緊満性水疱が出現。病理組織と蛍光抗体直接法から、LABDと診断した。潰瘍性大腸炎の7%に合併し、血便・排便回数・血沈・Hb・Albを指標とした臨床的な活動性が高くなったときに出やすいと言われている。
なぜIgAが沈着するのかがわからないが、原疾患と明らかに関連している。腸管免疫と分泌型IgAか。
-
横浜領域別漢方医学講座から(平成20年1月16日)
皮膚疾患に使用する漢方の重要処方解説。赤ちゃんの湿疹は、胃腸障害による「気・血・水」のうちの気の異常で水がめぐらず発症する場合が多く、脾虚に対する小建中湯(99)が第一選択となる。なお余談であったが、漢方薬は証があっていると、赤ちゃんでも喜んで飲む、とのこと。
え、本当という感じだった。苦い粉というイメージがあり、赤ちゃんに飲ませるということすら頭になかった。漢方に関しては個人的には当たるも八卦処方で、重要処方といわれるものも聞いてもすぐ忘れる。
-
第26回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成20年1月12日)
イギリスで行われた乾癬患者を対象とした前向き研究によると、重症乾癬患者(メトトレキサートなどの投薬を要した患者)の心筋梗塞発症率は2.9%であり、軽症乾癬患者(2%)や対照群の発症率(1.8%)よりも高率であった。なお、年齢により心筋梗塞リスクは異なり、30才の若年乾癬患者においては、重症乾癬の場合心筋梗塞発症リスクは3.1倍、一方、60才の高齢乾癬患者においては、重症乾癬患者で1.36倍であった。乾癬は心筋梗塞の独立したリスクファクターであり、特に重症乾癬を有するの若年患者においてリスクが高い。乾癬の悪化によるTNFα上昇がインスリン抵抗性を亢進させることがその理由かもしれない。特にBMIが30を超える患者では注意が必要。
RAではTNF阻害剤の無効例は有効例に比べて心筋梗塞の発生率が2倍以上増加していたという報告もある。重症乾癬の治療には心血管イベントの観点からもTNF阻害剤を用いる必要がありそうだ。
-
第37回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成19年12月16日)
2例の症例報告。47歳と77歳の女性患者で初診は夏。実験的にネッタイイエカを刺咬させたところ、白暈をともなう点状の紅斑が再現された。樋口の点状紅斑は蚊の刺咬に対して無反応になった患者が多数の蚊に刺されたときに出現する症状と考えられた。
47歳の症例ではヒトスジシマカの実験的刺咬では白暈が出なかった。ネッタイイエカというところがミソか。沖縄・奄美に生息すると書いてあるが、最近では本州にも定着しているらしい。刺されてもヒトスジシマカほど痒くならないという記載があるので、たぶん毒の成分が違うのだろう。ところで蚊の毒は酵素?という話だが何だったか、詳しくは知らない。
-
第37回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成19年12月16日)
これも自分の発表で恐縮だが、一般用医薬品には以前から指摘されているように、主成分以外にも様々な副成分が含まれていて、これらがかえって接触皮膚炎の原因になっている場合がある。水虫薬に含まれているクリオタミトンおよびジフェンヒドラミンの止痒剤による接触皮膚炎、湿布に含まれていたクロタミトンによる接触皮膚炎を経験した。成分のパッチテストが重要であることを再認識した。
OTC医薬品業界に、学会として色々な配合をしないように求める必要があるのではという意見もあがった。実は、OTC医薬品だけでなく、処方箋医薬品にもクロタミトンは副成分として使用されいる。ステロイド外用剤のマイザークリーム、湿布のセルタッチなど。セルタッチのかぶれにはマイザークリームを使わないように。
-
第37回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成19年12月16日)
自分の発表である。一般用医薬品はOTC(Over The Counter)医薬品と呼ばれ、医療費の削減にためにも促進が図られているが、皮膚障害を起こすことがまれではない。集計によると、夏期によく経験するOTC水虫薬による接触皮膚炎や、湿疹用薬・ニキビ用薬に含まれるNSAIDによる接触皮膚炎、外傷やおしゃれ(ピアスやタットゥー)に使用された抗生剤・消毒薬などが多かった。問題点として、最近では健康・衛生に関する商品を置く量販店、いわゆるドラッグストアが増え、一般用医薬品が薬剤師と対面することなく、商品を陳列棚から買い物かごに入れ、レジで会計をすますだけで購入されていることが多く、接触皮膚炎を生じた115症例のうち、GTRで購入されたものが73例(63%)に及ぶという結果だった。
一般用医薬品の購入に際しては、薬剤師の簡単な説明があった方がいいだろう。この問題については厚労省も懸念していて、現在、薬剤師が説明しないと購入できないもの、コンビニに置いたり、通販で購入してよいもの、その中間?の3種類に分類し、2009年4月から施行するための改正薬事法の省令を整備中とのことである。
-
第37回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成19年12月15日)
中華料理を食べた後に蕁麻疹、腹痛、悪心、眩暈、頻脈、手足のしびれなどの神経症状が出現することがあり、中華料理でよく用いられるグルタミン酸ナトリウムの大量摂取が原因で、不耐症と同様の非アレルギー機序、主として肥満細胞からの脱顆粒の閾値を下げるために生じると考えられる。
非アレルギー性の食物による蕁麻疹は診断が難しい。グルタミン酸ナトリウム以外にも防腐剤(安息香酸ナトリウム)や着色料(タートラジン、ニューコクシン)によるものがあるとのこと。
-
第37回皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から(平成19年12月15日)
職業性皮膚疾患の疾病管理・予防は患者に対する対応だけでなく、まだ発症していない他の従業員への対応、企業や行政への対応が必要となり、そのために得なければならないエビデンスは、1) 有病率・発生率などの疫学データ、2) 疾患の検査・加療に要する医療費、3) 疾病そのものによる、あるいは受診機会(割かなければならない時間)による労働生産性の低下・損失などの経済的なアウトカムである。
指摘の通りで、臨床医が取り組むのは簡単ではない。ただし、行政・企業向けのデータは是非必要で、開業医も協力しなければならない。皮膚疾患による労働生産性の低下についてはWPAI-AS(work productivity and activity impairment questionnaire: allergy specific)の検証がアトピー性皮膚炎では始まっていると聞いている。職業性接触皮膚炎でも集めていく必要があるだろう。なおWPAI-ASはMargaret Reilly氏のHPにある。
-
第125回神奈川県皮膚科医会から(平成19年12月2日)
多汗症の治療では、段階的に、1)塩化アルミニウム水溶液、2)水道水のイオントフォレーシス、3)ボツリヌス毒の局注、4)交感神経節切除で対応する。塩化アルミニウム液は20から50%を用い、まず布の手袋に溶液を浸して、その上からゴム手袋をして就寝するという夜間密閉療法が単純塗布よりも有効で重症例にも使用できる。水道水のイオントフォレーシスは、10mAのやや強い電流が流せる機器が必要で、vectronics IP-30などがおすすめである。通常施術は10分から20分で、週1~2回、8回ぐらいから効果がみられてくるとのこと。うすくワセリンを塗るとよい。ペースメーカー装着者や妊婦では行えない。自分で購入できるドライオニックも悪くはない。ボツリヌス毒は2単位/0.1mlを片手で20カ所ぐらいに皮内注射する。さらに、電位依存Naチャンネルをブロックする抗てんかん剤、topiramate(トピナ)も、発汗と関連するアクアポリン5を減少させる薬理作用があるため、乏汗症の副作用が知られており、多汗症に有効かもしれない。
具体的な内容でたいへんためになった。塩化アルミのODTはすぐにでもできそうである。イオントフォレーシスの機器も問い合わせをしてみよう。
-
第184回大阪皮膚科症例検討会から(平成19年11月22日)
Steal症候群は、内シャントを施された血液透析患者の5%に見られる合併症で、動脈血が内シャントを通じて多量に静脈に流入するため、シャントより末梢の血流が減少し、虚血症状を呈する疾患である。PDAのFontaine分類と同様、Ⅰ:アクロチアノーゼ、冷感、Ⅱ:透析中の除水により出現する疼痛、Ⅲ:安静時疼痛、Ⅳ:潰瘍・壊疽、以上のように重症度分類されている。
動脈硬化、糖尿病、異所性カルシウム沈着がさらにシャントより末梢の動脈閉塞の誘因になり、前腕切断にいたる例もあるので注意が必要である。
-
第184回大阪皮膚科症例検討会から(平成19年11月22日
高齢女性で心房細動がある。手指の急速に進行する壊疽、足背のリベド、下腿の紫斑と潰瘍を伴う。抗MMP-3抗体がやや高く、CRPとSAAは著明に上昇。IL-6も高値。RA?に伴う慢性炎症が原因で生じた血栓症と診断した。SAAはmonocyte tissue factor(MTF)のrapid inducerであり、MTFはfactor 8と結合するため、血栓を生じることになる。
これは重要な病態であると思った。それはそれとして、RAの抗体検査もずいぶんと変貌し、抗CCP抗体、抗MMP-3抗体、抗ガラクトース欠損IgG抗体など、早期のRAの診断、関節破壊の程度などを評価できるようになってきた。
-
第815回日本皮膚科学会東京地方会から(平成19年11月17日)
胸部に生じたPaget病の症例。報告は男性で、乳癌はなく、副乳もない。乳頭以外の胸部に生じたPaget病は、本邦では女性例も含め4例の報告があるとのこと。いわゆるmilk lineに沿う、乳腺由来と考えられるPaget病の他、アポクリン腺由来と考えられる乳房外Paget病の症例もあるらしい。
乳房に生じても、腫瘍が乳腺由来ではなく汗腺由来であるなら、やはり乳房外Paget病と呼ぶべきか。ちょっと不思議な感じではある。
-
第118回横浜市皮膚科医会例会から(平成19年11月10日)
HPS1型は、白皮症、出血傾向、全身へのセロイド・リポフスチンの沈着を伴う、常染色体劣性遺伝性の症候性白皮症である。小胞体、ゴルジ体からリソソームやメラノソームへと続く分泌系のオルガネラ間の蛋白質輸送は、脂質2重膜からなる輸送小胞によって制御されており、メンブレントラフィックと呼ばれるが、HPSはこのメンブレントラフィックに破綻をきたす遺伝子変異によって、メラノソームやリソソームなどの各オルガネラの生合成障害や機能障害起こり、発症する。中年以降に高率に間質性肺炎を合併し、肉芽腫性大腸炎を伴う例もある。日本人の眼皮膚白皮症の10%を占め、まれではあるが覚えておく必要がある。
幼児期の紫斑は虐待と間違われることもあるという。蒙古斑のない乳児には注意をはらう必要があると思った。
-
第57回日本アレルギー学会秋季学術大会から(平成19年11月1日)
アトピー性皮膚炎の顔面病変の管理、眼合併症の減少にプロトピック軟膏の果たした役割は大きい。プロトピック軟膏は治験時の顔面に対するhalf side testで、左右差が出ず、どちらにも有効だった。プロトピック軟膏外用当初に問題となる灼熱感は、外用する場所を狭めて、額と頬の一八塗りで充分かもしれない。
確かに遠隔効果は経験することがある。一八ちょんちょん。眼瞼炎などの患者に今度やってみよう。
-
第57回日本アレルギー学会秋季学術大会から(平成19年11月1日)
アトピー性皮膚炎以外にも、慢性の経過で広範囲におよぶ痒疹、貨幣状湿疹などでも血中IgEが上昇することがある。そこで、尋常性乾癬の重症度ごとに、IgE-RISTと抗原特異的IgEを計測した。血清総IgE値は、軽症の8例では平均95、中等症の5例では1425、重症の4例では7667で、重症度に平行して増加することがわかった。また総IgE値上昇例での抗原特異的IgEは、ダニ、HD1で平均スコアが3、スギ花粉で2で、アトピー性皮膚炎で陽性になる抗原と同様の傾向であった。
抗原特異的IgEが重症の乾癬でも高くなると言うことは、どのような意味があるのだろう。逆に言えば抗原特異的IgEの意味はどういうときにあるのだろう。
-
第57回日本アレルギー学会秋季学術大会から(平成19年11月1日)
慢性蕁麻疹患者の20%で、D-dimerの上昇があり、多くはFDP、CRPも同様に高値でそれぞれ症状の改善・増悪と平行して増減する傾向が認められた。血漿の凝固線溶マーカーが蕁麻疹の病勢の指標になる可能性がある。また凝固波形は深く急峻で、トロンビン生成試験ではtime to Peakが短縮し、Peak heightとEndogenous thrombin potentialが増加し凝固準備能亢進状態であることがわかった。ただし、蕁麻疹の病型とはいずれも関連はなかった。
これらの因子が血管内皮細胞の透過性亢進と肥満細胞のヒスタミン遊離促進に働くらしい。病勢を示すと言うことであれば、D-dimerは測ってみよう。抗ヒ剤の内服を中止してもいいかどうかの指標に使えるかもしれない。
-
第57回日本アレルギー学会秋季学術大会から(平成19年11月1日)
IL-18はマクロファージから前駆体として産生され、LPSで活性化したcaspase-1によって切断され、活性型となり分泌される。IL-18は抗原刺激がなくてもIL-12の存在下では、Th1サイトカインであるIFN-γを誘導するが、IL-12がないと、IL-2の存在下で、IL-4、IL-9、IL-13などのTh2サイトカインを誘導する。表皮細胞にcaspase-1を導入し、結果的にIL-18を過剰発現させたマウスは、抗原刺激がなくても高IgE血症をともなうアトピー性皮膚炎類似の皮膚病変を呈するが、stat6欠損マウスでもIgEの上昇なしに同様の皮膚炎が発症する。したがって、IgE非依存的、つまりアレルゲンが関与しないアトピー性皮膚炎があり、IL-18は自然型アトピーの誘導因子であると考えられる。
ちょっと難しいが、アトピー性皮膚炎でIgEが高くなく、アレルゲン特異的IgEも証明できない症例が確かにある。いずれは血中IL-18を調べるようになるのだろうか。
-
第57回日本アレルギー学会秋季学術大会から(平成19年11月1日)
SLEなどの合併のない原発性のAPSでも低補体血症がある。2回以上流産・死産を繰り返したAPSの症例は、C3の低下は60%、C4の低下は50%、CH50の低下は40%で認められた。補体低下群ではlupus anticoagulantの出現とも相関があり、また血中TNFαが高かった。しかし、C3a、C4a、C5aは逆に高値で、補体低下は補体の産生低下ではなく、活性化によることがわかった。
APSにみられる流産などの妊娠合併症は、胎盤の血栓が原因かと思っていたので意外だった。大事な報告だった。
-
第8回横浜デルマカンファレンスから(平成19年10月25日)
療養型病床の認知症患者に生じる感染症の話。1) 疥癬/異形のものが多い、手や頚部にないこともある、掻破痕もはっきりしない、感染ルートがわからない(血圧計のマンシェッット?)、神経系薬剤の内服をしているとイベルメクチンが効きにくい。2) 丹毒/発熱がないこともある、非定型的な紅斑、CRPやWBCの上昇がないこともある、胃瘻や気切のまわりに生じることがある。3) 膿痂疹/黄ブ菌性より溶連菌性が多い、丹毒の治ったあとに生じることがある。
確かにこれが丹毒かという症例は時々経験する。胃瘻や気切のまわりに起こるというのは気づかなかった。注意してみていこう。
-
第58回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成19年10月21日)
アトピー性皮膚炎患者で考慮すべき心身状態のひとつに、概日リズム(サーカディアンリズム)睡眠障害がある。特に夜間の痒みがあって入眠時間が遅くなり、翌朝の社会的要請に対応できないという、睡眠相後退症候群(Delayed sleep-phase syndrome: DSPS)ととらえられる症例がある。ヒトにとっての概日リズムは、光同期性クロックと食餌同期性クロックがあり、早寝・早起き・朝ご飯を勧めることで、皮膚症状の改善がもたらされる可能性がある。
確かに、睡眠不足のアトピー性皮膚炎患者は多いように思う。いつも遅寝の私が言うのも説得力がないが、早寝・早起き・朝ご飯を勧めてみよう。なお、欧米ではDSPSの治療として、概日リズム障害の代表である時差ボケに有効と言われているメラトニンが用いられることもあるようだ。ただしこれはFDAが認めた医薬品ではなく、健康食品として売られている。日本でも通販で売られているが、意識障害を伴う中毒の症例もあるらしいので勧めるのはやめておこう。
-
第58回日本皮膚科学会中部支部学術大会から(平成19年10月20日)
真菌症を疑って、鏡検で菌要素が陰性の場合はもちろん、陽性であると結論する自信がなかったら陰性と判定しておくべきである。糸くずなどを見誤って陽性とした場合には、それが確定診断になってしまうことと、皮膚炎に抗真菌剤を外用すると自家感作性皮膚炎に発展してしまうなどのトラブルが多く、逆に白癬にステロイド軟膏を短期間外用してもさほど大きな悪化にはつながらないこと、抗真菌剤の外用で次回の適切な診療機会に検査上悪影響を及ぼす可能性があることがその理由である。
わかってはいることだが、はっきり言ってくれるとすっきりする。研修医の頃は、KOH(±)などと書いていた記憶があって、恥ずかしい限りだ。なお、カンジダの鏡検は検体のへりを見るとわかりやすいなど、ためになった。ちなみに当院では、忙しい時の見落としが心配なので、KOHの検体は翌日まで残しておくようにしている。
-
某抗アレルギー剤発売記念講演会から(平成19年9月15日)
抗NIRS(近赤外線分光法)という装置で、working memoryを評価することにより、抗ヒ剤の副作用を測るという試み。working memoryとは、一般的に保持・操作して、答えを導く認知機能と定義される。頭にこの装置を当てて、光のはね返りを測定するのだが、強く活動している部分はヘモグロビンが多く集まるため、はね返り方が変化する。活動しながらの観察ができ、リアルタイムで測定でき、安全性が高いことが特徴。これを用いて、抗ヒ剤の内服をさせ、課題遂行時の前頭前野の皮質活動をみると、working memoryに支障をきたしたかどうかが評価できる。
この装置は血行障害の評価や血管拡張剤の効果判定にも使えそうだ。
-
某抗アレルギー剤発売記念講演会から(平成19年9月20日)
抗ヒスタミン剤のベシル酸ベポタスチンは、ヒスタミンH1受容体拮抗剤としての薬理作用の他、1) 血管内皮のICAM-1発現を抑制する。2) ダニ抗原添加時にリンパ球からのIL-5産生を抑制する。といった働きがある。こういった、ヒスタミンに対する主な作用の他にその薬剤が持つ薬理作用をプレイオトロピック作用(多面的作用)と呼ぶ。
そもそもはスタチンの血管壁に対する作用などが、このキーワードの始まりのようだ。太藤病のインドメサシンや色素性痒疹のジアフェニルスルホンによる治療も、きっとプレイオトロピックだろう。言葉だけは覚えておこう。
-
某抗アレルギー剤発売記念講演会から(平成19年9月15日)
花粉抗原暴露室の話。湿度45%、気温22℃に保たれた、5m四方のガラスで密閉された部屋で中央に煙突があり、そこから8000個/m3のスギ花粉が出て、四隅の空調機で室内をグルグル回っている。12人までの被検者がほっかむりをして入室し、抗ヒ剤の内服前後のくしゃみの回数、かんだ鼻水を含んだティッシュペーパーの重量などを比較するという臨床試験を行うことが可能。
花粉は市販の袋詰めのものを買ってくるとのこと。売っているとは知らなかった。ほっかむりをしなければ、まぶたに皮膚炎が生じる人もいるのではないだろうか。
-
神奈川県皮膚科医会在宅医療勉強会から(平成19年9月13日)
褥瘡・下腿潰瘍などの慢性皮膚潰瘍の創底管理で問題になる細菌感染症の臨床的なアセスメント法。創底の細菌負荷を、以下の4つのステージに分類する。1)contamination:創底に細菌がのっかっている状態、2)colonization:組織障害や治癒の遷延には至らない安定した状態、3)critical colonization:治癒がストップし、生体の免疫反応としての炎症の初期の状態、4)deep infection:細菌がより深部に、または周囲に向かって増殖し、強い炎症反応とともに組織障害が進行する状態。3)のcritical colonizationでは以下のサインに注目し(NERDS)、局所的な抗菌剤を使用する。 Nonhealing wound:傷がよくならない(4週で20%~40%の縮小がない) Exudative wound:滲出が多く、創周囲が白く浸軟する Red and bleeding wound:肉芽が盛り上がりすぎて、易出血性 Debris in the wound:黄色ないし黒色の壊死組織 Smell from the wound:緑膿菌ないし嫌気性菌の腐敗臭 4)のdeep infectionでは以下のサインに注目し(STONES)、全身的な抗菌剤を使用する。 Size is bigger:細菌感染による深達性ないし表在性の潰瘍拡大 Temperature increased:細菌感染による周囲の発熱 Os(probe to or exposed bone):骨髄炎の危険がある骨の露出 New areas of breakdown:主病変の周囲の潰瘍新生 Exudate, erythema, edema:炎症に伴う滲出、紅斑、浮腫 Smell:緑膿菌ないし嫌気性菌の腐敗臭
critical contaminationではAg含有の被覆材、外用剤が推奨されている。横文字の略語はともかく、今までの臨床的な経験から、だいたい見当がつく。
-
神奈川県皮膚科医会在宅医療勉強会から(平成19年9月13日)
寝たきりの褥瘡予防は体圧分散エアマットで飛躍的に進歩した。しかし、車いすに長い時間座りっきりが原因で生じる座位褥瘡は対応が遅れていた。特に施設入所の高齢者で、尾骨部周囲、臀列部上方の左右の褥瘡をよく経験する。そこで可視化車いす(ガラス張りで下からカメラを撮ることができる)を作成し、体圧分散と姿勢保持の両方を兼ね備えた車いす用エアーセルクッションが開発された。エア調整を自動化し、底付きを感知するセンサーを置き、体圧分散を行うとともに、両サイドに大きくやや硬いセルを配置し、座位の姿勢が不安定になるのを解消している。Medi-Airという商品名で近々商品化されるとのこと。
さっそく介護保険の適応になればと思う。なかなかうまい治療法がない、臀部角化性苔癬化皮膚にも有効か。
-
乾癬治療フォーラムから(平成19年9月4日)
coral reef psoriasisとは、厚くて岩のような鱗屑がガチッと付いている乾癬のplaqueをさす。一般的に外用に抵抗性といわれているが、鱗屑を剥がすような薬剤を使用しなくても、ステロイド軟膏の外用だけで改善することがわかった。つまり、coral reef plaqueをみたら、それはadherenceがpoorな証拠、つまり外用をしていないということを意味する。皮膚科医自身は外用の指導が不十分であったことを認識しなければならない。
われわれが反省しなければならないというのは、たしかにその通りかもしれない。頭の厚い鱗屑は、某先生に教えてもらった親水軟膏パックを入浴1時間前にやってもらうことが多いが、他の先生方はいかがであろうか。
-
第14回 Alliance Hodogayaから(平成19年9月1日)
消化器内視鏡の話。2006年6月から販売されている内視鏡では、狭帯域光観察(NBI:Narrow Band Imaging)ができるようになった。血液中のヘモグロビンに吸収されやすい狭帯域化された2つの波長(390~445nm/530~550nm)の光を照射することにより、粘膜表層の微細構造や毛細血管を観察でき、拡大内視鏡とともに使うと、赤血球が動く様子さえみえる。これによって、上部消化管では咽頭癌、喉頭癌早期食道癌、バレット食道癌、大腸では平坦型病変などの前癌病変の発見が飛躍的に進歩した。
他科領域だが、先進的でおもしろかった。ダーモスコピーの先から出る光の波長を変えるなど、皮膚病変にも応用できるのではないかと思った。
-
横浜市立市民病院研修会から(平成19年8月30日)
日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会が設立された。多職種の在宅医療従事者同士が互いに情報交換することにより、在宅褥瘡の現状を把握し、問題点を抽出して、対策を立てることを目標としている。重要な項目としては①利用者、家族の意向の尊重、②在宅と施設間の適切な連携、③在宅における褥瘡治療法、④在宅栄養療法、⑤有効な体圧分散法、⑥寝たきりにさせない予防的運動療法、⑦壊死組織除去や難治化した創に対する有効な局所療法、を挙げている。
講師として参加したが、この協会の存在は知らなかった。活動を期待したいところだ。褥瘡学会からも在宅のマニュアルがでるらしい。
-
第25回日本美容皮膚科学会から(平成19年8月18日
ストレスの定量は、従来は血中あるいは尿中コルチゾールを指標としていたが、日内変動が大きく評価が難しい。最近では、ストレスに際してのステロイド合成に重要といわれている末梢型ベンゾジアゼピン受容体(PBR)の計測が可能となり、有用である。ヒトの場合には血小板が測定に用いられる。血小板PBRの値は個人によって大きく異なり、最大20倍の開きがあるが、不安の心理テスト(STAI)を用いて検証すると、PBR値が高い人は不安になりやすく、PBR値が低い人は不安になりにくいことがわかった。血小板の寿命は8日から10日なので、測定されたPBR値は過去1週間にわたり血小板に写し撮られたストレス履歴と言える。また、日本人のPBR遺伝子485における遺伝子多型をみると、G/A置換のないGGの人が60%、GA置換をもつ人が33%、AA置換をもつ人が6%であったが、GAないしAAの人の血小板PBR値は置換のないGGの人の半分ほどで、ストレスに強いことを示唆している。
アトピー性皮膚炎や蕁麻疹ではどうなのか。臨床に使えそうだが、どこで測ってくれるのだろう。当院でもcocoro meterで唾液中アミラーゼの計測を行っていたが、あまり症状と相関せず、また、日内変動を考慮するといつ測ればいいのかがわからず、データを出すまでには至らなかった。
-
第813回東京地方会から(平成19年7月21日)
コスタリカへ旅行、帰国後に側腹部の結節に気づく。粉瘤の疑いで切開すると、中からヒトヒフバエのウジが出てきた。ウジは、皮膚に穴を開けて尾端の気門を外に出して呼吸しているので、ダーモスコピーでみると、プクプクと泡が出てくるので、これだけで確定診断可能とのこと。
術前検査による術前診断も大切だが、ゆっくりみていないで、早く取ってあげた方が、、と思った。
-
第25回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成19年7月19日)
数10年来の重症な関節症性乾癬の患者。下痢に加えて血清中クレアチニンの上昇をきたした。腎障害は進行し血液透析に至る。診断は、慢性の皮膚の炎症によって、血清中amyloid A蛋白が持続的に高値であったことが原因のsecondary systemic amyloidosisだった。皮膚にはアミロイドの沈着はないが、十二指腸と腎に沈着があった。ただし、全例そうなるわけではなく、アミロイドの沈着を処理できない遺伝的背景が発症に関与しているらしい。先天性表皮水疱症でも同様の合併症があるので、注意が必要。
SAAは皮膚疾患においても、やはり大事な炎症マーカーだと思う。皮膚疾患でルーチンに測るようにして3年ほどたつが、そろそろまとめる必要があるかもしれない。
-
第25回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成19年7月19日)
HAIR-AN症候群:女性に生じる。hyperandrogenism(HA)、insulin resistance(IR)、acanthosis nigricans(AN)の頭文字。黒色表皮腫が診断の契機になり、Ⅱ型糖尿病の診断に至ることがある。 SAPHO症候群:Synovitis、Acne、Pustulosis、Hyperostosis、Osteitisの頭文字。骨関節病変を伴う好中球の関与する疾患は、日本では膿疱性乾癬ないし掌蹠膿疱症、欧米ではacneの患者が多い。
頭文字症候群は冠名症候群以上にすぐ忘れる。知っていると症状・合併症が思い出せるので便利なのだが。CREST、POEMS、TORCH、HELLPなどなど。RUDやJOBは人名だったか、症状を思い出そうにも出てこない。だれかがまとめてくれるとよいのだが。
-
第56回神奈川医真菌研究会から(平成19年7月14日)
高齢者施設からの報告。足白癬を治療しないで放置するとどうなるかという話。入所者80%に足の爪白癬をみとめるが、角化型足白癬はほとんどいない。足白癬は、その終局像として、角化型足白癬に至る、という経過を想像するが、実はそうではなく、寝たきりになると足蹠は、逆につるつる、ふにゃふにゃになってしまうという。小水疱を伴うことも少なく、薄い鱗屑ついている程度だが、鏡検ではしっかり糸状菌が認められる。寝たきりのため、表皮にも廃用が生じているのであろう。言い換えれば、角化型足白癬は、健康サンダルの使用に代表されるように、たえず足蹠に物理的な刺激が加わった状態で発症すると言える。
確かにその通りだと思った。つるつるふにゃふにゃ型足白癬という呼称が広く普及することを期待する。
-
第2回横浜皮膚免疫アレルギー懇話会から(平成19年6月29日)
コリン性蕁麻疹の患者で時に眼瞼の浮腫をきたす例があり、時に開眼不能になる場合もある。これらの患者では、コリン性蕁麻疹を伴っており、涙に対する過敏症状がある。涙がやや黄色っぽいのが特徴。涙を採取して、それを薄めて点眼すると、症状の誘発が可能。運動をした際に出る涙の方が、タマネギで誘発した涙よりも症状が強い。汗によっても誘発されることがある。
汗過敏は聞いたことがあるが、涙過敏とは恐れ入った。神戸系の講演はいつも楽しく聞いている。ところでクインケの浮腫ではどうだろう。眼瞼の患者は涙過敏、口唇の患者は唾液過敏?今度調べてみよう。
-
第32回横々会から(平成19年6月28日)
正常の皮膚組織では、真皮のリンパ毛細管は見えない。これが見える時には、1)組織液をうまく吸収できない場合(浮腫)と、2)弾性線維が変性してしまっている場合(pseudoxanthoma elasticum、Pringle病、SLEなど)がある。リンパ毛細管の拡張を見逃さないことが大切。Nonne-Milroy-Meige 症候群という先天性の足背のリンパ浮腫を来す疾患があることも留意しておくこと。
先天性のリンパ浮腫は今まで経験がないが、外胚葉奇形を伴う遺伝性の疾患がいくつもあるようだ。今後は注意してみていこう。
-
第812回日本皮膚科学会東京地方会から(平成19年6月16日)
ウィルソン病に対して使用中の、D-ペニシラミン内服によって腋窩に生じた、特有の皮膚病変。D-ペニシラミンは結合織の架橋形成の阻害作用があり、elastinのアルデヒド型に直接結合するため、経表皮的排泄をきたすことがある。治療では、tazarotene外用が有効な症例があるとのこと。
tazaroteneはビタミンA誘導体で、TazoracあるいはZoracという名前で欧米でacneに使用されているようだ。2008年に発売されるadapaleneではどうだろうか。
-
第22回日本皮膚外科学会から(平成19年6月10日)
自家血を採血し、遠心分離して得られたplatelet rich な血漿分画に、KClとトロンビンを加え凝集、活性化し、ゲル状となったPRP(platelet rich plasma)を難治性の下腿潰瘍や褥瘡の瘻孔に外用、注入する治療法があり、有効である。
これは知らなかった。PDGFやTGF-βなどの成長因子を多く含み、創傷治癒が促進されるとのこと。機会があればやってみよう。疣贅に液体窒素凍結を行ったあとにできる血疱をはがした時のねっとりした感じを想像した。調べてみると、歯科口腔外科のほか、しわ伸ばしなどの美容目的でも盛んに使われているようだ。
-
第27回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成19年6月6日)
脱毛をきたす脱毛症以外の皮膚病の話。乾癬、掌蹠膿疱症、DLE、SLE、PSS、尋常性天疱瘡、癌の皮膚メタ、粘液水腫、Cronkhite-Canada症候群、aplasia cutisなど。色々な疾患を鑑別する必要がある。また、乳児の限局的な脱毛斑では、meningoceleが下にある可能性があるので、安易な処置や治療を行わないようにすることが大事。
経験はないが、触診が大事だろう。穿刺などしたら大変なことになる。
-
第12回横浜南西部皮膚科勉強会から(平成19年5月31日)
クロレラ加工品で有名になったな光毒性反応。クロロフィルからMgが抜けて、フェオホルバイトになると皮膚に光毒性反応を生じる。現在はフェオホルバイトの含有量を規制しているので、少なくなった。そのほか、最近はやりのアロマオイル、春のアワビのキモ、野沢菜の浅漬けなどには注意が必要。
アワビのキモは昔から有名らしい。私だけが知らなかったようだ。春先のphotodermatosisでは貝類の摂取を聞いてみよう。意外に、micropapular light eruptionなどでも関係がある?
-
第23回日本臨床皮膚科医会総会から(平成19年5月20日)
多型慢性痒疹の患者14例で、便中のヘリコバクター・ピロリ抗原の有無を検索した。14例中10例で陽性だった。そのうち7例に対して、AMPC、CAM、PPIによる除菌治療を行った。5例で除菌終了後、3~14日後に皮膚症状が軽快し、さらに4例では再発を認めなかった。
再燃を繰り返すため、当院では症例がたまっている。抗原の検出をやって、陽性なら除菌をお願いしてみよう。ただし、CAM自体が色々と免疫調整作用を持っているため、という可能性も否定できないと感じた。
-
第106回日本皮膚科学会総会から(平成19年4月22日)
アトピー性皮膚炎の外用剤のEBMの話。ステロイド軟膏を塗ると色が黒くなるという、よくある患者さんからの不安に対し、炎症が治まった後の色素沈着であると常識的に答えるよりは、火事の焼けあとが黒いのは、火が燃えたためで、消防士が水をかけたからではないと答える方がわかりやすい。なお、ステロイド軟膏を塗ると色が黒くなると思っているのは全世界的には日本人だけで、これは文化結合症候群である。
ある地域・民族・文化環境によって発生しやすい精神疾患を文化結合(依存)症候群というらしい。その辺もおもしろかった。
-
第106回日本皮膚科学会総会から(平成19年4月21日)
足背・下腿・手背などの多発性の有棘細胞癌と表皮細胞異形を伴うびらん。職業は漁師で50年にわたり、網の補強のためコールタールを素手で塗っていたことが原因のタールピッチ皮膚症と診断された。労働安全衛生法に基づき定められた、特定化学物質障害予防規則(特化則)では、タールピッチを使用する労働者には半年に一度の皮膚検診が義務づけられているとのこと。
電離放射線検診は大学時代に行っていたが、恥ずかしながら、法規自体を知らなかった。法律にはなかなかなじめないが、安全衛生情報センターのHPに詳しく書かれているので、ひまがあったら勉強しておこう。
-
第106回日本皮膚科学会総会から(平成19年4月21日)
cold-induced sweating syndromeというまれな疾患がある。幼児期から生じる発汗異常で、夏には汗をかかず、冬になると体幹、腋窩などからの発汗が顕著となる。外気にさらされている顔や手足には発汗がない。脊柱側弯、外反肘、手指のPIP関節の腫脹・変形などの骨格異常を伴い、また指間の皮膚が水かき状で、歯牙の脱落も認めた。ciliary neurotrophic factor (CNTF) receptorの第2リガンドであるCRLF1の遺伝子変異が原因の常染色体劣性の遺伝性疾患であることがわかっている。
よくぞ、このような症例を見つけたものだと感心した。それにしても遺伝子変異まですでに見つかっているとは驚きである。
-
第106回日本皮膚科学会総会から(平成19年4月21日)
高齢者の水疱性類天疱瘡に対して、ステロイド全身投与前に試みてよい治療にミノサイクリン+ニコチン酸アミドの併用があるが、高脂血症治療薬であるペリシットはニコチン酸アミドのプロドラッグで、体内で代謝されニコチン酸アミドとなる。ペリシット1000mgが885mgのニコチン酸アミドに相当する。ただし、耐糖能異常の副作用があるので、血糖には注意しなければならない。
これは知らなかった。今度使ってみよう。特に高脂血症を伴う口唇炎や口角炎などにも使えそうである。
-
第106回日本皮膚科学会総会から(平成19年4月21日)
イトラコナゾールパルス終了後に生じた発熱を多型紅斑の2例のうち、1例は内服テスト陽性。1例は内服テスト陰性で、その後の2クールでは発疹の出現なし。後者では一時的に白血球減少を伴い、イトラコナゾールによる免疫系の変調?が引き起こしたウイルス感染症かもしれない。
2例目は、よく残りの2クールを施行できたものだと感心する。白血球の低下が鑑別に重要なのかもしれない。
-
第106回日本皮膚科学会総会から(平成19年4月21日)
高齢者の腰部・下腹部(右Th11領域)に帯状疱疹が生じ、通常通りの治療を受けた。その2年後、罹患部位、およびそれからやや離れた背部にも、痒みを伴う多数の扁平に隆起する、やや硬い、大豆大までの赤い小結節が生じた。組織学的には類上皮細胞・多核巨細胞を伴う肉芽腫性病変で、帯状疱疹後肉芽腫(postzoster granuloma)と診断した。
これだけ帯状疱疹の患者をみているのに、1例の経験もない。組織も瘢痕ではないし、肉芽腫であることは間違いない。巨細胞中にvaricella-zoster virusを証明した報告もあるようで、いわゆる異物反応か。
-
第106回日本皮膚科学会総会から(平成19年4月21日)
亜急性結節性遊走性脂肪織炎(Vilanova's disease)は、30~60歳の女性に生じ、多くは片側の下腿伸側の無痛性の紅斑で始まり、2~3週間で10~20㎝の局面に変化し、古い病変は硬化を伴ってくる。潰瘍化や静脈炎の合併はない。生検では脂肪小葉間結合織に種々の程度の肉芽腫性、線維性の変化を認める。治療ではヨードカリが有効で、数週間で治癒するが、再発をきたすこともある。原因は不明だが、溶連菌感染や甲状腺疾患に伴うことがあるとのこと。
これは、初めて聞いた病名であった。今まであったかもしれないが、静脈瘤性症候群や結節性紅斑と診断しているだろう。記憶にとどめておこう。
-
第106回日本皮膚科学会総会から(平成19年4月21日)
おむつや生理用ナプキンで生じる皮膚炎には高湿度環境による水和(hydration)が原因のひとつと考えられる。水和閉塞負荷が及ぼす影響を検討するため、生食を含ませた綿を健常人の膝膕部皮膚に24時間貼付密閉し、検討した。その結果、70%に皮膚炎が発症した。皮膚炎発症群では水和閉塞直後のTEWLが高く、角層の厚さの増加が少ない傾向にあった。また、皮表では皮膚炎の有無にかかわらず、Staphylococcus属の菌が増加したが、皮膚炎のない被検者では速やかに減少して通常状態に戻るのに対し、皮膚炎が生じた被検者では、細菌の減少が遅れる傾向にあった。したがって、水和閉塞による皮膚炎の発症には、角層の水分保持能の低下および、ブドウ球菌属の関与が示唆された。
もともと水分保持能のよくない、アトピー性皮膚炎やドライスキンがあると、高度湿潤環境で湿疹が誘発されやすいということ。細菌の増殖も関与しているようだ。これはまさに、サッカーシンガード皮膚炎で経験した状況であり、興味深かった。
-
第30回横浜西部皮膚科臨床懇話会から(平成19年4月14日)
疥癬トンネルの詳細な観察。疥癬虫は、角層が柔らかくて掘りやすいため、皮膚の皺を好む。また、角層に潜って前に進んでいくため、水面に水鳥が残すような水尾の先、Y字型鱗屑の根もと、ないし涙型の痂皮のとがった所にいる。また、ダーモスコピーでは、茶色い「ほっかむり」として成虫そのものを確認できる。
これは指摘の通りである。水尾・ほっかむり・涙型の痂皮など、表現が大変ユニークで忘れがたい。
-
アトピー性皮膚炎と抗アレルギー薬講演会から(平成19年4月12日)
乾癬の治療薬、ビタミンD3外用剤は酸に不安定なため、混合はもちろん重擦もしてはいけない。角質溶解剤のサリチル酸ワセリン、ウレパール軟膏(0/W)、また、デルモベート軟膏の後発品であるマイアロン軟膏にもクエン酸が入っているので、注意が必要。
当院でも足蹠の乾癬や掌蹠膿疱症で併用処方している例があるかもしれない。気をつけよう。
-
第116回横浜市皮膚科医会から(平成19年4月8日)
糖尿病などでビタミンB2が欠乏した際に生じる、粘膜病変の臨床例。紅斑局面の中央にびらんがあり、その周囲に乾いた鱗屑を付着するのが特徴。また、これに似た疾患に腺性口唇炎(cheilitis grandularis)があり、下口唇粘膜の小唾液腺開口部に点状のびらんや陥凹を認め、分泌管の拡張と種々の程度の炎症を伴い、小児に多い。
口唇炎も原因の鑑別が難しい。口唇炎や口角炎は、広く一般的にもビタミン不足と思われているが、なかなかそれが原因だと確信をもって診断することはほとんどない。口唇炎の治療では、慣習的にB2とB6を用いることが多いが、実際の血中濃度を調べたことはそういえば、一度もない。今度調べてみようか。
-
第4回相模原皮膚科学セミナーから(平成19年4月7日)
DIHS(Drug-induced hypersensitivity syndrome)の診断基準は、日皮のHPにある通りで、1)限られた薬剤投与後に遅発性に生じ、急速に拡大する紅斑で、多くの場合、紅皮症に移行する。2)原因薬剤中止後も2週間以上遷延する。3)38℃以上の発熱。4)肝機能障害。5)血液学的異常。6)リンパ節腫脹。7)HHV-6の再活性化、である。この診断名は患者の救済を目的として提唱された診断名という一面があるが、これに対して、国外からは、薬剤性アナフィラキシーなどの即時型のアレルギーを想像させるという批判があるようで、欧州では、DRESS(Drug Reactions with Eosinophilia and Systemic Symptoms)という、臨床を重視し、HHV-6の再活性化を伴うことを条件としない病名が用いられている。DRESSの中に、HHV-6の再活性化を伴うDIHSが含まれると考えてかまわないが、横文字の報告は、DIHS/DRESSとして報告した方がよいとのことである。
米国ではDIDMOHS(Drug Induced Delayed Multi-Organ Hypersensitivity Syndrome)という病名もあるようだ。全世界的にDIHSでいいと思うが、政治と同様に、総意が必要ということか。
-
Dermaフォーラム2007から(平成19年3月10日)
ヘビースモーカーの硬口蓋に生じる白板症(leukokeratosis nicotinica palati)、時に頬粘膜、下口唇粘膜にも発生する(stomatitis nicotinica)。早期には粘膜が乳白色に混濁し、その中に唾液腺開口部に一致する点状の赤い斑、ないし光沢のある白色の病変を伴う(粘膜上皮細胞の空胞変性)。慢性に移行すると不規則な白色角化局面となり、粘膜上皮は肥厚し表面が皺状に凹凸するが、全経過を通して炎症性の潮紅は伴わないとのこと。
そういう診断をつけたことがない。ただ、当院の電子カルテで使っているICD10にも、ニコチン性口蓋白色角化症、ニコチン性口内炎という病名がちゃんと入っていた。
-
第8回関東皮膚脈管懇話会から(平成19年3月11日)
顕微鏡的多発血管炎の疾患マーカーであるMPO-ANCAに影響を与える因子のまとめ。1)シリカ:重症の肺・腎障害が多い。阪神大震災で倒壊した建造物の撤去作業に従事した症例がある。2)薬剤:プロパジールでは21例中13例(48%)、メルカゾールでは34例中3例(9%)で陽性になるという報告がある。3)黄色ブ菌:細菌感染がトリガーになり、MPAが発症することがある。
シリカについては知らなかった。なお、PR3-ANCA陽性のWegener肉芽腫症が欧州に多く、MPO-ANCA陽性のMPAが日本に多いという、人種、遺伝的要因も関連しているとのこと。
-
Dermaフォーラム2007から(平成19年3月10日)
爪白癬のイトリゾールパルス療法の改善度を生活習慣によって比較した。パルス療法6ヶ月後の改善度は、著効・治癒が喫煙者で33%、非喫煙者で44%、また飲酒の週間がある患者では36%、ない患者では48%、また、スポーツ習慣のある人に治癒症例数が多い傾向があり、飲酒・喫煙・運動不足で効きが悪いという結果だった。
何となく、わかる気がする。治療に熱心かどうかの性格と生活習慣の関連か。
-
墨東病院オープンカンファレンスから(平成19年3月8日)
露光部に発生し、老人性色素斑に炎症を伴い、組織学的に苔癬型反応を認めるlichen planus-like keratosis、あるいはbenign lichenoid keratosisと考えられる個疹が、四肢の露光部に多発する疾患に対して、mutiple benign lichenoid dermatosesという病名がある。文献によると、比較的高齢の女性に多く、先行する老人性色素斑の完全ないし部分的な消褪をみることが多いようだ。
これは最近よく目にする疾患である。当院ではLPLK like LPと呼んでいたが、既報告に従うことにしよう。ただし、文献には自然消褪もあり、ステロイド外用で数週間で改善するということだが、それ以上にかかる例が多いような気がする。一度ちゃんとまとめてみよう。
-
第26回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成19年3月7日)
ニキビに似るがニキビでない疾患の話。perioral dermatitis、本態性のrosacea、油症、ヨード疹、クロールアクネ、ヒダントインやイソニアジドによるacneiform eruption、Nevus comedonicus、ざ瘡型の亜急性単純性痒疹、atrophoderma vermiculata、vascular spider、hydroa vacciniforme、eruptive vellus hair cystなど。このほか全身疾患の症状として、クッシング症候群、クローン病、ベーチェット病、副腎性器症候群を考えなくてはならない。
なるほど。「痒疹のざ瘡型」は印象的だった。顔に限局する痒疹で、血液透析に伴うことが多いらしい。さっそく明日からの診療に役に立つ。
-
第123回神奈川県皮膚科医会から(平成19年3月4日)
骨髄の中には造血幹細胞のほかに様々な臓器・組織へと分化する間葉系幹細胞がある。皮膚の再生に基底層にある幹細胞の他に、骨髄中の幹細胞が関与しているかどうかを調べるため、GFPという蛍光を発する蛋白の遺伝子を導入した骨髄を移植したマウス(GFP-BMTマウス)を作成した。そのマウスの皮膚にキズを作ると、特殊な条件下では半数近い表皮基底細胞がGFP陽性となった。生体には、組織が損傷した場合、その組織になる能力のある体性幹細胞を、骨髄から血流を介して引っぱってきて、できる限り短期間で組織の修復を行うという機構があることが証明された。また、皮膚が大量に欠損したときに、欠損部の皮膚が出す、骨髄幹細胞を呼んでくる因子(コイコイシグナル)も明らかになりつつある。先天性表皮水疱症や重症熱傷などに骨髄幹細胞移植が治療として用いられ、またコイコイシグナルの遺伝子導入によって皮膚の再生が短期間に行えるようになるかもしれない。
夢のある大きな仕事で感動した。再生医学と遺伝子治療の融合は、大きな可能性を秘めていると思った。
-
第1回横浜皮膚病免疫治療研究会から(平成19年2月22日)
乾癬患者では、特に衣服の選択、入浴、スポーツ活動においてQOLが障害されており、また、英国の調査ではうつ症状も62%の患者に認められた。また、QOLのスコアが高いほど服薬のアドヒアランスが低下し、それがさらに乾癬を悪化させる負のスパイラルが存在する。したがって、乾癬患者の治療ではQOLの評価が重要である。また、体表面積(BSA、手のひらが1%)、PASIスコア(self PASIスコアの方が楽)、PDI(Psoriasis Disability Index)のいずれかが10を超えた症例は重症と見なし、シクロスポリン内服などの全身療法を考慮する必要がある(10の法則)。
PDIのほかにもDLQI(Dermatology Life Quality Index)は知っておかないといけないようだ。さっそく準備しよう。
-
日本皮膚科学会東京支部総会から(平成19年2月18日)
糖尿病などの慢性疾患において、患者自身が管理しなければならないことは、以下の3つである。1.治療の管理:くすりの服用など、治療方針について医師と話し合い、自ら正しく実行していくこと。2.社会生活の管理:慢性疾患と上手につきあいながら、仕事をしたり、家事や育児をしたりといった役割をとっていくこと。3.感情の管理:病気があるために感じる怒りや疲労感、無力感、不安などと向き合い、対処すること。2005年秋に日本慢性疾患セルフマネジメント協会(http://www.j-cdsm.org/)が設立され、ワークショップの開催のほか、教材の開発、人材育成などの事業を行っているとのことである。乾癬やアトピー性皮膚炎などの皮膚科の慢性疾患でも有意義なプログラムである。
当院の患者さんにも紹介していくことにしよう。社会的な活動として、学会や医会が取り組んでいく必要があると思った。
-
日本皮膚科学会東京支部総会から(平成19年2月18日)
女性のびまん性脱毛は、①女性の男性型脱毛(female pattern AGA:FAGA)、②休止期脱毛(後頭部は起こりにくい)、③加齢(伸びるスピードが遅くなり、全体として少なくなる)④全身性疾患に伴うもの(polycystic ovary、粘液水腫など)があり、②はさらに、(1)acute telogen effurium(出産後、ダイエット)、(2)chronic diffuse telogen effurium(内科的疾患)、(3)chronic telogen effurium(薬剤性など)にわけられる。原因となる薬剤には、抗癌剤以外では、三環系抗うつ剤、SSRI、リチウム製剤、βブロッカー、メチルドーパなどがあり、またベサフィブラート、シンバスタチンなどの高脂血症治療剤では内服して3~4ヶ月たってから脱毛を生じることがある。また、閉経後にぐるりとハチマキ型に脱毛を生じる、post menopausal fibrosing alopecia(PMFA)という特殊なタイプの脱毛症がある。
いろいろあって難しい。薬剤性の脱毛症は診断が難しいが、具体的に名前が挙がったので、今後の診療に役に立つだろう。
-
日本皮膚科学会東京支部総会から(平成19年2月17日)
下肢の筋肉痛、足関節の腫脹を伴う関節炎、しびれ、発熱。発疹は膨疹様の紅斑。ANCAは陰性。血管炎を疑ったが、細胞浸潤はリンパ球主体。抗SSA抗体陽性と下口唇の生検からシェーグレン症候群に伴うリンパ球性血管炎と診断した。PSL20mgの内服で軽快。関節症状が強いのが特徴のようだ。
病名はともかく、シェーグレン症候群のひとつの皮膚症状と考えよう。たしかに臨床症状は血管炎に似ていると思った。
-
横浜市耳鼻科医会・花粉症講演会から(平成19年2月7日)
第2世代の抗ヒスタミン薬の効果の比較の話。3種類の抗ヒ剤を比較したところ、3者で優劣の違いはなかった。しかし、それぞれにおいて、日中の眠気があった患者となかった患者の2群間で医師の判定による改善度を比較すると、いずれも眠気がなかった患者の方が、眠気があった患者より改善度が高かった。これらの抗ヒ剤では「眠いと効かない」と結論できる。
同じことが蕁麻疹やアトピー性皮膚炎でもいえるだろうか。眠気と効果は必ずしも比例しないというエビデンスはアトピー性皮膚炎でも出ているようだが、患者さんに効いてみよう。眠くなる抗ヒ剤は、即変更の必要がある?
-
横浜市耳鼻科医会・花粉症講演会から(平成19年2月7日)
スギ花粉症には予備軍があり、無症候性スギ花粉症と呼ぶ。スギ花粉特異的IgE抗体の量とは関係がなく、閾値では説明できない。12月末に取ったTリンパ球と3~4月に取ったTリンパ球それぞれにCriJ1抗原を加えた際のIL-4とIL-5の産生性を比較すると、健常人ではいずれも産生性の違いなし、鼻炎症状を伴う患者ではIL-4、IL-5ともに産生性が亢進、無症候性花粉症患者ではIL-4は産生するが、IL-5は産生しないという違いがあった。また、特異的減感作療法が奏功したスギ花粉症患者では、CriJ1に対するIL-5産生が生じなくなることが判明した。
スギ花粉皮膚炎の無症候性患者もあるのだろうか。同様の検査をするとおもしろいかもしれないと思った。
-
日本皮膚科学会東京支部・生涯教育セミナーから(平成19年2月4日)
抗菌薬のPK/PDとは、血中濃度と効果の間の相関性を示す指標である。体内動態(Pharmacokinetics:PK)のパラメーターは、最大血中濃度(Cmax)および曲線下面積(AUC)、薬理作用ないし抗菌活性(Pharmacodynamics:PD)のパラメーターは細小発育阻止濃度(MIC)を用いることが多く、PK/PDのパラメーターはCmax/MIC、AUC/MIC、t>MIC(time above MIC: TAM)などで示される。一方、抗菌薬には、薬物濃度がMIC以下でも菌の増殖が抑制されるというPAE(post-antibiotic effect)のある薬剤がある。キノロン、アミノグリコシドは濃度依存性で、PAEあり。抗菌力を高めるためには、1回投与量を増やして、Cmax/MICを高くする必要がある。セフェム、ペニシリンは時間依存性、グラム陰性菌にはPAEなし。したがって、抗菌力を高めるには投与回数を増やして、TAMを長くすることが必要。また、カルバペネム、マクロライドは、時間依存性でPAEありとのことである。
内服の使い方の革新。キノロンは3錠分1の方が、3錠分3より有効と言うこと。また、眼科領域の抗菌点眼薬でも様々なデータがある。皮膚科領域の外用抗菌剤には、だれも興味を持っていないようだ。
-
半導体レーザー治療研究会から(平成19年2月1日)
帯状疱疹後神経痛は、帯状疱疹の発症によって壊れた神経が、治癒過程で本来つながっていない神経線維に配線がつながり(エファプス)、触覚・圧覚を伝達するAβ線維の刺激がAδ線維やC線維に伝わることによる痛み(アロデニア)を起こすことが主な原因で、シャツに触れた時などに感じる痛みはこのためである。また、交感神経からは常に電気的信号が送られており、それがエファプスを通してAδ線維に伝わるため持続痛と関連している。
皮膚に分布する神経については、かゆみの神経生理の話で時々耳にするようになったが、エファプス、アロデニアなどの単語は始めて聞いたような気がする。生理学や麻酔科の授業で出てきたかどうか、記憶にない。
-
第30回皮膚脈管膠原病研究会から(平成19年1月25日)
歯周病菌のほとんどはグラム陰性桿菌で、通常は歯垢として歯と歯肉の間にバイオフィルムを形成している。しかし、、特に癌や糖尿病などの疾患あるいは高齢者などの免疫低下の状態では、これが血中に入ると心内膜炎や動脈内膜炎を起こし、それが血管の粥状硬化を増長させ、重要な心血管イベントの引き金になることが報告されているとのこと。
TV番組的であるが、おもしろい討論であった。
-
第30回皮膚脈管膠原病研究会から(平成19年1月25日)
若い男性の症例。足を捻挫、ギブス固定をしていたところ、同側下腿に腫脹をきたし、血管エコーで深部静脈血栓症と診断された。へパリン投与で改善。原因は、先天性のアンチトロンビンIII欠損症で、父にも同症を認めた。本疾患は先天的な異常にもかかわらず、20歳から50歳ぐらいに外傷や妊娠を契機に血栓を生じることが多い。治療はアンチトロンビンIIIの補充療法が用いられる。
なかなかそこまで調べられない。血管エコーは皮膚科でも有用な検査であり、当院でも最近これを導入し、現在勉強中である。
-
第811回日本皮膚科学会東京地方会から(平成19年1月20日)
血清5SCDは転移性のメラノーマの腫瘍マーカーであるが、慢性腎不全患者、化学療法中の患者、レボドーパを内服中の患者、さらに健常人でも夏季には高くなることがあるということで、注意が必要。
開業医ではまずやらない検査だが、一応そういうことがあることは知っておこう。
-
第2回筑駒医師会から(平成18年12月29日)
破骨細胞をめぐる免疫学の話。RAでは、滑膜が異常増殖し、そこに破骨細胞が過剰に形成されて骨破壊を起こす。滑膜内で破骨細胞形成を促す分子が、T細胞の膜上に存在し、リンパ球を活性化する分子として既知のRANKLであるとわかっていたが、T細胞はRANKLと同時に破骨細胞を抑制するIFN-γも作るため、どのようなT細胞が破骨細胞を増やすのかが不明だった。しかし最近、IL-23によって増えるTh17細胞だけが破骨細胞を増やす作用をもつことがわかった。Th17細胞は、IL-17を作り出すことで、周囲の細胞の炎症を引き起こすと同時に、RANKLを増やすことで、破骨細胞の形成を誘導している。
class="moji-12">Th1、Th2、Tregまでは聞いたことがあったが、Th17は知らなかった。皮膚科で扱う自己免疫疾患にも関与していそうでおもしろそうである。
-
第810回日本皮膚科学会東京地方会から(平成18年12月16日)
成人のアナフィラクトイド紫斑病患者20例(男性12例、女性8例)で、血中抗カルジオリピンIgA抗体を計測した。15例で検出され、平均は9.6U(正常は4.0U以下)であった。抗カルジオリピンIgG抗体、IgM抗体、および、抗β2GPI抗体は検出されなかった。臨床症状と平均測定値との関連では、15例の陽性例のうち、関節痛のある9例では12.0、ない6例では8.9、蛋白尿のある7例では13.0、ない8例では6.6、腹痛のある5例では7.5、ない10例では10.6であり、腎障害、関節痛と相関していた。
病因とも関連している可能性もあり、貴重な報告だった。
-
第31回横横会から(平成18年11月30日)
全身性の多毛症だが、そのすべてがうぶ毛で、ずっとhair patternが変わらない状態をいう。先天性と後天性があるが、後天性の全身うぶ毛は肺癌などの悪性腫瘍に合併する、デルマドロームである。
始めて聞いた疾患であった。調べてみると、直腸癌・膵癌などに伴った症例もあった。めったにはないだろうが、今後は注意してみていこう。
-
第809回日本皮膚科学会東京地方会から(平成18年11月18日)
ネフローゼでステロイド内服中の67歳、女性。肛門部に深い潰瘍ができ、急速に全周に拡大した。発熱などの全身症状なし。生検でサイトメガロウイルス感染症に特異的な核内封入体を有する巨細胞が証明され、診断に至り、ガンシクロビルの投与で軽快した。
なかなか生検をしようと思わない場所だが、生検をしないとわからない。貴重な報告であった。HIV感染に伴って起こることも多いらしい。これは既感染の再活性化か、新しい感染の血行性播種か、それとも皮膚への直接の感染か、質問するのを忘れてしまった。
-
第115回横浜市皮膚科医会から(平成18年11月11日)
糖尿病患者のフットケアについての総論。切断に至るようなハイリスク因子としては、1) 糖尿病の経過が10年以上、2) HbA1Cが7.0以上、3) 合併症特に糖尿病性腎症に対するHD、4) 喫煙、5) 独居の男性、6) 教育不足、7)切断の既往歴、があげられる。また、糖尿病性の神経障害と皮膚病変の関連は、知覚神経障害→痛みを感じない→潰瘍・壊疽の悪化や進行、運動神経障害→支配筋の萎縮→足の変形、自律神経障害→発汗の低下→乾燥・キレツの3つの要素がある。
足の皮膚の乾燥、キレツが糖尿病性神経障害と関連するのは知らなかった。角化型足白癬が糖尿病患者で多いのも、易感染性だけではないのかもしれないと思った。
-
口腔カンジダ症学術講演会から(平成18年11月9日)
口腔外科の先生の講演。ドライマウスを主訴に来院した690名の患者の唾液分泌量を測定し、安静時唾液分泌量が15分で1.5ml以下、刺激時唾液分泌量(ガムテスト)が患者10分で10ml以下を指標とした。690名中295名では安静時、刺激時ともに減少、66名では安静時減少、刺激時は正常、106名では安静時正常、刺激時に減少、223名ではいずれも正常だった。これらの患者で唾液からのカンジダの培養を行ったところ、安静時、刺激時ともに低下していた295名のうち、69%からカンジダが培養され、コロニーの平均が375個、安静時、刺激時どちらか一方が低下していた、172名のうち、カンジダが培養されたのは67%でコロニー数の平均は66.8個、安静時、刺激時ともに正常であった223名からは、カンジダが検出されたのは48%で、平均コロニー数は7.8個であった。
きれいなデータである。カンジダが原因で口腔内乾燥が生じているとは思わないが、ドライマウスが口腔内カンジダ症の誘因になることがわかった。ちなみにドライマウスは、唾液分泌の低下(唾液腺の破壊・神経伝達の障害)と唾液の蒸発が原因だが、歯ぎしりをする人は、下顎の筋が疲れて口が開いてしまい、夜間口腔乾燥を訴えることが多いらしい。
-
第65回日本アレルギー学会から(平成18年11月3日)
キャッスルマン病に対する、トシリズマブ(アクテムラ)の有効性の報告。キャッスルマン病、特に多発性のリンパ節腫脹をきたす多中心性キャッスルマン病では、IL-6の過剰産生が原因となって、臨床症状(発熱、倦怠感、やせ、皮膚の形質細胞腫、間質性肺炎など)あるいは検査異常(CRPや血清アミロイドAなどの急性期蛋白の上昇、血中アルブミン、ヘモグロビン、総コレステロールなどの低下)が生じるが、ヒト化抗IL-6受容体抗体(トシリズマブ)8mg/kgの2週間隔での静注によって、症状、検査異常ともに改善した。それに加えて、治療前には高値であった、total IgE、血中IL-4、RAST scoreや、血中VEGFも正常化したとのこと。
モノクローナル抗体の治療は非常に興味深く、期待している。癌の悪液質もIL-6の過剰産生による病態であるとのことで、コストはかかるが使えるのではないか。
-
第65回日本アレルギー学会から(平成18年11月3日)
アスピリン不耐症はCOX-1阻害作用を持つNSAIDに対して、喘息や蕁麻疹などの過敏症状を呈する後天的な薬理学的変調体質である。アスピリン喘息では、COX-1阻害薬による誘発のあとに2-5日間の不応期が生じる。これを利用して、アスピリンを連続投与することによって、NSAIDに対する耐性を維持し、発症の予防が可能である。まず50mg程度で軽度の喘息発作を誘発し、翌2日目はそれと同量、さらにその数時間後に2倍量を負荷。3-4日目はさらにその4倍量(200mg)、8倍量(400mg)を3-4時間ごとに投与し、耐性を完成させる。維持はアスピリン300mg-600mg/日で行っていくとのこと。ただし、皮膚型のアスピリン不耐症(蕁麻疹など)では病型が複雑で、耐性誘導の評価も一致していないらしい。
理論的には「確かにその通りだ」と思う。蕁麻疹での耐性誘導、維持療法の評価も必要だろう。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成18年11月2日)
運動誘発性食物依存性アナフィラキシーの原因で最も多いのが小麦であるが、誘発テストの場合には小麦粉で作った20gないし100gの「おやき」を利用する。20gでは出ず、100gで出る症例がある。なお、アスピリン負荷をかける場合には、20mg、50mg、100mg、200mgと少ない量から始める必要がある。症例によっては200mgのアスピリン内服で、血中グリアジン濃度が5倍にもなることがあるとのこと。
このような負荷試験は、実際はどうやっているか、わからないことが多く、参考になった。ちなみに100g「おやき」は中力小麦粉(それがない時は強力粉と薄力粉を半々) を100g、サラダ油を大さじ1/2、塩を少々、熱湯を1/3カップ混ぜて、よくこね、棒状にまとめてぬれぶきんをかけ30分以上置いてねかせ、切り分け丸め、麺棒などで伸ばし、蒸すあるいは焼いて作るそうだ。また生地を小さく薄く伸ばすと、餃子の皮として使えるらしい。
-
第2回神奈川皮膚アレルギー疾患研究会から(平成18年10月28日)
金属フタロシアニンが花粉、ハウスダストなどのアレルゲンを吸着することが判明。加工繊維を用いて花粉症用のマスクの他、寝具、下着を開発。アレルキャッチャーという名称で商品化した。アトピー性皮膚炎でこの下着を使用したところ、かゆみスコアの低下を認めた(http://www.jst.go.jp/pr/info/info293/index.html)。さらに、給気口や空気清浄機・エアコンなどの家電向けフィルターもすでに商品化されている。
かゆみの抑制は理解に苦しむが、エアコンフィルターはいいだろうと思った。これから有名になるかもしれないので、名前は覚えておこう。
-
第2回神奈川皮膚アレルギー疾患研究会から(平成18年10月28日)
抗リン脂質抗体症候群では臓器や大血管の血栓予防が重要であり、抗血栓療法についての知識が必要である。ワーファリンの使用法については、まず、少ない量(1mg)から始めて、1.5mg、2mgと増やしていく。最初は3日に1回はINR(プロトロンビン時間のInternational Normalized Ratio)を測定し、1.6から2.0ぐらい、トロンボテストでは20~30%で維持していくのがよい。いつまで内服するかについては、血栓に対する予防投与なので、一生涯とのこと。
皮膚科で治療することもあるだろう。覚えておかなくてはいけない。恥ずかしながら、INRという評価法を知らなかった。
-
第2回神奈川皮膚アレルギー疾患研究会から(平成18年10月28日)
抗核抗体の検査は血清を希釈し蛍光抗体直接法を行う。この検査では①抗核抗体が陽性か陰性か、②抗セントロメア抗体(discrete speckled pattern)が陽性か、③染色パターンから抗原特異性がある程度わかる。逆に、SSA、SSB、Jo-1、1本鎖DNAは抗原が不安定で溶出してしまうため、この方法では抗核抗体としては検出できず、結果としては陰性となる。
検査結果を読む上で、大事な復習であった。
-
第50回医真菌学会から(平成18年10月21日)
脂漏性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、酒さ、皮膚筋炎、ざ瘡の患者で、顔面脂漏部位のマラセチアの寄生形態をKOH直接鏡検で調べた。脂漏性皮膚炎では79例中、陰性15例、胞子型55例、菌糸型15例。アトピー性皮膚炎では50例中、陰性11例、胞子型28例、菌糸型1例。皮膚筋炎では5例中、陰性なし、胞子型1例、菌糸型4例であった。
癜風以外にも、皮膚筋炎の顔面脂漏部でマラセチアの菌糸がみられるらしい。どういう意味があるのか考えてみたい。
-
第50回医真菌学会から(平成18年10月21日)
爪の先から中枢側に進展するクサビ状の混濁で、爪甲下に空洞を形成するものをdermatophytomaとよぶ。通常爪白癬の原因菌は90%がTrichophyton rubrumであるが、dermatophytomaから検出された真菌は90%以上がT. mentagrophytesであった。
SWOもメンタが多いようだし、メンタと爪の関連はなかなかおもしろそうだ。
-
第50回医真菌学会から(平成18年10月21日)
アトピー性咳嗽あるいは咳喘息の一部の患者の喀痰培養から、環境真菌であるヤケイロタケ(Bjerkandera adusta)が検出され、全例咳嗽に対して抗真菌剤が有効であった。即時型アレルギーを惹起する環境真菌として注目する必要がある。
class="moji-12">サクラの木の幹にくっついているサルノコシカケのようなクチャっとしたキノコ。こんなのが病因になるとは知らなかった。アトピー性皮膚炎との関連もあったりするのだろうか。
-
第5回横浜デルマカンファレンスから(平成18年10月19日)
生後1ヶ月前後の乳児の股部に発症する炎症性角化症。乾癬なのか、脂漏性皮膚炎なのか、カンジダが関与するのかで、結論が出ていない。通常は1歳頃までに軽快・消褪すると言われている。しかし、その後6~7年以上経過をみた11例のうち、3例で4歳、6歳、14歳で尋常性乾癬が発症した。napkin psoriasisではやはり乾癬の素因が関与していると考えられる。
脂漏性皮膚炎の特殊な形で、すべてが自然経過で改善すると思っていたので意外だった。
-
第57回中部支部学術大会から(平成18年10月8日)
OCA2型(P遺伝子関連型)は日本人のOCAの10%に認められる。OCA1型(チロジナーゼ関連型)より症状が軽く、日焼けを起こしやすいことは自覚していても疾病として認識していない人が多い。100名ほどの調査では、メラノソームの生合成に関わる蛋白をコードするP遺伝子のA481T alleleの変異を有するキャリアーが、日本人健常人のうち、heteroが20%で、homoが2%で認められた。
美白変異とよばれてきたようだ。近くにもいるかもしれない。UVによる皮膚癌発症には注意が必要とのことなので、注意してみていこう。
-
第57回中部支部学術大会から(平成18年10月7日)
パスツレラ感染症は通常は犬や猫に咬まれたあとに発症する。ペットの口腔内の常在菌で、犬では75%、猫では97%に認められる。ただし、猫はグルーミングをする関係で、20%では爪にも菌の保有が認められる。したがって、猫に引っ掻かれたあとに発症することもあるので、注意が必要。
口腔内の菌という認識があったので、咬まれた後だけ注意すればよいかと思っていた。猫が前足の先をペロペロなめている姿を思い出した。
-
第15回皮膚科在宅医療勉強会から(平成18年9月14日)
難治性の下痢を伴っている患者の仙骨部の褥瘡の汚染回避に対して有効なおむつ(軟便吸収パッド)を作って、すでに市販されている(http://www.elleair.co.jp/takecare/)。水様便が8g、10秒間連射であるという観察から、まず濾過して液体成分と固形成分に分離し、液成分を吸収することで便モレと便による一次刺激を軽減した商品とのこと。
8g、10秒連射を突き止めるまでがかなり大変だったと思われる。このほか、褥瘡のポケットを確認するために鑷子を差し込むのは野蛮との見解から、柔らかいファイバーで先端に赤いライトがつくポケット検査用ライトの紹介もあった。医者では考えつかない仕事にはいつも頭が下がる。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成18年9月7日)
デング熱とデング出血熱は、いずれもネッタイシマカなどが媒介するデングウイルスが原因で、高熱とともに風疹様の中毒疹を生じる。東南アジアなどの流行地に行った人の急性発疹症では念頭に置く必要がある。デングウイルス感染後、デング熱と同様に発症して経過した患者の一部に、突然に血漿漏出と出血傾向を主症状とすることがあり、デング出血熱とよばれる。点状出血、鼻出血、消化管出血などをきたし死に至ることもあるので注意が必要。血小板数のフォローが大事。
デング熱とデング出血熱は違うウイルスかと思っていた。どうすれば出血熱にならないですむかが、臨床医としては知りたいところである。国立感染症研究所のHPに詳しい解説がある。
-
第24回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成18年9月6日)
若い女性の外陰部にみられる深い潰瘍で瘢痕を残す。通常は慢性再発性だが1回きりで治癒する例もあり、感染症の除外が必要。かつては膣桿菌が関与するといわれていた。一般的には年齢とともに改善。幼児での発症はない。必ずしもすべてが不全型ベーチェット病というわけではないが、結節性紅斑を伴ったら、それも考慮するというスタンスでフォローすること。
不全型ベーチェット病が最近また増加してきたという報告がある。ちなみにベーチェットの陰部潰瘍は通常はアフタで、急性陰門潰瘍はsweet病の外陰部潰瘍にあたるとのことだ。
-
横浜労災病院症例検討会から(平成18年9月6日)
手背から手指背面に径1mmほどの白色~淡紅褐色の小結節が多発。一見、青年性扁平疣贅。疣贅状肢端角化症(acrokeratosis verciformis Hopf)と診断。爪甲が全体的に乳白色で、透明な縦の線条を伴うこととともに、Darier病にみられる手の症状の特徴である。
忘れかけた病名を思い出した。手背に扁平疣贅と思われる角化性小結節をみたら躯幹の観察が必要だ。
-
第7回関東脈管懇話会から(平成18年9月3日)
MPAの概説。ANCA関連血管炎のひとつで、MPO-ANCAが陽性であり、急速進行性糸球体腎炎、肺出血、皮膚症状が主症状。ときに多発単神経炎(乏血性末梢神経障害)と消化管出血をきたす。発症機序は、MPO-ANCAと結合して活性化された好中球が細小血管の血管内皮を損傷することであるが、罹患血管が細小血管であるため、血管壁の壊死性変化はおこらず、フィブリンも外へ流れてしまうため、フィブリノイドにはならない。また免疫複合体は関与しないので、DIFも陰性である。かつてはhypersensitivity angiitisといわれ、急性に増悪して生命予後が不良で、病因として抗甲状腺剤などの薬剤との関連が深かった。
血管壁の壊死性変化は認めないというところに注目。ここが内科・病理の意見といつも食い違うところだ。診断基準もPNと一緒では無理があると思われる。
-
第2回神奈川県皮膚科医会サマーセミナーから(平成18年8月26日)
自分の講演で恐縮だが、AGAの内服治療の話。わが国ではプロペシア0.2mg錠あるいは1mgが認められているが、実はフィナステリドはプロペシアだけではなかったという事実を知った。そもそも前立腺肥大の治療薬である、フィナステリド5mgのプロスカー、あるいはそのジェネリックであるフィンカー・フィスタイドといった薬剤がインターネット経由の個人輸入で出回っている。5mg錠をを4分割、5分割してプロペシア1mg錠の内服と同じ効果を期待している。特にフィンカー5分割はコストが安くすみ(1mgあたり15円~20円)、若者に人気があるとのこと。
そういう薬があって、そうしている人がいるという情報として大事。ただし適正使用ではなく、全く薦められない。ファイザーがバイアグラで調査をしたところ、正規品以外を内服している人が22%あったという。ただし、インターネットで販売されているものの半分は中国や南アフリカで作られている偽造品だそうで、WHOもこれについては警告を発した。プロペシアでも同じことが起こってきそうで、心配である。
-
日本臨床皮膚科医会中国支部学術大会から(平成18年7月30日)
PCB、PCDFなどのダイオキシンが混入した米ぬか油を食したために生じた食品公害。クロールアクネが有名だが、そのほか歯肉・爪の色素沈着やコーラベビー(全身が黒い色素沈着の赤ちゃん)、マイボーム腺肥大とチーズ様眼脂、乳頭モンゴメリー腺増大などの皮膚粘膜症状がある。油症と認定された患者の検診では、30年たった今でも3-4割にクロールアクネの症状が残っているとのこと。
皮膚科医が覚えておく必要のある、歴史的事件だと再確認した。九大皮膚科のホームページに詳しい解説と文献があることを最近知った(http://www.kyudai-derm.org/part/yusho/)。
-
日本臨床皮膚科医会中国支部学術大会から(平成18年7月30日)
害虫専門家による皮膚疾患と関連するダニの話のまとめ。①ヒトの血を吸うダニ(マダニ、ツツガムシ、イエダニ、ワクモ、トリサシダニ、スズメサシダニ):イエダニはネズミにつくダニで越冬のため11月頃に住居に侵入した際に持ち込まれる。ワクモ以下は鳥につくダニだが、5-6月に雛が巣立った後、ヒトを刺すことがある。②ヒトの体液を吸うダニ(ミナミツメダニ、シラミダニ):血は吸わないが虫さされの症状を起こす。ミナミツメダニは畳についていて夏に発生。シラミダニはシバンムシなどの室内の虫に寄生して、時にヒトを刺す。チクリとはせず、遅延型反応を起こすらしい。チクリとした場合は、同じくシバンムシに寄生する、シバンムシアリガタバチの可能性が大。③ヒト寄生性のダニ(ヒゼンダニ、ニキビダニ)④アレルゲンとなるダニ(チリダニ、コナヒョウヒダニ、ヤケヒョウヒダニ)。
夏場の虫さされの患者さんに、何に刺されたかを聞かれて困ることが多いので、参考になった。シバンムシアリガタバチが大穴だろう。最近は鳥の飼育歴、近くに鳥の巣がないかも聞くようになった。
-
第23回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成18年7月20日)
魚鱗癬はバリア形成不全であるという当たり前だが、実は細胞生物学の最先端の話。表皮のバリアは①角層蛋白(ケラチン・フィラグリン)、②cornified cell emvelope、③inter cellular lipid layerからなるが、それぞれの形成不全が①では尋常性魚鱗癬と水疱型魚鱗癬様紅皮症、②では非水疱型魚鱗癬様紅皮症と葉状魚鱗癬、③では道化師様魚鱗癬とX-linked ichthyosisの表現型をとる。その中でも道化師様魚鱗癬では表皮細胞の脂質輸送に携わる蛋白であるABCA12の高度な機能異常で細胞間脂質の形成が妨げられることが病因であると確認された。これによって胎児皮膚生検(19週から可能)あるいは絨毛膜生検(10週から可能)で得た検体のDNA解析による、道化師様魚鱗癬の出生前診断が可能になった。
アトピー性皮膚炎の乾燥肌にもフィラグリンの異常が関与しているとのこと。さらに一般的な疾患でも解明されていくに違いない。
-
第36回日本皮膚アレルギー学会から(平成18年7月14日)
夏季に潰瘍をきたすlivedo racemosaの原因検索の話。通常加温で凝固する血清ないし血漿中の蛋白は、Bence-Jones蛋白ないし、pyroglobulineであるが、凝固にはいずれも56℃以上の必要である。しかし一部の夏季潰瘍をきたすlivedoの患者の血漿中には、42℃、6時間の加温で凝結する約40kDaの蛋白が認められた。これは、ESI-TOF/MSという方法による質量分析の結果、actinとくにβactinとの相関が示唆された。
生体内で夏季に何が変化するのかは以前から不思議に思っている。ただし、細胞に広く分布しているactin蛋白が、どのように血栓ないし塞栓と関連するのかは、解釈が難しいと思った。
-
第36回日本皮膚アレルギー学会から(平成18年7月15日)
高血圧・心不全治療でβブロッカーを内服している患者では、アナフィラキシーを生じた際に通常の第一選択であるエピネフリンが効きにくく、この場合にはグルカゴンを投与する必要があるかもしれない。
めったに遭遇するわけではないが、覚えておく必要があると思った。ただし、どこの皮膚科外来にもグルカゴンは置いていないだろう。
-
第36回日本皮膚アレルギー学会から(平成18年7月15日)
四肢・腰部に色素沈着のある症例。ナタマメを煎じたお茶を飲んだあとにその部位に紅斑を生じた。組織も固定疹の反応。薬剤との因果関係は証明できず、お茶の再投与で、24時間後後に紅斑が誘発され、固定食物疹と診断。固定食物疹はこれまでに、アスパラガス、ラクトース、レンズ豆、チーズ、トニックウォーターによるものが報告されている。
確かにこういう症例はあってもいいだろう。固定疹をみたら、食物も原因として考えておく必要があると思った。
-
第36回日本皮膚アレルギー学会から(平成18年7月15日)
豆乳アレルギー3例の報告。すべて女性でいずれも春季花粉症を合併していて、ハンノキ・シラカンバの特異的IgEが陽性。豆腐の摂取は問題なし。症状は口腔内アレルギー症候群からアナフィラキシーまで様々。抗原としてはⅠ型アレルギークラス2抗原であるBet v1 ホモログなどと関連があるとのこと。
豆乳アレルギーが花粉アレルギーだとは思わなかった。最近特に増えているとのこと。成人でなぜか女性?今度OASの症例があったら豆乳との関連も聞いてみよう。ハンノキ花粉症はスギと重なっているので忘れがちになる。
-
第807回日本皮膚科学会東京地方会から(平成18年7月8日)
寝たきり高齢者の末期の乳癌・皮膚癌で、根治手術が行えないケースで、癌からの出血・疼痛・細菌感染による悪臭に対してモーズペースト(Mohs paste)外用を試み、それぞれの症状に対して有効であり、また癌組織のvolumeの減少にも効果があった。モーズペーストによるchemosurgeryは古くからある方法で、塩化亜鉛と亜鉛化デンプンを主成分とする外用剤による組織硬化作用を用いる方法である。
在宅や介護老人施設で時々遭遇するようになった。切除不可能なターミナルな症例に対しては、今まではお手上げだったが、今後は試してみる価値があると思った。なお、私の出向いている横浜労災病院では、開放創用ダラシンパテという院内製剤があり、特に悪臭には有効とのことだ。
-
第807回日本皮膚科学会東京地方会から(平成18年7月8日)
結節性紅斑と肛門部潰瘍をきたしたクローン病の症例。ステロイド内服で結節性紅斑は消褪したが、肛門部痛と肛門部潰瘍は改善せず。消化器症状も不変であったため、レミケードを投与したところ、潰瘍・疼痛ともに軽快した。
TNFαの抗体による治療がいよいよ皮膚科にも入って来そうである。経過表からはステロイドでいったん消褪した後、再燃した結節性紅斑にもレミケードが効いたようにみえた。
-
第13回皮膚創傷治癒フォーラムから(平成18年6月24日)
褥瘡のポケット形成には2通りがある。初期型は虚血によって生じた壊死組織の融解が原因で、これは起こってしまったことなのでさけられない。その後、経過中に除圧がうまくいかないと、外力がかかるのは皮膚の表面に近い所と、下床の骨や筋に接触している所で、ちょうど砂時計型に虚血状態になるため、遅発型のポケット形成に至る。遅発型は圧迫とずれの力を排除すれば予防が可能である。
確かに同じようなことを経験する。だたし治療はいずれも切除をおこなうということで、かわりはないようだ。
-
第105回日本皮膚科学会総会(平成18年6月4日)
コリン性蕁麻疹は毛孔一致性のものとそうでないものの2型に分類できる。前者は自己血清の皮内反応が陽性で、汗の皮内反応が陰性のものが多い。後者は汗の皮内反応が陽性で、アセチルコリン皮内反応で衛星膨疹を認めるものが多い。
なかなかできない検査だが、機会があったらやってみたいものだ。毛孔一致性かどうかはダーモスコピーが役に立つと思うので、今度見てみよう。
-
第105回日本皮膚科学会総会(平成18年6月4日)
ネフローゼ症候群の患者で、通常は食後に内服されるシクロスポリンを食前にすると吸収が改善されたという報告があり、乾癬の患者でもこれを検証した。結果は、全例で内服4時間のの血中濃度-時間曲線下面積、最高血中濃度ともに食前投与が食後投与の1.8倍に増加し、吸収が改善することがわかった。
危険性の問題が気になるところだが、高い薬だし、食前にすることにより減量が可能であれば、その方が良いかもしれない。
-
第22回日本臨床皮膚科医会(平成18年5月21日)
顔面の老人性疣贅の治療として、活性型ビタミンD3外用を試みた。1日1から2回を3ヶ月以上続けて外用した症例116例のうち、35例が著効、54例が有効であった。腫瘍は炎症性変化を伴うことなく退縮し、自覚症状を伴うこともないので、高齢者のQOLの改善には有効な方法である。
たくさんあると処置に時間がかかるし、液体窒素では炎症後の色素沈着も気になるところだ。我慢強く続けてくれる患者さんにいいかもしれない。
-
第7回横浜皮膚悪性腫瘍研究会(平成18年5月18日)
ダーモスコープの所見を読む勉強会。まず、第1段階として、pigment network、aggregated plobules、branched streak、homogenous blue, pigmentation、parallel pattern(掌蹠の病変)があるかないかで、メラノサイト病変かどうかを見分け、次に第2段階としてパターン解析を行い、メラノーマ、境界部または複合型母斑、真皮内母斑、Spitz・Reed母斑、青色母斑を鑑別していくという流れが説明された。なお、顔の真皮内母斑では白いドットは毛孔と脂腺で、ネットワークが見えないので、pseudonetworkという。
まだ、用語に慣れていないせいか、忘れる。私的には、purpuraといわれたらこんな臨床、というひらめきが、まだダーモスコープ用語にはないのが現状。勉強が必要だ。
-
横浜北部地区皮膚科クリニック懇話会から(平成18年5月17日)
マラセチアがアトピー性皮膚炎の悪化に関与することが指摘されていて、抗真菌剤の内服が併用治療として用いられることがある。コマーシャルでもピチロスポルムIgE抗体の測定が可能であるが、これはM.synposialisの抗体であり、評価には注意が必要である。しかし、M.restrictaおよびM.globosaにも交叉反応があるので少しは役に立つとのこと。
あいかわらず、malasseziaは混乱している。ピチロスポルムIgE抗体を測定して、アトピー性皮膚炎の治療にいかすための指針がほしいところだ。
-
横浜皮膚疾患研究会(平成18年5月11日)
東京郊外の基幹病院からの報告。伝染性膿痂疹の細菌培養を行った結果、MRSAが26%に認められた。前医のあり、なしで分類すると、前医がなく直接来院の場合は15%であったが、前医で治療を受けた患児では46%と効率であった。したがって市中での感染例は15%、抗生剤の内服や外用を行ったためにMRSAの頻度が高くなることが明らかになった。
前医のあり、なしでこんなに違うものかと思った。とびひでの抗生剤の使い方はいつも難しいと思う。個人的には毎年、10例に1例ぐらいの割合で、表在性ではない、滲出性紅斑のような伝染性膿痂疹を経験するが、必ずしもMRSAとは関連がないようだ。これについては、どうも細菌を抗原とするDTHのように思うが、解決できていない。
-
第2回皮膚膠原病研究会から(平成18年4月8日)
抗CADM-140抗体陽性例:clinically-amyopatic DMの略。筋炎症状が少なく、急速に進行する間質性肺炎を合併する例が多い。
抗ARS抗体陽性例:Jo-1抗体もこの仲間。皮膚症状を伴わない多発性筋炎の症例に多い。レイノー症状が強く、間質性肺炎が合併する例が多い。
抗Mi2抗体陽性例:皮膚のみの症例で、光線過敏症を伴うことが多い。間質性肺炎なし。悪性腫瘍の合併が多い傾向がある。
皮膚筋炎・多発性筋炎がこのような病型にわけられるとは知らなかった。非常に参考になる発表だった。
-
第2回皮膚膠原病研究会から(平成18年4月8日)
SLEの皮膚生検組織には、時にリポフスチンを含む組織球が多数浸潤し、これを黄色腫反応と称する。リポフスチンは、過酸化脂質と蛋白質の複合体で、UVをあてると自家蛍光を発することで確認できる。臨床症状としては萎縮を伴うリベド様、浸潤性紅斑のことが多く、SLEの病勢とも相関する。
組織をよく見るとなるほどと思う症例がある。この臨床だと生検すれば黄色腫型反応があるだろう、という感触が何となくわかってきた。
-
第120回神奈川県皮膚科医会例会から(平成18年3月5日)
IL-7は骨髄細胞や胸腺細胞から分泌され、胸腺細胞の増殖に関与するる糖タンパクであるが、これが腸上皮細胞からも分泌されていることが確認され、IL-7の欠損マウスではパイエル板が形成されないことがわかった。腸上皮が周囲の免疫環境を自ら整えているということである。また、IL-7のover expressionでは腸炎が発症、炎症性腸疾患との関連が考えられた。なお、皮膚の表皮細胞も同様にIL-7を分泌しているとのこと。
皮膚も周囲の免疫環境を自ら調節していることは想像できる。疾患との関連はどうなのだろう。関節リウマチと同様の慢性関節炎もIL-7のover
-
中予アレルギー性鼻炎懇話会から(平成18年2月23日)
スギの雄花が落ちるのは、以下の3通りがある。1) 2月から4月の開花して花粉を放出したあとに落下する。2) 8月から5月、特に晩秋から冬季にかけて、開花せずに緑色のまま落下する。3) 古くなった暗褐色のものが、落下する。
実際、2004年の11月にスギ花粉の飛散が観測されたのも2)のためか。秋にスギ花粉症があってもいいようだ。
-
神奈川県高血圧・糖尿病を考える会から(平成18年2月22日)
メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積、インスリン抵抗性、糖代謝異常、脂質代謝異常、高血圧、凝固亢進などが集積して、心筋梗塞、脳卒中などの動脈硬化性疾患発症のリスクが高い。この疾患では、正常脂肪細胞が産生するサイトカインである血中アディポネクチンが低下していることがわかっている。インスリン抵抗性改善剤であるアクトスは、大規模なprospective studyで2型糖尿病のハイリスク患者で総死亡、大血管イベントの発症を抑制することが証明されたが、糖尿病患者で血中アディポネクチンを上昇させる働きがあること、また血管内皮に対する直接的な抗動脈硬化作用を有することがその理由である。
内科の話もたまにはいいものだ。糖尿病治療もずいぶん変わってきたと感じた。アクトスはおもしろい薬だ。necrobiosis lipoidicaや下腿潰瘍などの皮膚疾患の治療薬にもなるかもしれない。
-
第4回関東脈管懇話会から(平成18年2月19日)
PNCは主として皮膚の小動脈に血管炎を生じ、皮内結節を初発症状としてヘモジデリンによる色素沈着、atorophie blanche、潰瘍、summer ulcerationなどの皮膚症状が主体で、時に筋、末梢神経の症状をきたす疾患である。これに対して、PNはそれに加えて、生命関わる主要な臓器(心、中枢神経、肺、腎)にも病変をきたす。病理学的にはPNCの方がPNより肉芽反応が強い。PNCよりPNを考える必要がある皮膚症状は、症状が多彩である場合、出血性の変化が強い場合、壊疽があげられる。
壊疽になりそうになったら注意。心、中枢神経、肺、腎を調べないといけない。
-
第29回小児皮膚科セミナーから(平成18年2月18日)
食物アレルギーを多く診ている小児科からの報告。食物アレルギーのガイドラインを日本小児アレルギー学会(http://www.iscb.net/JSPACI/)、厚労省(http://www.allergy.go.jp/allergy/guideline/05/index.html)がまとめている。この中に、食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎の記載もあるが、検討した乳児のアトピー性皮膚炎の症例のうち、70%では食物抗原による即時型反応がみられ、30%では遅延型反応が陽性であった。パッチテストの試薬はキューピーが提供した乾燥粉末食物抗原を用いて、48時間後に判定したとのこと。
食物パッチが陽性ということは何を意味しているのか。IgE-dependentの反応なのか、食物によって口のまわりなどがかぶれたことのある乳児で陽性になるのかなど、疑問もあるが、非常に興味深い。食物アレルギー検査が保険適応になったこともあり、近々食物パッチテスト用のスタンダード抗原が試薬として提供されるらしい。皮膚科医がしっかりと反応を見る必要があるだろう。個人的には乳児の湿疹では、アトピー性皮膚炎と自信を持って診断できていないので、今後は是非やってみたいと思った。
-
第1回神奈川フットケア研究会から(平成18年2月16日)
特に糖尿病で問題になるフットケアの話題。体重による圧迫、動静脈やリンパ系のトラブルが生じやすいこと、靴によるむれによって、足は特別なケアが必要である。鶏眼・潰瘍などのトラブルに対しては、シューフィッターに適合靴を使ってもらう必要がある。シューフィッターの所在は「足と靴と健康協議会」のHP(http://www.fha.gr.jp/)で検索できるとのこと。
近くにいないと紹介できないのが問題だ。最上級のスキルを持ったいわゆるマスターは全国に13名しかいないらしい。
-
第69回日本皮膚科学会東京支部総会から (平成18年2月12日)
慢性疲労症候群(CFS)は、日常生活を妨げる重篤な疲労(通常6カ月以上継続)にリンパ節の腫大、咽頭痛、頭痛、関節痛、筋肉痛、微熱のほか、認知障害、睡眠障害を伴う疾患であるが、ウイルスの持続感染や再活性化が発症誘因と考えられている。経過を追った154例の伝染性紅斑患者のうち、2名がCFSを発症、いずれも女性であった。
成人女性のパルボウイルス感染は、膠原病的な変な症状がおこる。妊娠の有無にかかわらず注意しないといけないし、経過を追う必要もありそうだ。治療、CFSの発症予防はどうしたらよいのだろうか。
-
第69回日本皮膚科学会東京支部総会から (平成18年2月12日)
禁煙目的のニコチンパッチの部位に接触皮膚炎が生じて、その後、喫煙すると全身性の湿疹をきたすようになってしまった、systemic contact dermatitisの症例報告。1日5本に減らすと改善して、喫煙量によって湿疹が悪化するという。
湿疹が出てはたまらんと言うことで、結果的には禁煙に結びつくかもしれないが、ちょっと気の毒だ。これから多くなるかもしれないので、注意していこう。
-
第805回東京地方会から(平成18年1月21日)
汗孔角化症の症例報告。項部をやや斜めに上向する線状の汗孔角化症であった。線状汗孔角化症は母斑性と考えられ、表皮母斑などと同様、ブラシュコラインに沿って生じる疾患である。示されたブラシュコラインの説明図をみると、後頭部は、なんと渦巻きであった。
後頭被髪部の症例報告を探してみよう。
-
神奈川県皮膚科医会広報委員会から(平成18年1月15日)
HD中の患者に生じた帯状疱疹の治療で、バルトレックスを添付文書にしたがって1回1000mgを使用したところ、ふらつき、ろれつがまわらないなどの精神神経系の副作用が出現した。HD中の患者では、推奨容量以下の500mgの単回投与でも同様の副作用の報告があって、添付文書の量では明らかに過量であると考えられる。
重要な報告である。HD中の患者では、血中濃度の上がりにくいゾビラックスの方が安全かもしれない。なお、血中アシクロビル濃度の測定には血漿が必要で、SRLで測定可能とのこと。副作用が起こったら血漿を採ることにしよう。
-
第22回神奈川皮膚科免疫アレルギー疾患懇話会から(平成18年1月7日)
パッチテストでアレルギー反応と刺激反応を見分けることは、本邦基準に沿った臨床教育のため、信頼性、再現性が高まってきた。しかし、皮膚刺激性の評価についてはさらに高いスキルが必要とされ、0から6までの7段階のスコアリングを試みたが、専門家の間でもばらつきがあるとのこと。また、肉眼所見と写真での評価の間にも、相違があって、今後の標準化が待たれるところである。
皮膚刺激の評価のためのパッチテストの際には、まず濃度の調整をどうするかで悩む。開業医の日常診療では、希釈系列をたくさん作ることや、正常人コントロールで行うことも容易ではなく、ついつい遠慮してしまうのが実情である。
-
第3回相模原皮膚科セミナーから(平成17年12月3日)
扁平苔癬など、基底細胞がターゲットになる疾患では、角化のスピードにブレーキがかかるため、角層剥離遅延が生じて、顆粒層の肥厚を伴う角化が生じ、これをretention hyperkaratosisと呼ぶ。反対に、乾癬のように表皮細胞全体がターゲットの疾患は、角化のスピードが速くなるために、顆粒層の喪失した角化を生じ、これをproliferation hyperkeratosisと呼ぶ。
病変の経過を考えると納得がいく。acneのcomedo形成の時にもretentionという言葉が使われるが、意味は若干異なるようだ。
-
第3回相模原皮膚科セミナーから(平成17年12月3日)
自己免疫性水疱症の治療の話。ステロイドパルス療法を施行する際には、non specificな血清中IgGをモニターするとよい。ステロイドパルス療法施行の2-3週後になると、血中IgGは20-30%低下する。この減少の傾向と、自己抗体のtiterが解離していれば、効果があったことになる。IgGと自己抗体のtiterの変動に差がない時には、2週間後にもう1回ステロイドパルスを行ってみる。1回目が無効でも、2回目に有効なことはまれではない。
なるほど、今後の治療の指針になる話だった。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成17年12月1日)
くも膜下出血のために、血管造影とintervensionを計9時間半にわたって施行、後頭から側頭にかけて4Gy、一部は8GyのX線の照射を余儀なくされた。施行後3週間後ぐらいから脱毛を生じてきた。4Gyの所は3ヶ月後から徐々に発毛、8Gyのところは脱毛斑として残った。難しいことができるようになった反面、処置に時間がかかるようになっているIVRの現状があるようだ。しきい線量が3Gyで一時的な脱毛斑、7Gyで永久脱毛斑になるということである。2004年にはガイドラインができて、皮膚障害の追跡調査を行うことを勧告している。
生検組織には慢性放射線皮膚炎の像はなく、脱毛の原因が放射線とは言えないという意見が多かったが、圧迫などの他の要素もなく、やはり被爆が原因ではないかと思った。皮膚科でフォローすることになるので病院勤務では重要かも。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成17年12月1日)
不明熱で入院中の患者。治療としてFOYが右前腕から投与された。そのしばらく後に静脈に沿って皮下硬結。中央は潰瘍となった。ステロイド局注で加療し潰瘍は一旦消失、硬結もやや改善。2ヶ月後、FOYの投与は行っていないが、再び同じ部位に硬結と潰瘍が出現。遅発型の皮膚障害と考えられた。最初の硬結と潰瘍は、薬剤の血管内皮に対する障害で、若干の薬剤がにじみ出て、皮膚に損傷を与える機序。遅発型は、1~2ヶ月後に生じる皮膚障害で、FOYのパッチテストで陽性となる例もあり、生検部の組織で好酸球が多いので、アレルギー性の機序も考えられると結論づけた報告もある、ということであった。
何もしないのに何ヶ月も後に、同じ部位に潰瘍が再発するのは納得できない。潰瘍や硬結の部分に薬剤が残っていて、その場でじわっと感作が成り立つと言うこと?アレルギーではないと思うが、、。
-
第13回毛髪科学研究会から(平成17年11月26日)
正常人の白髪の統計である。白髪のある人の全体を通してみると、後頭部は男女差なく頭頂部や側頭部に比べて白髪が少ない。個々を抜いて調べてみると、白髪はふつうの毛に比べると太く、のびが早く、成長期毛率が高かったが、60μm以上の太さの黒い毛と比較するとそれぞれについての有意差はなくなり、つまり、細い毛には白髪が少ないということであった。なお、白髪はふつうの毛よりもやや平べったい傾向があった。
白髪だけがピンとはねることがあるのは、ふつうの毛より扁平だからだということがわかった。自分の髪を見ても、細い白髪はあまり見かけない気がする。おもしろい観察であった。
-
第13回毛髪科学研究会から(平成17年11月26日)
先天性乏毛症の症例報告。ちぎれやすい毛で、毛孔性丘疹と連珠毛(monilethrix)を伴うがhair keratin遺伝子は正常。しかしDSG4遺伝子の病的変異が見つかった。DSG4は正常のhair cortexに分布しているので、ここでの細胞接着が不十分なために、毛の発育に異常をきたすのであろうとのこと。DSG4は表皮顆粒層にも分布しているが、落葉状天疱瘡のような紅斑・水疱などは見らず。国外の報告ではひげや体毛には影響しないという。atrichia with papular lesionsという先天性疾患にも似ているが、完全な無毛症ではないことが鑑別点。
なかなか見る機会はないが、連珠毛や先天性乏毛症の病因解析がここまで進んでいるとは知らなかった。hairに異常をきたす遺伝性の疾患は、奥が深くて難しい。
-
第13回毛髪科学研究会から(平成17年11月26日)
萎縮性脱毛症は、最近ではcentral centrifugal scarring alopecia(CCSA)という名称で包括され、この中にpseudopelade、folliculitis decarvans、follicular degeneration syndromeなどの名称で呼ばれていた疾患が含まれる。組織所見の違い(炎症の多い・少ない、膿疱がある・ない)は生検した時期や部位が違うためで臨床的には明確に鑑別できない。また、眉から始まり上行して前頭部髪際の脱毛を来す、frontal fibrosing alopecia(FFA)という疾患の報告があった。
CCSAなどという難しい名前は使わず、萎縮性脱毛症や瘢痕性脱毛症でいいだろう。FFAについては心当たりの症例があるので、今度よく見てみよう。これは何で起こるのだろうか。
-
第21回日臨皮三支部合同学術集会から(平成17年11月23日)
小児期、特に新生児に見られる、生理現象に近い皮膚の疾患(変化)のまとめである。
・新生児生理的落屑(胎児期の周皮の落屑で、生後数日後まで見られる)
・陰嚢生理的色素沈着(約30%にあって、数ヶ月で正常になる)
・sebaceous hyperplasia of the nose in newborn(病名の通り、鼻尖部の脂腺増殖)
・大理石様皮膚(機能的な血管の変化)
・infantile perianal pyramidal protrusion(肉芽腫性炎症で自然に消褪する)
・Epstaein's pearl(歯肉の角質嚢腫で自然治癒)
・neonatal adonexal polyp of skin(乳輪部に単発するmilium)
・新生児中毒性紅斑(膿疱に好酸球が多いのが特徴)
・traumatic anserine folliculosis(学童期のあごの毛孔性丘疹、別の名称で既出)
アメリカ式の名前に占領されている。protrusionはでっぱり。anserineはガチョウ?
-
第21回日臨皮三支部合同学術集会から(平成17年11月23日)
尿膜管(urachus)は臍と膀胱頂部をつなぐ線維筋性索状構造で、発生学的にはアラントイス管に由来し、その退縮が不完全である場合に尿膜管遺残がおこる。その全長が開存すると尿膜管開存、膀胱側の一部が遺残すると尿膜管憩室、臍側の一部が遺残すると尿膜管洞、尿膜管中央の嚢胞状拡張を尿膜管嚢腫(urachal cyst)とよぶ。このうち尿膜管嚢腫がもっとも頻度が高く、通常は無症状であるが、時に腹部違和感、腹痛、臍からの出血、皮下膿瘍、膀胱炎様症状、血尿・膿尿を来すので臍の皮膚病をみたらこれも念頭に置く必要がある。
実は症例の経験がなく、見落としているかもと思って、焦った。ヘソの周りには注意しよう。
-
第21回日臨皮三支部合同学術集会から(平成17年11月23日)
慢性活動性EBウイルス感染症のスペクトラムの話。種痘様水疱症、蚊刺過敏症、血球貪食症候群などを見た際に重要な検査として、血中のアズール顆粒をもったLGL(large granular lymphocyte)の確認、再活性化に伴うEBウイルス抗体価の上昇の有無、EVウイルスのDNAコピー数、EBER(EBV-encoded small nuclear RNA)の局在がある。EBERは皮膚生検を施行しなくても、種痘様水疱症の痂皮の中にも存在が確かめられ、1~2ヶ月間は常温で保管しても検出できる。疑わしいときには、痂皮を剥がして、テープで固定し、岡山大学に郵送すれば、検査をやって下さるとのこと。
種痘様水疱症では、水疱の時期をとらえるのはなかなか難しく、しかも子供に多いことを考えれば、痂皮を剥がすだけの処置ですむということは、大きなメリットだと思った。
-
第112回東京地方会神奈川分会から(平成17年11月19日)
爪甲が膜様に白くなる爪真菌症の異型で、爪甲の肥厚を伴わない。療養型病床に入院している認知症を伴う患者64名のうち、全体の40%にみられ、手の爪に多かった。この施設では手の爪白癬の81%、足の爪白癬の9%がこの病型(SWO)であった。白く混濁した部分は表面からスライドグラスなどで容易に剥離でき、KOH直接鏡検では菌糸とともに分節胞子が多数みられるのが特徴。培養ではT.mentagrophytesがT.rubrumより多く、通常の爪白癬と反対である。削って外用するだけで改善するので抗真菌剤内服の必要はない。
認知症があることや拘縮があって手を握ったままにしていることと関連があるかもしれない。時々高齢者で見かけるが、私の往診している特養や老健では、全体の10%以下だと思う。これについては機会があったら回診をして、しっかり調べてみよう。
-
第112回横浜市皮膚科医会から(平成17年11月12日)
角層にはreservoir(レザバー)機能があって、外用したステロイドは5日間はそこにとどまるが、その後は角層と共に排泄される。この間吸収されるステロイドの量は前腕で約1%である。ステロイドはもともと脂溶性なので、脂腺が多いところは吸収が良い。吸収率が部位によって差があるのは1967年にMeibachが報告した通りだが、C14でラベルし、アセトンに融解したステロイドを外用したのち、5日間蓄尿中に排泄されたC14を測定した結果であり、その後追試は行われていない。また副腎抑制を来すにはどのくらいの外用が必要かというと、strongestで1日10g、very strongの単擦では1日30g、very strongのODTでは1日10gが目安とのこと。
5日間そこにとどまるというのは初耳だった。湿疹でも軽い場合は5日に1回塗ればいいと考えていいのだろうか。確かに光かぶれをおこすケトプロフェンでも、もっと長く表皮に残っているようだし、皮膚の生理も簡単ではない。
-
横浜労災病院症例検討会から(平成17年11月9日)
アフタは直った後に瘢痕にならない、つまり粘膜のびらんと定義される。これに対して粘膜でも潰瘍は瘢痕を残す。したがってアフタ性潰瘍という言葉はまちがい。皮膚に置きかえると、びらん性潰瘍になってしまう。また口内炎は口腔内の炎症の総称で、ヘルペス性歯肉口内炎などは、アフタ性口内炎を来す疾患と呼んでよい。クローン病では腸外症状として口内炎が生じるが、この場合はアフタよりも潰瘍が多い。
自分で使う事はないが、確かにたまに耳にする用語である。定義をしっかりとすれば、なるほど、理解しやすい。
-
第1回皮膚膠原病研究会から(平成17年11月5日)
SLEに合併した、抗リン脂質抗体症候群の症例。皮膚症状としては手掌の皮内結節があり、組織学的に血栓が認められた。経過中、家族が患者の行動や言動が普段と若干異なり、やや反応が遅いことに気づいたため、大事をとって入院したが、その直後に急性腹症を発症。APSが原因で生じた、上腸間膜動脈閉塞症が原因だった。APSの患者に生じる急性動脈閉塞症は、SLEなどの合併症の増悪とは関係なく、また、APSの検査異常(β1GPⅠ抗体など)とも平行しないので、余地が難しい。しかし、頭痛、数分程度の半盲、めまい、さらに不定愁訴が初発症状となることがあり、今回の症例のように、何か普段と違う、ということが初発症状のこともあるので、家族によく説明をして、日常を管理することが大変重要であると思われた。
家族が偉い。家族に何か変だったらすぐ連れてきて、というムンテラをしていた医者も偉い。
-
第1回皮膚膠原病研究会から(平成17年11月5日)
ステロイド、シクロスポリンなどの免疫抑制剤に反応しない中枢神経症状とループス腎炎をともなったSLEに、B細胞リンパ腫の治療薬であるリツキシマブを投与して、劇的に症状が改善した症例のレポートが出たという情報。B細胞をリセットすることで、自己抗体の産生に抑制がかかったということであった。SLEの新しい薬として期待されており、欧米ではすでに治験が進行中とのこと。
皮膚科ではSLE以外にも多くの自己抗体と関連する疾患がある。ステロイドや免疫抑制剤で管理できない水疱症にも効果がありそうで、今後注目していきたい。
-
第57回日本皮膚科学会西部支部学術大会から(平成17年10月30日)
腰部の深いところに生じた膿瘍を考えた高齢の女性。切開で排膿を認め、培養では大腸菌が陽性。また周囲の組織に、豊富な細胞質を持つ組織球の反応性増殖を認め、特徴的なVon Hansemann細胞の出現とその胞体内にPAS染色陽性のMichaelis Gutmann小体が認められ、マラコプラキアと診断した。マラコプラキアは膀胱、前立腺などの泌尿器科領域に多く、今回のように後腹膜に生じることもある。慢性膀胱炎を繰り返す高齢女性に多い。組織で認められる空胞化した細胞質を要する組織球が特徴で、これは尿の細胞診でも検出可能らしい。
初めて耳にした。皮膚科領域では聞いたことがない。確かに組織は1回見たら忘れないほど特徴的。ただし大腸菌の感染が証明され、しかも実際に排膿があるにも関わらず組織に好中球がないのが納得できなかった。
-
第57回日本皮膚科学会西部支部学術大会から(平成17年10月30日)
血管炎診断の条件としては1)好中球の核破潰を伴う浸潤と出血、2)血管壁のフィブリノイド変性の両方が必要。血管壁のヒアリン変性が主体で、Leucocytoklasieがない場合や、血管内腔および壁のフィブリン沈着が主体で、Leucocytoklasie がない場合、また、強い線維素性炎症で、Leucocytoclasieがあるが、フィブリノイド変性のない場合は血管炎に似るが、血管炎ではない。こういった病理組織を呈する疾患に、livedo racemosa、SLE、PSS、RA、心粘液腫、亜急性心内膜炎(Osler結節)、コレステリン結晶塞栓症、多血症、血小板増多症、抗リン脂質抗体症候群などがある。
理屈ではわかっていても、臨床的には大変苦労する分野である。開業医としても色々な鑑別疾患に対して充分な検査をしていかなければならないと思った。
-
第57回日本皮膚科学会西部支部学術大会から(平成17年10月30日)
小児期からアキレス腱部に黄色腫があった。それに加えて精神発達遅延、錐体路症状、小脳機能異常、若年性白内障がある成人例。検査では血中コレステロール値はなんと正常。そのかわり血中コレスタノールが異常高値で、これだけで脳腱黄色腫症と診断できる。脳腱黄色腫症はsterol 27-hydroxylase遺伝子 (CYP27)の変異が原因で生ずる常染色体劣性遺伝の疾患。コレスタノールが皮膚・腱・脳・目・肺に沈着するのが特徴で、腱黄色腫と知能低下は学童期前半から、小脳症状は思春期ごろから生じる。
経験がなく、知識としても持ち合わせていなかった、知っていそうで知らない、古そうで新しい病名であった。
-
第1回神奈川皮膚アレルギー疾患研究会から(平成17年10月22日)
T細胞のマーカーのおさらい。ケモカインレセプターの解析が進み、CD4陽性T細胞(Th)は、表面マーカーから以下の通りに分類されるようになった。Th1:CD7陽性、CXCR3陽性。Th2:CD7陰性、CCR4陽性。Treg:CD28陽性、CTLA-4陽性、Foxp3陽性、G1TR陽性。T細胞の増殖する疾患を、細胞のプロフィールから分類すると、セザリー症候群はTh2の腫瘍、ATLはTregの腫瘍であると考えられる。
最近はずいぶんと進んだものだ。リンパ腫だけはどうも苦手で、なかなかついて行けない。大学病院にお任せしよう。
-
第4回横浜デルマカンファレンスから(平成17年10月20日)
抗酸菌は、もともとの宿主が何かを考えると、培養の至適温度がわかる。ヒト型結核菌(M.tuberculosis)はもともとヒトを宿主としているので37℃、海水魚についていて皮膚に肉芽腫をおこすM. marinumは海水なので30℃、24時間風呂で繁殖し、皮下膿瘍を生じるM.aviumはもともとは体温の高いトリが宿主なので、40℃。
なるほど、わかりやすい。インキュベターを置くところがないので、抗酸菌培養までは自院ではしないが、検査の指示を出すときに、役に立つはずである。
-
メディカルフォーラム2005から(平成17年10月15日)
肺血栓塞栓症(pulmonary thrombo-embolism: PTE)と深部静脈血栓症(deep venous thronmosis: DVT)はまとめて、静脈血栓塞栓症(venous thrombo-embolism: VTE)と呼ばれることが多い。古くは横綱玉ノ海が虫垂炎の術後の肺梗塞で死亡、少し前には、いわゆるエコノミークラス症候群(ロングフライト症候群)でサッカー日本代表の高原選手が肺梗塞を発症。また、昨年の新潟県中越大震災で車内での長時間生活を余儀なくされた方でも問題になった。最近ではe-thrombosis(電子血栓症)といって、オフィスで長時間座っているだけでもVTEの危険とは背中合わせらしい。しかし、もっともVTEが多く発生するのは、危険因子が重複しやすい病院内で、ことに周術期である。これを受けて、2004年にはVTE予防ガイドラインが公表された。最近の病院の手術現場では、麻酔科医、循環器内科医が術前のリスクレベルの評価を行い、それに応じて、弾性ストッキングや間欠的空気圧迫法(IPC)、低容量未分画ヘパリン投与(LDUH)などを行うのが常識になっている。
開業医はこういうことを知らないから、よくない。ガイドラインにさっそく目を通した。
-
第49回医真菌学会総会から(平成17年10月6日)
Malasseziaがアトピー性皮膚炎の湿疹、特に顔面の病変に対して、増悪因子になることが知られている。ケトコナゾールクリームの外用やイトラコナゾール100mg/日の4週間内服で、Malasseziaの菌量の減少、Malasseziaに対する特異的IgE抗体価の減少と平行して臨床症状もかなりの割合で改善した。また、タクロリムス軟膏にはMalasseziaの増殖抑制効果があり、特にケトコナゾールやイトラコナゾールと相乗的に作用し、MICを低下させることが示された。
癜風にタクロリムスを外用すると、症状が改善するかどうか。脂漏性皮膚炎でタクロリムスを使用してdemodexが増殖し、rosaceaを生じた経験がある。その辺がよくわからないところである。
-
北里大学特別講演会から(平成17年9月22日)
ドイツ人Proffesorの講演。日本ではまだ使われていないImiquimodクリームの使用経験の話。この薬剤はtoll-like receptor(TLR)に直接結合し、免疫担当細胞を活性化させる働きがあり、尖圭コンジローマの治療薬として欧米ではすでに用いられている。しかしコンジローマ以外のウイルス性疣贅や伝染性軟属腫にはもう一つ効果が明らかではない。しかし、日光角化症と表在性の基底細胞上皮腫には有効で、単純に外用するだけなので、特に高齢者では手術に代わる有効な治療法である。
日光角化症に対する効果は5FU軟膏と同等とのこと。個人輸入で入手は可能なので、機会があれば使用してみたい。
-
第21回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成17年7月21日)
免疫学的特権部位(immunological privileged site)とは、容易に自己に攻撃されることがないように、免疫学的に保護されている部位のことをさし、1)古典的MHC-1分子を発現しない、2)TGF-βの恒常的発現がある、3)Fas-ligandを常時発現しているという特徴を持ち、脳、精巣、卵巣などがこれにあたるが、正常毛包もこれらの特徴を備えている。円形脱毛症ではこの「免疫学的特権」が何らかの理由で破綻し、自己のeffector細胞(CD4+-killer cellか?)によって攻撃を受けるために脱毛になってしまう、という可能性がある。
ちょっとわかりにくいが、頭の片隅に入れておこう。確かに寒いところのほ乳類ではhairも生命の維持に必要な大事な臓器といえるかもしれない。
-
北里大学皮膚科同門会講演から(平成17年7月18日)
全身性汎発性の乾癬が完全緩解した症例の報告でそれぞれ、1)加齢によって自然軽快した症例。2)乳癌の手術後に改善した症例。3)心筋梗塞・大動脈瘤で人工血管バイパス術を受けた後に改善した症例。4)生活習慣病のコントロールを厳重に行った症例。5)病巣感染の除去によって改善した症例。6)膿疱性乾癬から紅皮症化したあとに改善した症例。7)合併するnon-Hodgikin lymphomaに骨髄幹細胞移植を行った症例であった。
大きなストレスがかかった時に乾癬が消えてしまう場合があることは全く予想外であった。乾癬は完治しないということが間違っている証拠で、今後も長く患者さんたちとつきあっていきたいと思った。
-
第35回日本皮膚アレルギー学会から(平成17年7月17日)
数ヶ月前に公表された蕁麻疹・血管性浮腫の治療ガイドラインでは、「特定の刺激ないし負荷により、皮疹を誘発できる蕁麻疹」を可能な限り鑑別していくという方向性が再確認された。これに伴って、特発性の蕁麻疹に、特定誘因のある蕁麻疹が合併することが多いことが報告され、特に、慢性蕁麻疹+機械的蕁麻疹、慢性蕁麻疹+アスピリンイントレランスの合併は多く、アスピリンイントレランスは慢性蕁麻疹の30%に合併しているということであった。
慢性蕁麻疹の患者さんはたくさんあるが、個人的にはアスピリントレランスの経験は少ない。ちゃんと悪化因子を聞いていないからだろう。もっと問診をしっかりしないといけないと思った。
-
第35回日本皮膚アレルギー学会から(平成17年7月17日)
Stevens-Johnson症候群(SJS)やdrug-induced hypersensitivity syndrome(DIHS)などの重症薬疹では、再投与試験が難しく、DLSTが原因薬剤の被疑薬検索に用いられるが、陽性となる期間は一時的であり、この時期を逃すと陰性になってしまい、原因薬剤の同定ができなくなってしまう。SJSでは発症後2から3週までの間、一方DIHSでは病初期には陽性にならず、発症後1ヶ月以上たってから陽性となる。
SJSとDIHSの免疫学的違いとは何だろう。薬疹も実に奥が深い。
-
第4回関東脈管懇話会から(平成17年7月10日)
マイクロリベドは主として手掌・足蹠あるいは手指・足趾などに部分的、限局的にみられる、非閉鎖性のリベドで、末梢の皮膚小動脈ないしそれよりも小さい血管の閉塞性変化を示す状態で、血栓(抗リン脂質抗体症候群など)や塞栓(コレステロール結晶、左房粘液腫、高γグロブリン血症など)による閉塞性の循環障害、あるいはこのレベルの血管炎に基づく変化で、臨床的にlivedo racemosaとまではいえない皮膚症状を表す、よい症状名である。
元々はAPSの皮膚症状として用いられたようだ。今後さらに、病理学的変化に基づく定義や関連する疾患を整理していってほしいところだ。
-
第54回神奈川医真菌談話会から(平成17年6月18日)
アトピー性皮膚炎患者にみられる足白癬は、角化型・鱗屑型が多く、小水疱型は少ない。一般的に足白癬の患者でトリコフィチン反応を行うと即時型反応が陽性の人と遅延型反応が陽性の人があり、再発性で角化型の人は即時型が陽性で、炎症の強い人では遅延型が陽性である。アトピー性皮膚炎の患者の多くは、即時型が陽性で遅延型は陰性である。
知らなかった。実際のところ、手に入らないので検査ができないのが残念だ。T.tonsurans感染症でも炎症の強いタイプと、弱いタイプがあるが、是非やってみたいと思う。
-
第54回神奈川医真菌談話会から(平成17年6月18日)
Malasseziaは好脂性酵母でヒト皮膚、特に脂漏部に高頻度に定着している。real-time-PCRを用いて菌叢を解析すると、正常皮膚でも、アトピー性皮膚炎患者でも、脂漏性皮膚炎でも、癜風でもM. globosaとM. restrictaが多く検出され、疾患による菌叢の違いは明確でない。ただし、病変部とそうでないところを定量的な非培養法によって比較すると、脂漏性皮膚炎の病変部ではM. restrictaが他の菌種に比べて多く、癜風ではM. globosaが多いとのことであった。したがって、癜風はM. globosaが主因となって発症する疾患であるといえる。なお、M. furfurは正常でも疾患においてもマイナーで検出率の低いMalasseziaである。
Malasseziaの分類が変わってしまって、すっきり理解できないところがある。いくつもの菌種が検出されてしまうのは、テープストリップで病変部以外の菌も拾っているからではないだろうか。一つの病変は1種類の菌で成り立っていてほしいし、癜風という疾患は、病変部をこするとたくさん鱗屑がとれて、鏡検すると菌糸がたくさん見える皮膚病である、というところは変わってほしくないと思う。ちなみにミコナゾールシャンプーはコラージュ・リストリクタに名前を変えないといけないかもしれない。
-
第21回日本臨床皮膚科医会から(平成17年6月12日)
ハチ毒によるアナフィラキシーの講演の中で、刺された直後に試みて損にはならない処置ということで紹介された。何のことかと調べてみると陰圧をかけて毒を吸引する道具で薬ではなかった。山歩きには必需品で、キャンプ用品を扱うネットショップでも購入が可能であるhttp://www.iizukaco.co.jp/catalog/index.html。
備えあれば憂いなし。一つ購入しておこう。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成17年6月2日)
大腿伸側に典型的な発疹を認めた症例の報告。Elastosis perforans serpiginosaは弾性線維の変性をきたす疾患、特にpseudoxanthoma elasticumに伴うものが有名だが、ダウン症(trisomy 21)に伴うこともある。ダウン症では四肢に多く発生し、男性に多い傾向がある。
今後は注意して見ていく必要があると思った。ダウン症でも弾力線維に変性をきたす事ががあるということだろう。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成17年6月2日)
Spitz nevusは若年にみられる後天的な母斑細胞性母斑であるが、これが顔面にあった先天性の扁平母斑上に生じた症例の報告である。黒褐色のコニーデ型の結節で中央のへこみは増殖の早さを物語っている。組織では左右対称性の細胞浸潤・増殖で、melanomaと鑑別できた。ドイツの統計によれば。946例の扁平母斑上にSpitz nevus'sが3例、melanomaが2例生じたとのことであった。
Spitz's nevusも診断が難しい疾患だと思う。特に最近は、若年者のspitzoid melanomaという疾患も提唱されていて、注意が必要だと思われた。
-
第799回日本皮膚科学会東京地方会から(平成17年5月21日)
血球貪食症候群では血中のフェリチンが増加し、病勢を反映するマーカーとなる。鉄の代謝を考えたとき、体内に入った鉄は腸管から吸収され、まずフェリチンと結合し、肝で蓄えられる。フェリチン鉄は血清鉄の減少があると、ヘム合成に利用されるので、貧血の最初の過程はフェリチンの減少から始まる。反対に血球貪食症候群では、網内系への鉄貯留や、肝・骨髄などの細胞破壊による血中への逸脱血中フェリチンが上昇すると考えられている。
ところで、診断基準にもあるが成人スティル病で血中フェリチンが上昇する理由は何だったか?
-
横浜皮膚科臨床懇談会から(平成17年5月19日)
果物を食べたあとに口腔・咽頭がイガイガする口腔アレルギー症候群(OAS)の多くは、花粉によって感作された個体に生じる交叉反応で、pollen-food allergy syndromeないしclass 2食物アレルギーと呼ばれている。北海道で有名なシラカンバ花粉症に合併するリンゴ、サクランボ、モモ、ナシ、メロン、キウイ、スイカのOASが多い。関東のOAS患者ではハンノキ花粉によって感作されている頻度が高いようだ。シラカンバ以外にも、スギ・ヒノキ→トマト、カモガヤ・オオアワガエリ→トマト・メロン・スイカ、ブタクサ→メロン、ヨモギ→リンゴ・キウイの交叉反応が指摘されている。一方、食物そのもので感作された場合をclass 1食物アレルギーと呼び、ラテックスアレルギーを合併することが多く、latex-fruit syndromeと呼ばれる。クリ、アボガド、バナナなどで生じ、重症例が多い。
OASではハンノキの特異的IgEを測ってみよう。各種花粉のプリックが陽性だったら、OASの合併の有無を聞いてみなければいけないと感じた。スギ花粉患者でトマトによるOASの合併はどのくらいあるのだろうか。
-
第104回日本皮膚科学会総会から(平成17年4月23日)
小麦によるについての研究報告。まず小麦の主要なアレルゲンと考えられるω5-グリアジンに注目し、ELISAによって血中の抗原量を測定した。個々の症例で見ると、アナフィラキシーの症状が出ているときの血中グリアジン濃度が症状のないときより高くなっていた。小麦摂取後に運動負荷をかけると血中グリアジン濃度が上がり、アスピリンの内服によっても、同様に血中抗原量の増加が見られた。運動やアスピリンのために、未消化な原因抗原がたまることによって、アレルギー症状が励起されるという可能性がある。
抗原量が増加するというのは驚きで、貴重なデータだと思った。消化酵素と併用することで運動をしたりアスピリンを内服しても、発症を予防できるのであろうか。
-
第104回日本皮膚科学会総会から(平成17年4月23日)
柔道、レスリング競技者のタムシ、頭部白癬で有名になったTrichophyton tonsuransは、ribosomal RNAのITS領域の塩基配列から、柔道型のNTS1とレスリング型のNTS2に分けられる。最近では競技人口の多い柔道型が増え、レスリング競技者でも半分は柔道型になってきている。これとは別に1926年に長崎で、black dot ringwormから検出された、Trichophyton coccineumという菌があり、T. tonsuransと同種である可能性が高いとのこと。塩基配列のパターンからNaeI型と呼んでいる。
古くから日本にあったとは驚きである。歴史をたどる仕事というのは大変だが貴重だと思った。
-
第104回日本皮膚科学会総会から(平成17年4月23日)
30週で帝切で出生した双生児が、ともに頭頂部の皮膚欠損を伴っていた。母が妊娠26週まで甲状腺機能亢進症治療剤であるチアマゾール(メルカゾール)を内服していたことが原因かもしれない。添付文書にも、妊娠中の投与により、新生児に頭皮皮膚欠損、臍帯ヘルニア、臍腸管遺残、食道閉鎖症などがあらわれたとの報告がある、と書かれているとのこと。
全く知識として持ち合わせていなかったので、勉強になった。
-
第6回北里臨床皮膚フォーラムから(平成17年4月7日)
フィブリンはまさに急性期の線維素性炎症の際に出てくるもので、PTAH染色陽性。皮膚の毛細血管はそれを支えきれるほど太くないので、周囲の結合織に流れてしまう。フィブリノイドはフィブリンに免疫グロブリンや補体がくっついているもので、PAS染色陽性。フィブリノイドになると核などの細胞成分も線維成分も見えなくなって、均一な染色性になる。なお、HEでエオジンに濃く染まるのがフィブリンで、フィブリノイドはそれよりやや薄く、もっと薄いのがヒアリンで、これは無構造で脂質が多く含まれている。
何度聞いても忘れてしまうので、今回はきっちりメモっておこう。
-
第6回北里臨床皮膚フォーラムから(平成17年4月7日)
中年女性でいわゆる大根足の人に生じる、下腿の皮下脂肪織炎をどのような病名にするかの議論。病理学的にはlipolysisが一番最初に起きる変化で、進展すると組織学的にはlipogranulomaになる。これをそのまま症状名として用いて、その原因として①静脈性の循環障害、②外傷、③リパーゼの逸脱(膵癌など)を検索し記載するのがよいと考える。
確かにlipogranulomaという症状名ないし病名は最近使わなくなってきてしまった。idiopathic nodular panniculitis、Hypodermitis sclerodermiformis、Rothman-Makai症候群なども概念のはっきりしない病名で、lipogranulomaに戻った方がかえってすっきりするかもしれない。
-
第110回横浜市皮膚科医会から(平成17年4月3日)
もともと幼弱な真皮メラノサイトが潜在しているところに、多くは紫外線照射が誘因となって色素斑が後天的に顕在化してくる、日本人に多い疾患。女性に圧倒的に多く、男性の約10倍の頻度。約10%の症例で母と娘に同症をみとめる。やや青みがかった灰褐色の色素斑は、頬では点々、額ではべたっとなる。女性では思春期以降の発症が多く、女性ホルモンとの関連も考えられる。男性では中高年に多く、アトピー性皮膚炎の増悪に伴って額や手背に発症することが多い。治療はQ-switch ruby laserが有効である。
実際よく観察すると、決してまれな疾患ではないことに気づいた。アトピー性皮膚炎の男性例の手背にも、たびたびみられる変化である。「しみ」の鑑別疾患としても重要だと再認識した。
-
相模原真菌症講演会から(平成17年3月24日)
ペットショップ勤務の若い患者。形は環状でタムシを思わせるが、滲出性の炎症が強く水疱をきたすなど、まるで膿痂疹のような臨床症状が、前腕などのペットとの接触部位に生じる。原因菌はzoophilicな真菌であるArthroderma bemhamiaeで、Torichophyton mentagrophytesのvariantと考えられている。ハリネズミなど、齧歯類のペットと一緒に輸入され、今後は一般の家庭ににも拡大していく可能性があり、注意が必要である。
「ペットショップ勤務」が問診の際のキーワードだろう。柔道部のトンズランスとともに覚えておかなくてはならない。
-
横浜労災病院症例検討会から(平成17年3月17日)
肉芽腫性口唇炎を診たときに、考えるべき原因疾患は、1. Melkersson-Rosenthal症候群(日本人には顔面神経麻痺は少ない)、2. クローン病・潰瘍性大腸炎の腸外症状、3. サルコイドーシス(顎下腺の肉芽腫を伴う)で、それ以外の場合には慢性の感染病巣の有無を検索すること。なお、肉芽腫性口唇炎はほとんどの場合に顔面にrosaceaを伴っており、先天的な血管・リンパ管の異常が基盤にあるのではなかろうか。
特にrosaceaとの関連については注目してみていこう。
栄養障害特に低アミノ酸血症による壊死性遊走性紅斑
第19回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成17年3月17日)
グルカゴノーマ症候群に典型的な壊死性遊走性紅斑は、メープルシロップ症候群、肝硬変などに伴う低アミノ酸血症においても認められる。治療的には外用のみでは不十分で、アミノフリードの点滴で改善するが、原疾患の検索がもっとも必要である。組織学的には表皮の壊死、栄養障害で、真皮に炎症がないのが特徴であり、したがって臨床的には丸くならず、辺縁が不規則な暗紅色斑となる。
グルカゴノーマ症候群では血糖の上昇のためにタンパク質が動員され、したがって低アミノ酸血症が発生するとのことであった。基礎疾患の鑑別が、確かに重要であると感じた。
-
第13回皮膚科在宅医療勉強会から(平成17年3月3日)
マウスの熱傷モデルで、皮膚欠損創被覆剤の治療効果を、上皮化(epithelization)と創収縮(contraction)にわけて観察した。一般的にepithelizationが主体だと若干時間がかかるが創はきれいで、contractionが主体だと早いが、創は瘢痕になる。いくつかの被覆材の中では、ハイドロゲル製材がもっともcontractionが少なく、epithelization主体で創が閉鎖していくため、美容的にはもっともきれいであった。
ハイドロコロイドに比べて自着性がないために、使いづらいと考えていたが、逆にそこが重要なポイントであると理解した。臨床の現場でもいわゆるモイスト・ウンド・ヒーリングを活用していく必要があると思った。
-
第68回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成17年2月20日)
眼の下の「くま」は鑑別が必要で、1. 眼精疲労などによるうっ血で、青っぽい色調、2. 炎症後の色素沈着で、褐色。3. 加齢に伴う眼窩脂肪のherniation、いわゆるbaggy eye formation。このうち、3. は形成外科的な治療が有効である。
治療方針が異なるので、今後はしっかり鑑別していこう。
-
第68回日本皮膚科学会東京支部総会から(平成17年2月20日)
まぶたを上げる筋肉、上眼瞼挙筋が瞼板に付着している部分の挙筋腱膜が剥がれることによる眼瞼下垂を腱膜性眼瞼下垂と呼ぶ。この際、挙筋腱膜の裏にあって上眼瞼挙筋と瞼板をつなぐミュラー筋が伸ばされ、支配神経である交感神経が緊張し、通常は物を見上げる時、びっくりした時に反射的にしか収縮しない前頭筋や肩や首周囲の筋群が正面視でも常に収縮しているために頭痛・肩こり、人によっては便秘、手足の冷えなど自律神経症状が引き起こされる。
眼瞼下垂の手術を薦める際の参考になった
-
第19回皮膚科心身医学研究会から(平成17年1月30日)
交流分析(TA)で用いられる「ストローク」ということばは、ある人の存在や価値を認めるための言動や働きかけと定義される。ストロークには、陽性のストローク(それを受けると快適な気持ちになるもの)、陰性のストローク(それをもらうと不快感や苦痛を味わうもの)、条件付きストローク(相手の行為や業績と引換に与えるもの)、無条件のストローク(その人の存在や人格そのものに対して与えられるもの)がある。ストロークには法則があって、1. 人は陽性のストロークを無条件に得ている限り安定している。2. 人は陽性のストロークが不足して心理的飢餓状態になると、陰性のストロークを集め始める。3. 陰性のストローク集めは、陽性のストロークが与えられないかぎり永遠に続く。4. 条件付きのストロークばかりを得ていると、陰性のストロークを集め始める。5. ストロークがないことは人にとって最大のデメリットである。
特に家族の交流を評価する上で、重要な考え方である。皮膚疾患を抱える小児や老人にもあてはまるのではないかと思った。
-
第19回皮膚科心身医学研究会から(平成17年1月30日)
患者の治療に必要な家族とのかかわり方は、A. 診療関係の支援、B. 患者の心的環境の調整、C. 家族メンバー間の病的な相互作用の治療、D. 家族そのものの病理の治療、E. 家族代理の役割(小此木)であり、このうち、子供や思春期の患者では、家族面接、特に母親並行面接が有効である。家族関係のあり方が患者の症状に影響を与えている場合、患者への対応に家族が途方にくれている場合、家族が子供の病状を子育ての失敗と思いこみ、その責任を強く感じている場合、家族と子供の共生関係が強い場合、患者と家族の関係が心理ゲームになっている場合に考慮しないといけない。
アトピー性皮膚炎などの慢性疾患で、必要とは感じながらも、なかなか時間がとれない現状であるが、確かに必要な事だと感じた。
-
第28回皮膚脈管・膠原病研究会から(平成17年1月27日)
livedo、難治性下腿潰瘍をきたす抗リン脂質抗体症候群では、ループスアンチコアグラント(LA)、IgG、IgM抗カルジオリピン抗体(aCL)、β2-グリコプロテインI依存性抗カルジオリピン抗体(β2-GPIaCL)以外にも、IgA-aCL、フォスファチジルセリン依存性抗トロンビン抗体(aPS/PT)が陽性の症例があり、これらの自己抗体も測定する必要がある。
血栓症と抗トロンビン抗体の関係は念頭におく必要があると思った。なお、LAの責任抗体といわれているaPS/PTは強皮症やCNSループスでも陽性率が高いとのことで、注目する必要がある。
-
第797回東京地方会から(平成17年1月15日)
臨床的にも病理学的にも落葉状天疱瘡から尋常性天疱瘡に移行したと考えられる症例において、経時的に抗デスモグレイン抗体を計測した結果、当初はDSG-1が単独陽性だったが、尋常性天疱瘡への移行とともにDSG-1とDSG-3の両方が陽性となった。また尋常性天疱瘡に移行したあとも粘膜疹は出現せず、それは粘膜疹を発症させるには抗DSG-3の値が低かったためと考えた。抗DSG-1と3を両方測定することは、1. 病型の判定、2. 病勢の把握、さらに3. 移行の予測のために必要である。
抗DSG-1と3は初診時以外では両者の保険算定ができないが、こういう症例をみると、やはり両方を定期的に追っていく必要があると感じた。
-
第19回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成17年1月8日)
皮膚の発疹がなににもかかわらず、全身性のかゆみをきたす、胆汁うっ滞や尿毒症患者では血中オピオイドペプチド値が上昇していることから、これが中枢性のかゆみのメディエーターと考えられる。オピオイドはμ、δ、κの3種類の受容体に結合し作用を発揮するが、μ-オピオイド、κ-オピオイドはいずれも鎮痛的に働き、かゆみに関しては、μ-オピオイドで増強し、κ-オピオイドでは抑制する。今後はμ-オピオイド拮抗薬(ナロキソン)、κ-オピオイド作動薬(TRK-820)による治療が、特に透析中の患者の中枢性かゆみに対して行われていくだろう。
待望の薬剤であるが、注射剤らしい。
-
第116回神奈川県皮膚科医会から(平成16年12月5日)
健常人ないし健常皮膚では痒みを感じないようなわずかな刺激(熱・電気・酸・ピンプリックなど)に対しても、痒みを感じてしまう状態を「かゆみ過敏」という。また、かゆみ刺激が続いた状態で痛み刺激を加えると、かゆみを感じるとのことである。アトピー性皮膚炎や乾燥はだでは、この「かゆみ過敏」の状態である。また、乾燥はだが48時間持続すると、末梢神経のC線維が表皮まで到達することが観察され、「かゆみ過敏」さらには湿疹の病態と関連している可能性が高い。
実際の生理学的実験によるデータであり、今まで何となく印象として思っていたことを実証する貴重な話であった。
-
第2回横浜みなと皮膚科懇話会から(平成16年11月18日)
悪性腫瘍において、原発巣に接触せずそこから少し離れた場所に転移巣を認める場合を、intransit(原発巣がリンパ節に向かって転移する途中の)metastasisと呼ぶ。皮膚腫瘍ではメラノーマで時に認められるが、有棘細胞癌やメルケル細胞癌でも同様の報告がある。メラノーマでは、領域リンパ節を超えない、原発巣から2cm以上離れた場所の皮膚転移ないし皮下転移と定義され、これがあるとTMN分類ではN2bに分類され、stageIIIと評価されるので、治療方針を決定する上で注意が必要である。
いままで、認識していなかった。多中心性に発生した場合には鑑別が難しそうだが、今後は原発巣の周囲に注意して診察する必要があると思った。
-
第109回横浜市皮膚科医会から(平成16年11月14日)
舌が通常は白く見える状態、舌の上に何らかのものがのっかっている状態(角化ではない)を舌苔(belaq)という。口腔内の温度の上昇、乾燥が原因であり、咽頭炎や扁桃炎に伴うことが多い。注目すべきは片側性の場合で、舌苔がついている側の耳下腺腫瘍や片麻痺があって、唾液の分泌低下を伴う際に生じる。
すばらしい観察であった。今後は舌の診察も心がけていこう。
-
第109回横浜市皮膚科医会から(平成16年11月14日)
舌に多発性の丘疹性血管拡張をみたときに念頭に置かなければならない全身疾患は、(1)PSS、(2)Osler病、(3)POEMS症候群、(4)blue-rubber-bleb nevus syndromeである。(4)は青みがかっているのが特徴で、鑑別が可能である。
POEMSは鑑別診断としてなかなか出てこない。大変参考になった。
-
第109回横浜市皮膚科医会から(平成16年11月14日)
乳児の額の癜風の報告。数ヶ月で12名の患者が集まったそうである。脂漏性皮膚炎との関連がありそうだが、鱗屑の鏡検で菌糸が証明される。額や眉間に多く、お母さんがだっこをする時に、癜風の好発部位である胸と接触するために発生するのではないか、とのことであった。
これまで、そのように診断したことがないと思う。今後は乳児の眉間・額に注目して診察し、鏡検を行っていこう。母の癜風についてもみていこう。
-
横浜労災病院症例検討会から(平成16年11月10日)
学童期の小児のオトガイよりやや頚部に近いところに、毛孔性の角化性丘疹を混じる表皮肥厚を伴った局面をきたす疾患があり、follicular keratosis of the chinとして報告されている。テレビを見たり、マンガを読むときに、膝でアゴを支える姿勢をとるのが癖になっているために生じると考えられている。
おもしろい疾患である。今後、注目してみていきたい。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成16年11月4日)
強皮症の末梢循環障害に基づいて発症した難治性の潰瘍と胼胝様の角化性変化を足趾にきたした症例の報告である。第1趾の切断後も断端周囲や足蹠にも同様の角化が再燃している。末梢神経障害、特にコントロール不良の糖尿病やハンセン氏病などにみらる病態と同じと考えられ、papillomatosis cutis carcinoides Gottronと診断した。
忘れかけていた病名であった。最近、脛骨複雑骨折後に生じた末梢神経障害によって、足趾の潰瘍と鶏眼様角化性病変をきたした症例を経験したが、こう呼ぶのがふさわしいかもしれない。
-
第2回横浜デルマカンファレンスから(平成16年10月20日)
スポロトリクスを皮内に注入すると、そこには、まず好中球の浸潤がおこり、膿瘍を形成する。2週間ほどすると組織球も浸潤してくるが、注目すべきは、膿瘍がだんだん真皮の上方にあがって行くことで、膿瘍ごと病原体を上に押し上げ、最後は潰瘍化をきたして、それを経表皮的に排泄していくという免疫・防御機構が認められるようになる。
症例があれば、組織での膿瘍の位置に注目して見てみよう。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成16年10月7日)
RAが原因と考えられる胸鎖関節炎で、左胸鎖関節部に腫脹を来たし、それに伴って、左前胸部鎖骨下に分枝状の毛細血管拡張を生じた症例の報告であった。左腕頭静脈に閉塞があることが確認されている。
解剖学の知識が必要であると感じた。貴重な症例であった。
-
第12回神奈川県皮膚科医会皮膚科在宅医療勉強会から(平成16年9月8日)
褥瘡の経過評価用DESIGN分類を、別々の症例・患部で比較できるように、各項目の重みを再評価した。D:深さが15点、E:滲出液が30点、S:大きさが150点、I:感染が15点、G:肉芽組織が10点、N:壊死組織が3点、P:ポケット形成が80点とすると、治癒までの日数の予測を行うことができるようになった。予後予測用DESIGN修正版はこちら。
詳細な観察に基づく多くのデータの蓄積からなる、敬服すべきデータである。さっそくあしたからの褥瘡診療に応用していきたい。
-
第12回神奈川県皮膚科医会皮膚科在宅医療勉強会から(平成16年9月8日)
褥瘡の肉芽形成期に治癒の遷延をきたす場合は、以下の4点に注目する必要がある。1.DinD(褥瘡の中に圧迫による褥瘡を生じている)。2.白っぽい不良肉芽(潰瘍の底が除圧不足による血流障害をきたしている)。3.創縁の血流障害(潰瘍のふちに圧迫が加わり、壊死をきたしている)。4.クレバス(肉芽組織中がしわになって、中央にスジを形成し、優良肉芽の形成が見られない)。
日常よく目にする状態が整理できた。それぞれに対応が異なるので、注意して見ていきたい。
-
第19回乾癬学会から(平成16年9月5日)
尋常性乾癬の管理上、コントロールが難しい症例はどういった特徴があるかを統計的に観察すると、1.男性、2.初診時年齢が25歳以下、3.BMI(body mass index)が25以上、の3点が重要であった。今後、治験や統計的観察を行う際には、例えば「男性で、25歳以上で、BMIが25未満の症例」など、それぞれのグループにわけて解析をする方がよい。
コントロールの難しい群と容易な群が混ざっていると、治験の際の効果判定などにばらつきが出てしまうので、非常に重要な指摘であった。日常の臨床にも役に立つデータだった。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成16年9月2日)
足の第4趾の爪が丸くなっていて、のびると下に食い込んでくるという疾患がある。第4趾爪甲前方彎曲症といい、伴性劣性遺伝で男性に多い。症状は出生時からみられ、通常は両側性であるが、片側の場合もあるとのこと。
始めて耳にした疾患である。何となくこの疾患の患者さんに遭遇したことがあるような気がするので、過去の症例を調べてみよう。こういう疾患は知らないと診断できない。なお、手の第2指におこる、先天性示指爪甲形成異常症との関連はなさそうである。
-
第34回日本皮膚アレルギー学会から(平成16年7月18日)
乳酸菌を加熱処理した菌末を内服すると、接触皮膚炎の感作経路と発症経路の両方で抑制がかかり、接触過敏症が起こりにくくなる。ニッケルや松ヤニなどの接触皮膚炎の症例で、症状が改善し、パッチテストの反応も弱くなった事が示された。
歯科金属が原因の1つと考えられている異汗性湿疹や、職業上、原因物質との接触が避けられない美容師さんのかぶれに使ってみる価値があると思った。
-
第34回日本皮膚アレルギー学会から(平成16年7月18日)
軟膏を塗る際に量のめやすとなる単位である。指の先からDIP関節まで、チューブを搾って軟膏を出すと、これが0.5gにあたる。これをひとつの単位として、one fingertip unit と呼ぶ。片手の裏表に軟膏の外用をすると、ちょうど 1unitでまかなえる。さらに足は 2unit、上肢は 3unit、下肢は 6unit、胸とおなかであわせて 7unit、背中とおしりであわせて 7unit、顔面・頚部は 2unitがめやすである。全身に軟膏を塗るには、計算上1x2 + 2x2 + 3x2 + 6x2 + 7 + 7 + 2 = 40unit、つまり1回20gの軟膏が必要である。
どのくらい患者さんが軟膏を塗っているかの把握、どのくらい塗るべきかの説明、保険請求の時に処置で使った軟膏の量の目安として使えると思った。
-
第115回神奈川県皮膚科医会から(平成16年7月4日)
末梢血管拡張作用のあるPGI2誘導体は、PSSの指端潰瘍に有効だが、そのほかにも肺高血圧症の予防、また抗リン脂質抗体症候群の血栓形成予防にも有効で、一石三鳥である。PSSの診断がついたら早期に使っていく方が良い。
なるほど。脳出血などの心配はあるが、その通りにしよう。
-
第115回神奈川県皮膚科医会から(平成16年7月4日)
ステロイドの全身投与の際に知っていくべきことのまとめ。
・生体は1日プレドニソロン(PSL)を5mg作っている。
・PSLを恒常的に5mg/day以上使用する場合は、ビスフォスフォネートを使用する。
・PSLが20mg以下なら日和見感染なし。20-40mgでは7倍、40mg以上では35倍。
・静注するときには50%増しで内服と同量になる。
・減量の目安は2週間で10%。60→50→40→35→30。
・内服は分割の方が効果的。40mg 朝1回より、20mg 朝夕2回の方が効く。
・減量中の再燃は2倍量に戻って再スタート。
・PSLは胎盤を通らない。rinderonは胎盤を通過する。通常妊婦にはPSL。胎児の治療はrinderon。
・授乳は4時間あければ問題なし。特に30mgまでならいつでもOK。
知らなかったことがたくさんあった。とても大事な内容だった。永久保存版。
-
第115回神奈川県皮膚科医会から(平成16年7月4日)
肺線維症では以下の2つのマーカーを同時に測定した方が良い。1. KL-6: 特異度が高い。2.SP-D (surfactant protein D): 特異度は低いが感度が高く、治療による反応を見る際にふさわしい。
SP-Dは知らなかった。どちらも保険適応だが、残念ながら両方の請求はできないようだ。
-
第115回神奈川県皮膚科医会から(平成16年7月4日)
PSSでtopoI 抗体が陽性であっても、その30%はlimited typeである。diffuse typeの強皮症でも発症から6年をすぎると硬化が改善し、topoI抗体価が低下する例がある。抗体価が100u/ml以下の場合は、症状は安定しており心配はない。100u/ml以上の症例では、そのうち45%が抗体価の変動がなく症状も不変、30%は抗体価が低下して、症状も改善。25%が抗体価の上昇をきたし、症状が増悪するという結果が得られた。
topoI 抗体はdiffuse typeの強皮症の診断に有用であることは常識だが、抗体価の変動が活動性の指標になる事は知らなかった。重要な統計であったと思う。なお、抗U3-RNP抗体(抗核抗体でnucleolar pattern)が陽性の強皮症が肺高血圧症をきたしやすいこと、抗RNA polymerase抗体陽性の強皮症が肺線維症が軽く、ステロイドで硬化が改善する予後良好タイプであることも初耳だった。
-
第115回神奈川県皮膚科医会から(平成16年7月4日)
抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体は皮膚筋炎で検出されることのあるJo-1抗体の親戚で、免疫沈降法で検出可能である。この抗体が陽性である症例は、1. MCTD的な臨床症状であるにもかかわらず、抗RNP抗体が陰性。2. 間質性肺炎・肺線維症を伴うが慢性進行型で致死的ではない。3. メカニックハンドと呼ばれる手指の関節変形と多関節炎をともなう。4. 発熱、レイノー症状をともなう。5. 皮膚筋炎の30%でみられるが悪性腫瘍の合併はない。6. 筋力低下が軽く、ステロイド反応性がよい。以上のような特徴がある。
恥ずかしながら初めて耳にした。北里大学の膠原病外来をやっていた頃には、きっとそのような症例を診ていたのではないかと思う。今後は疑わしいケースがあったら検査を依頼しよう。
-
第16回横浜北部皮膚科臨床懇話会から (平成16年6月2日)
伝染性紅斑(リンゴ病)の原因ウイルスであるヒトパルボウィルスB19の感染によって生じた、papular-purpuric gloves and socks syndrome (PPGSS) の11歳女児の症例が報告された。発疹は左右対称性に手関節部、足背・足関節部にみられる紫斑を混じる紅斑性丘疹で、組織学的には血管障害を伴う滲出性紅斑の所見であった。ヒトパルボウィルスB19のIgM抗体は高値であった。関節痛を伴うこともあり、臨床的にアナフィラクトイド紫斑病との鑑別も重要なポイントである。
伝染性紅斑以外にもパルボB19感染症があることを再認識した。あやしい症例があれば抗体価の測定をしてみよう。
-
第20回日本臨床皮膚科医学会から(平成16年5月23日)
小麦に含まれる蛋白質は、水溶性蛋白と不溶性蛋白に分けられる。小麦アレルギーや小麦の関与する食物依存性運動誘発性アナフィラキシーのアレルゲンはグルテンと考えられているが、これは不溶性分画に属する蛋白である。通常のRASTの「小麦」および鳥居のプリックテスト用試薬の「小麦」は、実は水溶性蛋白抗原であり、グルテンは含まれていないので、解釈の際には注意が必要である。なお、RASTではグルテンに対する特異的IgEが測定可能であり、また、鳥居のプリックテスト用試薬では「パン」がグルテンを多く含む強力粉を用いて作成されている。
これは皆、知らないのではないか。当院でもプリックテストを施行するケースがあるが、「小麦」を用いていた。さっそく明日「パン」をたのんでおこう。
-
第20回日本臨床皮膚科医学会から(平成16年5月23日)
症例の報告である。歯科治療の30分後に全身に蕁麻疹が生じ、アナフィラキシーに至ったケースで、原因の検索が行われた結果、根幹貼薬剤のホルマリングアヤコール(FG)が原因であった。ホルマリンはガスなのでそれ自体はアレルゲンとはなり得ず、ホルマリンで変性したアルブミン蛋白がⅠ型アレルギーの原因となったらしい。
蕁麻疹と歯科治療との関連を今後患者さんに聞いてみよう。
-
第20回日本臨床皮膚科医学会から(平成16年5月22日)
赤く見える発疹で、紅斑でも、血管拡張でもないものがある。表皮の栄養障害をきたす病態がそれである。これにあたる疾患は、亜鉛欠乏症、壊死性遊走性紅斑、ペラグラの3つで、それらの臨床と病理を想像すること。
なるほど、共通点があるなと思った
-
第20回日本臨床皮膚科医学会から(平成16年5月22日)
白癬菌がスーっと根をはるように四方八方に広がるのは、菌にとって住みやすい環境にある場合である。ひとたび滲出液や白血球に出会うと、白癬菌はのたうち回るように徐々に鎖状になり、さらに丸いイースト状になって休眠状態に陥る。そのうちのいくつかが生き残り、再び根を伸ばしていくことになる。
ジクジクした趾間型白癬で、糸状菌が見つからないことをよく経験する。丸い隔壁のイーストを見落としているかもしれないので、今後は気をつけてみてみよう。
-
第4回横浜心身症アレルギー研究会から(平成16年4月22日)
予防医学的な見地からの話で、数多くのお母さんと赤ちゃんの前向きコホート調査から、次のような事が判明した。臍帯血の非特異的IgEが500u/ml以上で、かつ新生児の血清中の非特異的IgEが5u/ml以上だと、その児が3歳児検診でアトピー性皮膚炎を指摘される確率がきわめて高いとのこと。
悪い予測はなかなかしたくないし、新生児の採血も難しい。開業医にはできないが、なるほど、そういうものかと思った。
-
第4回横浜心身症アレルギー研究会から(平成16年4月22日)
スギ花粉症の人はその季節になると、皮膚の「チクチク度」が増加する!乳酸に対する刺激性を頬の皮膚でみた結果であるが、その原因として、角質水分量や経皮的水分喪失量は異常がなく、形態学的に角層の乱れもなかった。しかし角層内の神経栄養因子(NGF)が増加していた。花粉飛散の時期を過ぎると改善するとのことで、スギ花粉が皮膚過敏性に対して何らかの作用をしていると考えられる。
スギ花粉症の患者さんにこの季節、まぶたの湿疹ができてしまうことをよく経験するが、何か関連がありそうだ。
-
第103回日本皮膚科学会総会から(平成16年4月18日)
疥癬虫が歩いた、というか走った。1分間に5cm移動した。そして、テントウムシのように指を登ったりくだったりして、30分後にしわに沿った所で止まって皮膚を掘り始めた。20分後に頭半分をもぐりこませ、その後は1日に0.4mm、途中で空気穴をあけながら、トンネルを作っていった。疥癬虫は体長0.4mmで、10円玉の裏にある平等院の屋根のはじっこに乗っかっている鳳凰と同じ大きさだとのこと。胸の黒い点は、皮膚にもぐっていてもダーモスコピーがあれば確認できる。それにしても楽しい人体実験であった。ただし1年後の今も時々かゆくなるらしい。
いやぁ、疥癬が動いているところを始めてみせていただいた。わざわざ京都に行った甲斐があった。
-
第15回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成16年3月11日)
皮膚筋炎の皮膚症状の一つにゴットロン疹があり、難病情報センターのHPでは、「手指関節背面の皮が剥けた紫紅色の皮疹」と説明されている。しかし、この皮膚症状は Dr. Gottron が定義したものではなく、色々な Dr. の色々な解釈であって、どういう皮膚症状をさしているか、統一した見解がない。我々が目にすることの多い、皮膚筋炎の手指関節背面の皮膚症状は、上記のような紫紅色萎縮斑であるが、これは、罹病期間が長いためにそうなるのであり、始まりは、おそらくムチンの沈着による丘疹の変化であると考えられる(皮膚筋炎のムチンはメタクロマジーを呈する事が特徴で、SLEに伴うムチンとは性質が異なる)。その後、基底層の液状変性が顕著となり、 始めは顆粒層の肥厚や表皮の乳頭腫状の変化があって、臨床的にも敷石状にみえるが、その後は徐々に表皮の萎縮が生じ、血管拡張もめだってくる。ゴットロン疹は年齢や罹病期間とともに変化すること、組織学的には皮膚筋炎の皮膚症状そのものであることを覚えておくことが重要である。
よく使用する用語でも、よく考えると、定義が曖昧なものも多い。記載をするからには、それが何を指しているのかを理解し、場合によってはその用語の歴史を知る必要があると思った。
-
第2回神奈川皮膚臨床研究会から(平成16年3月6日)
表皮には増殖・分化のかなめとなる stem cell が存在する。stem cell は真皮乳頭の突端が接触する表皮基底層にある。β1インテグリンを強く発現し、真皮と強く癒着して局在を維持している。それ自身の増殖は遅いが、増殖の早い transient amplifying cell (TA細胞) の「もと」となる。そしてさらに、TA細胞は post mitotic cell へと分化し、表皮の最外層である角層を形成していく。尋常性乾癬においては、表皮細胞の増殖が通常より亢進するため、乳頭部の直上に存在するすべての stem cell を支点として表皮細胞が増殖し、2つの増殖する表皮がぶつかり合ったところが、下へと伸びていくために、表皮の延長が病理学的に生じることになる。また、尋常性疣贅においては、ヒト乳頭腫ウィルスの感染がこの stem cell におこると考えられており、一つの stem cell が増殖する範囲で表皮細胞の増生が起こるために、となりあったイボがモザイクを形成することになる。
表皮に stem cell があることは何となく理解していたが、その局在や、疾患との関連を認識したのは今回が初めてで、非常に勉強になった。
-
第1回横浜デルマカンファレンスから(平成16年2月26日)
ステロイド軟膏の外用は湿疹・皮膚炎の治療において、きわめて一般的で、かつ有効な治療法である。しかし、生物学的に皮膚という臓器をとらえると、たとえば接触皮膚炎の病態は、角層に付着した生体にとって有害な異物ないし抗原物質に対する生体防御反応であり、これらの侵入を防ぐために、(1) 角層は増加し、(2) 表皮が肥厚し、(3) 角化のターンオーバーが促進されることによって、有害物質を除去するように働いている訳である。ここで、ステロイド軟膏を外用すると、角層がはがれにくくなり、spongiosisが見られなくなり、表皮の肥厚も起こらず、ターンオーバーが抑制され、異物や抗原物質の除去が遷延化してしまう。さらに、Langerhans細胞の数も減って、樹状突起も少なくなってしまう。今後は、湿疹がステロイド外用剤によって「異型湿疹」と呼ぶべき状態に陥っていないかを見極め、いわゆる局所的免疫不全が病態に関与していないかを念頭において診療にあたるべきである。
「かぶれ」のステロイド外用は、皮膚科医にとってごく当たり前の治療であると考えていた。しかし、今後は、ステロイドの外用で、かえって免疫抑制をかけてしまって、不都合がないかどうかを考えながら、治療にあたる必要があると思った。
-
色素細胞母斑は、上から、A型(nestあり・メラニンあり)、B型(nestなし・メラニンなし)、C型(シュワン細胞様)へ推移し、下に行くほど細胞が小型化する。これを「maturationがある」という。maturationがない場合はmelanomaを疑う。
なるほど、体系的で分かりやすい。年齢による臨床、病理の変遷もこれと同様と考えてよさそうだ。最近では、Unna、Clark、Miescher、Reed、Spitzと色々と人名が出てくるが、まだピンとこない。
-
第788回東京地方会神奈川分会から(平成16年1月17日)
肝硬変の人が、夏場にアジやボラなどの生魚を食べると、Vibrio vulnificusによる敗血症を生じ、急性腎不全で死亡する例がある。症状は生食いの24時間後ぐらいから急速に始まり、抗生剤で救命できないことが多い。皮膚症状は、四肢の敗血症疹(有痛性紅斑)で、急速に壊疽に陥る。この菌は食中毒のVibrioとは関係なく、22℃以上の海水に住む魚には、ほとんど付着しているとのこと。日本近海では7月から9月には海水が22℃以上となるので、九州などの南日本では、特に注意が必要。ただし、温暖化の影響もあって最近では東北地方の海水もこの温度に達するようだ。しかし、この感染症は、正常人で発症することはまずない。この菌は鉄の多いところで増殖するらしく、肝硬変の人は血中トランスフェリンの減少のため、血清鉄が高くなっており、したがってこの菌の増殖が早いらしい。
発症すると生命に関わる事態になってしまうので、肝硬変の患者さんに教えてあげる必要があると思った。
-
第17回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成16年1月10日)
アスピリン不耐症はCOX1阻害剤に対する過敏症で、皮膚科的には蕁麻疹やアナフィラキシーを生ずることが知られている。この疾患では、コハク酸エステル構造のステロイド剤(ソルコーテフ・サクシゾン・ソルメドロール・水溶性プレドニン)に過敏症を示すことがあり、これらの静注によって症状が増悪することがある。したがって、リン酸エステル構造のステロイド剤(水溶性ハイドロコートン・デカドロン・リンデロン)を選択するほうが安全である。また、抗ロイコトリエン受容体拮抗薬(オノン)が有効なことがある。
即効性のステロイドというと今まではソルコーテフを使うことが多かったが、考え直さねばならない。
-
第17回神奈川皮膚科免疫アレルギー懇話会から(平成16年1月10日)
高血圧症や蛋白尿の治療で用いられるACE阻害剤の内服によって、血管神経浮腫(クインケ浮腫)を生じることがあり、注意が必要である。内服を開始してから5日後に生じる例もあり、診断が容易でない。あごのまわりや舌に好発するが、まれに気道に生じて呼吸困難につながることもある。治療は薬剤の中止に加え、抗ヒスタミン剤が一般的だが、抗エストロゲン製剤であるダナゾールやトランサミンも有効とのことである。
知らないと質問ができない。今度さっそく聞いてみようと思った。
-
第14回横浜北部皮膚科臨床懇話会から(平成15年12月11日)
顔面、体幹、手掌、爪の色素沈着がビタミンB12の欠乏によって生じる!呈示された女性の症例は悪性貧血があり、顔面や体幹にまだら状の不規則な褐色色素斑を伴っていた。Hunter舌炎はなし。手掌や爪も濃さの違う汚らしい色素斑を認めた。しかし、悪性貧血の治療で、ビタミンB12の筋注続けたところ、次第に色素沈着が改善していき、爪は基部から、正常色へと変化していった。
絶対に見逃していると思うので、変な色素沈着の患者さんがあったら、貧血、場合によってはビタミンB12の検査をしようと思った。
-
横浜皮膚疾患研究会から(平成15年12月4日)
コレステロール結晶塞栓の治療に、LDLアフェレーシスという方法が有効である。リボソーバーという血漿中のLDL(及びVLDL)を選択的に吸着する機器を用いて、二重濾過膜血液浄化を行うもので、従来は家族性高コレステロール血症、巣状糸球体硬化症、閉塞性動脈硬化症(ASO)の治療に利用されている。なぜ効果があるかに関しては、塞栓をきたしたコレステロール結晶がぬけるのではなく、血液、血漿粘度の低下や血液凝固因子の減少、ブラジキニン産生増加に基づく血管拡張作用が改善の理由と考えられている。
治療に困る疾患なので、今度からは紹介しよう。ちなみに皮膚科でもASOの潰瘍でやってみてもいいのではないかと思った。
-
第1回神奈川皮膚臨床研究会から(平成15年9月13日)
特に更年期以降の女性にみられる「うす毛」をfemale pattern hair lossという。男性と同様にandrogenic alopeciaと考えられている。時には思春期頃から認められ、心理的ストレスやダイエットが原因のことがある。貧血と甲状腺疾患に伴うこともあり、血算とマイクロゾーム抗体は調べた方がいいらしい。治療は欧米ではミノキシジルの外用をまず試みるようだが、日本で使えるミノキシジル(リアップ)は、いまのところ男性専用で、そのうちに女性用のリアップが出るそうだ。ケトコナゾール(ニゾラール)にも若干の発毛効果があるとのこと。
あまり今までは意識しなかったが、これからは検査や治療をやっていこう。ケトコナゾールがよいなら、ミコナゾールシャンプーはどうだろうか。薬局で手に入るので勧めてみよう。